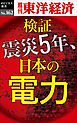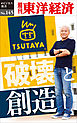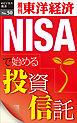週刊東洋経済eビジネス新書シリーズ作品一覧
-
-異例の超金融緩和長期化でも経済成長率が上向かない。中央銀行抜きに経済は維持できないのか。 そんな中、ヘリコプターマネー論まで登場している。日銀のマイナス金利政策や量的緩和政策は、なぜうまくいかないか。日銀論や為替論を通して、金融緩和依存症とも言える世界経済の病理を解剖する。 本誌は『週刊東洋経済』2016年4月2日号掲載の16ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 金融緩和が効かない! 【INTERVIEW】アデア・ターナー・日本はヘリコプターマネーに踏み込むべきだ 【講義1】小幡績の日銀論・黒田緩和はもう必要ない 【講義2】野口悠紀雄の為替論・怖いのは円高より円安 消費増税先送りこれだけのリスク
-
-日本銀行が突如繰り出したマイナス金利政策。水面下に沈んだ金利を前に銀行は焦りと危機感を募らせている。これまでと同じ競争を繰り広げるだけでは、もはや展望は開けない。 本誌では総合力の“三菱”、国内営業の“三井住友”、追いかける“みずほ”の姿をリポートする。メガバンク3つのアキレス腱とは。 本誌は『週刊東洋経済』2016年3月26日号掲載の13ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● マイナス金利が直撃 追い込まれる銀行 焦燥のメガバンク 【三菱UFJ】 頼みの海外戦略を3つの逆風が襲う 【三井住友】 アジア展開に誤算 国内強化へ東奔西走 【みずほ】 稼ぐ力に見劣り 組織再編は吉と出るか 【日本郵政グループ】国債運用は前途多難 漂流するゆうちょ銀行 金融庁が迫る銀行の「変革」 【住宅・不動産】 盛り上がらない現場 【INTERVIEW】 マイナス金利の気になる効き目 慶応義塾大学教授・池尾和人 東京大学大学院教授・渡辺 努
-
4.0知識はあっても、何となくスッキリしない中東・イスラムをめぐる理解。 中東では今も宗派対立と大国の利害が錯綜している。まずは、この地域の国々の文化、歴史を大まかに知ることで危機の本質を把握する必要がありそうだ。原油価格の下落は産油国の経済に大きな変革を迫ると同時に、世界の金融危機の火種にもなりかねない。 本書では、中東の専門家が文化、宗教、歴史、国際政治、紛争、経済などのテーマを誌上講義していく。ポイントは中東をめぐる複合的な危機の理解にありそうだ。 本誌は『週刊東洋経済』2016年2月27日号掲載の18ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 歴史と文化で危機の本質を知る イスラム教の基礎知識 サウジに見る 女性の地位ウソ? ホント? ざっくりわかるイスラム史 欧米に振り回されてきた 中東の歴史 世界を揺るがす中東複合危機 原油暴落で資金逆流が加速 中東経済の未来を握る富豪たち
-
-人工知能(AI)をめぐる話題が沸騰しているが、人工知能以外でも注目のテクノロジーはまだまだある。 そこで、2016年を代表する注目のテクノロジー・トレンドを紹介する。生活、産業、そして人の仕事はどう進化するのか。科学技術はどのような未来をもたらすのか。 自動運転を生んだグーグルX創設者、セバスチャン・スラン氏へのインタビューも掲載。夢だけではない現実の姿を知ってほしい。 本誌は『週刊東洋経済』2015年12月26日・2016年1月2日合併号掲載の13ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 【IoT】「モノ」のデータで効率化 【人工知能】新たな解析手法が起爆剤 【INTERVIEW】人工知能は人間を解放する グーグルX創設者・ユダシティCEO セバスチャン・スラン 【ロボット】楽しいだけのロボットはイノベーションではない 安川電機 会長兼社長・津田純嗣 【ドローン】無人飛行機の宅配が“実現” 【フィンテック】銀行の収益源を侵食 【バイオ】本丸の再生医療に勢い 【スパコン】「ポスト京」で世界一へ 【アップル】破壊力不在のiPhone
-
-福島第一原発事故から5年。日本の電力をめぐる環境は大きく動いている。 福島では収束や廃炉作業が続く中、電力会社は自由化の時代に入った。東電は事故の責任と自由化競争を貫徹し再建を果たせるのか。 一方で、国の再生可能エネルギー政策には幕引きムードが強まっている。政・官・電力業界を取り巻く「力学」に見えてくるものは? 日本の電力を検証する。 本誌は『週刊東洋経済』2016年3月12日号および3月19日号掲載の12ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● [前編]東京電力 再生の虚実 東京電力 再建計画の達成状況 INTERVIEW/安全対策に終わりはない 巨大ビジネス狙うJERA(ジェラ)の野心 難航する廃炉・汚染水対策 [後編]再生エネ “幕引き”の深層 FIT法改正の主なポイント 色あせる「再生エネ拡大」公約
-
-高齢な親を持つ家族は、健康面だけでなく、さまざまなリスクに直面する可能性がある。認知症には至らなくとも、高齢者の脳の変化を知っておくことは、親のリスクを理解することに役立つ。 本書では、脳と心の変化を知ることで、車の運転、恋愛、相続・財産トラブル、お酒への依存、金銭管理、不慮の事故など高齢者のリスクをドラマのような実例で学んでいく。 親を見守る家族にできることは、まだまだある。 本誌は『週刊東洋経済』2016年3月19日号掲載の17ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 激変する脳と心 高齢者の“暴走”は必然だ 【COLUMN】21世紀の高齢者を襲う デジタル認知症 【車】過信が生む高齢運転の悲劇・「自分は大丈夫」が危険 【恋愛】争族を生む老いらくの恋・財産トラブルの火種 【健康】アルコール依存症に要注意・暴言、自己中は酒のせいかも 【金銭】高齢者の銀行信仰は危険・カモにされる理由がある 【COLUMN】被害総額は年間477億円・特殊詐欺の巧妙な手口 認知症患者の鉄道事故・「家族に責任なし」でも残る課題
-
-アマゾンは世界最大のネット通販会社であると同時に、デバイス・メーカーでもあり、コンピュータ・テクノロジー企業でもあり、ロジスティクス(物流)カンパニーでもある。 本誌では、アマゾン関係者へのインタビューから、端末や物流の米国最新事情、「AWS(アマゾン・ウェブ・サービス)」の実力までをリポート。その規模、スピード、品ぞろえ、先進性での挑戦とは。「アマゾン・プライム」だけではない、その経済圏の最先端を紹介する。 本誌は『週刊東洋経済』2016年3月5日号掲載の16ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● ・ついに日本上陸! 驚異の1時間配送 ・「プライム・ナウ」のまとめ ・INTERVIEW/買い物の歴史上でプライムは最強だ /米本社 アマゾン・プライム・担当副社長 グレッグ・W・グリーリー ・【米国最新事情・端末編】 買い物体験が劇的に変化 日常を支配する注文革命 ・INTERVIEW/スマホすらいらない 注文はボタン一つ /アマゾン・ジャパン・バイスプレジデント ~Kindle事業本部長・玉木一郎 ・【米国最新事情・物流編】 一般市民まで活用 脱・宅配会社 「自前配送」の衝撃 ・アマゾンも参戦濃厚 千葉“ドローン宅配”の現実味 ・巨額投資支える黒子役「AWS」の実力 ・INTERVIEW/古いIT企業ができない薄利多売で成功 /Amazon最高技術責任者(CTO) ヴァーナー・ボーガス ・ジェフ・ベゾスの頭の中
-
-今後10~20年で人工知能(AI)やロボットに代替される可能性が高い職業に就いている人は、米国で47%に上る。日本でも、ほぼ同程度との調査が発表された。テクノロジーの進化はどこまで人間の仕事を奪うのか。もはやSFではない技術革新の驚異的なスピード。その現実を紹介しつつ、あわせて誰もが大きな変化に直面する近未来へ向けたポイントを探る。 本誌は『週刊東洋経済』2016年2月20日号掲載の15ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● テクノロジーは仕事を奪うか AIが変える仕事の未来 ロボットが同僚になる日 シリコンバレー・年収相場は青天井 トヨタはAIで勝てるのか プログラミング教育が注目を集めるワケ 【COLUMN】 シェアリングが雇用を揺さぶる 【INTERVIEW】 会社任せは禁物・スキルは自分で磨け
-
-2016年1月29日、日銀は電撃的なマイナス金利導入を決定した。2014年10月の量的・質的金融緩和発表に勝るとも劣らない黒田総裁一流の奇襲といえる。 マイナス金利導入の真の目的な何か? 副作用はないのか? 円相場や株価への影響は?、国債はどうなる? そして個人の預金は・・・? さまざまな疑問に対し、専門家がその「功罪」をズバリ!解説する。 本誌は『週刊東洋経済』2016年2月13日号掲載の12ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● マイナス金利の「功罪」 疑問にズバリ! マイナス金利とは何か? 銀行収益に大打撃! 欧州のマイナス金利政策 手探りで効果は不透明 マイナス金利下で株が「買い」の理由 マイナス金利導入でも円安効果は限定的
-
-訪日外国人客の好需要に沸くホテル業界。活況を呈すのはビジネスホテルも同様だ。インバウンド需要だけでなく、国内リピーター獲得に向けに付加価値路線を追求するホテルも多い。異業種からの参入も増加し、業界は沸騰している。 本誌ではホテル業界の最前線とともに、空室減で予約が取れないビジネスマンへ予約を確保するテクニック「3つの3とT」を紹介。 また、利用客の急増で注目が高まる「民泊」。利便性と警戒感が交錯する中でビジネスチャンスをどう見いだすか・・。業界の今を追う。 本誌は『週刊東洋経済』2016年2月6日号掲載の15ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 未曾有のインバウンド需要、サービス合戦も過熱 沸騰!ビジネスホテル 火花散らす異業種ホテル アパホテル「頂上作戦」で狙うもの ホテルを確保するテクニック ディズニーホテルが申込金制度を導入 空室減で激戦のネット旅行予約 プロはホテルをこう見極める 民泊「解禁」で何が変わる? 【Interview】民泊でビジネスチャンスは広がる●大田区長 松原忠義
-
-空前のAI(人工知能)ブームが巻き起こっている。AI関連のニュースリリースが相次いでいるほか、都内では連日のようにセミナーが開かれている。決算発表でも、将来見通しの中でAIに言及する企業はもはや珍しくなくなった。米グーグルやフェイスブックに続き、国内でもドワンゴやリクルートがAI研究所を設立。トヨタは今後5年間で1200億円を投じる。何が企業を引き付けるのか。 本誌は『週刊東洋経済』2015年12月5日号掲載の10ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 企業もカネも群がるAI(人工知能)ブーム 第3次ブームの期待と不安 人工知能は人間を超えられるか? Interview「シンギュラリティに懐疑的。人間に愛される技術に」慶応義塾大学環境情報学部長●村井 純 Interview「脳の仕組みを解明し日本らしい攻め方を」電気通信大学大学院教授●栗原 聡 Interview「AIは『生まれつきのニート』」。芥川賞受賞も夢ではない」ユビキタスエンターテインメント社長兼CEO●清水 亮
-
-2015年秋に発覚した、横浜市のマンションの杭打ち不良による傾斜問題は、なぜ起きたのか。 「信頼を裏切られた」--。杭問題の本質は、元請け企業の幹部が思わず漏らした本音に象徴されている。いまだ責任の所在は不明確で、建物の実態すらわからない。 購入者はどうすれば自分のマンションを欠陥から守ることができるのか。購入から管理、修繕まで、マンションの新常識を徹底検証する。 本誌は『週刊東洋経済』2015年12月5日号掲載の18ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 杭問題はなぜ起きたのか 経済設計がはびこる理由 一括請負は時代遅れ。発注者も応分のリスクを Interview「外注範囲が広がり建設現場が空洞化した」東京大学生産技術研究所教授●野城智也 Interview「品質責任は元請けの三井住友建設にある」トータルブレイン社長●久光龍彦 【ルポ】放置される欠陥、救われない住民 補償負担は誰がする? 大手デベの損得勘定 高騰するマンション保険 あなたのマンションは大丈夫? マンション点検の勘所 【業界人座談会】あなたの知らないマンションの世界 資産価値が上がるブランド&施工会社はここだ
-
-2015年11月、三菱リージョナルジェット(MRJ)の試験機が飛び立った。半世紀ぶりの国産旅客機が離陸した歴史的な瞬間だ。 旅客機ビジネスは巨大かつ長期的な成長が期待される産業。国産旅客機MRJの開発に挑む三菱重工業、さらに航空機関連の主要な国内サプライヤー企業にも焦点を当て、日本勢の実力と課題を探る。 本誌は『週刊東洋経済』本誌は『週刊東洋経済』2015年11月28日号掲載の22ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 〈第一部〉三菱重工業、国産旅客機への挑戦 MRJ離陸で始まった三菱の総力戦 【開発トップに聞く】 岸信夫・三菱航空機副社長 三菱に立ちはだかる「型式証明」の高い壁 MRJで問われる日本の“審査能力” 事業成功のカギ握る三菱重工の量産力 ライバル徹底比較、エンブラエルに勝てるか またも納入スケジュール延期でどうなるMRJ 〈第二部〉日の丸サプライヤーの戦い ボーイング競争激化で重工各社に試練 【IHI】有力機のエンジン開発に相次ぎ参画 【ジャムコ】内装品の大手、シートにも本格参戦 【ナブテスコ】制御機器でボーイング信頼勝ち取る 【住友精密工業】“Tier1”目指して北米進出 欧米勢が支配する世界の航空機産業
-
-「経済と財政」「経営とビジネス」「日本政治」「中国の歴史と社会」「中東・イスラム」の5つの分野で、各界の識者が15冊ずつお薦めの本を紹介。 5つの分野を学び、理解するために基本に忠実な本や、歴史的な視点を身につけるための本、原点から知るための本などを紹介している。 日々のニュースを読み解くために、まずは読書で知識を得よう。 本誌は『週刊東洋経済』2015年12月26日・2016年1月2日合併号掲載の10ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 【経済と財政】経済を見る眼を養う基本に忠実な15冊 【経営とビジネス】戦略は「ノウハウ」より「知恵」から学ぶ 【日本政治】一連の改革経緯から平成政治を読み解く 【中国の歴史と社会】中国情勢の理解には歴史的な視点が必須 【中東・イスラム】まず宗教、型破りなアプローチで読む
-
-就職人気ランキングで、毎年上位に入る保険業界。文化放送キャリアパートナーズ就職情報研究所の調査によれば、2016年卒業予定の大学生・大学院生が「就職したい企業ベスト20」には損保ジャパン日本興亜、日本生命、第一生命がランクインした。 だが、実際の働く現場はどうなのか? 企業イメージの創造、子会社立ち上げ、海外での保険普及や若者向け自動車保険の開発など、若手活躍の機会があふれる保険業界の魅力を解説。 また、女性の能力発揮や管理職登用に向けて独自の施策を取るなど、女性活用を進める会社も多い。各社の最新の取り組みを紹介する。 本誌は、『週刊東洋経済臨時増刊 生保・損保特集2015年版』掲載の19ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 【保険業界最新事情】加速する大型M&A。欧米軸の買収時流に 若手が語る保険の魅力 【日本生命】“想い”を伝える仕事に一つの答えはない 【第一生命】自分の中の違和感に成長へのヒントがある 【明治安田生命】目標を達成したときの高揚感がやりがいの一つ 【住友生命】自分の伝え方次第で相手の選択が変わる 【太陽生命】視野を広く持ちストイックに仕事に挑む 【東京海上日動】保険の概念が希薄な国でいかに販路を拡大するか 【三井住友海上】何も知らない強みで新商品を開発 【損保ジャパン日本興亜】リスクを厭わず緻密にコミュニケーションを 女性を起点に広がり進む「多様性」施策 【Womenomics】能力発揮への意識を高めて管理職、役員登用進める Interview「成果と品質へのこだわりが私の原点」東京海上日動常務執行役員(九州・沖縄地区担当)●柴崎博子 両立の悩み解消! 初の業界横断イベント開催 【Work Smart】多様な働き方を許容して育児、介護との両立可能に Interview「トップの積極関与が企業文化を変える」アクサ生命企業文化変革&ダイバーシティ推進室部長 チーフダイバーシティオフィサー●金子久子
-
-ソフトバンクグループの株価が冴えない。国内通信事業の苦戦、巨額買収した米国携帯電話4位のスプリントの不調、踊り場を迎えたかに見えるヤフーや中国アリババといった投資先。三つの爆弾が株価の上値を抑える要因だ。 特に国内の苦戦が響いている。国内で稼いだ巨額のキャッシュを海外での成長投資に振り向けることで勝ちパターンを作ってきたソフトバンクの戦略上、大きな痛手だ。 袋小路に入ってしまったかに見えるソフトバンク。孫社長は三つの爆弾に頭を悩ませている。 本誌は『週刊東洋経済』2015年11月14日号掲載の24ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● もはや破壊者にあらず! 色あせる国内通信事業。急成長神話の終焉 スプリント 土壇場の攻防戦! アリババ株急落。薄れる成長期待 「政治と距離を縮める馬雲」『英国ニュースダイジェスト』編集長●長野雅俊 ヤフーの親孝行はどこまで続く? 側近、幹部、ライバルが語った「孫社長のアタマの中」 次を任せて大丈夫? 海外メディアが報じたニケシュ Pepperは本当に稼げるか? Pepper事業の社長が語る!「単にかわいいロボじゃない」 【ニケシュ×孫正義】特別講義で見せた笑顔 【破壊と創造の歴史】孫正義はどこへ行く 「ヤフーBB以前に戻っただけ」トライオン社長●三木雄信 「1度に3つの懸念は経験がない」多摩大学客員教授●嶋 聡
-
-あなたは、携帯料金を高いと感じていないだろうか? 日本におけるスマホの月額平均料金は6342円。この料金水準は世界の中でほぼ真ん中だ。だが、日本の場合、契約したスマホをあまり使わないライトユーザーが冷遇され、長期利用者が月々支払う通信料の一部は、MNPを使う短期利用者の利益に充てられている。家計支出に占める通信費の割合は10年間で2割上昇。もはや大手による値下げは期待できない! 国策で値下げが始まる今こそ知りたい、賢いスマホとの付き合い方。 本誌は『週刊東洋経済』2015年11月14日号掲載の18ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 携帯料金はどうすれば下げられるのか? ここがおかしい! 日本のケータイ事情 首相指示が招いた料金値下げの大騒動 新電電の二の舞いを避けよ! 国策を先取り! 賢いスマホ節約術 有名機種を安く手に入れる! MVNOを使い倒せ! 性能が上がる格安スマホ。個性あふれる機種が続々 揺れる「iPhone神話」
-
2.0カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)による公立図書館の運営が議論を呼んでいる。「TSUTAYA図書館」には一定の評価がある一方、選書や独自分類のあり方について強い批判もある。誤解と憶測に満ちた、見えざる「企画会社」の素顔とは。 経済メディアの取材をほとんど受けないCCCの増田宗昭社長の独占インタビューも掲載。 本誌は『週刊東洋経済』2015年10月31日号掲載の20ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 「俺たちはお化けなんだ」 気がつけば書店チェーン最大手。成長はまだ続く Interview「変化し続けるのがTSUTAYAの強さだ」日本出版販売専務●吉川英作 TSUTAYA図書館の賛否 Interview「図書館のこと、本のこと、すべてに答えよう」カルチュア・コンビニエンス・クラブ社長●増田宗昭
-
-2015年から相続税の課税対象が拡大し、相続税への関心はますます高まっている。一方で世帯主変更の手続きや遺族年金の申請など、身近な人が亡くなった後にやらなくてはいけないことは膨大で煩雑だ。本誌では相続をめぐる新たな動きを広範に取り上げた。相続や身近な人が亡くなった時にするべきことについて、総合的に勉強しよう。 本誌は『週刊東洋経済』2015年8月1日号掲載の24ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● これからの相続 手続きなどの基本も解説! 増税後の最新事情 ケーススタディで見比べる。損しないコツ Interview「家族という幻想に囚われるな」作家●下重暁子 後悔しないで済む相続対策。カギは家族の意思疎通 相続対策総まくりチェック 【保険】さまざまなニーズに対応 海外への資産移転。国税はここを見る! 信託商品を賢く使いこなす 遺言書で家族を守る おひとりさまの遺言書。希望どおりに資産を残すには
-
-「バイオベンチャー列伝」第2弾!今回もさまざまなバイオベンチャーを紹介する。 米国で設立後に日本で上場、中国で創薬を行う異色ベンチャー・ジーエヌアイグループ、遺伝子治療薬の開発を行うアンジェス MG、がん治療薬を開発するナノキャリア……。 創薬系バイオベンチャー企業は高い成長が期待できる反面、新薬開発には長い年月と多額の研究費用を要するうえに、すべての開発が成功するとは限らず、リスクも高い。 はたして今回紹介する中から大化けする企業は出てくるのか!? 本書は、東洋経済新報社のサイト「会社四季報オンライン」に掲載された連載「大化け創薬ベンチャーを探せ!」を加筆修正のうえ制作しています。 ●●目次●● 異色の創薬ベンチャー、ジーエヌアイグループの展望 Interview「アイスーリュイに続く戦略」ジーエヌアイグループ社長●イン・ルオ アンジェス MG、世界初の遺伝子治療薬の実力 Interview「遺伝子治療薬のこれから」アンジェス MG社長●山田 英 「ミクロの決死圏」。がん治療の先端技術磨くナノキャリア Interview「創薬研究開発の中期展望とナノキャリアの今後の戦略」ナノキャリア社長兼CEO●中冨一郎 リプロセル、「門外漢」が描くバイオビジネスの最終形 Interview「iPSを核にしてリプロセルが目指すバイオビジネスの『最終形』」リプロセル社長●横山周史 「第2の創業」で悲願の黒字化、研究用マウスのトランスジェニック Interview「黒字化を果たし、次の戦略は?」トランスジェニック社長●福永健司
-
-歴史問題や尖閣諸島をめぐって日中関係は緊張をはらむが、東京や大阪の繁華街には中国人旅行客があふれている。やたら押しが強く、声が大きい。金回りがよく、自信満々。そんな中国人とも、つぼを押さえて付き合えば百戦危うからず。歴史と文化を学んだうえで、彼らの頭の中をのぞいてみよう。 本誌は『週刊東洋経済』2015年8月22日号掲載の20ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 中国人の攻略法 中国人を動かす10の行動原理 歴史と古典で学ぶ中国人のツボ 爆買い旅行者の正体 訪日旅行の主役は内陸住民 まるわかり 爆買い客の傾向と対策 日本企業は働きやすい? 中国人若手社員の赤裸々なホンネ なぜ移住? 日本に住みたがる富裕層
-
-
-
-日本のお墓と葬式が変わってきている。地方にあるお墓の面倒が見られず、墓じまい(改葬)する人が増え、永代供養墓、期限付き墓地、樹木葬といった新しいスタイルの墓も出てきている。 葬式にも変化が出てきた。通夜や告別式を省略した「直葬」、近親者を中心とした「家族葬」といった簡略化した葬式が増え、インターネット上には低料金の葬儀プランを打ち出す新しいタイプの葬祭業者が台頭している。いざ喪主となった時、あなたはどうする? 本誌は『週刊東洋経済』2015年8月8日・15日合併号掲載の16ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● どうする? 実家のお墓 いざ購入! 契約書はここをチェック Interview「宗派や寺を脱し、もっと自由に」宗教学者・作家 島田裕巳 樹木葬、期限付き墓地、寺院墓地に新たな動き プロが教える手順とおカネ「もう失敗しないお葬式」 何が違う? 創価学会員の友人葬 気になる戒名のお値段 納得できる家族葬とは 直葬を行う際の注意点 【葬祭互助会】解約手数料は要チェック 岐路の葬儀仲介会社 Interview「寂聴さんを継ぐスターがいない」東京工業大学教授 上田紀行
-
-ニッポンのお寺が危機に瀕している。地方では急速に進む少子高齢化、都市への人口流出による檀家減少、住職の高齢化と後継者不在などの問題に直面。都市部でも檀家を確保できないお寺が増えている。ニッポンのお寺はどうなってしまうのか? 本誌は『週刊東洋経済』2015年8月8日・15日合併号掲載の18ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 仏教界に迫り来る危機 無残! 寺が朽ちていく 【島根県石見地方ルポ】消えていく寺の姿 データで見る「寺院消滅」の現実 Interview「地方の寺は3割以上消える」国学院大学教授 石井研士 うちの寺の収入すべて見せます 【お布施】寺院と業者との深~い関係 巨額損の高野山真言宗。積極運用の苦い教訓 野村証券とのADRは不成立
-
-ベンチャー企業の資金調達額やIPO(新規株式公開)件数が増え、久しぶりにベンチャー業界が盛り上がっている。大企業もベンチャーとの協業に活路を見いだし急接近しているが、一方でバブルの懸念もささやかれている。スマホゲーム会社gumi(グミ)のように、期待されながらIPO直後に業績を下方修正するベンチャーもある。一時のブームで終わるのか、それとも新たな産業を創出できるのか。ベンチャー投資の舞台裏に迫る。 本誌は『週刊東洋経済』2015年4月4日号掲載の10ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 過熱するベンチャー投資 最強投資家・孫正義社長の懐刀 Interview「明らかなバブルで緊張感に乏しい」サイバーエージェント社長/藤田 晋 わが社のベンチャー投資事情 オムロン/ヤフー/KDDI/伊藤忠商事 【匿名座談会】ベンチャーバブルに踊らされるな
-
-家電量販チェーンの業界再編が進んでいる。かつて売り上げ全国トップを誇ったベスト電器やコジマはそれぞれヤマダ、ビックカメラの軍門に下った。その一方、業界最大手のヤマダは2カ月で50もの大量閉店という事態に追い込まれた。 薄型テレビなどのデジタル家電の普及が一巡し、需要が右肩上がりの時代は終わった。生き残りを懸けた熾烈な攻防戦が繰り広げられる家電量販業界。その最前線を追った! 本誌は『週刊東洋経済』2015年7月25日号掲載の22ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 【名古屋編】ついにヨドバシが進出! ビックは駅前に2号店 Interview「名古屋の地盤は渡さない」岡嶋昇一/エディオン副会長 【広島編】駅前再開発でビック、エディオンが全面対決 Interview「ヨドバシだけ好業績のなぜ」藤沢和則/ヨドバシカメラ副社長 衝撃の再編から3年。コジマの店舗が大変貌 ヤマダ電機 落日の流通王 後継店舗はドンキ? テナント探しにも難題 “爆買い”狙ったヤマダ電機免税専門店のその後 家電量販店を振り回す「価格.Com」の正体
-
-6ミリの昆虫型や4足歩行するチーター型ロボット、負傷兵を抱き上げるロボット、無人航空機(ドローン)…。 米国では世界一の国防予算を背景に、精鋭たちが日々ロボット兵器開発にいそしむ。冷戦終了後、「世界の警察」を自認してきた米国だが、9・11同時多発テロ以降、イラクやアフガニスタンでは多くの戦死者を出し、従来の戦略・戦術の転換を迫られることになった。そこで期待を寄せるのが技術革新、とりわけロボットやドローンの活用だ。彼らが描く「次の戦争」は、日本人の想像を超えたものになりそうだ。 本誌は『週刊東洋経済』2015年3月14日号掲載の14ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 米国軍事ロボットの未来 軍事技術を主導する“DARPA”って何だ? ドローンが戦争のすべてを変える 日本防衛産業に明日はあるか 日の丸兵器はガラパゴス Interview「日本の経験不足は補える」ロッキード・マーティン日本法人社長 チャック・ジョーンズ 軍事研究「解禁」へ。狭まる東大包囲網 Interview「輸出振興と東大の動きは裏表」拓殖大学特任教授、元防衛相 森本 敏
-
-「『働かないおじさん』は給料ばかり高い」と、叩かれることも多い年功賃金制度が日本企業から消えつつある。しかし変わって登場した「成果主義」も成功したとは言えない。次に登場したのが「役割給」だ。 日本の賃金制度はどこへ向かうのか?電機業界の事例や海外の報酬制度、「アジア年収データ全比較」などから日本の会社の将来を見ていこう。 本誌は『週刊東洋経済』2015年5月30日号掲載の18ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 成果主義が総崩れしたワケ 40代以上は賃金がフラット化 海外のジョブ型雇用慣行の採用、報酬の仕組みを全公開 ブラック企業の特徴は、日本型と欧米型の混用にあり 電機業界に見る人事改革のうねり 外資はどうしているか? 18職務 アジア年収データ全比較 誤解だらけの「残業代ゼロ法案」 Interview 「『残業代ゼロ』と考えるのは間違っている」大内伸哉/神戸大学教授 Interview 「多様な働き方を導入しないと世界との競争に負ける」橘・フクシマ・咲江/経済同友会前副代表幹事
-
-首相官邸への侵入事件を皮切りに、日本を騒がせているドローン。だが、日本ではドローン利用に関する法規制が整備されていない。空撮やホビー、配送などドローンの需要は急拡大しているが、期待どおりにドローン産業が立ち上がるかは、極めて不透明な状況だ。本格的な盛り上がりを見せるドローン産業で、日本はどう対応すべきなのか。 本誌は『週刊東洋経済』2015年6月20日号掲載の12ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● ドローンバブル沸騰 分解マスターが大解剖 ドローン王、現る。中国発DJIの素顔 日本のご飯の3杯に1杯はヤマハの“ドローン”育ち
-
3.0工場見学第三弾。洗剤、化粧品、お札、漢方薬、ランドセル、靴からお札まで……。おなじみの製品はどのように作られているのだろうか。自動化が進む工場や、完全手作りの工房、最先端の技術が使われている工場などさまざまな現場に潜入! 牛乳パック、新聞が新品の製品に生まれ変わるリサイクル工場や、漢方医学の歴史も勉強できる記念館など、夏休みの自由研究に使えそうな工場紹介も! 本誌は2011年6月2日発行の『ニッポンの工場』掲載の26ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 【資生堂】官能検査員が厳格判定。五感が頼りの品質検査 【花王】「アタック」製造の本拠地。日本の「キレイ」を生み出す 【ツムラ】世界最大の漢方製剤工場。漢方記念館で徹底的に勉強 【クラレ】人気ランドセルを支える「超極細」と「レンコン」 【JX日鉱日石エネルギー】原油処理能力は国内最大級。関東首都圏へのガソリン供給担う 【大建工業】4万種類のドアが製造可能。生産効率でも業界首位 【日本製紙グループ】牛乳パックや古紙が新品の製品に生まれ変わる 【国立印刷局】日本の技術の粋を結集。緊張感漂う紙幣の製造現場 【大塚製靴】100年以上続く靴メーカー。完全手作りの工房に潜入 町工場をアトリエへ
-
-格差の進む日本。2012年の相対的貧困率は過去最悪を更新して16.1%と、国民の6人に1人が貧困状態。さらに子育て中の一人親世帯では54.6%にも達する。 特に厳しいのが母子家庭だが、若い女性の貧困も問題だ。 元AV女優・日経記者という異色の経歴を持つ著者が書く「セックスワーカーの貧困」、子どもの貧困に取り組む大人たちの取り組み、生活保護の実態など女子の貧困に迫った。 本誌は『週刊東洋経済』2015年4月11日号掲載の22ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 元AV女優・日経記者が歩く女性の貧困最前線 6世帯に1世帯が貧困。困窮する子育て家庭 column「2分の1成人式がえぐる心の傷」 住民の「おせっかい」が子どもを貧困から守る 生活費も家賃もカット。改悪続く生活保護制度 column「カード支給は違法? 揺れる大阪市」 はびこる生活保護への誤解 厚労省が物価を偽装? 揺らぐ保護費削減の根拠 国際比較で見た「生活保護」。日本の特徴は家族まかせ 自立支援法は機能するか Interview 私ならこうする! 慶応義塾大学教授 竹中平蔵/首都大学東京教授 阿部彩/ビッグイシュー日本代表 佐野章二
-
-医者を目指す若者が増えている。医学部の延べ志願者数は、2007年度の12.8万人から14年度は16.9万人まで増加。中でも近年目立つのが、一般家庭の子どもの受験だ。 ある医学部受験専門予備校では、生徒の親の職業は、半分が医師、2割が歯科医師、そして3割が経営者や一般のサラリーマン。「8割が医師の子どもだった10年前とは様変わりした」という。私大医学部は医師の家庭だけが受ける特別なもの、という時代ではなくなっている。 何が若者を引き付けるのか。医学部受験の現状、大学病院の実態を探った。 本誌は『週刊東洋経済』2015年3月21日号掲載の23ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● Part1 過熱化する医学部受験 一般家庭の志願者が増加。吸い寄せられる「理系秀才」 9歳からの「ロケットスタート」 ここまできた医学部入試。新しい傾向と対策 Interview 天野篤●天皇陛下執刀医・順天堂大学医学部教授 Part2 「白い巨塔」の裏側 医学部の知られざる内実 column「国試“9割”合格の嘘」 群馬大外科医の「暴走」 【覆面座談会】勤務医はけっこう大変 有力教授の「副収入事情」 被災地医療は変わるか。東北の「医師不足」
-
-2015年秋、ネットフリックスがついに日本に上陸する。月10ドル前後の定額で、映画・ドラマがインターネット経由で見放題。ケーブルテレビ(CATV)やDVDレンタルから利用者を奪い、欧米で6200万人の会員を集める有料動画配信の最大手だ。 すでに吉本興業やフジテレビが、ネットフリックスに独自番組を供給することを発表している。知られざるネットフリックスの全貌をリポート。創業者リード・ヘイスティングス氏の独占インタビューも掲載! 本誌は『週刊東洋経済』2015年4月25日号、5月23日号掲載の18ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● NETFLIX 動画の覇者の正体 InterviewHJホールディングス社長 船越雅史「おカネをかけずにいい作品を作る」 Interviewエイベックス通信放送取締役 村本理恵子「黒船上陸で市場が活気づく」 米国を揺るがすネットワーク中立性 ネットワーク中立性は日本でもイシュー化しうる Interviewネットフリックス共同創業者・CEO リード・ヘイスティングス 「今秋、日本で未来のテレビが始まる」
-
-僕たち、ほぼ、上場します――。 「おいしい生活。」「不思議、大好き。」、コピーライターの代名詞的存在だった糸井重里氏が「ほぼ日刊イトイ新聞」を始めて17年。月間訪問者数130万を超える人気サイトとなった今、新たな仕掛けに打って出る。「できるだけ小さく上場したい」と語るイトイ的、「ボクと会社と市場とおカネ」。 本誌は『週刊東洋経済』2015年4月18日号掲載の14ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● Interview 糸井重里「ボクと会社と市場とおカネ」 糸井重里の人脈図「堤清二さんからビジネスを学んだ」 「ほぼ日」ってどんな会社? 大ヒット生むイワシの群れ
-
-国際会計基準(IFRS)が日本で導入されてから5年。2015年度からは26社が導入予定だ。 「何社が導入予定」という社数報道が過熱する一方で、IFRS導入企業が実際にどんな決算をしているかの中身についてはこれまで検証されてこなかった。 同業他社との比較が困難な異常事態や、ROEの急激な低下、IFRS導入で黒字化する不可思議なからくりに迫る! 本誌は『週刊東洋経済』2015年4月11日号掲載の14ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● IFRSの減損は謎だらけ! IFRS導入企業はどう会計処理をしているのか ソフトバンク「子会社で減損21億ドル計上だが『認識しない』」 三菱商事「過去に減損したローソン株で600億円の『戻入益』を計上」 Interview「IFRSに恣意性は入らない」内野州馬/三菱商事CFO キーパーソンインタビュー「減損も戻し入れも頻繁なのがIFRS」辻山栄子/早稲田大学教授 IFRSの不可思議 旭硝子・日本板硝子「同業なのにこんなに違う営業利益の中身」 武田薬品・アステラス・中外「三社三様のコア営業利益を発表し、それを最も重要視」 総合商社「IFRS導入で分母が膨らみROEが低下」 そーせいグループ「連続赤字のベンチャーがIFRS導入で黒字化」 キーパーソンインタビュー「のれん償却は何年がいいのかが難しい」ハンス・フーガーホースト/IASB(国際会計基準審議会)議長 IFRS適用・予定の73社
-
-『週刊東洋経済eビジネス新書・工場見学シリーズ』第二弾! ハム、お菓子、ウイスキーから納豆まで……。おなじみの食品の工場をのぞいてみたら、どの工場も作り手のこだわりや熱い思いが込められていた! 一般見学を受け付けている工場も多く、見学後に味わえる出来たての生ビールやお菓子、持ち帰り用のお土産も楽しみの一つ。今年の夏休みは親子で工場見学してみよう! 本誌は2011年6月2日発行の『ニッポンの工場』掲載の26ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 身近な食品のワクワク工場 サントリー・山崎蒸溜所「本場スコットランドも顔負け。本物にこだわるウイスキー造り」 column「神の舌を持つ男」 サントリー・白州蒸溜所「天然水工場も併設。珍しい高地の蒸留所」 明治「職人が食感をチェック。出来たての試食も可能」 キリン「たっぷり手をかけた出来たてビールを満喫」 大塚製薬「大豆粉にこだわり、『カロリーメイト』も応用」 コスモフーズ「ローソンのスイーツ躍進を裏で支える手作り食品工場」 サイゼリヤ「安さ、鮮度を支える究極の“効率”工場」 味の素「薫って触って味わって。五感で感じるほんだし工場」 日本ハム「国内最大のソーセージ工場。見学から手作り体験まで網羅」 column「本場ドイツでも学んだマイスター」 タカノフーズ「国内最大の納豆工場。省人化で低価格を実現」
-
-2000年初頭、日本ではバイオベンチャーブームが起きていた。が、現在までに上場にこぎ着けた会社は三十数社。各社とも技術面での実力はすごく、ノーベル賞を受賞したiPS関連の技術、遺伝子分析、細胞生物学、免疫学などいずれも学問的な水準は世界でもトップ級だ。だが、その大半が研究開発費先行のため赤字経営だ。 そんな中でも黒字を叩きだしている企業は存在する。ミドリムシで有名なユーグレナなど、代表的なバイオベンチャーを紹介する。 本書は、東洋経済新報社のサイト「会社四季報オンライン」に掲載された連載「大化け創薬ベンチャーを探せ!」を加筆修正のうえ制作しています。 ●●目次●● 日本のバイオベンチャー ペプチドリーム「『赤字が常識』の創薬ベンチャーが、4期連続最終黒字達成」 Interview 窪田規一/ペプチドリーム社長「創薬ビジネスの将来」 プレシジョン・システム・サイエンス「バイオ分析装置で医薬の研究現場を変える!」 Interview 田島秀次/PSS社長「アボットとの共同研究中止で中核技術に集中」 ユーグレナ「ミドリムシで快進撃。『緑汁』から燃料、医薬へ!」 Interview 出雲充/ユーグレナ社長「大量培養法では特許を取らず、秘匿情報化」 UMNファーマ「実務家に経営トップを禅譲し、創薬専業から製薬メーカーへ!」 Interview 平野達義/UMNファーマ会長兼社長「会社の形が変わる中で、2度目の社長就任」 メディネット「『お家騒動』終結で注目の今後」 Interview 木村佳司/メディネット会長兼社長「『免疫』をキーワードに起業を決意」 そーせいグループ「480億円で英社買収の勝算」 Interview 田村眞一/そーせいグループ社長「480億円を投じた買収は無謀な賭けか」
-
-バンダイのガンプラ工場から海洋堂のフィギュア開発現場、新幹線や路線バスの製造所まで、各ジャンルのマニアの聖地を探訪。マニアたちを満足させるものづくりの世界は、徹底的にこだわり抜かれた、マニアックな世界だ! そこにあるのは、モノだけではない。おのれの技術と情熱の限りを注ぎ込む、職人たちの物語が繰り広げられている。 本誌は2011年6月2日発行の『ニッポンの工場』掲載の27ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● マニア垂涎の現場 バンダイ「憧れと羨望のガンプラ工場」 ヤマハ「最高級ピアノの工場」 海洋堂「感性で突っ走るフィギュアNO.1企業の横顔」 イワコー「人気のおもしろ消しゴム。手作りで長寿ヒット」 全日本空輸「6カ月先まで予約はいっぱい! 大型旅客機を間近で見る興奮」 川崎重工業「国内最大の車両工場。鉄道マニアの聖地」 大和軌道製造「多様なレールが織りなす技」 モリタ「日本最大の消防車工場」 三菱ふそうトラック・バス「路線バスから観光バスまで。バス造りなら全部お任せ」
-
-「14年7月23日に社長を解任された大塚久美子取締役が、会長兼社長で実父の大塚勝久氏を含む現経営体制を一新するよう、『株主提案』を検討していることが明らかになった――。」 父と娘が争った大塚家具の“お家騒動”は、15年1月の『週刊東洋経済』スクープで明らかになった。父と娘が解任の応酬をし、世間の注目を浴びた騒動をじっくり解説。大塚家具だけではない、ロッテ、雪国まいたけ、大王製紙のお家騒動や創業家と企業との争いも追った! 本誌は『週刊東洋経済』2015年1月24日号、3月14日号、3月21日号等掲載の19ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 父に解任された娘が反旗 父娘が“解任”の応酬 「娘は“失敗”だった」。大塚会長が宣戦布告 大塚家の相続問題が絡む 総会終わる。果てなき両者の攻防 創業家の乱 ロッテ「兄弟の仲を父が裂く。韓流お家騒動の顛末」 Interview「ビジネスモデルに限界も」神戸大学大学院教授 三品和広 雪国まいたけ「果てしない内紛劇めぐる人とカネ」 Interview「もう反対はしない。雪国にも戻らない」雪国まいたけ創業者 大平喜信 大王製紙「業界再編の思惑も絡む」
-
-ホンダにアクシデント発生――。13年に鳴り物入りで投入した3代目「フィット」が、短期間に5回のリコールを出し、タカタ製エアバッグのリコール問題では、対応のまずさでホンダに批判が集中。米国の安全当局に対する報告漏れという失態も明るみに出た。ホンダにいったい何が起こっているのか。 6月に退任予定の伊東社長の独占インタビューや創業者・本田宗一郎氏の半世紀前のインタビューも掲載。本田氏は「50になってから重役になるなんてことが不思議でしょうがない(中略)。日本の経営者というものはもう古すぎる」と語っていた。50代の新社長の下、ホンダは復活できるのか。 本誌は『週刊東洋経済』2015年1月17日号等掲載の26ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 独占インタビュー 本田技研工業(ホンダ)代表取締役社長 伊東孝紳 飛躍の準備は万全か。ホンダ社長交代の狙い 【ホンダ3つの失敗】危機は日米同時多発的に起きた 600万台、6極体制。「6の呪縛」がなかったか 創業者ならどうする? 本田宗一郎の「格言」 伝説の名経営者インタビュー 本田技研工業社長(当時) 本田宗一郎 ホンダにモノ申す! モータージャーナリスト清水和夫氏の直言 やまぬ、タカタショック NHTSAに集まる批判
-
-2015年1月、国内航空3位のスカイマークが破綻した。1996年の設立後、日本の空の自由化を牽引してきたスカイマーク。一時は高収益体制を築き上げた異端の経営者・西久保氏は、巨額の債務を残して舞台を降りた。最後の独立系勢力は、このまま消えてしまうのか。 経営破綻の原因となった、エアバスA380購入計画の詳細について解説。西久保氏はなぜ無謀ともいえる極端な拡大戦略をとってしまったのか。創業者の澤田秀雄氏(エイチ・アイ・エス会長)の独占インタビューも掲載。 本誌は『週刊東洋経済』2014年9月6日号、2015年2月14日号、28日号掲載の20ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 折れた「叛逆の翼」 Interview慶応義塾大学商学部教授 中条 潮「官主導の共同運航案にはあきれた」 スカイマークを「買う」男、佐山展生の勝算 財務で読み解くスカイマーク。破綻は必然だった 航空業界の「革命児」は勝機を読み違えた 創業者 澤田秀雄(エイチ・アイ・エス会長)激白 元祖ベンチャー経営者・澤田秀雄とは 西久保氏はスカイマークに私財108億円をつぎ込んだ スカイマーク破綻で地方空港に激震走る スカイ再生のカギ握るエアバス10機の重荷
-
-牛丼チェーンの「すき家」やファミレス「ココス」などを傘下に抱えるゼンショー、日本マクドナルド、さらには居酒屋のワタミ……。外食業界を代表する大手企業が、2014年度決算で多額の赤字に陥った。競争激化に原材料高、人手不足などの問題を抱える外食業界は、この窮地を克服することはできるのか。 また、「マクドナルドの不振は、原田前社長時代の改革のツケ」との批判は正しいのか。2006年の『週刊東洋経済』掲載記事から原田時代に迫る。さらに、ブラック問題で非難集中「すき家」の小川社長インタビューも掲載! 本誌は『週刊東洋経済』2014年12月6日号、2006年8月5日号掲載の21ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 逆風吹き荒れる外食業界 日本マクドナルド「チキン問題で巨額赤字に」 原田改革の超真相 Interview 原田泳幸 日本マクドナルドホールディングス代表取締役会長兼社長兼CEO(当時) 松屋、吉野家、すき家「泥沼の安売り競争で疲弊」 すかいらーく「勝ち残りへの改革続く」 ワンオペの大きな代償。すき家、営業縮小で窮地 バイト集まらず、外食各社が悲鳴 Interviewゼンショーホールディングス会長兼社長 小川賢太郎「すき家のブラック批判にすべて答える」
-
-「日本礼賛本」がベストセラーになり、テレビでは外国人が日本を褒め称える番組が数多く放送されている。ネットの世界では「中国人が日本の美点を紹介した」情報が大人気。まるで日本礼賛ブームといえる状況だ。だが、ここはクールに日本の実力と立ち位置を再点検したい。 クールジャパンの実態、「ニッポンすごいぞ」商法の背景など日本礼賛ブームのなぞに迫るほか、トンデモ本ではない「いま読むべき日本論」の名著を紹介。 本誌は『週刊東洋経済』2015年1月17日号掲載の26ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 世界が見たNIPPON いま読むべき日本論30冊 ベストセラーにご用心。まず俗論を疑え 野口悠紀雄vs.御厨貴「高度成長の幻想を暴く」 アジアとの一体化こそ活路 お手軽観光立国に喝! クールジャパンなんて誰も知らない 愛国本読者の正体 自己過信では日本が沈む 盲目のスーダン人博士から辛口エール「型にはまるな日本人」
-
-固定価格買い取り制度(FIT)の導入で膨張した太陽光発電ビジネス。だが、FITへの申し込みが殺到したため、2014年9月25日に九州電力は受け入れに対する回答保留を発表。立て続けに北海道、東北、四国、沖縄電力も新規接続契約保留を発表し、多くの事業者に衝撃が走った。 バブルが沈静化し正常に戻るだけなのか、あるいは普及そのものが停滞してしまうのか。ソーラービジネスは大きな岐路を迎えている。 本誌は『週刊東洋経済』2014年12月13日号掲載の20ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● どうする再生可能エネルギー 中小企業も飛びついた、ソーラー投資の“魅力” 九電ショックの波紋。バブル崩壊に焦る企業 太陽電池メーカーは中国勢と淘汰競争へ パワコン業界も環境一変。コスト競争力がカギに 【風力・地熱】ソーラー以外の再生可能エネルギーはどうなった? 日本は今こそドイツに学べ! 再エネの最大限導入へ国に問われる本気度 【論客2人に聞く】再エネFITはこうすべき
-
1.0実家問題に直面する人が増えている。親が残した荷物の整理から相続、空き家管理、売却まで。40代以上の世代は誰しも「実家の片付け」問題を抱えていると言っても過言ではない。 核家族化が進み、親のいなくなった実家は空き家として放置される。放置された実家が増えれば、地域にも影響を与える。 実家の片付けに直面した12人の実体験を詳細にリポート。そのほか実家にまつわる問題を総まくりした。個人も、社会も、実家問題に真剣に向き合う時が来ている。 本誌は『週刊東洋経済』2014年8月23日号掲載の26ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 誰もが直面「実家の片づけ」 【アンケート】実家の片付けはこんなに大変! 【生前の片付け】健在な親が抵抗に回る きっかけを逃さない、親とのコミュニケーション術 初心者でもわかる! 整理整頓の極意 【相続後の片付け】片付けはまるで「修行」 これだけは知っておこう。実家の扱い方 空き家管理・遺品整理サービスを上手に使う リバースモーゲージは本当に使えるか 「家賃30年保証」にご用心 【実家の売却・賃貸】知人経由の賃貸でもめ事も
-
-子どもと向き合えず、雑務に忙殺される教師。心を病み、学校を去る教師。そして着々と進行する教師の非正規化──。学校現場が大きく揺れている。 「仕事量が多すぎて、自分の子どもに勧める仕事ではない」 「単なるサービス業か?と思ってしまうことがある」 教師たちの気持ちや働き方の現状を無視したまま、新たな施策が押し付けられようとしている。 教育現場で今何が起きているのか。日本の教育の今を追った。 本誌は『週刊東洋経済』2014年9月20日号掲載の34ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 先生たちのSOS ルポ1 先生が辞めていく ルポ2 燃え尽きる先生 ルポ3 ブラック化する職場 ルポ4 多忙と疲労の果てに 現役教師・覆面座談会「教師は“24時間受付可能”と思われている」 大公開 忙しい先生の実像と本音 学力世界上位でも低い先生の満足度 Interview「北風だけじゃ耐えられない」教育評論家 尾木直樹 Interview「学力は家庭と学校の力の掛け算」大阪大学大学院人間科学研究科教授 志水宏吉 これが最強・秋田モデルだ! ルポ 広がる子どもの学力格差と貧困 進学塾が教員研修。学力アップにあの手この手 「花まる学園校」の衝撃 (佐賀県武雄市) Interview「公教育はもう限界だ」武雄市長 樋渡啓祐 Interview「メシが食える大人にする」「花まる学習会」代表 高濱正伸 橋下教育改革は何をもたらしたのか 始まった教育のICT利用
-
-オバマ大統領誕生の熱狂から6年。米国が再び岐路に立たされている。 金融危機から景気は回復し、株価は最高値圏を推移しているが、その恩恵を受けているのはわずか一部のスーパーリッチだちだ。スーパーリッチの1%とその他大勢の99%の格差は広がり、政治的な二極化も加速。長期的な経済停滞の懸念も浮上している。 国中から聞こえる不協和音を奏でながら「強いアメリカ」はどこへ向かうのか。 本誌は『週刊東洋経済』2014年11月1日号掲載の24ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● オバマの夢から覚めた迷える大国はどこへ 格差に翻弄されるニューヨーク Interview ローランド・フライヤー/ハーバード大学経済学部教授 「ピケティのアイデアでは米国の格差は解決しない」 カリフォルニアの夢と絶望 図でわかるアメリカ50州の「格差」 大都市だけじゃない! 顕在化する州内格差 Interview ジョージ・パッカー/『ザ・ニューヨーカー』誌記者、『綻びゆくアメリカ』著者
-
-私たちの生活にeコマース(電子商取引)が登場して15年ほどだ。今では毎年10万程度の新規オンラインショップが立ち上がり、ネット上で競い合う。 その中でオムニチャネルなど多様な戦術に長けた28店舗を一挙紹介する。ショップ開設の関係者らに必ずや参考になること請け合いだ。ぜひ、“生きた教科書”として活用してほしい。 (注)オムニチャネルとは、実店舗やネット上のストアに加えて、ソーシャルメディアやブログなど各種の手段を使って、顧客と接点をもとうとする考え方のこと。 本誌は『週刊東洋経済増刊 eコマースの強化書』(2014年10月3日発行)掲載の34ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● SAKELIFE「定期購入のサービス使い『日本酒好き』を育てる 」 夢展望「スマホ顧客が8割。リアル店を戦略化」 ドゥクラッセ「体型気になる世代のオシャレを徹底支援」 丸善&ジュンク堂ネットストア「店舗在庫を開示、絶版本も手に入る」 サンリフレプラザ「追加費用請求せず。価格の透明性徹底」 ファクトリエ「初の工場ブランド。高級シャツが激安」 メルカリ「安全性をウリに支持獲得。テレビCM打ち500万DL」 クリーマ「ハンドメイドECの先駆け、個人間売買で安心感を醸成 」 bento.jp「発注2分で即届く。型破りの弁当配達」 KAJIN「大手にも負けないフォーマル子供服」 エソラワークス「子供の描いた絵を『ぬいぐるみ』に」 VEGEO VEGECO「社長は現役大学生。面倒、ムダを解消」 竹虎「背水の陣でEC販売。虎斑竹専門店の挑戦」 ワジャ「個人向け少ロット管理でニッチトップを複数運営」 オジエ「豊富な襟型で需要を深耕。常連客には80代男性も」 サンコーレアモノショップ「面白い商品だけで年商8億円を稼ぐ」 漫画全巻ドットコム「漫画全巻一気買いを開拓。イラスト入り“箱”が人気」 DIY-TOOL.COM「国内最大級の工具サイト。体験を軸にファンづくり」 チーズハニー「個性派チーズ200種。写真で食べ頃解説」 復刊ドットコム「懐かしい本を投票で復刊。ネット時代の新ビジネス」 ポポンデッタ「品ぞろえ増やして差別化。価格競争から距離を置く」 ピクトケーキ「スマホでデザイン、2日で写真ケーキ」 MARUMARU「ママの声を商品化、伸び盛りの子供服」 スーパーデリバリー「『ネット問屋』の先駆者。厳格ルールで信頼を獲得」 ペットビジョン「動物病院を買収し安価な医薬品、療法食を提供」 SUPER8SHOES「商品伝える秘密は蘊蓄とヒップ画像」 和える「日本の伝統産業を次世代につなげる」 リリー&アリー「育児中の主婦が子供の宝石箱深耕」
-
-イスラム教の教えに従って生産された食べ物を示す「ハラル」。ハラル食品を提供する店舗や加工食品にはハラル認定マークが表示される。いま日本国内では、ハラルビジネスがカネになるとみて、ハラルマークの認証団体が乱立している。だが、中には怪しげな団体も多く、そうした団体が国益を損ねる可能性も出てきた。 何が問題で、そのように対処すべきなのか。ハラル市場をめぐる動きを追った。 本誌は『週刊東洋経済』2014年7月12日号掲載記事や「東洋経済オンライン」掲載記事の加筆に加え、書き下ろし記事も含めて電子化したものです。 ●●目次●● そのハラル、大丈夫? マーク認証団体が乱立 増殖するハラルレストランが背負うジレンマ ブルボン「プチ」が巻き込まれたハラル騒動 ニセモノハラルが蔓延する「観光立国」の瀬戸際 ムスリムが日本で最も困ること なぜかヨックモックが中東でバカ売れに!
-
-仕事で調べ物をする時に、ウィキペディアのみを見ていませんか? プレゼン資料に3D円グラフを多用していませんか? インターネット全盛のデジタル時代であっても、五感を活用するアナログ的な手法の大切さは変わりません。 安易なウェブ検索に頼らず、五感を使ってインプットし、「シンプルで、美しく、わかりやすい」アウトプットを目指しましょう! プロがわかりやすく解説します。 本誌は『週刊東洋経済』2014年9月6日号掲載の32ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● プロに学ぶビジネススキル Part1 デジタルに依存しない! 情報収集術 質を高める聞き方 調べる、リサーチの大原則 人を観察する 良書の見つけ方 身になるノートの取り方 不要な情報を捨てる 仕事に集中できる文具の使い方 スマホアプリで名刺情報を一括管理 Interview GMOインターネット会長兼社長/熊谷正寿 座談会「マッキンゼーで学んだこと 学べなかったこと」 「頭いいやつら」の理論で終わらない Part2 小手先に頼らない! アウトプット術 伝わる! プレゼン資料 使える英語のプレゼン 心に響くスピーチ Interview 『暮しの手帖』編集長/松浦弥太郎
-
-普段何げなく服用している薬は必要なのだろうか。そして、本当に安全なのだろうか。薬を飲めば症状は抑えられる。だが、その根本原因をなくす努力を忘れていないだろうか。 2015年は、ノバルティスや武田薬品工業をはじめとする製薬メーカーが、相次いで不祥事を起こしたのも話題となった。製薬業界の信頼が揺らぐ中、本当に必要な知識を身に付けたい。 本誌は『週刊東洋経済』2014年9月13日号掲載の22ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● もうクスリはいらない?! 「基準値」とは何だったのか 降圧剤は飲まなくていいのか 「薬が病気を作る」は本当だった! 調剤薬局も選択の時代 【記者体験記】薬代の“余計な費用”を実感 特許抜けでもブロックバスター 煩わしい身近な病気もいよいよ根治が間近に 【エボラ出血熱】世界中の注目集める日本発のインフル薬 高額療養費にメスを入れる。「費用対効果」の導入 医療界の利益相反めぐり業界が踏み出す苦しい一歩 Interview 日本製薬工業協会会長 多田正世
-
-2015年は日本による韓国の統治が終了してから70年。日韓基本条約で、植民地時代の「清算」を終えてからも50年を迎えます。 それだけの歳月を重ねても、受難の記憶は消えるどころか強化されてきました。ビジネス上は緊密化を進める日韓の間に、歴史問題はいまだに深い亀裂を走らせています。 また、尖閣問題を抱える中国は、歴史を利用して日本包囲網を形成中です。 日本のビジネスパーソンが、いま知っておくべき歴史問題とは。 本誌は『週刊東洋経済』2014年9月27日号掲載の24ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 日中韓 不信と憎悪はなぜ続く 歴史問題の焦点 「歴史認識と政治・経済を分離せよ」東京大学大学院准教授 川島 真 【慰安婦問題】「日本が世界に言うべきは何か」神戸大学大学院教授 木村 幹 【ソウル現地報告】「慰安婦問題のすれ違い」毎日新聞ソウル支局長 澤田克己 アジアの歴史問題に米国からの視線 「中国では『歴史地雷』にご用心」ジャーナリスト 富坂聰 「中国を動かすコンプレックスの正体」米シートンホール大学准教授 汪錚 Interview小林よしのり「愛国バカは国を滅ぼすぞ」 反中・嫌韓の深層を読む 「戦前80年の教訓を見据えよ」東京大学名誉教授 坂野潤治 「永続敗戦国家 日本の孤立」文化学園大学助教 白井 聡 「『国家の歴史』の呪縛を解こう」中国・南開大学准教授 熊培雲 石橋湛山のアジア認識に学ぶ
-
4.0きつい、汚い、給料が低い、離職率が高い…。介護職にはこうしたイメージが付きまとう。だが、その多くは“誤解”だ。若い職員が生き生きと働き、利用者の笑顔が絶えない職場が少なからずある。なかなか心を開かない利用者と関係を築こうと試行錯誤を繰り返したり、おむつをつけずトイレに誘導する取り組みを進めていたりと、その仕事内容は実にクリエーティブだ。 現在、日本の介護職員の数は約150万人。団塊世代が一斉に75歳以上となる2025年には、介護保険の利用者数は現在の約1.5倍にまで増え、そのときに必要とされる介護職員は237万~249万人と推計されている。人材確保が今以上に差し迫った状況になる。 さまざまなイノベーションが起こりつつある介護の現場に迫った。 本誌は『週刊東洋経済』2014年5月17日号掲載の28ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● もう3Kとは言わせない 介護職の賃金は低いのか。広がる格差の原因は? 介護現場のいろいろなKの真実 事業所の多くは低離職率。カギはマネジメント 現場からキャリアアップ。介護の仕事をどう極める 職業能力のレベルを測る「キャリア段位制度」って何? 介護現場カイゼン(1)「辞めない!集まる! 人手不足の克服法」 目指せ!甲子園優勝。変わる現場の士気 介護職の若者たちに広がる情報共有の場 介護保険に縛られない! 利用者目線の新ビジネス 参入相次ぐ介護ロボット、普及にはハードルも 介護現場カイゼン(2)「利用者と職員のためにムダをなくして効率化」
-
-2014年、激安スマホが世界各地で続々と登場。アップル、サムスンの2強が支配してきたスマホ市場に大きな地殻変動を起こしつつある。 14年に世界で販売されているスマホの平均価格は前年比で14%下落し、初めて300ドルを割り込む見通しだ。市場の主役は今や、アンダー200ドルのスーパーチープなのだ。 激安スマホの製造現場・中国への突撃ルポ、激安スマホの分解・分析、日本の激安スマホベンチャーリポートなど、激安スマホを徹底解明。これからは激安スマホが主流になるか! 本誌は『週刊東洋経済』2014年9月20日号掲載の18ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 激安スマホ、世界各地で続々登場 製造現場に突撃ルポ。スーパーチープの源流を探る 鴻海ブランドのスマホは登場するか 小米は日本製部品の活路になる 日本でも続々登場、激安スマホベンチャー 携帯会社はどう動く?
-
-「うまい、やすい、はやい」で有名な牛丼の吉野家社長・安部修仁。ミュージシャンを目指して福岡から上京した青年がアルバイトとして入社し、社長になって22年。 1980年の倒産、2004年BSE騒動による牛丼販売休止、激しい価格競争…。吉野家の浮沈をすべて見てきた男が、経営の第一線から退く。一つの時代が終わろうとしている。 本誌は『週刊東洋経済』2014年8月9・16日合併号巻頭特集の14ページ分を抜粋して電子化したものです。 ●●目次●● 安部修仁と吉野家の時代 Interview 吉野家ホールディングス会長 安部修仁 「規模は問題じゃない。肝心なのは存在感だ」
-
-「移民は受け入れたくないが、安い労働力は欲しい」という日本。自国にとって都合のいい方法で、安価な労働力を手に入れてきた。それが「外国人技能実習生」だ。 「開発途上国への技能移転」を名目に始まったこの制度、実際は時給650~700円程度の法定最低賃金で単純労働をさせているのがほとんどだ。 単純労働での外国人受け入れを国策として認めてこなかった日本で、技能実習制度はその受け皿となってきた。制度のひずみに目をつぶったまま、拡大に向けた議論が進む。 本誌は『週刊東洋経済』2014年8月2日号第2特集の10ページ分を抜粋して電子化したものです。 ●●目次●● 搾取?それとも国際貢献? 人出不足を補う技能実習制度 消えた実習生 夢見る若者と即戦力求める企業 もう日本には戻らない
-
-東日本大震災の復興事業や2020年の東京五輪に備えた施設整備など、この数年で建設需要は急拡大。技能労働者の不足で、工事にかかわる人件費はうなぎ上りだ。 国内生産が上向いた自動車産業にも労働者が集まり、小売りや外食などのサービス業にも人手不足が飛び火。牛丼のすき家が人手不足のため一時休業に追い込まれる店舗が相次ぐなど、多くの業界が人手不足だ。 だが、今の日本は繁忙なのに儲からない「豊作貧乏」になってないか? 人手不足の正体に迫る! 本誌は『週刊東洋経済』2014年7月26日号第2特集の20ページ分を抜粋して電子化したものです。 ●●目次●● 設備も足りない「豊作貧乏」 人手不足が迫る発想の転換 陸運 値上げ、女性活用に活路 Interview ヤマト運輸社長 山内雅喜 自動車 エンジニア枯渇の危機 建設 職人と現場監督が不足。民間工事は先送りも 小売り・外食 時給1000円が目前。出店競争はもはや限界 Interview ワタミ社長 桑原 豊 システム開発 人材争奪戦の激化で業界の「ホワイト化」が進む 設備不足が成長を止める 電機 デジタル家電不振が傷に 中小企業 老朽化がボトルネック。設備投資は動きだすか 不動産 倉庫の新規供給が半減。首都圏湾岸はもう限界 通信 膨張続くデータ通信量。綱渡りの基地局工事
-
-最近の日本企業は、新興国の勢いに押されて元気がない・・・なんて言われますが、技術力や開発力、日常業務の仕組みはまだまだ強い! あなたの知っているあの会社の、知られざる“すごい現場、すごい場所”を大公開します。 『週刊東洋経済』の人気連載を電子書籍で完全収録。誌面に載せられなかった写真や、電子版オリジナル特典として『東海道新幹線の総合事故復旧訓練の一日』も収録しました。 本誌は『週刊東洋経済』2013年11月16日号から2014年6月28日号までの連載31ページ分に、未掲載写真や電子版特典を付加したものです。 ●●目次●● ★電子特別付録 東海道新幹線・総合事故復旧訓練の一日 完全遮断で調べ尽くす 日産自動車【電波暗室】 飛行機の心臓部を支える 富士重工業【オートクレーブ(加熱圧力釜)】 切る・削る・磨くを極める ディスコ【アプリケーションラボ】 手作業の梱包にこだわる オルビス【東日本流通センター】 細やかな監視が通信品質を守る NTTドコモ【ネットワークオペレーションセンター】 150万トンの塩を素材に 東ソー【南陽事業所】 世界中の建機を「見える化」 コマツ【グローバル販生オペレーションセンタ】 安全運行を支える実地体験 JR東海【総合事故復旧訓練】 自販機大国ニッポンを支える 富士電機【三重工場】 世界ブランドの品質を造る カシオ計算機【羽村技術センター】 世界最速、被災地支援にも一役 トーモク【館林工場】 「持つ」ファブレスの強み ザインエレクトロニクス【本社】 タイヤの最先端を追う ブリヂストン【技術センター】 全国650キロメートルの知られざる道 NTT東日本・西日本【とう道】 全自動で実現した超大量生産 中村屋【つくば工場】 極寒・猛吹雪にも屈さない ヤマハ発動機【低温実験室】 仮想訓練で突発事態に臨む エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン【フルフライトシミュレータ】 トレー“循環”、陰の立役者 エフピコ【関東リサイクル工場】 ガラスが震える試運転 全日本空輸【ANAエンジンテストセル】 燃費世界一に不可欠な実験 トヨタ自動車【風洞実験棟】 1000分の1ミリを削る ジェイテクト【刈谷工場】 信頼担う職人の「耳」 クラリオン【試聴室】 都心地下に潜む巨大な樽 帝国ホテル【楕円木槽の受水槽】 地震再現する縁の下の力持ち 大林組【遠心模型実験装置】 最高の快適性を追求 旭化成ホームズ【温熱技術開発棟】 最高峰で見る異次元の光景 三菱電機【あべのハルカス内・シャトルエレベーター】 経験と勘が守る伝統の音 ヤマハ【豊岡工場】 自由化にらむ工場の深奥部 日清製粉グループ本社【福岡工場】 最新鋭機、建物内に再現 エティハド航空【イノベーション・センター】 ふぞろい許さぬ徹底品質 コクヨ【コクヨ工業滋賀】 マッチ作り、職人技で守る 兼松日産農林【マッチ部 淡路工場】
-
1.0世界6位の海域を誇る日本のEEZ(排他的経済水域)は、“資源の宝の山”。日本人の常識になりつつあるこのストーリーに、政官民が相乗りし、海底資源をめぐる動きは、さながらゴールドラッシュのようである。 建設、エンジニアリング企業を中心に構成される日本プロジェクト産業協議会は、10年に「日本のEEZ内のメタンハイドレートは総額120兆円、海底熱水鉱床は80兆円の経済価値があり、それぞれ年間5.4万人、3.5万人の雇用を生む」という、強気の経済効果をはじき出し、世の中を刺激した。 だが資源開発の専門家たちは、商業化は無理筋で、資源大国のフレーズが幻想であることに気づいている。 “海底資源狂騒曲”の内幕は──。 本誌は『週刊東洋経済』2014年6月21日号第2特集の10ページ分を抜粋して電子化したものです。 ●●目次●● 国産海底資源 バブルの内幕 資源大国という壮大な幻 「海底資源ムラ」の構図 再現される海洋開発の熱狂
-
-日本の製造業がアジア勢に食われて久しい。だが、スゴい工場が日本各地にはまだまだある! 超効率化を目指すコマツ、国内生産比率9割・匠の技で勝負のオークマ、東レを支える北陸の繊維工場…など各地の工場を紹介。 労賃が安いとされていた新興国も、賃金が高騰している。今こそ日本の強い工場復活を! 本誌は『週刊東洋経済』2014年3月15日号第1特集の14ページ分を抜粋して電子化したものです。 ●●目次●● コマツ超効率化へ燃やす執念 Interview コマツ会長 野路國夫 オークマ1ミクロンへのこだわり Interview オークマ社長 花木義麿 地方発の部品ベンチャー、サイベック 東レを支える北陸の繊維 東北を第三の拠点化。トヨタ飽くなきカイゼン キヤノンが試行する“マンマシンセル” Interview キヤノン会長兼社長 御手洗冨士夫 新興国も賃金高騰。今こそ日本の強い「現場」を 高級キットカットは精鋭の手作り
-
-2014年1月にNISA(少額投資非課税制度)がスタートした。制度の認知度はどうなっているのか。そして実際に使っている投資家は、NISAをどう考えているのか。“NISAの本当の使い方”を考えていこう。 また、株主優待も大きな魅力の一つだ。本書ではとっておきの15銘柄を紹介しながら、その魅力を探る。 本誌は『会社四季報プロ500 2014年夏号』『会社四季報2014年夏号で見つけた驚きの銘柄』から、12ページ分を抜粋して電子化したものです。 ●●目次●● NISA 本当の使い方 NISAのキホンをおさらい NISA口座を通じて投資した人は41% 圧倒的に多いのが株式投資信託と日本株 投資信託? それとも 個別銘柄? NISAに適した商品の選び方 自分の資産の棚卸しを忘れずに 2014年度税制改正でNISAはこう変わる 現行制度では長期投資が困難 1年単位の口座移管が可能に ジュニアNISAや投資対象の拡大も 消費者目線で考える 株主優待投資 (1)どんな銘柄を選ぶか? (2)いつ買うか (3)投資戦略 (4)いつ売るか (5)優待投資失敗例 日々の買い物で優待フル活用 消費者目線の優待銘柄ベスト15 業界別・賢い優待術
-
-少子高齢化、単身世帯の増加、そして増税。いま小売業をめぐる環境が激変している。この難局をどう乗り切るのか。 セブン-イレブンは「第2の創業」を掲げ、オムニチャネルを推進している。ローソンは首位セブンとの差を埋めるべく「イノベーションラボ」を立ち上げ、商品開発に熱心だ。 一方、イオンに買収されたダイエーは長年しみついた赤字体質から抜け出せない。 スーパー・コンビニ業界の新たな勝者は誰だ! 本誌は『週刊東洋経済』2014年4月26日号第1特集の22ページ分を抜粋して電子化したものです。 ●●目次●● 消費税8%後の勝者は誰だ セブン&アイ オムニ戦略の全貌 オムニが小売業の競争原理を変える Interview セブン&アイ・ホールディングス 会長兼CEO 鈴木敏文 H2O×イズミヤ 異業種統合の真意 地方スーパーで進む地殻変動 ダイエーの看板が消える日は来るのか スマホユーザーを呼ぶ、リアル店舗のO2O作戦 激烈! ローソンのオンリーワン戦略 Interview ローソン次期社長 玉塚元一 食品スーパーが都心で熾烈な陣取り合戦 情報武装でおしゃれに変身。進化する100円ショップ 地方スーパーは電子マネーに活路
-
-企業の競争環境が激変し、「社長の器」も大きく形が変わりつつある。 日本マクドナルドホールディングスの経営トップからベネッセホールディングスの次期会長兼社長に就任する原田泳幸。米GEの日本法人会長から、LIXILグループ社長になった藤森義明。日本コカ・コーラの社長・会長から資生堂トップとなった魚谷雅彦……。“職業は社長”ともいうべき「プロ社長」が日本でも続々と登場している。この背景は何なのか。 ユニクロ、サンリオ、ユーシン、タカラトミーの事例や、「後継者がいない!」と揺れるファミリー企業、大企業で生え抜き社長が選ばれる理由などから、ニッポンの社長たちに迫る! 本誌は『週刊東洋経済』2014年5月31日、6月7日、6月14日号短期集中連載の20ページ分を抜粋して電子化したものです。 ●●目次●● 「プロ社長」の真実 ベネッセ「原田マジックは通用するか」 LIXIL「2人の“破壊神”が出会い世界へ打って出る」 資生堂「官僚主義をなくす! 魚谷雅彦の意気軒昂」 後継者はどこにいる? ファミリービジネスの苦悶 サンリオ「帝王学授けた息子が急死。86歳トップは決断できるか」 ユニクロ「息子2人がスピード昇進。ユニクロに世襲はあるか」 ユーシン「2度目の社長公募は成功するか」 タカラトミー「外国人の手腕に託されたトミカとリカちゃんの将来」 生え抜き社長は巨大企業を変えられるのか 日立製作所・コマツ・オムロン Interview オムロン社長 山田義仁 三菱自動車「危機救った指揮官があえて社長を譲る理由」
-
-2011年6月に誕生したLINEは、今や登録ユーザーが4億人を超えた。だが、ゲームや広告事業では、周囲との軋轢も生まれている。 2013年8月に「年内リリース」と発表していた音楽配信「LINEミュージック」も、2014年7月現在いまだにリリースされていない。2013年秋開始としていたネット通販「LINEモール」も、一部機能の公開にとどまり、本格展開は行われていない。 アドバルーンだけでは、法人顧客との信頼関係にひびが入りかねない。世界展開と法人顧客の声に応えるという、難しい舵取りを迫られているLINE。収益化を急ぐ日韓連合に死角はないか。 本誌は『週刊東洋経済』2014年4月26日号巻頭特集の16ページ分を抜粋して電子化したものです。 ●●目次●● 絶好調LINEの盲点 岐路に立つ日韓連合! 携帯電話会社がLINEに反撃 韓国NAVERが抱える強者の悩み LINEは世界で勝てるのか 世界で先行する ワッツアップ 中国市場で立ちはだかる微信(WeChat)の実力 LINEvs.「異業種」ライバル勢 nterview ジャーナリスト 佐々木俊尚 日本のキーパーソン4人に直撃 LINE取締役COO 出澤 剛 LINE上級執行役員CSMO 舛田 淳 LINE上級執行役員法人ビジネス担当 NHNプレイアート社長 加藤雅樹
-
-日本の工場で、事故・事件が相次いでいる。化学メーカーではこの数年に深刻な事故が頻発した。いずれも死傷者を伴うものだった。 消費者の不信を買ったアクリフーズの冷凍食品・農薬混入事件。逮捕された契約社員は自身の待遇に不満だったという。人件費削減のあおりで、今や日本の労働者の3割以上は非正規だ。 コスト競争に負けた工場の閉鎖も相次ぐ。戦後の高度成長を支え、脈々とつないできた「ものづくり」のDNAは、もはや日本メーカーに受け継がれていないのか。 多くの“プロ”がいたはずの工場で、今、何かが揺らいでいる。 本誌は『週刊東洋経済』2014年3月15日号第1特集の21ページ分を抜粋して電子化したものです。 【主な内容】 どうした日本の製造業 マルハニチロ事件の「必然」 食品の現場はこんなに危ない 冷凍食品、なぜ投げ売り? 化学メーカーの「油断」 日本の工場から消えた高卒正社員 工場は日本で成立するのか ソニー撤退の深い爪跡 薄型パネルを敗戦処理するパナソニック、シャープ 国内大リストラのJT
-
-中国の超巨大ネット通販企業・アリババ。年間の商品取扱高は25兆円にも及び、イーベイや楽天を圧倒。利益水準ではアマゾンにも勝つ。 そのアリババが米国への上場計画を発表し、世界の株式市場を揺るがしている。いまや同社は内需拡大や金融改革など中国の経済政策を動かすほどの存在だ。 創業15年でここまで駆け上がった「怪人」馬雲(ジャック・マー)会長の実像、アリババを動かす中核メンバー、創業期を支えたソフトバンクや米ヤフーとの関係など、謎に包まれた企業の正体に迫った。 本誌は『週刊東洋経済』2014年5月24日号緊急特集の20ページ分を抜粋して電子化したものです。 【主な内容】 世界を揺るがすネットの怪人 迫るソフトバンクとの決別 ヤフーがタオバオを“積極学習” 米国投資家の話題独占。アリババのお値段は? 美人社長から学生まで密着取材!「アリババ依存症」を追う 買い物が大好き! でもいい店がない バイト学生も熱中! タオバオにはまる理由 配送先は職場! 忙しい上海人もやはりネット派 偽物も多いけど、何でもあるのが魅力 余額宝のおカネで買い物もしてしまう タオバオで月商100万元のスーパー主婦 タクシー配車アプリが爆発的に普及 アリババの金融大革命 日本企業のアリババ活用術 革命児 馬雲 野望の原点
-
-2014年のサッカーW杯、2016年夏季オリンピックの開催国となったブラジル。人口2億人のうち半数の1億人が中間層を占める新興国だ。 ルーラ前政権下では強い製造業、豊富な資源を背景に年平均4%の高成長を満喫。一人当たりGDPは年8000ドルを超え、すでに新興国の水準にはとどまっていない。 ここ数年は経済低迷が伝えられるものの、失業率も5~6%台と低水準で推移しており、雇用や所得は一定の水準を維持している。 が、ビジネスチャンスの地平線が広がるブラジルの大地に、日本企業の影は薄い。「世界にも類を見ない親日国」とも言われるブラジルに、日本はもっと目を向けるべきではないか。 「遠くて近い親日国」ブラジルを解明! 本誌は『週刊東洋経済』2011年2月12日号第1特集の32ページ分を抜粋して電子化したものです。 【主な内容】 「親日派新興国」の存在 「爆食龍」中国の野望 石油、鉄鉱石、エタノール。吹き上がる資源獲得競争 日本企業の挽回大作戦 【デンソー】南米全体の「核」に技術拠点も新設 【ソニー】「新生チーム」で韓国勢追撃 【NEC】サンパウロに統括会社を設立 【日立アプライアンス】エアコンに省エネ化のうねり 【IHI】撤退から17年。DNA生かすラストチャンス サンバの国の巨大企業 【JBS】怒濤のM&Aで食肉世界一に 【エンブラエル】産業界リードする「優等生」企業 独特!ブラジリアンカンパニー どうなった? 日系ブラジル人問題
-
-70歳、さらに75歳まで働く時代が迫ってきた。年金の支給開始が70歳前後まで引き上げられる可能性が高い。60歳になったら引退生活に入るというパターンは、完全に過去のものだ。 起業にしろ、再就職にしろ、武器となるのは、これまでの仕事で身に付けたノウハウや人脈。会社で10年以上続けた仕事があれば、それを核に、自分の「わざ」を磨くこと。 その「わざ」を求めている職場はたくさんある。中小企業では、人材不足もあり大企業で経験を積んだシニアへの期待が大きい。ベンチャーも同様。企業社会のルールを熟知したベテランは、まさに「即戦力」になりうるのだ。 起業から再就職まで「定年後」の仕事を徹底的にガイドする。 本誌は『週刊東洋経済』2014年2月15日号第1特集の33ページ分を抜粋して電子化したものです。 【主な内容】 45歳から考える「次の仕事」 Part1 ゆる起業で長く働く 起業熱に沸くシニア ローリスクで成功する「ゆる起業」のすすめ 知らないと損をするシニア起業支援策 シニア起業の達人たち Part2 発見! シニアの仕事図鑑 人気度・難易度別再就職先総まくり 人材不足の介護業界はシニアこそ活躍できる 営業も人脈も不要、クラウドでフリーに 対談 出口治明(ライフネット生命保険会長兼CEO)/柳川範之(東京大学大学院経済学研究科教授) Part3 「次の仕事」探しの基礎知識 “資格仕事”のリアル 年収1000万円も。アジア再就職の実情 ハローワークは宝の山。シニアのための活用指南 現実は厳しい再雇用の道。会社人生終盤の正しい歩き方 Interview 歴史小説作家 童門冬二
-
-ネット界のガリバー楽天。2013年12月には東証1部へ市場変更し、時価総額もついに2兆円を突破した。 会長兼社長を務める創業者の三木谷氏は、安倍首相の肝いりで設置された産業競争力会議のメンバーに選出。新経済連盟の代表理事も務める。三木谷氏は新興ネット経営者以上の存在になりつつあることを印象づけた。 が、2013年の楽天イーグルス優勝セールで、セール価格の不当表示が発覚。三木谷氏が謝罪会見を開く騒動となった。 そんななか、長らく後塵を拝してきたヤフーショッピングは、出店費用や手数料無料を武器に楽天を追撃する。同じソフトバンクグループである中国・アリババが生きた教材だ。 順風満帆に見えていた「楽天市場」はこれからどうなるのか。楽天をめぐる人々をつむぎながら、激変する環境下でのネット通販王国の異変に迫る。 巻末にはコラム「楽天イーグルス日本一への軌跡」も収録。 本誌は『週刊東洋経済』2013年12月21日号第1特集の20ページ分を抜粋して電子化したもの、お求めになりやすい価格となっています。 (登場する人物の役職は冊子掲載時のものです) 【主な内容】 ネット通販王国の異変 セール依存に限界。一強神話崩れるか 「楽天ここがおかしい」 優良店舗も激白 電子書籍コボはポイントを大盤振る舞い 三木谷王国の全貌 ~現経営陣と去った人々~ 「財界人 三木谷」への逆風 ヤフーショッピング 決死の反撃! interview アリババグループCEO ジャック・マー 二重価格だけじゃない! ネット通販の罠 ついに住宅ローンの提供も開始、多角化する楽天の金融 楽天イーグルス日本一への軌跡
-
-アベノミクス効果による景気回復もあり、日本の労働市場はここ数年で最も活気づいている。 特に転職市場では大きな変化が起きている。長らく定説だった「転職35歳限界説」が崩れ始めているのだ。 転職成功者のうち35歳以上が占める割合は07年に1割程度だったが、年々高まってきており、13年は2割強まで上がった。 団塊ジュニアより後の若手世代は人口が先細り。企業が中途採用で従業員を補充しようとしても、転職35歳限界説にこだわりすぎると、欲しい人材を確保できない。 「もうアラフォーだから」と転職をあきらめていた方、チャンスはあります! 本誌は『週刊東洋経済』2014年1月25日号第2特集の10ページ分を抜粋して電子化したもので、お求めになりやすい価格となっています。 【主な内容】 崩れ始めた「35歳限界説」 中途ミドルが吹かせる新しい風 大幸薬品/ナゴヤパッキング製造/ベネッセスタイルケア カリスマコンサルタントが教える ミドル転職、7つの気構え ネットの進化が生む転職の新たなカタチ
-
-男女ともに、結婚しない「おひとり様」が増えている。特に中高年男性の4人に1人は一人暮らしとなり、男性の単身化が加速する。 「おひとり様」傾向を後押しする変化も次々と起きている。非正社員職の拡大など、雇用や将来への不安から結婚したくてもできない若者が増えている。一方、コンビニや「おひとり様」向け製品の増加で、一人暮らしでもまったく不便を感じなくなった。 SNSやスマートフォンの普及も大きい。一人で家にいようが、電車の中にいようが、好きなときに誰かとつながっていられる。 が、「おひとり様」が老後を迎えたらどうなるのか、どう備えたらいいのか。おひとり様の将来プランについて考える! 本誌は『週刊東洋経済』2014年3月1日号第1特集の27ページ分を抜粋して電子化したもので、お求めになりやすい価格となっています。 【主な内容】 超単身社会が到来する 私がシングルの理由 おひとり様の将来プラン 一人だからこそ考える、老後のマネープラン 資産形成すれば老後も独身貴族 ライフステージに合わせて「住プラン」を決めておく 「シングル介護」とどう向き合うか 単身者に保険は不要 「昭和の下町」がおススメ! 男が暮らしやすい町 Interview 吉田類(酒場詩人) 進化する「おひとり様」ビジネス 単身女子の貧困問題 Interview 水島広子(精神科医)
-
-あなたの会社では何人がうつで休んでいるだろうか。 公務員の統計では国家公務員の1%強、地方公務員の1%弱が、主にうつが原因のメンタル休職者だ。民間企業でもこれが目安となる。 わずか1%の休職者といっても、大企業ならかなりの人数になる。社員1万人なら100人がうつで休んでいることになる。 職場のうつは、復職を焦れば焦るほど再発する。再休職に追い込まれれば、本人も会社もつらい。 会社を悩ませ、社員の人生を狂わせかねない、うつの正体を追う。 本誌は『週刊東洋経済』2014年1月8日号第1特集の24ページ分を抜粋して電子化したもので、お求めになりやすい価格となっています。 【主な内容】 職場のうつ 元うつ患者匿名座談会「私がうつになるとは思わなかった」 再休職させない秘訣教えます 日産自動車「民製リワーク施設」 フジクラ「ジレンマ抱えつつのメンタル疾病予防」 ホンダ「再発率を1割下げる」 味の素「再発率が限りなくゼロに」 NTTデータ「病気の未然予防に力点」 ソフトバンク「ストラップで攻めの予防策」 横河電機「外国人をうつにさせない工夫」 アイエスエフネット「本社の3分の1は障害者」 人事部長覆面座談会「このままでは会社はうつだらけ」 うまく復職する・させるには 企業編「休職時に復職の条件をしっかり紙に残しておく」 社員編「主治医のお墨付きあれば休職命令は出せない」 うつ再休職の背後に発達障害 Interview 筑波大学大学院医学医療系教授 松崎一葉 うつにして辞職に追い込むブラック企業の手口
-
5.0日本勢が牽引してきたデジタルカメラ市場が急変している。 これまで2ケタ成長を続けてきた一眼レフカメラの販売が減少に転じ、コンパクトデジカメも急縮小。デジカメ全体では市場は4割も減少している。また、スマホの登場により、低価格帯のコンパクトデジカメは事実上消滅したとまでいわれている。 こうした事業環境の急変に対し、瀬戸際に立たされた各メーカーの現状と将来について迫る。 本誌は『週刊東洋経済』2014年2月8日号第2特集の10ページ分を抜粋して電子化したもので、お求めになりやすい価格となっています。 【主な内容】 市場4割減の衝撃 キヤノン「成熟化の議論は早い。革新の余地はある」 富士フイルム「光学関連事業全体で伸ばしていく」 パナソニック「動画性能、クラウド関連を強化」 ニコン「ニーズ多様化に対応、さらなる成長狙う」 リコー「販売数が少なくても儲かる仕組みを作る」 カシオ計算機「コンデジで新しい分野を開拓する」 オリンパス「ミラーレス売上拡大、新規ビジネスも」 フルサイズで大攻勢。ソニーの「脱家電」戦略 Interview ソニー デジタルイメージング事業本部長 石塚茂樹 イメージセンサーに求められる次の展開 国内外部品メーカーにデジカメ変調が波及
-
-大学選びは、日本だけでなく世界も視野に入れて考える時代に入った。 東大合格者数トップの開成高校は、2013年から海外大学の説明会を実施。米イェール大学、米ミシガン大学などに9人が合格。東大合格者数2位の灘高校も英オックスフォード大学、米ハーバード大学など五つの海外大学に合格者を出す。 欧米の有名大学だけではなく、アジアにも世界レベルの大学が多く存在する。地方出身者にとっては、学費や生活費、語学習得などを考えると、東京よりもアジアの大学にしたほうがメリットがある場合も。台湾の大学の授業料は年間30万円、フィリピンの国立大学はなんと年間4万円! 授業の中身や学費、生活状況など、日本人留学生の話も含めて海外進学のリアルを伝える。 本誌は『週刊東洋経済』2013年11月2日号の第1特集の16ページ分を抜粋して電子化したもので、お求めになりやすい価格となっています。 【主な内容】 国際化が待ったなしの日本の大学と大学生 米国名門大学がハイレベルである理由 米国リベラルアーツカレッジと豪州職業訓練学校の魅力 アジアの一流大学が狙い目 すべて解説! 海外の大学へ進学するのに必要なこと 海外進学をサポートするスクール 日本人が陥りやすい海外大学留学の誤解
-
-うつ患者が急増したのは、製薬会社のキャンペーンがきっかけだった! 「うつは心の風邪」というキャッチコピーが広く知れ渡ると、「自分はうつではないか」という患者が病院に押し寄せた。その後も、新たな薬が発売されると、うつ患者が急増する現象が世界中で起こっている。 キャンペーンによって受診の抵抗が減り、救われた人もいるが、軽症の患者にまで安易に薬が処方されてはいないか…? 本誌では製薬会社のキャンペーンによるうつ急増のからくりや、薬に頼らないうつの治し方、うつから生還した元日本テレビニュースキャスター・丸岡いずみさんインタビューなど、うつに対する正しい知識を解説します。 本誌は『週刊東洋経済』2014年1月18日号の第1特集の19ページ分を抜粋して電子化したもので、お求めになりやすい価格となっています。
-
-2014年1月からNISAが始まりました。これまで投資に興味がなかったけれど「税金がかからないのなら始めてみようか」という方も増えているのはないでしょうか。 NISAについて、口座の選び方、配当金の受け取り方、利益確定の時期…などなど丁寧に解説。 NISAについて理解ができたら、次はどの投資商品を選ぶか? 本誌では投資初心者に打ってつけの投資信託を選んでみました。 NISAに合った投資信託、ブロガーが選んだ投資信託など、これを読めば初めての方でも大丈夫! 本誌は『週刊東洋経済』2014年1月25日号の第1特集10ページ分と『会社四季報別冊・2014年新春号で見つけた先取りお宝株』の8ページの計18ページ分を抜粋して電子化したもので、お求めになりやすい価格となっています。
-
-日本人の6割以上が当たり前のように取っているサプリメントやトクホ。グルコサミンやコラーゲン、ヒアルロン酸など多様な種類のサプリがインターネット通販で売られているほか、100円ショップなどでも取り扱いが増えている。 利用者は成人だけでなく、ペット用や子供向けサプリまで登場。2010年の調査結果によると、就学前幼児の15%にサプリの利用経験ありという結果も出ている。 サプリとともに健康食品と呼ばれる特定保健用食品(トクホ)も、最近ではサントリー食品インターナショナルの「特茶」や花王の「ヘルシアコーヒー」などがヒットを飛ばしている。 今やサプリ、トクホを含む健康食品の市場規模は1兆7000億円以上に膨らんでおり、巨大な産業だ。しかも、サプリの規制緩和で2兆円の健康食品市場は4兆円、6兆円になろうとしている。 だが本当に効くのか、宣伝に嘘はないのか。 本書では人気のサプリ商品が本当に効くのか、サプリによる健康被害や死亡例など「天然成分だから大丈夫」「薬と違って副作用がない」と思われがちなサプリの真相に迫った!
-
-ビジネスの手法を導入し、変わり始めたNPO業界。年収200万円といわれた職員の待遇も改善。清貧に甘んじる時代は終わるのか――。 「求人をすると、ゴールドマン・サックスやマッキンゼーなど、一流企業に勤める30歳前後の会社員が何人も応募してくる。年収は大きく下がってもいいから、社会のためになることをやりたいと口をそろえる」と、NPO理事は語る。 こうした若者たちを引き付けているのが、「社会起業家」の存在だ。著書がベストセラーになるなど、この領域に変革をもたらす存在として、数年前から注目を集めている。社会起業家の運営する団体では、社会問題の解決に加え、安定した利益を上げるケースが増えている。 社会貢献への想いを抱く若者が活動に専念できるようになれば、日本は変わるかもしれない。最近のNPO業界を追った!
-
-2月7日からソチオリンピックが開幕した。晴れの舞台で闘う冬季オリンピックの選手たち。 一方で2020年の東京オリンピックを目指し、日本のスポーツ界はメダル獲得へ必死の形相だ。JOCがブチ上げた東京五輪の目標は「金メダル30個前後、国別順位で3位」というもの。過去、日本の最多金メダル数は1964年の東京と04年のアテネで記録した16。「30個前後」はその2倍近くになる。 選手だけでなく、企業も東京五輪需要に懸命だ。東京五輪によって14.9兆円の新規需要が生まれるが、そのうち12.6兆円のインフラ投資は、五輪がなくても実施される予定だった案件が多くを占める。 メダルを目指す選手強化の現場と、五輪特需を狙うビジネス界の動向に迫る!
-
-都市部で、医療・介護難民が発生するかもしれない――。医療・介護の課題といえば、財政問題だけではない。仮に国費で何とか医療・介護の財源を支えたとしても、各地域で施設や人材が不足すれば満足なサービスは受けられない。 医療・介護の受け入れ能力が今後逼迫してくるのは、首都圏や名古屋などの大都市圏だ。2030年まではすべての都道府県で75歳以上人口が増加する反面、30年以降は減少に転じるところが多くなる。しかし、東京都や神奈川県、埼玉県、大阪府、愛知県などの3大都市圏では、30年を過ぎてからも75歳以上人口は増加し続ける──。 地方の高齢化がピークを過ぎた後も、大都市圏の医療・介護需要の増加には拍車がかかるだけでなく、財源である住民税も減少していく。 高齢化のピークが迫る中、対策は待ったなしだ。
-
-スマホの普及で、「誰でもいつでもどこでも」ネットにつながる環境が急速に整ってきた。その裏側で、ネットの閲覧を奪い合う熱戦が繰り広げられている。ウェブサイトの閲覧数を競う、「ページビュー(PV)争奪戦」だ。 PVとはあらゆるウェブサイトの実力を測る共通指標。ヤフーやサイバーエージェントなどのネット専業に限らず、メディアや一般企業、個人などもPV獲得に関心が高い。 無数のウェブサイトをページビュー(PV)争奪戦に突き動かしているのが、インターネット広告市場の成長だ。2012年のネット広告市場は8680億円へと拡大。新聞・雑誌広告の合計に匹敵する水準となり、4マスと呼ばれるテレビ、新聞、雑誌、ラジオの各広告市場と比べ、成長力は断トツである。 主要サイトのPVランキング、スマホで変わる勢力図、ホリエモンとサイバーエージェント藤田社長の対談から、8680億円市場の表と裏を解明する!
-
-経済政策を優先してきた第二次安倍政権だが、2013年末に安倍首相が靖国神社に参拝。中国、韓国のみならず、在日米大使館も「米国政府は失望している」との異例の声明を発表した。現在、外交的には厳しい立場に立たされている安倍首相だ。 金融緩和政策、財政出動、成長戦略の「3本の矢」でアベノミクスは構成されている。そのアベノミクスを進める司令塔、財界の安倍親衛隊「さくら会」、ネット右翼との関係、経団連の米倉会長との不仲…安倍首相を取り巻く人脈について詳しく解説。 「限定正社員」という名で解雇自由化は進んでしまうのか? 会社員必読!解雇規制緩和の全内幕。 横浜方式による待機児童解消の実現度は? 憲法改正についての首相の本音は? 安倍首相の秘められた本心と、首相を取り巻く人脈に迫った!
-
-核実験を続け、国際社会からの経済制裁が続いている北朝鮮。金一族の若きプリンス・金正恩が最高指導者となって2年目となるが、北朝鮮メディアでは連日、金正恩第一書記の現地指導をはじめ経済ニュースが大きなスペースを占めるようになった。3月には「経済建設と核武力の並進路線」を公言、経済の立て直しに力を入れ始めた。「経済強国」建設をアピールし、国を挙げての経済成長を目指しているようだ。 だが、12月に金正恩第一書記の叔父・張成沢氏が失脚。経済改革を重視した張氏の失脚で北朝鮮の経済政策に変化は起こるのか。 北朝鮮住民の収入状況、経済政策など、若き指導者の登場で変化する北朝鮮に迫る!
-
3.0肉体労働にも頭脳労働にも当てはまらない第3の労働「感情労働」をご存じか。職務として、表情や声、態度で適正な感情を演出することが求められる仕事のことで、過度の疲労や精神的ストレスを招く労働問題として、関心が高まりつつある。 働くうえで、感情をどうコントロールしていけばよいか。上手に感情をマネジメントすることで仕事の成果を高める方法を学ぶとともに、そうした感情労働で疲弊しないための方策を考えていこう。 <主なテーマ> ・理解できない上司や部下にどう向き合うべきか ・プロジェクトリーダーはメンバーの感情をどうマネジメントすればいいか ・突っかかる人、話さない人、混乱させる人、ずれている人、話しすぎる人、それぞれへの対応 ・営業スキルとしての感情労働~気質別8つのタイプ~
-
-
-
-
-
-今は「第3次アウトドアブーム」なのはご存じか。1956年に日本隊がヒマラヤの巨峰マナスルへ世界初登頂した第1次、1990年代の「日本百名山」ブームが起きた第2次に続いて、2008年ごろから「山スカート」や野外フェスに象徴されるファッション革命で若い登山者が急増したのが、この第3次だ。富士山の世界文化遺産登録も後押しする。 国内の登山、キャンプなどアウトドア用品市場は08年以降4年連続で増加、13年も前年比5・4%の成長を見込む。関連メーカーはもちろん、不動産デベロッパーや家電量販店まで巻き込んだブームを探る。
-
-
-
-2013年7月、ソフトバンクによる米スプリント・ネクステル買収が完了した。早速、同月からデータ通信が無制限となる割安プランを投入するなど、日本で傘下通信3社をV字回復させてきたノウハウを生かし、陣頭指揮を執る孫正義社長。だが、ここまでの道のりは険しかった。 スプリントを1.6兆円(当初)で買収すると発表したのは、KDDIに対抗してイーアクセスの買収を決めたわずか2週間後。他社との争奪戦に発展し、買収額上乗せで、ようやく買収にこぎ着けた。 この間、立て続けに思い切った決断を下してきた孫社長は、何を考え、どう動いたのか。孫社長やキーマンへの直撃取材をもとに、1年間を『週刊東洋経済』の記事で振り返る。
-
-
-
2.5「弁護士を続けていくべきかどうか、正直悩んでいる。普通に家庭を築いて、安心して暮らすことができない」。20代の新人弁護士の男性の本音だ。 弁護士だけではない。会計士や税理士といった、難関の試験を突破し、高度な専門知識や能力を持つ、社会的地位も高いはずの「士業」が、大きく揺らいでいる。 人気失墜のロースクールを尻目に、出願者数が伸びる予備試験。登録抹消が急増する会計士、難化する一方の税理士試験--。なぜこんなことになってしまったのか。そして、これからいったいどうなるのか。それぞれの「士業」の現状と改革案の失敗などを深くリポートした。
-
4.0司馬遼太郎が『坂の上の雲』で描いたのは、20世紀初めの日露戦争までの数十年間だった。富国強兵と殖産興業によって、列強の一角に上り詰める時期の日本を生き生きと描いた。 100年後の日本は、司馬の描いた時代と正反対に、人口も、経済も、世界的な地位も、縮小、低下していく。まるで明治や昭和の高度成長期に駆け上がった坂道を、今度は数十年かけてゆっくりと下っていくかのようだ。 本書では2050年を中心に、30年から60年にかけての時間軸で、将来われわれの生活がどのように変わるのかを展望する。そのうえで、危機をチャンスに変えるきっかけを考えてみたい。
-
-
-
-経営者に助言を行うコンサルティングファームの代表がマッキンゼーだ。 マッキンゼーの出身者たちは緊密にネットワークされ、「マフィア」と呼ばれることもある。その関係から生まれるビジネスや事業は多い。また、ツイッター、ディー・エヌ・エー、ミクシィのSNS3強に、野菜ネット販売のオイシックスやiPS細胞関連のリプロセルなど、マッキンゼー出身者が経営する企業も多い。さらに茂木敏充・経済産業相、上山信一・大阪府市特別顧問など、国や自治体の中枢にも出身者のネットワークが広がっている。 マッキンゼーのいったい何がすごいのか。出身者による4つの誌上講義と日本支社長トップへのインタビュー、ライバルであるボストンコンサルティンググループとの対比などから、その深奥に迫る。
-
-若者の学力低下が懸念される日本だが、こうした中で優秀な生徒を集めたのが、私立の「中高一貫校」だ。6年間かけて勉強させるプログラムが見直され、難関大学への進学実績を積み上げていく。この動きに触発されて、公立でも一貫校の開校ラッシュが続いた。 さらに、全国から親子の集まる乳幼児知育スクールが注目を集めている。もはや「エリート教育は3歳までが勝負」の時代なのだ。 かつての開成→東大→財務省のような、約束された黄金ルートはもう存在しない。 本書では、幼児の英才教育から中高一貫校まで、教育現場の新しい姿を示した。これもグローバル時代の現実のありようである。
-
-安倍首相の鶴の一声で、ネット販売の原則解禁が決まった大衆薬。年初の最高裁判決以来、かつてないほど大衆薬が注目されているが、当の主役は戸惑っている、といった状況だ。市場規模は1兆円を少し上回る水準で、自動車の2%程度しかなく、長期的に縮小傾向が続く。周囲が成長戦略の目玉とはやす割に元気がないのである。 最大の要因は健康食品(健食)やサプリメントとの競合だろう。「大衆薬は摂取しすぎると危ない。健食やサプリは大丈夫」。もちろんこれは事実と違う。健食、サプリが原因の健康被害もあるし、逆に取りすぎて平気なものは効能が怪しい。それでもこうした妄信は根強くある。 本書では、ネット販売に揺れる大衆薬業界の動向に加え、胃腸薬や解熱剤などのカテゴリー別の状況を詳しくまとめた。
-
3.0アベノミクスに期待と不安を感じながらも株高・円安で一息ついている日本に対し、逆に不安だらけで日本を見つめている国が韓国だ。 安倍晋三、朴槿恵政権ともに、発足前後から続く外交的対立が経済面でも生じている。「アベノミクスは失敗する」と韓国メディアや有識者が批判すれば、日本も「韓国経済が危ういから日本を批判している」との舌戦が、半年以上続いている。では、そんなに韓国経済は悪いのか。 よく見ると、公約として掲げたが故の財閥規制と、経済成長の主役である企業をどう生かすかで苦心する朴政権の姿が見えてくる。円安が急速に進んだため、対応に手間取る韓国企業や国民の胸の内も垣間見える。 一方で、日本企業の韓国への直接投資がこの数年で急増し、韓国市場は日本企業にとって有望という現実も浮上。韓国がこの半世紀に受け入れた海外投資累計額で日本は2位。それだけ日韓の経済関係は成熟しているのだ。批判ばかりでこの関係を壊してしまうのか。今こそ、冷静に隣国との関係を見つめるときだ。
-
-東京電力・福島第一原子力発電所の事故発生から2年半ちかくが経過した。同原発近くの港では、海水の放射性物質の汚染濃度が原因不明のまま上昇し、事故収束のメドは一向に立たないなか、全国の原発が再稼働に向けて動き出した。 安倍政権が成長戦略の柱の1つとして推進する原発輸出政策も問題含みだ。年内をメドにエネルギー基本計画を策定するとしているが、安倍政権が原発を将来的にどう位置づけるのか、方向はまだ見えない。中小企業は電気代値上げに苦しみ、事故収束に当たる労働者の不足も懸念される。3・11後、原発に起因する問題は何一つ解決したとはいえないだろう。 7月に投開票が行われた参議院選挙の争点の一つは原発再稼働の是非だったが、残念ながら論戦が深まったとは言いがたい。5つの争点を軸に、原発と東電をめぐる問題点を徹底検証した。
-
3.0ネット通販の登場で「買い物のあり方が根本から変わった」と言っても過言ではない。IT活用のマーケティング理論を駆使し、新たな買い物市場を創出している。 とくに日本最大のインターネットショッピングモールである楽天は、1997年5月に13だった店舗数が、現在は4万を超す規模にまで成長。さらに約40の多様なサービスも抱えた「楽天経済圏」を介する、世界でも例のないモデルだ。 楽天といえば様々なポイント施策が有名だが、成長の理由はそれだけではない。大量の注文や納品をを支える物流体制や、“リアル”の世界への切り込み方、さらに各店舗向けに売上を伸ばすアドバイスをする「楽天大学」やECコンサルタントの実態などを、キーマンへのインタビューを交えながら詳しくリポートした。
-
-ダウンロード数が1500万件を突破し、ますます勢いに乗るスマホ向けゲームアプリ「パズル&ドラゴンズ(パズドラ)」。1個100円弱のアイテム販売だけで、月商100億円を超えるお化けタイトルだ。ここまで成功した理由と今後の課題を、開発元ガンホーの森下一喜社長と山本大介プロデューサーへの単独インタビューで探る。 また「そもそもパズドラとは何なのか」の紹介に加え、夏野剛氏・マックスむらい氏への「パズドラのすごさ」に関するインタビュー、パズドラを追いかける国内外の競合アプリ、そしてゲーム業界の3強である任天堂・ソニー・マイクロソフトの巻き返し策、さらに未成年課金の問題も含めて、「パズドラ」を徹底分析した。