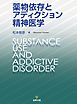金剛出版作品一覧
-
-現在薬物依存症の患者は全国に10万人と言われ,覚せい剤事犯者の再犯率は6割を超える。このように近年深刻な社会問題となっている「薬物依存症」であるが,わが国においては一部の特定施設を除き,標準化された治療システムが見当たらず「無医村」的状況が続いている。 本書は,「ようこそ外来」や「ごほうび療法」を実践する著者が,20年以上にわたる依存症臨床の経験から,患者や家族と向き合い,個別や集団での治療プログラムを使い,依存症者との信頼関係を構築することで依存症からの回復を目指すための指針を公開したものである。 当事者とその家族をはじめ,医療・福祉・行政・司法・教育など薬物依存症に携わるすべての人々に。
-
4.0これまで薬物依存は,ともすれば司法的問題として捉えられ,治療や援助ではなく,取り締まりの対象とされてきた。しかし,治療なき取り締まりは,わが国における覚せい剤取締法事犯者の高い再犯率以外に,問題を抱える当事者に対して一体何をもたらしてきたであろうか? 意外に知られていない事実がある。近年わが国において急激に乱用が深刻化しつつある薬物とは,覚せい剤でもなければ大麻でもないのである。それは,精神科治療薬という「取り締まれない」薬物である。 いうまでもなく,薬物依存から回復に必要なのは,罰ではなく,治療である。薬物依存は,世界保健機関(World Health Organization; WHO)によって認められた医学的障害であり,わが国の精神保健福祉法においても精神障害の一つとして明記されている,れっきとしたメンタルヘルス問題なのである。そしてメンタルヘルス問題である以上,その治療は,単に「薬物」という「モノ」をやめさせることではなく,その「ヒト」が地域で普通に暮らせるようになることを目標にしなければならない。 本書には,医療機関や保健機関の援助者・治療スタッフのために,現場で役立つ情報や考え方が数多く紹介されている。当事者,家族,すべてのアディクション臨床にかかわる治療スタッフに必携の書といえよう。
-
-著者は,人間学的精神医学や現象学的精神病理学,ラカン派の精神分析,近年注目されているナラティヴ・アプローチの交点に位置づけられるような領域研究と,自らが築きあげてきた精神療法家としての素地を柱とした臨床経験の精華として本書を書き上げた。 各論稿では,クラウス,ヤンツァーリク,ラカン,エランベルジェ,等,独仏の碩学の理論を止揚し,病いに苦しむ人の自己(身体),他者,世界との関係を明らかにしようと試みる。臨床の現場においては,精神病患者の語りに耳を傾け,患者の痛みと苦悩の内的世界を再構築し,現代における統合失調症・うつ病の病理を問うている。 さらに,本書にはいくつもの鍵概念が提示される。ひとつは、患者の〈虚偽主題 Lugenmotiv〉である。これは、うつ病や統合失調症等の病的体験に出現する「うそをついた」といった発言や自らの偽りの自白を指す。次に,具体的実践的な治療論への展開のために「自己回復力」とも大まかに理解される「レジリアンス」という概念を援用する。さらに,本書のタイトルにもなっている「ナラティヴ(語り)」については,物語(story)には病いを癒す力があり、そこでは、病者は物語の語り手としての能動的存在であり、語りと聴取をとおして、病者と聞き手とのあいだで、深い次元での共感と了解にもとづく紐帯が作り出されると述べる。これら重要概念を解説しながら,著者自身の一貫した臨床研究テーマ「心の病いにとって治療とは何か?」に到達する。それは,物語論(ナラトロジー)の見地から,現象学的精神医学の再生を目論むことにもなるのである。
-
-なぜ臨床場面に民族誌(エスノグラフィー)が必要なのか? 著者は文化精神医学や医療人類学の方法論を精神科の日々の臨床にいかに蘇生させるかということを,ライフワークにしてきた。本論集はその集大成ともいうべき労作である。 かつてA・クラインマンは,台湾をフィールドとする著作のなかで,憑依状態で治療にあたる現地の童ケイ(タンキー)を,癒しにおいて間違いなく西洋医にまさるものと結論づけた。ここで作動しているローカルな知を現代医療において生かす方法は何かと著者は問う。現代精神医療の変容(「大きな物語の終焉」),物語論の始原へと遡るジャネの心的治療論,民俗学への架橋,そして医療自身のもつ文化をたどりながら,読者は対話場面で偶発的に溢れるように語りだされる患者や家族の「もう一つの物語」を聴くことになるだろう。 精神療法は文化とどこで出会うのか? 心的治療の多様性とは? 臨床民族誌という方法を理論にとどまらず身体技法として身につけるにはどうしたらよいか?……本書(本論集)はこれらを模索する試みである。
-
4.9
-
4.1双極性障害の家族を持ち自身も発症の疑いを持つ大学生、唯(ゆい)は大学のサークル活動を起点として自助グループの運営にかかわるようになり、当事者研究とオープンダイアローグ(OD)を学んでいく。発達障害、吃音、摂食障害、LGBT、鬱、ひきこもりの親など、自助グループに登場するさまざまな困りごとを抱えた当事者たちのケースを通して、この物語は、対人援助職、当事者向けの実践的ケーススタディとなる。 一方で、物語は成長して大学で教鞭をとる唯先生による講義編へと展開する。 講義編では、「ユーモア」「苦労の哲学」「ポリフォニー」「中動態」などのキーワードを並べつつ、当事者研究、ODを基礎から丁寧に解説。さらに、ハイデガー、アーレント、バフチンの思想が交差する深みへと進む。 本編のほか、ほがらかタッチのへたうまイラストや、付録には「唯のひらめきノート」、荒唐無稽なゲームブックなどが収録され、読者はユニークな世界観を味わいながら、当事者研究とODを楽しく学ぶことができる。
-
-わが国では,覚せい剤取締法違反によって刑務所に服役する人の数は年々増加しており,その再犯率の高さも指摘されている。薬物依存症の治療は「貯金することができない」性質のものであり,出所後そして保護観察終了後にも,地域で継続されなければほとんど意味がない。 米国マトリックス・モデルを基に〈SMARPP〉を開発した著者が,新しい薬物依存症治療プログラムとしてのスマープの実際をわかりやすく説いたのが本書である。 後半では,薬物依存症治療の最前線として,現状の理解から法的問題,当事者と家族への援助まで,物質使用障害理解のためのさまざまな課題を明らかにしている。
-
-本書は,わが国の児童精神科医療に関わる関係者に向けて,臨床における現場感覚を生き生きと感じ取ってもらうことと,児童精神科臨床の現状と問題点や課題を提示することを,主な目的として企画した。 第1部では,齊藤万比古医師と岩垂喜貴医師による,『児童精神科入院治療の実際―子どもの心を守り,癒やし,育むために』(金剛出版)刊行記念として開催されたトークイベントが収載されている。児童精神科入院治療の草創期から始まり,入院治療の魅力,チームの連携,スタッフの燃え尽き防止策など,教科書的な知識ではなく,臨床実践に基づいた入院論・治療論が語られる。 第2部では,児童精神科という同じ臨床の場を持ちながらも,それぞれ異なるアプローチで臨床に携わってきた経験豊富な4人の医師が,児童精神科医療の実際や児童精神科における治療,東日本大震災・コロナ禍を経験し,ウクライナ戦争下における,これからの児童精神科臨床についてラウンドテーブルトーク形式で大いに語りあう。 児童精神科医として模索し,実践してきた臨床の道のりから生み出された,さまざまな知恵や示唆は,実際の臨床に携わる多くの関係者にとって指針となり,明日への臨床の活力を与えてくれるだろう。
-
-あるがままの自分すべてを受け止めよう。といっても簡単なことではない。「自分はダメな人間だ」と誰しも思ったことがあるだろう。ただそれにとらわれていては見えるものも見えなくなってしまう可能性がある。「思い込み」は怖い。それを取り去るには積極的な心と頭のトレーニングが必要であり、本書ではそのトレーニング方法を提示する。ありのままにすべての物事を受け入れられた瞬間あなたにとって真の自由が開かれるだろう。
-
-クライエントのパーソナリティを高解像度で解き明かすMMPI(Minnesota Multiphasic Personality Inventory:ミネソタ多面人格目録)の基礎知識・施行法・臨床応用を,「MMPIを知るためのQ&A」「MMPIを理解しよう!」「MMPIをはじめよう!」「MMPIをケースでまなぼう!」の全4章でわかりやすく解説。MMPIの始め方から,基礎尺度・追加尺度の基礎知識,解釈法,ケーススタディ,さらにMMPI試行の全体像をマッピングした付録「樹形図」まで,臨床心理アセスメント初学者はもちろん,アセスメントスキルをブラッシュアップしたいベテラン心理職,チーム医療を志す医師・コメディカルスタッフにもよくわかる実践本位テクニカルガイド!
-
-クライエントのパーソナリティを高解像度で解き明かすMMPI(Minnesota Multiphasic Personality Inventory:ミネソタ多面人格目録)の臨床応用を,「症例検討会」「症例呈示編」という2つの角度から徹底検証する。 MMPIの始め方から,基礎尺度・追加尺度の基礎知識,解釈法,ケーススタディまで,臨床心理アセスメント初学者はもちろん,アセスメントスキルをブラッシュアップしたいベテラン心理職,チーム医療を志す医師・コメディカルスタッフにもよくわかる実践本位テクニカルガイド!
-
-子どもの不適応行動として不登校を例にとると,不登校児はいじめや成績不振などの先行刺激を回避し,居心地のいい家にいることによる不安の軽減や安全確保という利益(強化)を得て不登校が長期化する。その解決には,個々の不登校にはどのように「回避・強化機制」が働いているかを分析し,学校復帰に向けた行動変容を促すアプローチを適用しなければならない。 本書は,行動療法の歴史と理論背景を解説したうえで,心や行動の問題に適切に対処するための機能分析の方法とさまざまな行動療法の技法を紹介し,抜毛症や場面緘黙,強迫症といった子どもにみられる15の疾患や問題行動について豊富な事例とともにその見立てと臨床アプローチの実際を示す。 子どもの心の臨床を目指す学生や心理専門職,また学校や幼稚園・保育園の先生,さらには子どもの問題行動に悩む保護者の方などにも参考となるテキストブック。
-
-1,760~2,640円 (税込)なぜ今,多元主義なのか? 臨床心理学における多元主義とは?―特集にあたって 黒木俊秀 多元主義が臨床の「知」にもたらすもの 村井俊哉 [ダイアローグ×ダイアローグ]臨床における多元主義とは何か?―いかに学び,いかに育てるか 村瀬嘉代子・森岡正芳・黒木俊秀 多元主義の諸相 PTMFとメンタルヘルスケアの社会化 石原孝二 価値における多元主義 榊原英輔 発達支援における多元主義―自閉症の多様な理解を踏まえて 白木孝二 心理臨床の倫理における多元主義― 倫理的転回の立場から 富樫公一 森田療法を支える多元主義的感情観 田所重紀 統合的心理臨床の多元主義 ケースフォーミュレーションの多元的な実践―支援対象者/クライエントへの敬意としての多元主義 三田村仰 統合的心理療法をめぐって―多元主義VS折衷主義 福島哲夫 精神分析的心理療法の多元主義的展開 上田勝久 オープンダイアローグの多元的支援 下平美智代 当事者からみる多元主義 外山 愛 コラム [インタビュー]学派的多元主義と現場的多元主義 東畑開人 学派を超えた実践のスタイル―多元主義と統合 杉原保史 多文化カウンセリングと文化的多様性 岩壁 茂 投稿 原著論文|被虐待事例へのホロニカル・アプローチの特徴―複線径路等至性モデリングによる検討 千賀則史 理論・研究法論文|二枚ぬり絵法からみた慢性統合失調症者とアルツハイマー型認知症者の構成障害―時計描画テストとの関連 五十嵐愛・畦地良平・内田竜人・津川律子・横田正夫 臨床心理学・最新研究レポート シーズン3 第46回「子どもの不安への親の巻き込まれ―巻き込まれの背景による適切な介入への示唆」 藤里紘子 主題と変奏―臨床便り 第66回「セクシュアリティと性行動の心理臨床」 中原由望子 書評 富樫公一 著『社会の中の治療者―対人援助の専門性は誰のためにあるのか』(評者:小川 基) 小森康永ほか 著『ナラティブと情動―身体に根差した会話をもとめて(評者:森 茂起) 中井久夫 著/高 宜良 編『中井久夫 拾遺―対人援助の専門性は誰のためにあるのか』(評者:神田橋宏治) きむらひとみ 著『ステップファミリーの子どもとしての私の物語―親の離婚・再婚でできた「ギクシャク家族」が「ふんわり家族」になるまで』(評者:福丸由佳) 青木省三 著『精神科医という仕事―日常臨床の精神療法』(評者:花房昌美) ステファン・G・ホフマンほか 著『プロセス・ベースド・セラピーをまなぶ―「心の変化のプロセス」をターゲットとした統合的ビジョン』(評者:谷 晋二)
-
-臨床領域・学問領域ごとに第一人者が展開する集合知の結晶、公認心理師時代を迎えた臨床心理学の新基準スタンダード。 公認心理師の職責から、心理学概論、臨床心理学概論、研究法・統計法・心理学実験、多岐にわたる心理学理論、アセスメント、心理支援、主要5領域、精神疾患と治療、そして関係行政論へ。公認心理師/臨床心理士として研究・臨床において研鑽を積むうえで不可欠の知識と理解と経験を、多様な視点と論点から語り尽くす。 臨床心理学の初学者から、すでに臨床現場に勤務する現任者、そしてベテラン心理職まで、つねに座右に置いて日々の臨床を検証し、みずからの臨床知を深化させていくためのスタンダードテキスト。
-
5.0精神分析においてクラインの名前を聞いたことがない人はいないだろう。 本書は、クライン精神分析を歴史から今日的発展までを含め、豊饒な業績だけでなく、社会の動向や他学問領域との関連とも併せて紹介していく。 全体は2部構成となっており、Part 1では時系列に沿ってクラインの臨床的な発展を解説する。Part 2ではクラインの思想を倫理、社会・政治との関連で読み解き深い理解へと誘っていくが、それらはいままでのクライン関連書には見られなかった本書の特徴の一つとなっている。 クライン派精神分析を学び・読み解くための最適なテキスト。
-
4.0「挨拶もできない」「人の話を聞いていない」「質問もできない」「何を言っているのかわからない」「ちょっと違う意見を言われるとすぐにつぶれる」「必要なときに相談してこない」「ミスしたときに立ち往生する」「根回しが全然わかっていない」「提案をまとめられない」「時間管理ができていない」……若者が社会に出たときに,こういった批判の声が上がることは少なくない。 本書では若者に社会人として身につけてもらいたいコミュニケーションスキルの基本を,豊富な場面設定を参照しながら1つずつわかりやすく解説している。 大学の就職支援スタッフ,学生相談をしているカウンセラー,ご家族を主な対象としながら,新入社員教育などコミュニケーションスキルを伝えるさまざまな場面でも繰り返し活用できるテキストブックである。
-
-
-
5.0支援者のチームワークこそ,グループワーク成功の鍵だとする著者は,東京大学病院精神神経科デイホスピタルでSSTを日本の現場に導入し,以来,精神保健の分野ばかりでなく,刑務所や更生保護施設でもSSTの普及とリーダーの育成に努めてきた。 本書の中心テーマは,グループの持つ力を仕事に活かす,グループワークという支援の方法である。著者は,グループワークの原理・原則をわかりやすく解説し,認知行動療法理論に基づくSST(social skills training)やソシオドラマなど,グループで使える方法や技法を数多く紹介する。グループの力を駆使して,クライエントが現実の生活に役立つものの考え方と行動を身につける手助けをするための,優れた援助者になるための必読書。