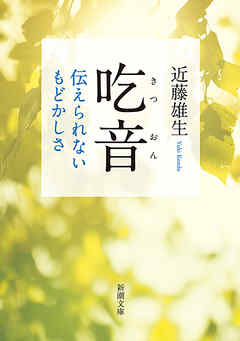感情タグBEST3
Posted by ブクログ
吃音が登場する作品を見たり、当事者に出会ったりしてもっと知りたい!と思った方にはぜひとも薦めたいです。
当事者の気持ちを知りたい方には専門書よりこちらの方が良いと思うからです。
自分は当事者ですが、吃音って何?と聞かれて詳しく答えることはできません。
それは本書にある通り吃音が極めて曖昧なものであるから、なのです。著者の近藤さんは相当な配慮をして文を書いていると思います。症状の軽さから悩みを軽んじられてきたのでそうではないんだよということがきちんと書いてあるのはありがたい限りです。
運が良かったことと続く秒数の少ない吃音であることからあまりこの本に出てくる彼らのような体験はありません。親の教育方針と言語教室のおかげで隠したいという気持ちはなく、吃音を気にすることなく話ができます。言い換えは時たまします。
それでも「普通になれない」葛藤があります。周りは私の症状を軽い、軽いと簡単に言います。でもいじめにも遭い、バイトの圧迫面接を受け、挨拶ができないことはザラにあります。酷いときには名前が1分以上言えないなんてこともありました。症状が軽いのは「無い」ことじゃないんです。
擬態して生きるように社会から強制されている部分もあり必死です。
この本の中に出てくる人は重い吃音の人(or吃音を隠して生き常に吃音に支配されて生きる人)が多いということを踏まえて読んでほしいです。
Posted by ブクログ
自身も吃音で悩んでいたことのある著者が、吃音に悩む人たちの現状、そしてこれからの展望などを関係者の心に寄り添いながらも忖度なく、真摯に取材を続けたノンフィクション。
身近に吃音の人はいないけれど、仮にいたとして、子どもの頃に出会ったとしても、多分私はからかったりすることはない。
けれど、彼らがどれほど苦しんでいるのかを理解もしなかったのではないかと思う。
だって、言葉が出にくいだけでしょう?
そんなの、もっと大変な障害を抱えた人がいるんだから、大したことないよ。
なんて言うことはないけれど、心の中で思うことはあるだろう。
その程度でしか知らなかったのだから。
一見大したことなさそうだけれど、当事者の悩みは様々だ。
人に知られたくないと思う人、理解してもらって少しの配慮が必要な人、個性として見てほしい人、障碍者として扱ってほしい人。
当人たちの性格もそれぞれ、環境もそれぞれ。
ひとくくりにできる正解なんてない。
だからこそ、もっと彼らの話を聞いて、もっと理解を深めなくてはならないと思った。
少なくとも、孤独のまま自死する人をこれ以上出してはいけないと強く思った
Posted by ブクログ
息子が吃音。吃音者の苦しみを今まで分かった気になっていた事に気づいて涙が止まらなかった。この本には吃音者のありのままが書かれていて、特に希望や救いは書いていないけれど、社会が吃音というものを少しずつ少しずつ理解しつつあるのかなと感じた。
Posted by ブクログ
吃音という一見同じような状況にある人たちがもつ悩みは、それぞれの人生で違う。これは吃音に限らず、さまざまな人と出会い続けるかぎり忘れてはならないことであると感じた。
目の前の1人が伝えたいSOSや気持ちに対し、出来うる限りの誠実さで向き合う大切さがわかる1冊。
Posted by ブクログ
浮き足立つことなく、絶望するでもない。
著者も当事者でありながら、取材対象との距離も持つ。
不思議なルポである。
しかし、確かな情報、適切な取材がここにはある。
Posted by ブクログ
吃音で思い出すのは、英国王のスピーチという映画。自分には知らない世界があった。吃音が、人の個性として認識され、より生きやすいように社会や人の寄り添い方が変わると良いなと思います。
Posted by ブクログ
2021年5月の文庫新刊で店頭に並んでいて、何となく気になり購入しました。解説は重松清さんがされています。
私は吃音について全く無知だったといえます。
例えば吃音の種類:撥音(音をくりかえす)伸音(音をのばす)軟音(音が出ない、出にくい)という調べればすぐに出てくる事すらも知らないでいました。
この作品はノンフィクションで、吃音を持つ人、その家族、治療にあたる人それぞれの目線で実体験とその時々の感情が繊細に綴られています。一つ一つのエピソードはとても重いです。
吃音に馴染みがない私にとってはノンフィクションであることが半ば信じられず、読み終えるのに時間がかかってしまいました。そして、一人一人考え方は違うので、一概にこうだ!という結論は出ません。
それでも読み終えてとても勉強になりました。
言葉にすると空々しいですが、
(思いやりと想像力、コミュニケーション)についてじっくり考えてみる機会にもなります。
トゥレット症候群に悩む人にも参考になるかもしれません。
メモ
・吃音を持つ人は、言葉を発することに緊張する、怖い、不安だという思いがつきまとう。
一見普通に生活できているようだから、困っている事がうまく伝わらず尚更もどかしいと感じる。
・吃音がある事で、いっそ障害者として認定されたいという人もいれば、老年期に入っても治療をして、死ぬまでにどうにか思い通りに話したいという人もいる。
・言葉につっかえた時に、じっくり待って欲しい時もあれば、相手が先に言葉を発してくれて助かる時もあるということ。どちらの場合も体が力み、その後はとても疲れてしまう。
・訓練をじっくりやれば、話し方をコントロールする事でスラスラと話せるようになった方もいる。
・吃音が理由で残酷な嫌がらせを受けることは現在にもある。
・近年はSNSなどの発達もあり、リラックスできる空間、仲間を持つ事ができ、その事が励みになっている。
・吃音の原因はまだ解明されていないが、研究は進められており、染色体がキーワードになるかもしれない。