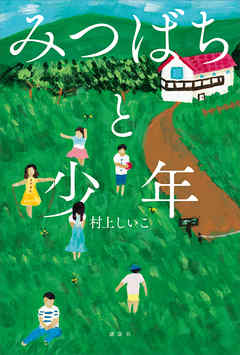感情タグBEST3
Posted by ブクログ
三重の特性ある男の子が13歳の夏に、叔父の北海道の養蜂所をたより、児童福祉施設の子どもたちと関わる中で再生、成長をしていく話。
#中学受験 の出題も多い。
#みつばちマーヤの冒険 (世界の名作全集12高橋健二訳)からの注釈もなかなか多く、施設長はキリスト教信者を匂わせる発言もある。故に、ミッション系での出題も多いのか?
個人的に16章は目頭が熱くなった。
#ブックサンタ
Posted by ブクログ
発達障害の疑いがある主人公・雅也は叔父のいる北海道に遊びに行く。そこで子供のための施設・「北の太陽」でしばらく暮らすことになる。その北の太陽で暮らす子供達と触れ合いながら成長する雅也を描いた物語ー。
とても考えさせられる本。北海道の、のどかな場所で成長していく雅也の姿に感動した。
また、雅也と触れ合う子供達が微笑ましい。
特に私は、海鳴と杏奈が好き。
是非手に取って欲しい一冊。
Posted by ブクログ
印象的なフレーズがいくつも。
「生きるっていうのは、いつもあきらめと背中合わせだ。残酷だな」
「ぼくたちは、前を向いて歩く前に、顔を上げなきゃいけない。それだけでもたいへん」
「空は、どれだけ多くの残酷をながめてきても、おだやかだ。空を見ていると、けっきょくわたしにできることなんて、なにもないとわかる。だからこそ、私も見ていよう。せめて残酷から、目をそらす人にはならないように」
などなど。
中学生におすすめ。
「みつばちマーヤの冒険」はタイトルしか知らないので、この作品を読んで、そちらも読んでみたくなりました。
Posted by ブクログ
「陰口を言うことより、いすを投げつける方がいつも罪が重かった」
本文中に出てくるこの文は、私も同じ思いに囚われている。おそらく今でも(お子さまですいません)。
冷静に考えてみると、確かにいすを投げつける方が、相手に取り返しのつかない大怪我をさせてしまう可能性が高いから罪が重いのだろうと、大人なら思うだろう。
ただ、こう返されると、当時の子供の私には、
「肉体の痛みと心の痛みは、肉体の痛みの方が上なの?」と反発するだろう。
「私がどういう環境で育ってきたか、あんたたち知ってるの。知りもしないくせに分かったようなこと、言ってんじゃないよ」と、今風に言うと「キレて」しまっていたのだ。
さすがに、その後の色々な経験や、この作品を読んだことで、これに対する今の私の解答としては、
「自分のみでなく、相手の立場も考えながら、冷静に自分の気持ちを、誠実に訴えればよかった」
ということになるのだが。ただ、当時の私にはそうした答えが分からなかったし、親も先生も誰も教えてくれなかった。まあ、結局、自暴自棄で高校を中退してしまい、しばらく荒れたという昔話で。
要するに何を言いたいのかと言うと、児童書って、物語として楽しめるのはもちろん、本当に必要な人のために書いてるんだなということです。前も、他の作品の感想で書いたかもしれないが、悩み苦しんでいた当時に、この作品と出会っていれば、と思っちゃうんですよね。
主人公の中学1年生の「雅也」は、発達障害なのではと思われてる中、親から「どうして、こんなふうに育ってしまったんだ」と。知るか。こっちが言いたいわとツッコミたくなる、嫌な始まり方。
雅也は、時に自分の感情を抑えきれなくなる時があり、ずけずけとしたもの言いをして、相手を傷付けたことを後悔するけれど、自分自身でどうにもできないもどかしさに苦しんでいた。言っていることは正当なんだけど、自分の立場だけでものを言っているようにも捉えられかねない。
そんなわけで、友達もいない雅也は、「みつばちマーヤの冒険」の本だけが信じられる存在で、鬱屈とした日々を過ごしていた。
そんな雅也だが、叔父の養蜂の仕事を手伝うために、向かった北海道で出会った仲間たち。そこの子供たちは、皆、家庭環境など様々な問題で苦しんでおり、その中の五人の子供たちのまとめ役で冷静に見える、雅也の同級生「海鳴(かいなる)」は、
「強くないよ。ただ、ぼくはゆっくりとがまんするしかないだけさ。逃げる場所がないから、一生懸命にがまんすると、なにもかもいやになる。ぼくたちは前を向いて歩く前に、顔を上げなきゃいけない。それだけでもたいへん」
と思いを語る。この台詞を覚えていたのだろう、後の雅也の台詞に
「あきらめる練習よりも、あきらめない練習が必要な人もいる。顔を上げるためには、心の奥にまで差し込んでくる光が必要」
ちなみに上記の台詞は、自分だけでなく、他人を守ることが自分自身の喜びにもなると気付き始めたときのもので、雅也もこういう台詞を言えるようになるまで、成長したんですよ。
また、養蜂での体験において、様々な立場で物事を見ることや、生きることの大変さを教えられる。
例えば、
「刺されるっていうのは、人間本位の考え方。みつばちにしてみれば、刺さなくてもいい相手を刺して死ぬこともある」
「病気でみつばちが大量に死んだり、水害で流されたり。生きるっていうのは、いつもあきらめと背中合わせだ。残酷だな」
このような話を聞いて、雅也は少しずつ世の中にはいろんな世界があることを、実際の体験により、実感していく。また、みつばちの話から、海鳴たちを思い浮かべた雅也の意識の変化には、爽やかで、納得できる確かな説得力を感じた。
みつばちマーヤの冒険の名言と、養蜂の体験と、家庭環境で苦しむ子供たちの要素のブレンドが絶妙で、物語の展開は、伏線もしっかり入った喜怒哀楽に、大人も子供も楽しめる内容になっております。エンディングも爽やかな切なさがあって良かったし、何より、雅也を含めた個性的な六人の子供たちが、最初はギスギスしたけれど、悩みながらもみんなで少しずつ考えて、助け合いながら人生に向き合う姿には、本当に感動しました。
内容に関しては、子供に言うには少し厳しすぎるかなとも感じたのですが、それって、子供にもよりますよね。ただ、それは日々どんな子供なのか、気にかけていないと分からないし、子供というだけで、甘い厳しいを勝手に判断するべきじゃないよなと、自省するきっかけにもなりました。
「不幸なことがあっても、人に自分の人生を任せてしまってはいけない。それは自分の価値を下げてしまう。自分で自分に期待できるような人になってほしい」
上記は、子供たちを見守る「志保子さん」の台詞。厳しいと思うけれど、おそらく自らにも課している。子供たちを見て、大人も成長する。
Posted by ブクログ
児童文学に求めるさわやかさがあった。
だれにでも生きる力が必要だ。経験は人生最大の財産であり、経験を共有できる仲間がいることの素晴らしさを感じた。
この本には心にとどめておきたいフレーズが多くある。
Posted by ブクログ
発達障害かもしれない雅也は空気が読めず友だちが作れない。普通でない雅也は普通に憧れている。そんな雅也は「北の太陽」で訳アリの子どもたちや志保子さん栄さんと過ごすうちに宝物をいっぱい手に入れ、普通にこだわらなくても前を向いて生きる力を得る。児童書らしく、良い言葉がいっぱい散りばめられてたな。普通に拘らなくてもいいこと、誰かを守るということは人と触れ合うこと、誠実に生きること。そしてミツバチの面白い生態にも触れることが出来る。良い本でした。
Posted by ブクログ
発達障害の疑いがある中学1年の雅也と、様々な事情を抱えて北海道の児童養護施設「北の太陽」で暮らす子どもたちとの交流を描く。
彼らが共通して読んでいる『みつばちマーヤの冒険』から大切な言葉の引用がスパイスになっている。
「普通」ってむずかしい。
「普通」になりたいよなぁ。
「普通に生きるって、世界を実感することだと思う。世界を実感すれば、きっと変われる」と雅也と海鳴の会話がやるせない。
コミュニケーションがうまく取れない雅也と家庭がない海鳴は自分たちを「普通」とは思えない。
でも「普通」ってなんだろう?
「自分の力ではどうにもならないことで悩む苦しさがわからないなら、大人失格です」
「あきらめる練習よりもあきらめない練習が必要な人もいるんです」
雅也が大人に向けて投げ掛ける言葉は核心を突いている。
そして雅也たちは、あきらめない練習をする。
贅沢と反対されたピアノの発表会ドレスを買うために、イカめしコンテストの賞金を狙って参加する子どもたちの奮闘が素敵だ。
イカめし食べたくなる。
雅也はこの地で、居場所と友と生きる力を得た。世界を実感した一歩だったのだろう。
「もう希望しかない」を合言葉にした雅也と海鳴は、心の奥にまで差しこんでくる光を受けとめたのだろう。
Posted by ブクログ
「北の太陽」の子どもたちと過ごすひと夏の物語。
雅也は夏休みに、北海道の養蜂場で働くおじさんを訪れる。寝泊まりするのは「北の太陽」。さまざまな事情を抱えた5人の子どもたちが暮らしている施設だ。相手の気持ちを考えて話すことができず生きづらさを抱えている雅也は、同様に困難を抱えた北の太陽の子どもたちと共に過ごす中で、前を向いて歩くことができるようになっていく。
『みつばちマーヤの冒険』の印象的な言葉の数々が、ときに雅也たちの心と重なり、ときに生きていく道を照らし、物語を彩っていたところが素敵だった。
クラスの中で遠ざけられ疎外感を味わい続けていた雅也が、「自分を受け止めてくれている」と確かに感じ、誠実に応えようとする姿が微笑ましかった。個性豊かな5人の子どもたち、特に同い年の海鳴との心の深いところでつながりあった交流は読み応えがあった。初めは隔たりのあった距離感が、徐々に縮まっていく様子が見事に描写されていた。
養蜂場で働くおじさんをはじめ、「北の太陽」で働く志保子さんや栄さんの、誠実に自然や子どもたちと向き合って生きている大人たちの姿も魅力的。
いかめしコンテストの優勝者の決まり方が、コントのように描かれていたのが個人的には残念だった。もう少し納得感のある、本人たちのがんばりが確かに認められるような形で決まってほしかった。