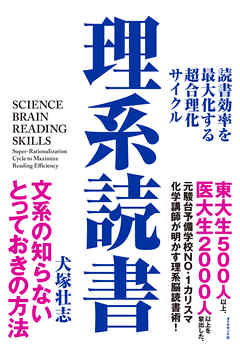感情タグBEST3
Posted by ブクログ
【理系読書】とは…超合理的な知的生産システム
◎理系は本を読んでいる瞬間を「楽しむ」より、読書で得た知識やスキルで自分が変わるのを「愉しむ」
【はじめに】
◎読書は自分の問題解決のためにするもの。全部読むよりも、本の内容をいかに実践するかが大切
◎理系読書で得られる5つの力
↳①問題発見力
↳②抽象化力
↳③仮説思考力
↳④行動デザイン力
↳⑤評価重視力
【1章】読書の効果が劇的に高まる3つのこと
◎本を読む前に読書効率を上げる方法
↳①問題意識の明確化
↳②①の解決した後の理想像の設定
↳③本から抽出した情報の活用
◎問題意識を絞り込む3つの有効な質問
↳①「なるべく解決したい重大な困りごとは?」
↳②「読んだ内容を使って、どんな状態になりたいか?」
↳③「周囲の人があなたに求めることは何か?」
◎情報は「絞る」が勝ち 残りの9割は捨てる覚悟でいい
【2章】読解力を高めて読書をモノにする理系読書
◎メタデータをチェックする…発行年月日/著者プロフィール/目次
◎スクリーミングする…本の旨味を抽出する
↳ポイントは「要約」や「図表」
◎クリティカルシンキング…疑う3つのこと
↳主張/ロジック/根拠
Posted by ブクログ
■ 印象的だった点
○ 本は1冊1ニーズ
○ 超合理化サイクル
○ 問題意識の明確化 外向的質問
○ 本の旨味を抽出する
今後、専門書・論文を数多く読んでいくことを想定し、読書効率の改善を目的にこの本を読んだ。今まで、買った本はもったいないので全て読んでいたが、読書とは「やってみる」と「確かめる」のためのものであり、自分の問題意識と合致する箇所のみ抽出して読むことが大切だとわかった。本書の超合理化サイクルは専門書・実用書・論文に適用可能な技術であり、汎用性と再現性に優れた情報なので、これらの本を読む人にはオススメ
Posted by ブクログ
【レビュー】
積読をなんとか片づけたいと思っていた矢先にたまたまネットで知り購入。
徹底的に効率的な読書を推奨する筆者の論調に最初は戸惑うが、単なる時間節約や多量のインプットを伴う速読術ではなく、本を「必要な情報を得るツール」と割り切って読む箇所を厳選し、読書のパフォーマンスをいかに高めるかに重点を置いている点でこれまでの読書術の本とは一線を画す。
著者の展開する方法論は、例えば卒論を書く際には大量の論文から必要箇所だけを拾い読みするが、それを日常の読書にも当てはめるイメージ。
何のためにその本を読むか(=目的)。どうすればその目的を達成する読書ができるかを突き詰めた合理的読書のすすめ。
自分は読書をする時間そのものが好きなので、著者の割り切り方に完全同意はしがたいものの、本のジャンルによっては取り入れていきたい。(専門書などは特に有効。)
【参考になった箇所】
・15分で集中して読書する
・その本を読む目的(自分が埋めるべき穴)を決めて拾い読みする
→質を向上
・効果/コスト=コスパを最大化する
・読む→実践→検証のサイクル
・本を読んでどうなりたいか、理想像を予め決めてから読む
・1冊1ニーズ。同時に複数のインプットをしない。(∵情報量が多いと結果定着しないから)
2章
・目次のラベリングでどこに何が書いているかを把握
・スクリーニングで読む箇所の強弱をざっと選別→強弱に応じて読む
・要約情報、図表などから読む(∵効率的、素早く理解するため)
・読書で得た情報をまとめるフォーマット(P142)
・小さな試し打ちをたくさんやってみてたくさん失敗する。何もしないでわからないままのほうが危険
Posted by ブクログ
数ある読書術の本の中でも、特にわかりやすく「読書をビジネスや実生活に役立てる方法」を解説してあった。
正直、めちゃくちゃおすすめ。
たいていの読書術に関する本は、「読書の仕方」に焦点が当たっている。
しかし、この本は違った。
読書の方法よりアウトプットの方法を重点的に。
さらには、その先のフィードバック(確認方法)のやり方まで教えてくれる。
そんな本に、ボクは、今までほとんど出会っていない。多くの場合が、せいぜいアウトプットの方法までだった。しかし、有効だったかの判定が出来なければ本当に役に立っているかはわからない。意味のないことを頑張って続けてしまうほど虚しいことはないはずだ。
だから、人生を変えたくて本を読んでるのに、現実に全く活かせている気がしないと感じている人にこそ、ぜひ読んでもらいたいと思う。
①まず、狙いを定めて本を選ぶ
②必要部分だけを読む
③何度もやってみて自分のものに(反復)
④フィードバック(効果判定)
上の流れが、主な「理系読書」の手順になる。
つまり、読んだ事を「実験」により試し「確かめていく」方法が「理系読書」になる。
さっそくやってみた。
理系読書そのものが、最初の実験だ。
ボクは今まで、上記の③までしかやってなかった。やりっぱなしでロクに成果も確認しない。だから、なんとなくでやめたり続けたりの判断をしてきた。
チェックを怠っていたから、なんとなく迷いながら続けてきたことも少なくない。
この本のおかげで、何処に問題があったか気付けた。
ありがとう、「理系読書」。
ありがとう、犬塚壮志さん。
Posted by ブクログ
まず気になったのはタイトル。理系とついているがあくまで理系出身である著者が行っている「理系的な」読み方と言うことであり、文系理系問わず実践できる読み方が書かれています。その辺はご安心して購入してもらって大丈夫だと思います。
この本はいわゆる「速読術」のような本を読む技術が書かれているものではありませんので注意。
本を読むときに、全てを読む必要は無いと著者は主張しています。
では、「どこ」を読めばいいのか。それを見つけるためにどのような準備をすれば良いのか、また読んだ効果を最大限に発揮するには、読んだ後にどうすれば良いのか、行動した後にその結果をどう評価すれば良いのか、そしてその結果を次の読書にどうつなげるかといった内容が書かれていました。
読書の本と言うよりは、本とどのように向き合っていけば自分の生活がどう変えていけるかということが書かれていて、なるほどなぁと思いました。
つまりこの本は、社会人が自己啓発や、自分を高めるための勉強に使う読書がメインターゲットになっています。
時間がない中で、今の自分を変えたい。それを読書で実現しようとしている人に向けて書かれた本です。概ねなるほどと思う内容で、啓発系の本を読むときには取り入れてみようと思う心構えがいくつかありました。
ただ、私が納得できなかったのは、やはり必要なところだけ読めば良いと言うところ。確かに時間を短縮するためには、読まないと言う場所を作る事は大切だと言う事は理解できますが、そうすると自分が読もうと思った場所しか読まないので、「自分では思っても見なかった知識や考え方との出会い」が減ってしまうと思うからです。
自分は理系出身なので、読んでみれば確かにネット思う内容が多く、新しい発見は少なかったですが、これまでなんとなく感じていたことが整理されて目の前に並んでいたのでそういう意味で理系の方々にもお勧めできます。
とりあえず本は読んでみているものの、自分の成長につながっているか分からないと言う人や、なかなか成長を感じられない人は読んでみて損はしないと思います。
また、多くの本を読んできた著者がこの本の中で紹介する別の著者の方が結構面白そうで、この本をきっかけに知らない分野の読書へと進めそうです。
Posted by ブクログ
理系的アプローチで読書する方法が学べます!
すごくしっくりきた方法。
やってることも結構あったけど、読書を実践した後の評価まではしてなかったなと反省。
読みっぱなしになってるなーと思う人には非常に参考になると思います!
Posted by ブクログ
本書で紹介されている読書の方法は、今までの自分の読書とは根本から違う読書のやり方だった。理系読書というタイトルの通り、読書の方法は、学校の理科の実験と同じ手順だった。まず、その本を読む目的を定め、自分の知りたい情報とそれについての仮説を決める。そして、目次から本の構成を把握し、自分の知りたい情報に辿り着く。さらに、その情報の質を見極めたうえで、実行にうつす。実行は、実験のように変える条件を一つにしぼり、結果からその効果を考察できるようにする。本書にはそれが筆者の経験から具体的に書かれている。
筆者が特に強調していたのが、問題意識をもつこと、実行することだ。私は読書をするとき、自分の知りたい分野の本を最初から最後まで一字一句ただ読んでいた。本書を読んで、読書はもっと能動的、積極的な心構えで読もうと思った。車でどこかに連れて行ってもらっても道は覚えられないが、自分で車を運転して行くと、道を覚えられるのと一緒で、何らかの意思を持って読み、実践することが大切だと感じた。
Posted by ブクログ
勉強の時の読み物は必要なところだけ読むのに、読書だとひたすら文字を頭から読んでいたと気付かせてくれた。
もっとも重要なのは問題意識であり、答えを見つけるために読むことだと思った。
僕はなんとなくで読む本が多いが、問題を1つ発見し、意識しながら読み、得られたもの評価することを心がけたいと思えた。ただ15分で十分な内容を得られるかは少し不安である。
Posted by ブクログ
何のために、本を読むのか。
結局は自分に何が足りていないのかを考察して、本から必要な物ことを最短で抜き出し、実践していかに活かすのか。
著書の説明がわかりやすく、これから実践していきたい!
Posted by ブクログ
本を使うということに特化した本。ただ読むだけじゃ勿体無いと思う人には刺さる内容です。気になるところだけ読むというのを筆者も推奨していることだし、まずは目次からどうぞ。
Posted by ブクログ
赤線で引かれたところだけを読んでも理解できる、とても親切な本だった。
ビジネス本を読む際、何かしら解決したい問題があるはずなので、全部を読もうとしなくていい。
解決策が載っているであろうところだけを辞書のように読み、得られた策を実践してこそ読書が生きる、という内容。
本の選び方や提示されている解決策の精査の仕方など丁寧に書かれていた。
ビジネス本を読む際に再度読んでみたい。
Posted by ブクログ
スラスラと読めた。内容は理系が得意とする準備、実験、評価といった一連の流れを読書においても実践する合理的な方法を説く。
何より実践をするということが、よくよく読書の後に私は抜けがちなところなのであるが、その一段階を乗り越えるために、「本は全部読まなくていい」とハードルを下げてくれ、また貪欲なところを「本からの部分的変化を目指す、変化率は1%未満」と本を読むこと自体をかなり軽くさせてくれる。
確かに「本は全部読まなくていい」ということは成毛眞さんも述べられていたことだったかなぁ。
しかしついつい最後まで読んでしまうのは、何処か私は正直なところで自己満足やらを充足したいところもあるのだろう。
Posted by ブクログ
理系が行う、効率的に情報を得るにはどうすればよいか教えてくれる本。
「1冊1ニーズ。欲張らない」「1%の変化でもやってみることが重要」と、もっと気楽に、しかし実践的に読書をする必要があると痛感した。
読書で学んだことを使える様に、試し打ちと反復は行なっていきたい。
超効率的に学びアウトプットができるようになる。
Posted by ブクログ
読書術習得を目的として読んでみた。自分が理系なので親近感が湧き期待もしていたが、少なくとも本の大筋に文理は関係なかった(理系の小話は登場する)。本書の本質は「読書する上での意識付け」を説いている序章にあると思う。読み方等のノウハウも紹介されているが、そこは本書よりも詳しい書籍があると感じた。読書術の本を何冊か読んでいる人にとっては目新しい発見はないかもしれない。とは言え序章で説くテクニック(意識付け)は、本に限らずwebでの情報収集でも役立つものと感じた。
Posted by ブクログ
読書で知識をどのように書籍から抜き出し、自身のスキルにするか。「読む」「やってみる」「確かめる」のサイクルで回すこと。「やってみる」がなかなか実践できないので、本書にあるように少しずつ実行にうつしてみたい。
Posted by ブクログ
本は最後まで読まなくて良い、ある程度、仮説を立てて眺め、必要なことを得られたらよしとする、重要なのは得られたことを実践すること、ポイントを絞れば15分で一冊は読める、とのこと。
意外に使えるのは、欄外にある著書が薦める本などが目録としても使えるのでいいですね。
Posted by ブクログ
問題解決のために本を読む。全部読まなくていい。
問題発見、抽象化、仮説思考、
一冊15分で合理的に読む。15分読書を数回繰り返す。記憶しやすい。
問題意識を明確にしてから読む。本から情報を抽出する。
読む:やってみる=1:5
反復練習しながら物事を覚える。15分読書。やってみるを多く。
知識を定着させるために口頭説明のトレーニング。