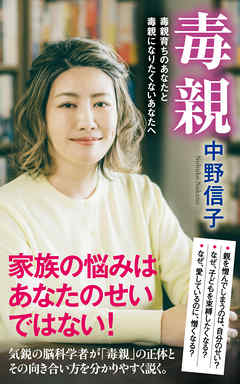感情タグBEST3
Posted by ブクログ
今の自分にぴったりな本だと思った。
まず、毒親は寂しいから、自分のコントロール下に置けない、自分の知らない能力を持っていることを嫌うのだと思った。怖いんだな多分。
オキシトシンの話もすごく沁みた、陣痛時に出るオキシトシンには母子愛着形成の作用があったのか。
あとは、親切な人が好きな人間の心理も理解できた。人間が元来から生き抜くためには、自己を犠牲にして集団を守ることによって生き抜いてきたことから、他人のために親切になれる人がモテるのだと学んだ。親切な人は自分を守ってくれるからって言うのが本音なんだなと思った。
毒親からの解放は、静かに暖かく自分の人格を認めてくれる人と出会いその人の真似をするということ。まさにパパとママみたいだなと思った。
家族関係が良いのが美とされる考え方は本当にいらない考え方だと思った。
私は正直愛し方がわからない。だからちゃんと人を愛せるように育ちの本も読もうと思った。教育についても学ぶべきだと思った。
いつまでもこんなに苦しんだんだからと親のせいにしたくない、変わるのは自分。
Posted by ブクログ
ハリーハーロー赤毛猿の赤ちゃんの実験結果は衝撃的。大きなストレス、躾としての体罰、夫婦喧嘩で子どもの脳は傷付くことがわかっている。自分を育て直すことが、希望。
Posted by ブクログ
「毒親」というタイトルに、親子間のモヤモヤの救いを求めるかのように手に取った節がある。
単に親の所為にして終わりということでは、毒親問題は解決できないことを、改めて気づかせてくれ、問題解決の糸口、ヒントを見つけられる一冊であった。
全ての親と子へ、互いの関係性に悩んだときに、その都度読み返して欲しい本である。
Posted by ブクログ
何故毒親が毒親になったのか、その連鎖はどのように起きていくのか。
様々なケースから紹介されていく事例はどれも心が痛い。こんな事があるのかと驚きの連続だった。
時代が変われば人間も変化するように家族の形も変わっていくのかもしれない。
Posted by ブクログ
勉強になった。メモした文章がたくさん。
子どもにとって完璧な親っているのかな。どんなに子どもこと考えて行動しても、自分とは違う人間。それが子どもが望む行動や対応とは限らない。親子関係って難しいなと思う。
Posted by ブクログ
タイトルに惹かれ、手に取ってみた。
子供の心と自分の心の両者に、親である人はゆっくり、ちゃんと向き合って、接していけるだけの余裕が本当は必要です、の一文が刺さった。
大抵のよくないことは、忙しかったり、感情が不安定で余裕がなくて視野が狭くなった時に起こる。更に距離感が近すぎると悪影響はより強くなる。親子といえども適度な距離感が必要だ。
子育ては、毎日試行錯誤だ。親も変わる努力が必要。
人間関係の基本にあるのが親子関係。
(生後6ヶ月〜1歳半までの間に、対人関係の基礎となる型を親との関係の中で身につけるんだと!)
その親子関係が歪な家庭も珍しくなくて、勉強したいなと思って購入した本。
もうすごいの。内容盛りだくさん。
毒親を非難・攻撃する内容ではなくて、どうしてそうなってしまうのか、脳の作りと共に解説もあったり、それから毒親に育てられた人へのメッセージもあり、とっても素敵な本です。
知らなかったことがたくさん知れて大満足です。
Posted by ブクログ
内容は割と軽く読みやすい。
脳科学者なだけあって、心理学的なアプローチで書かれる毒親本が多い中(本書にも出ては来るが)、脳から出てくるホルモンから毒親の特徴を分析していたのは新しい知識だった。
Posted by ブクログ
少しだけだったが、どうしたら毒親にならないか、どうしたら毒親による傷が癒えるかについて言及してあった点はよかったし、参考になった。母親の育児負担は減らさないといけないと思う。
Posted by ブクログ
大変失礼だけれども、正直、まったく期待していなかった。本書でも名前のあがったスーザン・フォワード氏、信田さよ子氏、岡田尊司氏をはじめ、斎藤学氏や海外の毒親関連本も多数読んでいたので、、中野氏の『毒親』は、きっと、本の厚みと同じくらい薄い内容だろうと高を括ってた。しかし、予想外に、心に残るものがあった。中野氏の理知的でありながらも毒親育ちへの優しいまなざしが感じられる筆致に励まされたのかもしれない。
特に印象に残っている部分に触れてみたい。
『毒親、というのは、「自分に悪影響を与えつづけている親その人自身」というよりも、「自分の中にいるネガティブな親の存在」』
⇒いまだに私は自分の中に毒が残っているのを感じる。
事あるごとに、母に責められるような感覚を持つ。
もう何年も物理的には離れているのに
「そんなことをしたらバカだと思われる」
「どうしてもっとテキパキできないの?」
「親不孝者!」
そんな声に怯えてしまうことがある。
『愛情と攻撃を司る機構は意外にも脳の中では近接している。また、この感情は、家族間のほうが他人よりも高く、互いの類似性が高いほど、高まってしまう。』
⇒同族嫌悪の最たるものだろうか。
母親が長女を自分の手足のように感じ、思うようにならないと激しく攻撃するのは、残念だが周りでもよく聞く話だ。
『受けてしまった傷の深さはどのように脳に刻まれるだろうか。脳は、物理的に危害を加えられたり、ひどい言葉を常に投げかけられたりしていると十分に発達しないことがある。背外側前頭前皮質が損傷を受け、キレやすく、欲望への抑制が効かなくなったり、冷静な思考がしにくくなったりする。ギャンブルやアルコール依存症のリスクも上昇、性的依存も一面ではこのような原因があると指摘されている。社会通念からみれば許されないことを判断できず行ってしまい、歯止めが利きにくくなってしまう』
『ハリー・ハーロウのモンスターマザーの実験。
赤ちゃんのサルを、布の母(スポンジと柔らかい布でできた人工の母親)とともに孤立させる。布の母には、赤ちゃんが近づくと突然激しく振動したり、板で弾き返したり、圧縮空気を噴出したり、一定時間がくると(先は尖っていない)針が飛び出して突いたりする仕掛け。どうなったか。なんと赤ちゃんは、どんな目にあっても何度も繰り返し抱きつこうと近寄るのをやめなかった。』
⇒虐待が執着を増幅させてしまうのだ・・・。
娘が60代、母が80代になってもこのようなことを繰り返す関係を知っている。母に振り回され、理不尽な目に合わされ傷つき、心を閉ざして一時的には距離を置くけれど、また自分から近づいてしまう娘。母親は、決して謝ることは無い。まるで20年前の自分を見ているようで、気持ちが痛いほどわかるだけに、とても切なくつらい。
『研究によると「子どもの前で夫婦喧嘩をすることそのものよりも、仲直りのシーンを見せないでいることの方が大きなダメージを与える。」仲直りの場面を見せることで、親同士の傷ついた関係は修復できるのだとという安心感を与えてあげる必要がある』
⇒完璧な関係なんてない。たとえ全部を受け入れられなくても、理解し合えないことがあっても、それでも仲良しで、ずっと一緒にいることができる。この世界は安全な場所だ、という安心感や信頼感を子どもたちに持たせることができると思う。
『自然な恋愛感情以外の何かを相手に求めてしまい、それが得られないと世界全体から拒絶されたような絶望感を味わってしまう、という人は、相手を対等なパートナーとしてではなく、かつて子ども時代に自分を愛してくれるはずだった人の代わり、としてとらえている可能性がある。大人になれば仕事もある。24時間、赤ちゃんを育てるようにあなたを見ろと望むのは酷だ。』
『そんなときは、信頼できそうな相手(恋人・パートナー・友人)を見つけよう。そしてその人の「愛し方」をよく観察すること。
(1)自分本位の感情であなたを振り回す人なのか。
(2)あるいは気が向いたときだけ愛して、あとは邪魔者扱いをする人なのか。
(3)それとも、静かな愛情で、いつも何がどうあろうと相手の人格を認め、大切に扱おうとする人なのか。』
『もし(3)に当てはまる人なら、その人は「あなたの運命の人」つまり、「あなたの人生を変えてくれる人」である。』
『しかし(3)の人に全身で寄りかかるのではなく、この人が自分に向けてくれる淡々とした、しかし深い愛情のあり方を、自分でも体得していこう。この人が向けるような静かな愛情を、自分でも自分に向けてみる。どんな失敗をしようと、どんな姿でも、あなたはあなたであり、僕/私の大切な人だ、というメッセージを、自分自身に発してあげてみてほしい。もしうまくできたなら、それが自然にできるようになるまで、毎日花に水をやるように、最初は意識的にでも繰り返してあげてほしい。』
⇒私は幸運なことに、親との関係を必死に見直し始めて10年経った頃、まさにこの(3)に該当する友人と出会った。彼女は『ここは私の居場所じゃない-境界性人格障害からの回復』のパジェット医師のように、静かだけれど深い愛情で、根気強く接してくれた。
私の知らない世界に生きる人だった。彼女を観察し、彼女がどう世界を見ているか、教えてもらった。そして自分の本当の感情と向き合い、どんな時も自分だけは自分の味方だと自分を励まし、私は長い期間をかけて変わっていくことができた。
まさに、中野氏が書かれた通りの過程を経て、私は私の人生を取り戻すことができたのだと思う。
毒親育ちだからこそ、周りの人の気持ちにもよく気づくし、痛みも理解できる。そこから立ち直って、新しい、自分自身の人生を歩める喜びは何にも代えがたい。
20年前の私のように悩んでいる人たちに伝えたい。
その気になれば、人間、必ず変わることができる。
楽な道を選んで、人生を他人に乗っ取られ、泥の中をはいずるような人生は終わりにして欲しい。
Posted by ブクログ
p. 110 母への葛藤が大きすぎて、自分は母を愛していたと、自分に言い聞かせなければならないほど、ギリギリの感情が彼女にはあったのではないでしょうか。(蜘蛛オブジェに「ママン」とタイトルをつけたルイーズ・ブルジョワ)
p. 158 子どもの前で夫婦喧嘩してしまったら、仲直りしている姿を見せることが重要。
自然な恋愛感情以外の何かを相手に求めてしまい、それが得られないと世界全体から拒絶されたような絶望感を味わってしまう、という人は、相手を対等なパートナーとしてではなく、かつて子ども時代に自分を愛してくれるはずだった人の代わり、としてとらえている可能性があります。
Posted by ブクログ
読み易くわかり易い。水島先生の毒親は、発達障害の観点から書かれていたが、中野先生は脳内物質を絡めて過去の実験等から紐解いている。
読んで1番に思ったのは「キャリー」と言う映画。
他にも沢山毒親が関わる映画もあったけど、、
閉鎖された個の家族では解決は難しいのかなぁ。自分を育て直す、と言う一文に癒された。
Posted by ブクログ
暴力を受けたり目の当たりにすると前頭葉が萎縮することが判明したのか2009年だったということが一番の驚きだった。つい最近じゃないか…
針金で作った母猿ミルクと布で作った猿の実験も興味深かった。
六本木の蜘蛛もフランスの女性が家庭環境に恵まれていなくて母をモチーフに蜘蛛を作った話も面白かった。
Posted by ブクログ
毒親、あまり聞きなれない言葉ですが、人のキャラクター構成する上では、家庭環境いわゆる親の存在が良くも悪くも影響してきます。親の価値観を押し付けたり、何気ない言葉で傷を抱えたり…
最後の言葉として、自身への愛情を深め、自分自身の人生を進んでいくことで未来は変えられる、と。
Posted by ブクログ
具体的な案件の対応に参考に参考になるかと期待して読んでみる
そういう意味では、具体的な親子関係で当該親が毒親に該当するかや、毒親の子供のために何ができるか、という問いに対する回答は得られなかった
子供を傷つけてしまう親の心情はなんとなく理解できた気にはなった その結果、子供にどういう影響が出てしまうのかも何となく分かった気になれる
Posted by ブクログ
(更新中)
・簡単な文章で分かりやすかった。
・白雪姫コンプレックスなど専門用語を知れた。
・パンドラの箱の語源を知れた。ギリシャ神話。
・六本木ヒルズにある謎のクモのオブジェ(ママンという名前)のゆかり、彫刻家の一生を知れた。
・ハロー氏による猿の実験(布の母、針金の母)が印象的だった。スキンシップの重要性。レイプマシーンという言葉に不謹慎ながらちょっと笑った。
・世代間連鎖の話
・独親のもとで育つことによる影響(下垂体皮質、前頭葉の萎縮など)など科学的根拠のある内容で構成されているが、作者の医学博士としての研究成果による仮説、論理が記載されているわけではないので、目からウロコ!という本ではなかった。(導入本を意図しているのかもしれないが)
・社会人になり一人暮らしを始めたあたりから、自分の中で直接の独親問題は解決し始めているので、毒親のもとで育った自分が現実社会でどう生きるか(たとえば自己肯定感が低いことでダメ男と付き合ったり、良い仕事を引き受けられなかったり、前に出るところで出れなかったり)ということを1番に知りたかったのだが、最後の章でチラチラと書いてあるのみだった。(これは自分の下調べが足りなかった)
・寝る前に、その日に何ができたかに関係なく、自分は素晴らしい人間だと唱えようかなと思う。無条件の愛を自分に向けてみる。
Posted by ブクログ
タイトル同様、内容も衝撃的だった。自分と似ていると毒ついてしまう、子どもと張り合ってしまう。自身がまだ未熟で、誰かに認めてもらいたいんだろう。周りの共感、共助が不可欠。
Posted by ブクログ
多様性を認めようという世界的な変化はあれど、家族の形や、それを構成している親と子の関係の多様性は、まだまだ発展途上なのかも知れない。
クローズな世界だからこそ、客観的な意見をもらいづらく、また他の家庭の問題に意見をするのは難しい。結果、自己解決が主な手段になってしまっている。
何を学べば、この問題が解決するのか分からないが、色んな家族の経過と結果を知ることが一歩なのかも知れないと本書を読んで感じた。
Posted by ブクログ
これまで多くの毒親関連本を読んでいたので、正直これと言って新しく感じる内容はありませんでした。
P173に愛情遮断症候群の治療について書かれていましたが、この内容については私も実感でその通りだと思いました。
申し訳ないけれど、家庭環境によっては、家庭環境から完全に引き離し、安心できる環境下で生活を送ることが、毒親育ちの子にとっては一番幸せになれるのではないかと、この本を読んで改めて感じました。