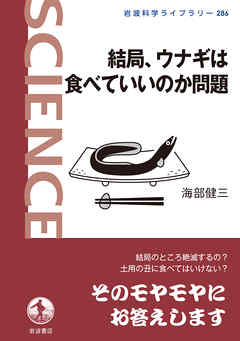感情タグBEST3
Posted by ブクログ
ウナギ好きの友だちと意見が合わず、もっと科学的な知見を得ねば〜!と思って読む。
すごくわかりやすく問題を整理して書いてあった。他人の行動を制限することはできないけど、わたしは生きてるうちはもう食べないかなあ。うなぎパイはどうしようかなあ。
Posted by ブクログ
ニホンウナギは早晩絶滅しちゃうかもな…
ウナギ産業はかなりブラック
みんな知っててみんなやってるって感じなんだろう
しかしなぁ、一消費者が不買運動したところで…目の前ですでに蒲焼になって売れ残ってるウナギを見たら廃棄される方が忍びないと思っちゃうんだよな
みんなやってる限り個人とか一企業でどうにかできる問題だとは思えないけど、この国は科学的根拠の乏しいやってる感だけの措置をやりがち(ウナギに限らず)なのでやっぱりニホンウナギは早晩絶滅しちゃうかも…
Posted by ブクログ
タイトルの通り、ウナギって食べていいの?という疑問の入門書。章立ても1つ1つの項目も文章も分かりやすい。ただ、結局食べていいのか悪いのかは断言してないので、本を読んで個人個人が考える結論になると思う
Posted by ブクログ
密漁や密輸、密売によってシラスウナギの正確な漁獲量が誰にもわからない状態になってしまっている。
そのため、うなぎが絶滅しそうなのかどうかの判断も難しくなっている。
うなぎが未来でも食べられるよう、消費量の上限を定めて、そのボーダーを守ることができるのなら、うなぎを食べてもいいと思う。
けれど少なくともこの本が発売された2019年の段階では、うなぎの養殖産業関係者やシラスウナギを獲る漁業関係者は、違法行為を黙認して、改善を望んで違法行為の事実があることを公にする人を煙たがっているらしい。
個人的にはうなぎのタレの味が嫌いなこともあって、今後もうなぎを食べる気はない。でも絶滅してほしくはないし、うなぎ産業の人たちが職を失うことも望んでない。
うなぎ好きな人はこの本を読んで、罪悪感なくうなぎを食べられるにはどうしたらいいのか学べると思う。
Posted by ブクログ
大半のウナギは違法な手続きを経ている、放流は生態系への悪影響があるからしてはいけないといった、なかなか厳しいことが書かれている。たかがウナギ、されどウナギ。考えさせる内容でした。
Posted by ブクログ
結論として、食べていいのか、悪いのかには
触れていません。
しかしウナギに限らず、絶滅の危機にある生
き物のことを少しでも考える契機になれば、
という著者の思いが見えます。
よくニュースで目にする稚魚の放流などでは
かえって環境を悪化させる恐れがあるという。
「自然のための寄付金を売り上げから捻出し
ています」などという活動も怪しいといいま
す。
など、従来の環境保全活動の見方が変わる
きっかけとなる一冊です。
Posted by ブクログ
以前、『サカナとヤクザ』を読んだときも思ったことだが、この国はおかしい。絶滅危惧種に指定されているウナギをなんの疑問も持たず、ありがたがることもなく、単なる風習だからという理由で大騒ぎして食べる。ウナギの増減についての調査も行われることはなく、ヤクザまでが絡んでいる密漁に対しても法の手が及ぶことはない。本書においてもウナギを巡る様々な“疑問”がQ&A形式で解説されていて、また新たな憤りを感じてしまった。
ウナギを食べる人を否定するつもりはない。本書でも結論は個人に委ねられている。
Posted by ブクログ
ウナギの漁獲量減少に伴い、スーパーでみかけるのは中国産ばかりで、国産は値段が高いのはおなじみの光景ですが、そのウナギ資源の減少について、よくまとっている。