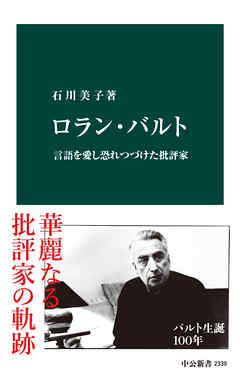感情タグBEST3
Posted by ブクログ
「作者の死」を言った人、くらいの認識しかなかったバルトの全体像を初めて読んだ。何よりも面白かったのは、バルト自身が、誰よりも「作者」であることにこだわって、作者の言葉を大事にした人であったということがよく分かる伝記だったことだ。作家や哲学者、評論家といった文章を書いた人たちを理解するのに、有名な文言や本だけを切り抜くことが、いかに間違っているかを、つくづく感じた読書だった。
特に一番印象的だったのは、やっぱり第四章のII節に出てくる「作者の回帰」の部分。読者の読みを重視して、テクスト論を唱えた印象とは異なり、バルト自身は、生身の「作者」の存在と大切にする人だった。
「「テクスト」の快楽は、作者の友好的な回帰ももたらす。回帰する作者とはもちろん、制度(文学や哲学の歴史と教育、教会の言説など)によって認められた人物ではない。伝記の主人公でもない。[……]それは、ひとりの個人(戸籍や精神にかかわるもの)ではなく、ひとつの身体なのである。」
バルトは、文学者や権威的な批評家による、「作者の伝記的事実に依拠する実証的な」批評を批判した。ただ、そこで批判されているのは、大学や文壇といった制度が生み出した一つの作家像の存在である。決して、「ひとつの身体」を持った生身の「作者」の存在を否定したわけではない。
そして、生身の「作者」というのは、常に、ひとつの解釈に収斂することがない、複数性を持ったものなのだとバルトは言う。だからこそ、のちに、バルトは、自分がもし「作者」だったらひとつの作家像に縛られない様々な自分を見出してほしいと言う。
「もしわたしが作家であり、死んだとしたら、友好的で気楽な伝記作家の配慮によって、わたしの生涯がいくつかの細部に、いくつかの好みに、いくつかの変化に、つまりいくつかの「伝記素」だけにしてもらえたら、どれほどうれしいことだろう。」
作家の書いた言葉自体を大切にして、テクストとして読むこと。それが、書いた作者に対する最大の敬意なのだと思った。
バルトの名前は知っているけれども、一度もちゃんと勉強したことはない人たちの入門書として、すごくいい一冊だと思う。
Posted by ブクログ
非常にわかりやすい文章で、ロラン・バルトの人生と作品を追っている。
惜しむらくは、バルトの翻訳作の案内が全て網羅されておらず、著者による読書案内がないのは残念であるが、その点を除けば、ロマン・バルトへの愛を感じさせる、彼の網羅的な案内となっている。
Posted by ブクログ
大学時代、バルトはフランスの作家で1番好きな存在だった。あれから20年たってもなお強烈な輝きを保っていることに素直に驚く。バルトの優しさ、人間味が現代性を帯びて何十年も愛され続ける、という近未来を、学生時代には全く想像さえしていなかった。本棚に眠る明るい部屋と、彼自身によるバルトからまずは久しぶりに読んでみようと思う。
Posted by ブクログ
バルトの生涯を、作品とともに詳説する。ただ重きを置いているのは作品の内容よりも、バルトが何に触れ、バルトの身に何が起こり、そしてバルトが何を感じたかという方に置かれている。最愛の母が亡くなった後のバルトの描写は、悲壮感もあった。
Posted by ブクログ
権威が嫌い。また、日本との出会いがいかに重要であったか。繊細な人物である印象を受けた。
・バルトは作品への向き合い方には三つの方法があると語る。読書と文学の科学と批評である。読書は作品を愛し、作品を欲することであり、作品以外の言葉で作品を語るのを拒むこと。文学の科学とは、作品のひとつの意味ではなく、意味の複数性自体を対象とする。批評はひとつの意味を生み出し、その責任を引き受ける。批評をするとは作品ではなく自分自身の言語を欲すること。
・「話し言葉は威嚇である」
・威圧的なただひとつの意味に抵抗するための新しい方法。意味の複数性とは異なるもう一つの可能性、すなわち(俳句にあるような)意味の中断であった。
Posted by ブクログ
バルトの著作の内容についてではなくバルトそのものの生涯について書かれてた。
『批評と真実』を読んだときさっぱり分からなかった部分が何故そういう風になっていたのかが分かってスッキリした。
それぞれの内容よりは文脈が紹介されていて、他の人間の分もこういうやつを読んでおきたい。
Posted by ブクログ
ロラン・バルトの生涯と思想について解説している評伝です。
バルトの生い立ちから、記号学への傾倒へと向かったバルトの修業時代につづいて、日本の俳句に「意味の複数性」ではなく「意味の中断」を見いだし、彼の思索が新たな表現を獲得したことが論じられています。さらに晩年の彼が手掛けようとしていた小説「新たな生」についても、コレージュ・ド・フランスの講義録を参照しながら紹介をおこなっています。
ときおりバルトの解説書のなかに、バルトのスタイルに感染したような文章でつづられたものを目にすることがあるのですが、本書は入門書にふさわしいスタイルで書かれており、バルトの仕事について一通りのことを知るためには有益な本だと思います。