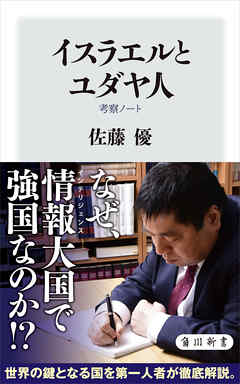感情タグBEST3
Posted by ブクログ
危機を認識し、警鐘を鳴らす思想家は預言者に連なる
イスラエルとユダヤ人から学んだ事柄について書いた論文とエッセイをまとめたもの。
中東に浮かぶ、自由主義、民主主義、市場経済の国、イスラエルと日本の物語
著者は、こういう。「全世界に同情されながら死に絶えるよりも、全世界を敵に回しても生き残る」という気概をもつイスラエル人の愛国心、さらにそれを支える神理解から、日本国家と日本人が生き残るための知恵を学ぶことが、私が本書を著した目的である。
イスラエルを地上から抹殺せんともくろむイランと、イランに核開発技術を供与する北朝鮮。それなのに、日本は親イランとしてイランを援助していた。
佐藤優を政治的に抹殺したのは、イギリスアメリカではなく、アラブイスラムなのかもしれない。
気になったことばは以下です。
・AIとバイオテクノロジー、生体認証などの融合により、独裁政府が国民すべてを常に追跡できるようになります。20世紀のスターリンや、ヒットラーなどの全体主義体制よりもずっとひどい独裁政府が誕生する恐れがあります。危険なのは、計画経済や、独裁的な政府が、民主主義国家に対して技術的優位に立ってしまうことです。
・巨大コンピューターにより、ビッグデータをアルゴリズムで処理する時代が到達しつつあるという予測をハラリ氏は改めて強調している。その時代が到来する結果、雇用環境は劇的に変化すると考えている。テクノロジーの発展によって仕事を失う人は多数出てくるが、転職するには高度の技能を身に着けなくてはならない。特にAI技術の発展によって雇用を失うのは、事務職のホワイトカラーと呼ばれる人々だ。この人たちが、荷馬車の馬と同じ運命をたどることになるかもしれない。
・イスラエルは、通常の国民国家ではない。全世界のユダヤ人を擁護するという特別の使命を持っている。それだから、イスラエル人はつまらない常識の枠組みにとらわれない自由な発想をすることができる。
・イスラエル人は、人間的関係を大切にする。一旦信頼関係を構築すると、どんな情報でも出し惜しみをせずに教えてくれる。
・イスラエルは、潜在敵国イランから、奇襲攻撃を受ける可能性を常に意識している。
・国交を断絶すると、利益代表国を指定する。ソ連におけるイスラエルの利益代表国はオランダになった。あるとき、モスクワのオランダ大使館領事部に勤務していたのが、オランダ人でなく、イスラエル人であったということを知るのである。
・ロシアの国境感、要するに国境線の外側にロシア領ではないが、ロシア軍が自由に移動できる領域、すなわち、緩衝地帯を求めるのである。状況が緊張すれば、そこに軍隊を常駐させる。ソ連体制が、1945年に第二次世界大戦が終結してから46年も存続したのは、東欧人民民主主義国という緩衝地帯があり、ソ連本土が直接戦争に巻き込まれた事例がないからである。
・ロシアがイランとシリアをたいせつにするのは、第一に経済利権で、第二に米国と対抗する上で、これら諸国と良好な関係をもっていることが外交カードとして有益だからである。裏返して言えば、極端なリスクをとってまでロシアは、イランヤシリアを守るつもりはない。
・イスラエルにとって米国は最大の軍事同盟国である。
・外国語には、突破しなくてはならないいくつかの層があり、ロシア語の場合、これ以上後退することはないという層を突き抜けたので、日常的にロシア語を用いる環境から離れても、いつでも、感覚を取り戻すことができる。だが、ドイツ語はそうはいかない。
・ロシア人は、国家のために命を捧げる気構えを持つ人ならば、外国人でも尊敬します。
・ロシアとユダヤ人、ロシア人の支配から脱してイスラエルに移住してきたユダヤ人は、政治的には、ロシアを好きになれないのだが、文化的には親しみを持ち続ける新移民が多い。そうした人脈がロシアとイスラエルとを緊密に結び付けている。
・北朝鮮がシリアやイランに核技術を援助している。イランがイスラエルを地上から消し去ろうとしている以上、日本がイランを支援してはいけない。
・ギリシア語でクロノスという流れる時間と、その時間を切断するカイロスという時間がある。アメリカにとってのカイロスは、2001.09.11、であり、日本にとってのカイロスは、2011.03.11 である。
・国際基準での無限責任とは、生命と職務遂行を天秤にかけるような状況が生じた場合、職務の方が重たくなるのが、無限責任である。
・日本版NSCの本質とは、「日本が戦争を行うか否かについての国家意思を決定する機関」である
・IT産業と軍事を切り離すことはできない。イスラエルと日本がIT産業で協力するということは、同時に防衛協力を進めるということです
・ヨハンセン工作:第二次世界大戦下、日本のスイス公使館では、イギリスのスパイである吉田茂元駐英大使に工作をおこなっていた。しかもその摘発をおこなったのは、陸軍中野学校出身者であった。
・中国とイランは同じ外交哲学をもっている。つまり、既存の国際秩序を一方的に変更しようとしている。
・日本の有識者には、親パレスチナが多い、ハマスや、イランの危険性を過小評価することにつながっている。
・米国のシリア攻撃について、日本では水面下で別の動きをしていた。それは、2020年の東京オリンピックを誘致するために、アラブ諸国、イスラム諸国に融和策を展開していた。
・1970.11.25 三島事件が起きる。左翼には、第二、第三の三島を左翼にいわせ、右翼は、本気だったのかと、三島が以来右翼の神となった。
目次は以下です。
新書版まえがき
まえがき
Ⅰ 私とイスラエルについての省察ノート
Ⅱ ロシアとイスラエルの考察ノート
Ⅲ 日本とイスラエルの考察ノート
Ⅳ イラン、シリア、北朝鮮の考察ノート
Ⅴ キリスト教神学生への手紙
あとがき
Posted by ブクログ
ユダヤ人が何故、長い歴史の中で虐げられながらも、世界経済、政治的に重要な存在であるのか、もっとふかけ知りたい、いや知らなければならないと感じさせてくれた。
そして宗教を学ぶ事は、世界の歴史のみならず、経済、政治を知る事であることも。
Posted by ブクログ
星4つをつけました。但しこれは記載の内容に感銘したとか、強く同意した、とかではありません。
著者の書籍はいくつか手にしてきた中で、その博識に強く感心しております。その原動力が何なのかを思う中に、本書にその断面を垣間見た様な気がします。
Posted by ブクログ
メディアで流れているものは誰かのフィルタを通したもの。1つを無条件に受け入れるのは危険だなと改めて感じました。イスラエルのこと、ユダヤのこと、キリスト教のこと、を自分で考えた事が私はあっただろうか。考える土台を学んでいきたいと思います。
Posted by ブクログ
著者の考え、思考が神学から由来している、というのはほかの著書でも何度も記述されているが、今回、はじめてその深掘りされているところを得られたように思う。
考え方や情勢分析など、著者の思考を追体験する形で得るものは多い。また、「スパイ」「ユダヤ人」「ロシア」「外交」といった切り口からの著述は、著者以外には書けず、それぞれが複雑に絡み合っていて深遠さを増している。
新書ではあるものの400ページ近くあり、かつ、記述が難解なところもあるので、人を選ぶ本であるのは事実である。ただ、「毛色の変わった少し難しい本を読んでみよう」という人が挑戦してみる価値は十分にある。
-----------------------------------------------
「日本の外交官は、日本国家だけを、日本国民だけを愛するんだ。それがわれわれの職業的良心だ。」
「どんなに立派な理念でも、それが現実に影響を与えなければ意味が無い。」
「新帝国主義国は、相手の立場を考えずに、まず自国の要求を一方的に行います。」
「(耳を傾けない人にも)事実に基づいて釘を刺しておくことは必要です。」
Posted by ブクログ
「全世界に同情されながら死に絶えるよりも、全世界を敵に回しても生き残る」これがイスラエルの国是だ。世界の政治・経済エリートへ大きな影響力を有す情報(インテリジェンス)大国。中東と世界情勢を分析するには避けては通れない国だが、その実態はあまりにも知られていない。「イスラエルは通常の国民国家ではない」と喝破する第一人者が、イスラエル人の愛国心、さらにそれを支える神理解を読み解く!
最近イスラエルとパレスチナの問題に興味を持ち始めて読みましたが、意外と著者の外交官としての矜持や心持ち、そして信仰のことが多く書かれていて意外でした。イスラエルという国の存在を認めようとしないイランやハマスの恐ろしさを日本人は全然分かっていないんだな。北朝鮮という国がすぐ隣にあってどうしてこんなのどかなんだろうと思ってしまうくらい、この国は危機感がない。世界から取り残されないようにインテリジェンスを身に着けていきたいし、外交官たちにはぜひ愛国心をもって働いてほしい。
Posted by ブクログ
私自身の基礎知識が無さすぎて、理解できなかったことも多かった。しかし、日本ではメディアの影響もあるかと思うが、どちらかというとイスラエルをあまり良く思わない見方の方が多勢に思われる中、はっきりとイスラエル側につくスタンスをとり続けている佐藤氏に敬意を表したい。
Posted by ブクログ
トランプ大統領の大使館をエルサレムに移転するニュースから、戦争が始まるのでは?と危機感を抱いた後、その後大きなニュースはなく、良かったとは思いつつ、どうなってるんだろう、と気になっていた。
そんなイスラエルの最近の情勢と、欧米とイスラエルの経済交流について書かれている。
読んだ内容を非常に感覚的に総括すると、結局イスラエルは経済的に成功し、欧米と経済的な関係を深め密接になったから欧米としてはなあなあになり、そして土地を奪われた形となったアラブ人的には自国政府(やハマス)が信用できない状態で、諦めムードということだろうか。
著者の立場はわりと中立的。だが、タイトルの通り、イスラエルとユダヤ人の内容なので、アラブ側の意見は少なかった。タイトル通りなのでそれで問題ないのだが、本書を読んでもっとアラブ側の意見の本も読みたいと思った。
Posted by ブクログ
イスラエルとユダヤ人について、しらないことが多いと思い、勉強のために読んだ。
置かれた立場により、これほどまでに評価が変わるのか、という感想を持った。
読みながら、「本当か?そうは思えない」ということが数多くあった。
筆者は「日本の外交官は、日本国家と国民だけを愛し、国益を考えるべき(要約)」と言い、イスラエルを支持することが国益と考えている。
外交官として、それが正しいということはわかったが、人としてどうかと思う。
外交官は、その考え方と自分の思想が違えば、思想を横において置かなければならず、精神的に厳しそう。入省の時点で心得ていればよいが、そうでもなさそう。
著者は国益と今現在に集中している。正しい正しくないではなく、そういう視点から考えて書いている。ただ、私はパレスチナの人々の立場にも立って考えるので、本書の記述に違和感を覚えることが多かった。いままさに虐げられている人々を無視し、二千年も前のことを持ち出されても納得感はない。
「イスラエルが消滅すると、中東は日本とまったく異なった価値観を持つ地域になる」とあるが、本当だろうか。イスラエルがあることでイランやイラクが自由主義や民主主義になっているとは思えないし、イスラエルが消滅しても、いまと変わらないのではないか。
その結果、日本が安定的に化石燃料を入手できないというのも「なんで?」と思う。イスラエルから輸入しているわけではないし、輸出国はイスラエルがなくても輸出して外貨を稼がなくてはならない。イスラエルがいなくなると他の産業が育つのか?いまは阻害されているのか?
「日本と人類のためにイスラエルとイランのどちらの立場を支持した方がよいか」も「日本とイスラエルのために」ではないか。
一方で、勉強になったのは以下の点。
イスラエルにはロシアからの帰還者が多く、日本にとってロシアとの交渉に有益であるという。この辺はまったくしらなかった。
ロシアとイスラエルの提携や、ロシアと日本の声明発表から、裏でどのようなことがあったと推測されるか、それぞれの国にとっての関心事と優先度から裏付けがされており、声明の読み方を学んだ。
マサダの戦いにからめて、外交官や自衛官は無限責任を負う職業であることを明示的に示しており、私はあまり明確に意識していなかった。