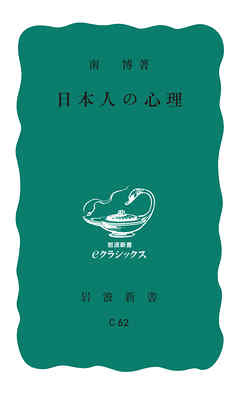感情タグBEST3
Posted by ブクログ
902
日本のキーワードは"自然を愛でる"なんだと思う。科学と日本の相性がさほど悪くないのは科学も自然に対する愛情がなきゃ観察しようという風にならないじゃん。だから日本人は科学的感性の高い国民だと思う。数学のノーベル賞受賞者数、日本人世界5位だし、西洋数学が入ってくる前の江戸の関孝和とかも凄かったしね。
南博
(みなみ ひろし、1914年7月23日 - 2001年12月17日)は、日本の社会心理学者。日本女子大学教授・一橋大学社会学部教授・成城大学教授を歴任。日本社会心理学会第3期・第9期・第10期理事長。
われわれ日本人は、外国人にくらべると、「幸福」ということばを使うことが非常に少ない。とくに日常の会話では、「ぼくは幸せです」とか「わたしは幸福よ」という文句を使えば、たいへんキザであるか、芝居がかって聞える。 そうして、書きことばでは、手紙などに、「幸甚に存じます」とか「幸せに存じます」と書いたりするけれども、それは、やはりよそ行きのことばである。どうみても、けっして実感を伴ったことばではない。 これは、つまり、日本人のあいだでは、幸福な状態についての生活感情が、なんらかの理由でうすいからであろうと思われる。幸福ということばが、日常に使われないのは、日本人が生活上、幸福に縁遠いことばかりでなく、幸福について遠慮しがちな習性を養われてきたからにちがいない。
そこで、日本人の幸福感がうすい由来をたどってみると、むかしから、幸福とは危険なあるいは空しいものであり、同時に不幸を忍ぶことが美徳であるとする観念が、くりかえし教え込まれているのである。いまそれを便宜上、幸福危険論、幸福空虚論と、不幸弁護論とに大きくわけて考えてみよう。
このように、歌道は、人生が無常で、はかないことを悟るための方法であり、のちに見るように、自然のなかに人間の無常を見てとろうとする日本独特の感傷詩は、中世の連歌以来今日の流行歌にまで流れ込んでいる。
また、今日でも多くの人によって特殊な精神修養の一つとして考えられる茶道には、無常感を会得して、人生の不幸に対処する心構えをつくることを目的とする、という考えがいまでもつよく残っている。 茶道では、茶会を「一期一会」といって、一回ごとの茶会に席を同じくする人たちは、それを一生に一度の機会として、再会することはないと思う気持でふるまわなければならない。そこに、茶会の無常感があるというのである。
「……一生に一度の茶会にて、……ふたたびめぐり合ふこともなき……うたかたの如く儚く消えてゆく茶会……人の世の儚さを、……真実に知らしてくれる」のが茶会である。
不幸への心理的免疫であるこの無常感に対して、積極的に、人生の無常から、かえって思いがけない幸福を予期するという態度も出てくる。このばあいには、無常感が、幸福の否定につながるのではなく、不幸の否定にみちびくのである。のちに運命主義の章でくわしくあつかうけれども、無常感は、賭けの精神と結びついて、日本に独得な運命論となっている。
これは一例だけれども、むかしから日本人が自然に親しみを感じ、社会よりも自然に関心が強く、とりわけ芸術の領分では、自然を材料として、うたい、描き、のべることが、さかんなのはなぜだろうか。
日本人が好んで自然を文学作品の題材にすることを、日本の「風光明媚」のせいにする人も多いが、ただ景色がよいとか、季節のうつりかわりが美しいから作品の対象になりやすいだけではなく、やはり自然を擬人化して、あるいは逆に人間を自然化して見る態度が、伝統的につづいているからでもあろう。
この態度がいちばんはっきり文学作品のなかに出ているのは、前にも引いた中世の連歌である。連歌は、まさしく、形式の上でも、また内容についても、自然と人生に共通な転変をあらわしているのである。二条良基は『筑波問答』に、「連歌は、前念後念をつがず。又盛衰憂喜、境をならべて移りもて行くさま、 浮世の有様にことならず。昨日と思へば今日に過ぎ、 春と思へば秋 になり、 花と思へば紅葉 に移ろふさまなどは、 飛花落葉 の観念もなからんや」と、連歌の形式が自然と人生の無常転変をそのままあらわしていることを説いた。
そうして心敬が、「心ふとく欲心をかまへ」ている人たちが、「言葉ばかりにて、うく、つらき、かなしき、あぢきなき、世をいとふ、身をすつるとのみいへども、かたはらいたくこそ候へ」(『心敬僧都庭訓』) と嘆いていることは、逆にいうと、心敬にとって歌道は、「心ふとく欲心をかまへ」るような態度を直すための修養であったにちがいない。これは、やはり、自然のなかに無常を見て、人間の不幸をあきらめ、悟りに達する心術としての歌道を考えたからであろう。
日本人が自然を愛する気持には、このように、人間の世界を逃れて、唯一の「我がもの」として心を休めるなぐさめがふくまれる。
不足主義の美を、いちばんはっきりと説くのは茶道である。とくに、侘茶といって、寂庵宗沢などがいう、茶禅一如の境地では、足るを知ること、不足に甘んじることが、茶道の真意であるとされている。宗沢の『禅茶録』に、「侘とは物不足して、一切我意に任ぜず、蹉跎する意」であり、「其の不自由なるも不自由なりとおもふ念を不生。不足も不足の念を起さず。不調も不調の念を抱かぬ」ことが侘である。 そうして、たんに不足を不足としないだけではなく、「 不如意をもつて楽みとす」るというのが、『禅茶録』の不足主義なのである。
また男女にかぎらず、他人の顔かたちについても、一般に関心の強いことは、アメリカの本には、かならず著者のポートレートがはいっていることでもわかる。 日本でも、戦後には、アメリカの影響から、右にのべたような肉体主義が、しだいに強くなってきた。たとえば戦後の本で、著者のポートレートをのせているものが、だんだんふえている。日本的な精神主義の心理的伝統によれば、本というものは、著者の精神労働の産物で、著者が、どんな顔つきをしているかは問題にならないはずである。戦前の読者は、本の著者へ「精神的」に近づくのであって、著者個人の肉体的条件は問題にしなかったのである。
〈著者略歴〉 南 博 1914-2001年 1940京都大学卒業 1943年コーネル大学大学院卒業 一橋大学名誉教授,中国人民大学名誉教授, 日本心理センター所長などを歴任 専攻—社会心理学 著書—『社会心理学入門』『日本的自我』(2点,岩波新書) 『体系社会心理学』(全4冊)『社会心理学の性格と課題』 『行動理論史』(岩波全書)『ストレスとのつき合い方』 『化粧とゆらぐ性』『日本人論—明治から今日まで』 編著書—『大正文化』『昭和文化』『続・昭和文化』 『近代庶民生活誌』(全20巻)
経歴
1914年、東京市赤坂区田町(現在の東京都港区赤坂)に生まれる。父は医師の南大曹(福島県出身、1878年生まれ[1]。日本医科大学教授、日本消化器病学会会長、財団法人癌研究会理事長、南胃腸病院院長)。近藤達児は父の兄[2]。石川千代松は母方祖母の弟[3]。大倉喜八郎は叔母の祖父であり[4]、林達夫も叔母の縁続きに当たる[4]。
慶應義塾幼稚舎、東京高等学校 (旧制) 尋常科から理科乙類を経て、父親の希望により医師を志すが、父の激務に恐れをなし[5]1937年東京帝国大学医学部を中退。1940年京都帝国大学文学部哲学科卒、同年京都帝国大学文学部副手就任。母親の幼友達であった高木貞二(心理学者、東京大学教授)の推薦を受け、アメリカのコーネル大学大学院に留学しダレンバックに師事、1943年コーネル大学Ph.D.。
日米開戦後は敵性市民として軟禁状態に置かれ、大学院修了後は日本への帰国を望んだが、入国ビザが下りずコーネル大学講師等を経て1947年に帰国。同年日本女子大学教授就任とともに、高木貞二の紹介で東京商科大学(現一橋大学)予科非常勤講師となる。1949年一橋大学法学社会学部専任講師、1950年一橋大学社会学部助教授、1958年同教授。一橋大学に国立大学で初めて社会心理学の講座を設け、1964年国際心理学会常任理事就任。1969年から1974年まで日本心理学会常任理事。社会心理研究所、伝統芸術の会、映画と心理の会を設立し、後にそれらを統合し日本心理センターとし、その所長を務めた。全日本気功協会会長。民主主義科学者協会でも活動。1962年文学博士(京都大学)。学位論文は「体系社会心理学」。
1978年に一橋大学を定年により退官し、同大学名誉教授。定年退官後は弟子の石川弘義の招きにより、1978年から成城大学教授をつとめ、1985年に成城大学を定年退職。中華人民大学名誉教授。また俳優座の養成所でも教鞭を執り愛川欽也等を教えた。1999年まで原宿に居住し、1999年から病気療養をかね国立がんセンターおよび聖路加国際病院に近い佃島に転居。2001年、肺炎のため死去。
受賞
1949年:毎日出版文化賞
家族・親族
妻は新劇女優の東恵美子で、日本で早くから夫婦別姓婚を行った夫婦としても知られた。その婚姻関係は「自由結婚」「別居結婚」「日本のサルトルとボーヴォワール」などとも呼ばれ、マスコミなどでも話題になった[6]。
業績・研究内容
戦後、アメリカ社会心理学を日本に導入し、国民性から大衆文化まで様々な社会現象の背景にある心理を解き明かし「日本人論」ブームをリードした。また、伝統芸能や映画、テレビ番組においても幅広く活躍した。フラストレーションの訳語に欲求不満という言葉を当てた。
人物像
仕事に熱心なことで知られ、子どもの頃から毎日8時間以上勉強するのが習慣だった。父から「勉強しすぎて死んだ奴はいない」と教えを受けたという。生涯無休で仕事を行い、亡くなる直前まで口述筆記で著書を遺している。
Posted by ブクログ
著者は心理学の専門家ですが、本書の内容はいわゆる日本文化論になっています。
古典的な文学作品から現在世の中に流通している処世訓などを題材に、日本人の幸福感、非合理主義、精神主義、人間関係などを解き明かしています。
日本人の心理を知るというよりも、日本人の自己理解の典型を示しているという意味で、興味深く読みました。
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
日本人の心理には「長いものには巻かれろ」といった処世法が生きている一方で、権威を否定し自我を主張する生き方が存在している。
また合理主義的な思考が広く定着しつつあるなかで、「物事は気の持ちよう」といった精神主義も根強い力を持っている。
複雑な日本人の心理とあいまいな人間関係を鋭く分析した、海外にも知られた名著。
[ 目次 ]
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]