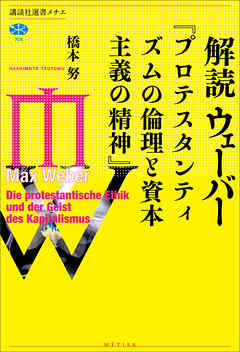感情タグBEST3
Posted by ブクログ
ウェーバーには非常に興味がありましたが、「プロ倫」そのものを読んでもピンとこないところが多くあり、わかりやすい解説書が欲しいなぁと思っていたところで本書の上梓のツイートを発見し、発売日買いをしてしまいました。
本書では「プロテスタンティズムの倫理」と「プロテスタンティズムの天職倫理」が断絶しているという前提のもとで、明確にその論旨の違いを図解してくれる「優しい」解説書であり、「プロ倫」を読むためのコンパスになること間違いなしといった読後感でした。
ウェーバーに興味を持ったきっかけが、何か現代社会の鬱屈とした状況を読み解くために役立ちそう!という期待を感じたことでしたが、本書を読んでその期待はあながち間違いではなかったことがわかったので、「プロ倫」再チャレンジの機運が高まります。
Posted by ブクログ
本書はマックス・ウェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』を解読(解説ではない)しようという試み。第1章から第2章まではその前提を確認する作業となっている。
著者は第2章の終わりで「資本主義の精神」の狭義の定義と広義の定義をおこない、「私たちは「広義の資本主義の精神(「勤労ー反消費」の生活スタイルで「子孫の幸福」「自身の繁栄」「社会の繁栄」を追求するもの。対して狭義のそれは目指すところが「倫理的義務の遂行」となる)を含めて、さまざまな立場を検討してみる価値があるだろう」(p.101)とし、そして、第3章以下ではルター派、禁欲的プロテスタンティズムの各派における「倫理」の分析、理念型を剔出していく。この辺が「解読」と銘打つ本書の真骨頂。
そして、第6章では禁欲的プロテスタンティズムの「倫理」と「天職倫理」の『プロ倫』上の定義の断絶を確認しつつ、「天職倫理」と「資本主義の精神」がほぼ同じ倫理内容をもつと論じている。いささかややこしいのだが、その辺は6章の図5と図6で綺麗に提示されている。
第7章ではウェーバーの『プロ倫』のメッセージから現代の我々が読み解くべきところのものが、著者なりの解釈も交えて示される。著者は、『プロ倫』が新保守主義的な発想からとらえた新たなリベラリズムの方向性を包含したものとして読み解くべきだと考えており、それはそれとしてわかるのだが、それが本当に禁欲的プロテスタンティズムのみから生まれてくれるものなのか。思想や倫理の歴史の世界史的な探求がまさに必要とされているのではないか、と感じた。
ウェーバーの宗教社会学研究という壮大かつ遠大な構想の限界と可能性を考えてみなくてはならないだろう。
Posted by ブクログ
ウェーバーの著作に忠実に沿って解読しているとはいえるが、これまで表題の著作についてきちんと解説した本は存在しないとするのはいささか乱暴ではないかと思う。
Posted by ブクログ
ウェーバーのあの名著を解説するありがたい本。ただあがめるでもなく、おとしめるでもなく、現代の視点から誠実に検証して分かりやすく説明してくれる。専門家でないなら、原著を読まなくてもこの1冊で十分といっても過言ではない。
Posted by ブクログ
「プロ倫」こと『プロテスタンティズムと資本主義の精神』でウェーバーがこたえようとした問題をていねいに解説し、その議論についてわかりやすく検証をおこなっている解説書です。
著者は、ウェーバーの代表作である「プロ倫」の全体について研究している本がこれまで日本にはなく、「研究の穴」になっているといいます。かつては、大塚久雄に代表される近代化論の枠組みのなかでウェーバーの議論が理解され、その後山之内靖がウェーバーとニーチェの問題意識をかさねるかたちで新しいウェーバー像を示しましたが、「プロ倫」全体の論証の構造を解明しているわけではありませんでした。そこで著者は、本書のなかでウェーバーそのひとの問題設定と論証過程をていねいに解説するとともに、自身の関心にもとづいて現代における「プロ倫」の意義を明らかにしようとしています。
著者の「プロ倫」解釈をおおまかに整理すると、ウェーバーは「禁欲的プロテスタンティズムの倫理」を、心理的内面における二重予定説と、組織形式における洗礼主義とゼクテの形成の二つの側面に分けて考察をおこなっているとされています。そのうえで、このことと「禁欲的プロテスタンティズムの天職倫理」とのあいだには断絶があり、「天職倫理」と「資本主義の精神」のあいだに親和性があることが確かめられると理解されています。
さらに著者は、新保守主義の社会哲学的な側面に通じる発想を、ウェーバーの問題提起から読み取るという試みもおこなっています。こうした著者の見立てがどの程度妥当するものなのか、わたくし自身は判断がつかないのですが、本書が入門的解説書であることを考えるならば、こうした現代的な興味にもとづいて「プロ倫」を解釈する視点を示す試みがあってもよいのかもしれません。