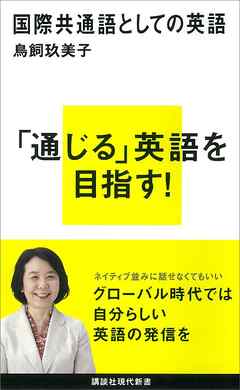感情タグBEST3
Posted by ブクログ
学研の「書評で学ぶ小論文の必須テーマ」に取り上げられていたので読みました。自分の無知を痛感したのは、単なる到達度の指標程度にしか思っていなかったCEFRは、EUの「多言語主義」「複言語主義」に基づく言語政策から生まれたものであったということです。これまでまったく調べようともしなかったことを反省しました。
Posted by ブクログ
意欲の喚起 動機づけ 教師にとって最大の関心事。馬を水飲み場に連れて行くことはできるけれど、水を飲ませることはできない。
ネイティブの真似をするのではなく、ノンネイティブの人同士でも伝えられる英語を教えること。
とても共感した。
Posted by ブクログ
英米人などのように、英語を母語とする人たちは4億人程度なのに対し、インドやシンガポールなどのように英語が公用語の人たちと、英語を外国語として使う国の人たちを合わせると、十数億人になるという。なので、我々が英語を使う相手もそれら十数億人になる確率がはるかに多く、そのような時代では英語は英米人の基準に合わせる必要はない時代になっていると著者は主張する。つまり、英語はネイティブレベルを目指す必要はなく、言語としての最低限のルール(文法、発音、アクセント、イントネーション)が守られていれば十分で、それを前提とした英語教育をすべきである、というのが本書の主張である。
英語に限らず、語学学習にはネイティブ信仰がつきものだと思っていたが、本書を読んで考えを改めた。小学校から英語が必須になるとの事だが、文部科学省はぜひ、本書の低減を参考にし、「世界共通語としての英語」教育が生徒にできるような指導要領を確立させてほしいと強く希望する。
なお、著者の本として本書の後に書かれた「本物の英語力」という本があるが、まず本書を読んでから「本物の英語力」を読むと、本書が理論編、「本物の~」が実践編という形で利用でき、効率的であると思う。
Posted by ブクログ
英語をしっかり学ぶけど、話すとき間違えるのは仕方ないとか激しく同意。言語は生き物で日本の前向きにとゆうのの直訳表現が定着した話しとか、ノンネイティブスピーカーの英語から英語のコアを特定し、そこから共通語としてのコアを探す研究の話とかも面白かった。
Posted by ブクログ
英語を学ぶ人は多いがその目的は曖昧な場合が多い。私がいつになっても英語をマスターできないのは、実はその目的がはっきりしていないからではないかと思う。
本書は英語を世界共通語と位置づけ、文化的な背景を一部犠牲にしてもコミュニケーションの道具として割り切って学ぶべきだと解く。
Posted by ブクログ
授業で薦められ、2011年5月13日(金)に阪大生協書籍部豊中店にて10%オフで購入。同日読み始め、翌14日(土)に読み終えた。
鳥飼さんは英語を聴いたり話したりできるようになるためには文法をしっかり習得しておくことが肝要であると以前から主張しており、私が彼女のことを支持していたのはそういう理由からであったと本書を読むことで思い出した。もちろん彼女は会話よりも文法が大事であるなどと安易なことを言っているのではなく、会話か文法か、あるいは実用か教養かといった二項対立で英語を捉える考え方をそもそも戒めている。誤解のないように書いておくと、本書の題名が『国際共通語としての英語』とあるように、本書の内容は文法がいかに大事であるかということではなく、私たちが英語を国際共通語として考えたときに、それをどのようなものとして考え、どのように習得していけばよいのかを中心に書かれている。この問題について考える切り口の一つがコミュニケーションであり、このコミュニケーションが本書のもう一つの主題である。
基本的には著者の意見に同意できるが、ところどころ疑問に感じるところもあった。
それから余談になるが、英語の授業で名前を姓名の順番に呼ぶのか、それとも姓と名を逆にして呼ぶのかというエピソード(140-6頁)は、立教大学に移ったあとの新鮮なエピソードとして紹介したかったのかもしれない(し、実際どういう意図があってのことなのかは分からない)が、最近になって初めて「名前を英語式に呼ぶことは本人のアイデンティティに関わることなのを、学生が教えてくれ」、それまで「ほとんど無意識に、学生の氏名を英語式に直し、ファーストネームを先にして呼ん」でいたというのは、いくらなんでもやりすぎだと思う。本当に最近になって初めて知ったというのであれば、それはそれでこの分野の研究者として問題だと思うし、以前から知っていたけど最近の出来事として英語式で名前を呼んだ学生から抗議されたことがあったためその授業を通じて学んだエピソードとして書いたというのであれば、それも誠実さを欠く行為であり問題だと思う。
Posted by ブクログ
これからの英語、英語教育のあり方を考える1冊。ネイティブ信仰を捨て、「コミュニケーション」の本当の意味を考え、国際共通語としての英語を学びましょう、という本。
EUの複言語主義の考え方や、カチュルーのWorld Englishesの考え方を紹介しながら、英米人の使う英語、ではなく、国際共通語としての英語について解説している。そして、従来からの学習指導要領でも重視されている「コミュニケーション」の意味を考察し、その上で英語教育のあり方や学習の動機づけについて述べている。
言いたいことは分かるし、単純に道具として英語を身につけるのではない、「文法はいいから会話ができれば」のような考えは甘い、学習指導要領では、あまりにも「コミュニケーション」という言葉が何も考えずに使われている、のあたりは本当におれも賛成できるし、当然のことだと思う。
けれども、著者自身も指摘するように、「国際共通語」に対する志向性、動機づけ、というのは、探すのが難しい。著者を含めた多くの学習者がそうであるように、英語を身につけたいという動機は、意識的にも無意識的にも、英語圏の文化が知りたいとか、英語圏の人と交わりたいというのがまずあるのではないだろうか。まず英語の母語話者がいるからこそ、英語に対する動機づけが高まるというものではないだろうか。もちろん、自分の使う英語として「国際共通語としての英語」を選ぶ自由は当然、認められてしかるべきだけれども、勉強するときは、母語話者の英語を規範として選ぶのが妥当だと思う。そもそも、「国際共通語としての英語」は、おそらく母語話者の真似をしようとしたけれども、学習者自身の母語による干渉を受けたり、それらの「規範から外れた」英語が交わり合ったりすることによって、その最大公約数として、結果として出てくるものだと思う。なので、使ってみなければ何が「国際共通語」かは分からない、という側面があるのではないのだろうか。要するに、国際共通語としての英語は教える、というよりは勝手に生まれるものだと、おれは思った。(11/12/28)
Posted by ブクログ
2月に同著者の『「英語公用語」は何が問題か』を読んだが,やはり英語は使えるに越したことはない。本書では,多言語共生という理想を追求しながら,普遍語となった英語を活用していく必要を説く。
前著でも繰り返し述べていたように,「英語支配」がもたらす弊害に注意することを強調。母語に裏打ちされた豊富な言語力を活かし,話す内容を生み出す思考力,対人関係の構築力,批判的読解力を磨いて,「世界語としての英語」でコミュニカーションできれば文句なし。
ネイティブスピーカーがどういう英語を話すかを気にしたり,「正しい英語」を追求するのでなく,英語を使う世界中の人たちが分かりあえる英語を目指すべし。英語教育界でもこういったパラダイムシフトが起きているらしい。
以前どこかで,"I can do it before breakfast!" でいいじゃんって話を見たことあるけど,著者も同意見のよう。え?どういう意味?って聞かれたら,日本ではそう言うんだよーと説明することで,話も弾み,異文化相互理解にも資する。うんおもしろい。
英語教育の新たな指針も示されてる。英米文化理解から,共通語としての英語を使っての発信へ目的をシフト。そのために,脱ネイティブスピーカー信仰,学習事項の仕分け,読み書きの重点化,自律した学習者育成を課題とする。(p.124)
国際共通語といえば,20世紀にはエスペラントが随分もてはやされた。英語よりずっと単純で憶えやすく,一時期は国際派知識人がこぞって普及を夢見ていた言語だが,全然定着せず,ただのマニアックな人工言語で終わってしまった。
結局,20世紀の歴史は英語を勝者とした。思考と密着し,日常的に使うのが言語だから,人工言語が失敗し,強者の言語が普及したのは当然すぎるほど当然だったのかも。今はそれを乗り越え,英語のコアだけが国際共通語として抽出され,活用されていくんだろう。それはもう本来の英語ではない。
何でもネイティブに倣えは最近流行らない。著者がショックだったのは,「何も姓名の順番を英米風にすることはない」って学生に気付かせてもらったことらしい。日本では鹿鳴館時代の欧化政策から,この慣習が長く定着してた模様。