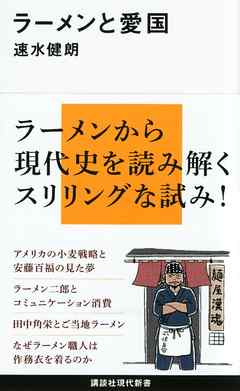感情タグBEST3
Posted by ブクログ
作務衣は伝統の着物ではないし、現代ラーメンは中国起源ではない。
ご当地ラーメンは地方の伝統とは関係ない。
現代のナショナリズムは、そういった伝統とは関係なく生まれ、そのことを恥じるものではない。
ひねくれた視点からの鋭い分析。佳作
Posted by ブクログ
・ラーメンが日本に広まった初期の要因としては、
①アメリカの余剰農産物処理法に基づく小麦戦略により、大量の小麦が輸入されたという物質的要因があった。
②安藤百福という一人の経営者が大量生産のメソッドを導入したことで、工業製品としてインスタントラーメンを広めた。
…という文化的要因だけではない側面がある。
・ご当地ラーメンは、地域の特産物・風土に根差したものではなく、地域の観光化に伴い生まれた「地域に縁のない観光資源」である。
このあたりが引っかかった。ラーメンは後から物語られたものなんですね。
現代史の精度はさておいて、高い教養を基にラーメンを絡めて書く様子は速水さんらしい気がしました。二郎ラーメンが食べたくなった。
Posted by ブクログ
ラーメンと愛国という言葉の取り合わせが面白くて手に取りました。
ラーメンという大衆的で、もうあまりにも当たり前に身近にある食べ物を軸に、戦前から現代に至るまでの社会情勢などが描き出されています。
チキンラーメンとアメリカのフォードが絡めて解説されていたり、ドラマ渡る世間は鬼ばかりで描かれた「幸楽」の話など、色々興味深い話が満載でした。
Posted by ブクログ
シナソバとか中華そばとか、バラバラに呼び習わしていたものが「ラーメン」という存在になったのは、チキンラーメン以降だったとか。「ご当地ラーメン」が郷土料理といえないのは、はやりの店が一軒できたのちにそれをみんなでマネしちゃうことからできちゃうものだからだとか。やたら人生訓好きだったりラーメン道とかいっちゃうのは麵屋武蔵から引き継がれてるのだとか。ラーメン屋の店主が作務衣を着るのは一風堂の影響だとか、いろんなトリビアが満載です。
Posted by ブクログ
タオル巻き&作務衣姿のラーメン店主、みつを風書体のお品書き、ご当地ラーメン、ジロリアン……
このあたりのラーメン現象を、メディアが意図的に作り上げたと批判するのではなく、そこも全部知った上で『日本文化』として消費されていくことを浮き彫りにしていく展開にわくわく。一気読みです。
ラーメン独特の文化の変遷から社会を読みとくということでイロモノ本かと思ったら大間違い!
インスタントラーメンの発明・受容、高度経済成長、地方の観光誘致作戦など、ラーメンと社会の関係は切手も切り離せないということがよーくわかりました。
確かに、この世の中で単価がキープされてるのってラーメンくらいかも……
Posted by ブクログ
日本人の国民食とも言えるラーメンというものを通して、日本人と現代史を論じている書籍です。面白かったですね。著者の本は毎回読み応えがあります。基本は戦後から現在までに至る現代史の流れを、ラーメンの歴史とともに紐解いていく流れです。ラーメンこそ戦後アメリカ化する日本の象徴であるといったものから、昨今のラーメン屋店員に見られるファッションがどのような意味をなしているのかといったものまで、もはや当たり前のように受け入れている現象が実に風変わりのあるということが詳細に書かれています。例えば、店員の作務衣姿には伝統や歴史を重んじるような印象がありますが、実際は日本の歴史と何の関わりもない単なるイメージとしての体裁に過ぎない、といった現実には驚かされます。そういったもの以外にも、戦後現代史に関してラーメン以外の様々な視点で論じられている部分も多いので、一般的な歴史認識とはまた違った認識の仕方が出来て為になるのではないかと思います。
Posted by ブクログ
戦後から現在までの日本文化史を大衆食の代表的食品であるラーメンから読み解こうというのが本書。
終戦直後の闇市から始まりチキンラーメンの発明、札幌ラーメン等「ご当地ラーメン」の登場から「作務衣化」した「ご当人ラーメン」の登場までの流れを当時の社会情勢を参照しながら読み解くのが実に痛快。
Posted by ブクログ
現在の「ラーメン」の置かれた状況を説明するには、過去に起こった様々な出来事や社会情勢を踏まえる必要がありますが、それらは大きく分けるとグローバリゼーションとナショナリズムという2つの観点が存在する、という筆者の発見を裏付けるための話が展開されていきます。
様々な歴史を紐解いてそれを繋げ直しながら、筆者が知りたかったことの答えを出せたということで最後は締めていますが、「歴史を丁寧に検証することで従来と違った視点で物事を見ることを繰り返す」という本書の手法はラーメン以外にも使えるため、私としては内容よりもこの論理展開が勉強になりました。
Posted by ブクログ
戦後日本社会の変化をラーメン文化をものさしにして語る。ラーメンという本来「日本的」なものではない食品がローカライズ、ナショナライズされていくプロセスを戦後日本の国土開発やマスメディアとの関わりのなかで論じられている。
Posted by ブクログ
“作務衣系"がラーメン屋を代表するスタイルとして完全定着を果たすのは、1990年代末。おそらくは陶芸家に代表される日本の伝統工芸職人の出で立ちを源泉。2000年代からは「ラーメン」から「麺屋」へ。店に掛かる暖簾も中国由来の赤と白から和をイメージする黒や紺へ。
Posted by ブクログ
文化系トークラジオlifeで知った速水さんの本。
タイトルで興味を持っただけでネタ本枠に入ったままずっと積読していた。
ようやく開いてみると、
小麦、戦争、インスタントラーメン、メディアと国民食、現代ラーメンのまとめなど、
近代日本をラーメンで斬ったちゃんとした歴史本なのだった。
速水さん元気にしてるかなあ
Posted by ブクログ
戦後から2010年ころまでのラーメン史を辿るにはよい本だった。中国から入ってきたものがいつの間にやら愛国に向かっているという視点もおもしろい。
タイトルにつられると政治的側面を強く語るのかと思いきや、文化的側面から戦後史を追うので読みやすい。
たしかに自己啓発・作務衣系は増えた
Posted by ブクログ
・ラーメンを軸にして見た戦後史と今の日本の一側面。日清食品の安藤百福に始まり、佐野実、天下一品、一風堂の河原成美、果ては二郎から六厘舎、夢を語れまで出てくるが、味がどうこうという本ではない。田中角栄の日本列島改造論から内田樹に須藤元気まで。その目配りの仕方が、自分にはちょうどいい感じだった。
・ラーメンという中国由来の食べ物が、今や「表層的な」ジャパネスク概念の体現の一翼を担っている。「作務衣」のユニフォーム化に加えて「ご当地」的な意匠のメニューでナショナリズム的なムーブメントすら漂わせているラーメン業界。でも、元々ラーメンは給食のパン食化というアメリカの占領政策の延長線上での小麦粉大量消費が背景。考えてみりゃ、うどんやパスタも小麦粉だった。また、言うまでもなく、中国由来。
・さらに、今のラーメン業界は、イタリア発の「スローフード」因子も包含、つまり、右派左派両方のベクトルも持ち合わせている。「右派」というのは「ご当地」との結びつきで、「左派」というのは大手資本によるファストフード店やフランチャイズ化を拒否している部分。ただし、ラーメン業界におけるナショナリズムは、多様な文化を認めた上でのナショナリズムだと本書では(他書からの引用ではあるが)述べられている。
・「世界という他者と向かい合わざるを得ない状況で、日本人は初めて『日本という自己』を意識させられ、自らの存在を問われる。あやふな自己を肯定し、セラピー的な効果を持ち得る、『都合のいい過去』が持ち出されるのは、そんなときである。(P252)」
・「本章で取り上げたような日本の右傾化、宗教化は、本質主義的なそれではなく、『趣味的』『遊戯的』そして、『リアリティショー的』なフェイクと結びついたものであると考えるべきだろう。(P262)」
・それにしても、チキンラーメン生みの親、安藤百福は、毎日昼にチキンラーメンを食べていたとあるが、他の本ではカップヌードルだったりして、どれがホントなんだろう?多分、幾つかの基本的な商品をローテーション的に食べていたというのが現実的なところではないかと思うんだけど。
Posted by ブクログ
良く調べてるなあと感心するし、論の進め方も丁寧で、研究者の書いた本という感じがする(実際は違うようだが)。
確かに最近のラーメン屋ってのは「和」をテーマにしているように思えるのだが、「なぜ」そうなっているのかの掘り方が弱いのがちょっと残念。
でも良書です。テーマも論構成もとてもよい。
Posted by ブクログ
ラーメンで紐解く日本史。否、日本史で紐解くラーメン。ラーメンの歴史だけでなく、ラーメンを取り囲む人々の歴史を俯瞰できる。そこに日本という特異なカルチャーの変遷を見て取れる。
Posted by ブクログ
最近のラーメン屋にある種のいかがわしさとか、押し付けがましさを感じ、すっかり行かなくなったと言うより、行きたくない。その訳が少し分かった。
特に、ラーメンポエムと作務衣の制服はやめてほしい。
ラーメンと昭和史、愛国心、郷土愛、そしてナショナリズム、壮大な大風呂敷を広げているが、少々理屈ぼっくすぎる。論理展開に強引さも感じる所もある。しかし、知らないことも教わったし、オォット思う視点もあった。
でも、年のせいか、押し付けがましいラーメン屋は嫌だな。行列などできない普通の中華屋のラーメンが一番好きです。
Posted by ブクログ
面白いっちゃ面白いけど、「つくられた伝統」なんて日本に限らずどこでもそうだし、だから言おうと思えばなんでも「国粋主義」とか「ナショナリズム」とか言えるわけだけど、単にそれを「ラーメン」と結びつける組み合わせの面白さってだけじゃないの、という気もした。
須藤元気を事例に「ナショナリストで多文化主義」っていうのは、もっと拡げて書いて欲しかったなーと思いました。そういう例を逆説的に捉えれば「地元のアイデンティティを否定して、多文化主義を肯定するリベラルの振る舞いは、マイノリティのナショナリズムや民族主義を肯定して、マジョリティの文化を否定する、マイノリティ側の排外主義」とも言える。まさに、そういう似非リベラルに対する反感が今の日本の右傾化を招いていると思っていたので。
Posted by ブクログ
ラーメンを題材に戦前から戦後にかけて主に日本の食文化の変遷、日本人のナショナリズムの変化に関して言及した一冊。歴史の変化とその変化が現代にどう影響されていたか簡潔に整理されて読みやすかった。
印象に残った点
日本の食文化のルーツは黒船来航以前は中国、それ以降はアメリカから輸入されるようになった。そんな中、ラーメンは中国発信の食であり、呼び方も支那そば、中華そば、ラーメン、今ではつけ麺と呼ばれるように変化した。変化過程で、日本は輸入したものを自国オリジナルのものに落とし込むことを得意とする国である。
ラーメンを独自なものにする中で、戦後ご当地ラーメン、テレビ特集が組まれるが、ご当地ラーメンはその土地に根ざしたルーツを持つものでもない。また、テレビにラーメンが登場することで、ニュースとしての夕方の報道番組に変化をもたらし(バラエティー的要素を加え)、公共性を重視していた放送から利益追求型へと放送局は変化した。また、ラーメン道といったように修行する様子を映すことで、テレビにリアリティを追求するようになった。
また、そもそも小麦が日本に根付いたのは戦後マッカーサーにより日本への低金利の融資と共に小麦を支援物資として送ることで、小麦文化を根付かせようとした。その結果、日本の小麦消費量は増加し、パン文化などが根付き、アメリカは小麦を輸出して稼ぐことができた。
食文化から解いたように、日本は海外から受け入れたものを独自に落とし込むのが得意である。その傾向はもの造りにおいても感じることができ、大量生産より優良な製品の製造が得意である。しかし、なぜ独自性の構築に活路を見いだしたのか、疑問が残った。
Posted by ブクログ
ラーメン屋さんほとんど行かないけど、作務衣系とかラーメンポエムとか、確かにそんな感じだなあと納得。みんなラーメン好きだよね…
普段あまり触れない情報なので興味深く読んだ。
Posted by ブクログ
斬新な試みが目を引いて読み始めた。戦後日本の庶民生活に関して色々面白い勉強にもなった。他国からの借用から始めて自分ならではの文化に成長させたものに関して面白い且つ挑発的な質問を投げ込んだと思う。ただし、話が進むにつれて論点がぼやけて散漫な気がした。
Posted by ブクログ
戦後復興期の工業生産とチキンラーメン、高度成長期の列島改造論とご当地ラーメン、バブル期以降のメディア展開と行列のできるラーメン、そしてこの数年の作務衣系・ラーメンポエム・「麺道」的ぷちナショナリズム。 時代の変遷と、その時代の特徴をラーメンブームの動向と絡めて論じる、というのは非常に刺激的だった。
とはいっても、筆者が本当に主張したい作務衣系とかの段にいたって、なんだか文章が荒れてきて、論旨が不明瞭になっていったのがちょっと残念。 わりと無駄話も多くて、いまいちこなれきってない感じはあった。
ただ個人的には、ラーメンなんてどうしようもないファストフードで、だからこそいいってなものを、薀蓄・ポエム・「麺道」的精神論・店主の個人推し等々 が激しい昨今のラーメン界に辟易していたので、それを冷静に分析しようという試みには溜飲が下がった。
よく見るビジネスマンの轆轤回しスタイルと、読モオサレさんの足クロス立ちと、この作務衣系腕組みラーメン野郎は胡散臭いと思っていたのよ。
Posted by ブクログ
自称瑛太に早水健朗が書いた日本ラーメン文化論。
でも、『論』までと言えるのかは正直疑問が残る。
日本ラーメン史という方が個人的にはしっくりと来る。
ラーメン好きと自称する人達にはそもそもアカデミックなところがないので、読む必要はないけれど、雑学の一つとしてはおもしろいかもしれない。
では、バイちゃ!
Posted by ブクログ
うーん。
いろいろと面白い話が聞けました、楽しかったです、勉強になりました、とは思ったのだが、関連した背景説明なんかが冗長で。何の話してるんだっけ、と思ったことが多々。
残念ですけれど、能書きも多くて、こんなにラーメンが大好きな私ですが、少なくとも読後感でラーメンを食べたいと思いませんでした。それは単に濃淡つけて読めない私のスキル不足に依っているのかもしれませんけれど。
で、うーんと思ったものの、個々のトピックが楽しかったのは確かで。特に、ご当地ラーメンのトピックはなるほどと感銘を受け、私にとって首肯すること多いものでした。