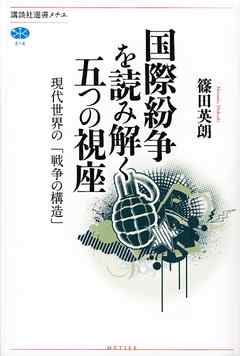感情タグBEST3
Posted by ブクログ
国際政治 東アジアの政治的勢力均衡を通しで解説
欧州地政学
大学の時以来見たウォータースタインの世界システム論
など 思考の軸を提供してもらった。
良書と思う。
Posted by ブクログ
日本人にとって他人事と思われがちな紛争について5つの理論的視座を地域とその歴史を通して対立の本質的要因を解いた本著はとても興味深かったです。正直、自分も意識的に注意しないと中東紛争など日本には関係ないと思ってしまっていた節がありました。しかし、他国(特にアメリカという超大国)と密接な関係を持ち、中国やロシアと地理的距離も近い日本こそ世界中の紛争に深く関係している事に気づかされ、事の重大さを思い知りました。今物議を醸している香港問題は米中対立や中国の東シナにおける台頭と拡張が挙げられていますがその背景にある地政学や勢力均衡、文明の衝突等の存在に文献のおかげで着眼することができました。
本著を通して普遍化した自由主義の①留保(韓国の立ち位置によって実現される勢力均衡やマッキンダーの理論を通して知った地政学)、②挑戦(中東混乱の根底にある西洋文明とイスラム文明の対立とその解決の有限性)、そして③欠陥(西洋的国民国家制度が馴染まない上に経済的不利で国際社会で行き詰まるアフリカ)について学び、その背後に自由主義を提唱し「明白な運命」を理由に拡張と侵略を正当化し成長を続けてきたアメリカの存在がある事が大変わかりやすく繋がりました。
そこで考えたのはまず成長と進歩についてです。アメリカの成長に対する執着は明白な運命という言葉と思想によって正当化された利己的な行動を促し、国際秩序を混乱させ世界情勢に悪影響を及ぼしてきたという点は以前から感じていました。しかし本著ではアメリカの上昇志向なくては限界を超えようとする存在が居なくなり、人類の発展をもストップさせてしまうと指摘されており、大変興味深く目から鱗でした。それもそれで困ると感じたと同時に、終盤の日本の格差問題の部分であるように「成長の限界を受け止める」事も必要なのではないかと考え、一度立ち止まって既存の問題を解決する事も成長なのではないかと思います。成長とは物事が大きくなる事と定義づけられがちですが、私は成長という言葉が持つ進歩の意味に着目すべきだと感じています。これまでは物事を大きくすればするほど新しい価値が生まれ社会は育っていました。しかし現代の世界に求められているのは拡大的な成長ではなく道徳・倫理の意味での成長、進歩なのではないでしょうか。
次に日本の外交について論じられている「曖昧さとの折り合い」の点について考えました。2章で言及されているように外交政策を通して達成しようとする目標に一貫性を大切にし、同時に目標達成の為に臨機応変かつ柔軟な対応が必要である為、時には曖昧な態度もとることが必要だという点に同意見です。日本の外交は曖昧な故に弱腰と批判されることが多いですが、批判すべきはその態度よりも外交目標の透明性さが故に起こる「軸」の欠如だと思いました。そもそも目標が不透明なのは目標がないからなのか、何を目標とすればいいかわからないのか、もしくはその他に理由があるのかは分かりませんがこの部分を明確にしない限り日本の外交は進展しないと思います。その目標に何を設定すべきか考えさせられ、香港問題や移民・難民問題を中心に日本もイギリスのようなバランサーとしての役割を担い実行する事はできないのだろうかとふと思いました。
また、地政学の重要さは分かったのですがその本来の意味について十分に理解できていないと感じ、更に学びを深めたいと思いました。
Posted by ブクログ
とても読みやすく勉強になる本だった。
この本の前に、安保論の本を読んだ。
その本だけ読んでいたら、言われてみればそうだ!ってことばかりだったんだけど、その後にこの本を読み、そもそもこの世界の作りを知って、安保論の世界観は未来永劫続くものではないし、そもそもこの価値観は欧米諸国主導で作られたものであって、脆いものなのだ。
こんなことを考えながら、ニュースを見ているとかなり怖い。
世界の中の日本、という考え方から目をそらして、私たちはこうだからって言いたくなる気持ちも分かるけれど、それじゃあ滅びるんだなぁ。
1歳になったばかりの甥っ子の将来を案じつつ、じゃあどうしよう、ということを考える本だった。
おススメ。
Posted by ブクログ
5つの理論的視座を通して、地域を別にして、紛争、対立の本質的な要因を読み解く。テレビ等の時事解説や政治家の言説がいかに浅薄なものだったか、この本で思い知る。
韓国の立ち位置、地政学の本来の意味、イスラムの混乱の本質、アフリカという国家制度がなじまない地域への視点、アメリカという成長神話を奉じる国家の限界などなどどれも目から鱗だった。
・国家間紛争に代わって、国家内紛争が主流になった、という言い方は、あまりに単純すぎる。
・米中という二つの超大国の双方が、他方に対する最善の窓口を韓国と指名するようなシナリオが韓国にとってベスト。
・東欧を制するものはハートランドを制し、ハートランドを支配するものは世界島を制し、世界島を支配するものは世界を制する:マッキンダー
・北米13州に加えて、19世紀に中南米諸国が独立したことを、20世紀にアジア・アフリカで広がった「脱植民地化」の波の先駆けの歴史としてとらえることができるかは、疑問が残る。
・フロンティアを求めて先住民を駆逐して国家を設立し、国家を膨張させ、そしてその後も「ニュー・フロンティア」を求めながら国力の増大を図り続けてきたアメリカは、もはや進歩する余地がないといった事態にはけっして耐えることが出来ない国である。
Posted by ブクログ
歴史と理論を踏まえ、現在の世界の在り方を根源から問い直し、未来について考える良著。
勢力均衡理論により東アジアにおける日本、中国、韓国等の関係について見たり、マッキンダー等の地政学によりヨーロッパと2つの世界大戦を見たり、文明の衝突論により中東を分析し、 主権国家という仕組みそのものの根源について見たり、ウォーラーステインの世界システム論により世界システムの周辺としてのアフリカを分析し、国民国家を主体とする現代の国際秩序そのものの根源について見たり、成長の限界という観点からマニフェストデスティニーの思想のもと成長を続けたアメリカの歴史を概観し、限界を迎えたときにどうなるのかを考えたり。
Posted by ブクログ
世界各地で発生している紛争の背景を理論的に理解でき、読みやすかったです。
日本では、こういった冷静な議論が少ないため、とても勉強になりました。
Posted by ブクログ
「『複数の人間(集団)が、相容れない目的をもっているとき』、紛争は生まれる」(P14)。分析のスタートとして的確な定義だと思う。つまりそう簡単に紛争はなくならない、ということだ。では不安定なりに維持しなければならない秩序とは何か。
著者が強調するのは、世界のそれぞれの地域に「国民」が存在し、その「国民」が「国家」を形成しているというしくみ(P38)自体が、せいぜい20世紀後半に確立したものであること、このいわば「今たまたま」の国際秩序を費用対効果に見合った方法で維持できるのか、その答えは見つかっていないこと(P42)、の二点。
当たり前だが、すべてを整合的に説明できるような統一理論は社会科学には(今のところ)存在しない。ただ冷静な観察からある種の傾向を見つけることは可能、ということは言えそうだ。
Posted by ブクログ
現在の世界情勢が過去の経緯や国際紛争の理論的枠組も踏まえて整理されていて、わかりやすい。
日高義樹の本にもあったが、このように整理すると、オバマ大統領の対外戦略(対内も?)は世界的に悪影響を与えたという結論になりそうだ。