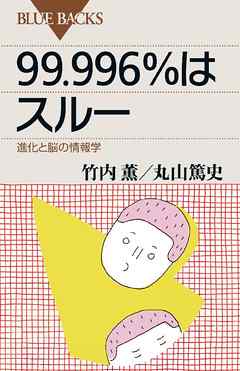感情タグBEST3
Posted by ブクログ
両生類はヒトよりゲノムの数が多いとか、ダンバー数、フレーム問題、ヒューリスティック、ブーバキキ効果…。私には馴染みのない言葉が沢山出てきた。スルーの定義もされてて、スッキリした。SNS疲れがなんだっていうんだという気持ち。ヒトっていうのは無意識に、無意識の選択をしてるんだなあ。
Posted by ブクログ
近年、流通する情報量が爆発的に増えてしまって、 人は情報を受け取り切れず、殆どの情報がスルーされている ことが書かれていると思います。 情報の発信や受信について考えさせられました。
Posted by ブクログ
タイトルは、全情報のうち、自分が対処できないものの割合。時々刻々と増え続けるのが情報だから、本作から少し時間が経った現在、更に数字は増えているかも。もはや誤差の範囲かもしらんけど。正直、心に残ったのはその点だけなんだけど、翻ってその他もろもろは、論を引っ張るためにしか思えなかったりして。対数の説明とかも、頁稼ぎにしか見えんし。あと何よりしんどいのは、特に後半で顕著なんだけど、関西弁の多用と、カッコ書きで繰り返されるしょーもないひとり突っ込み。そもそも、論文内で(特に地の文で)繰り出される関西弁に少なからぬ反感があるんだけど、せいぜい、本書と同時に読んだ中野徹氏くらいの使用が限度。本作は度を越えているから、イライラしてせっかくの中身も素通りしてしまう。著者としてもそれは本意でないと思うし、是非やめて頂きたいと思います。本書は共著なんだから、せめてどちらが書いたかを示して欲しかった。これまで読んだ竹内薫氏の著書では、上記を感じたことがなかったので、責はもう一人の方にあるのかな、きっと。
Posted by ブクログ
情報量が飛躍的に増えている一方で、私達の処理能力は変わらず、大多数の情報は意識的、無意識的にスルーされている。こちらからみんなに知ってもらいたくて何かを発信しても伝わらない時、歯がゆく感じるけども、確かに、これだけスルーされている事は自覚をした方がよいのかも。
本の中身は筆者が博識なためか様々な領域の理論を使って書かれているので、全て理解しながら読めているとは言い難いです。
Posted by ブクログ
久しぶりの「脳」をテーマにした本であり、また、久しぶりの竹内薫氏の著作です。それらしい興味を惹くタイトルでもあります。
本書を読み通して特に興味深く感じたのが「情報量」の捉え方でした。情報の大きさ」は「貴重なものほど(情報量が)大きい」「発現確率が低いものほど(情報量が)大きい」という考え方です。このあたり、私自身、あまり実感として腹に落ちきれていないのですが、理解しづらいだけにかえって興味が湧いて面白いですね。
Posted by ブクログ
第5章での脳の話や第6章の進化の話がまるまる1冊書かれていると思って購入してしまったので、正直、肩すかしをくらってしまった感じ。でも、他の章も「スルー」することなく一応ちゃんと読みました。
こういう内容にまったく接したことのない人には、文体も親しみやすい(私は、ブルーバックスなのに軽すぎない?って思っちゃうけど…)し、とっかかりとしてはいいんじゃないんでしょうか・・・。