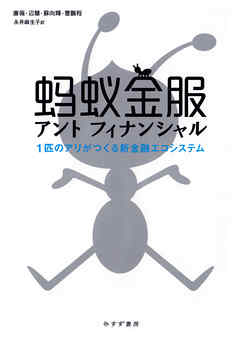感情タグBEST3
Posted by ブクログ
難読書 やっと一読できました 見慣れない中国企業名、わかったようでわかっていなかった金融用語、そして、IT用語。加えて、箇条書きの改行をとって一文につめこんだような、凝縮された各ページ。要所で、用語を調べるために、何度もスマホに打ち込んでいました。
恐るべき中国金融のテックフィン(アリババはフィンテックではないと言っている)、日本の金融システムとは異質だが、解放感がある。
要点
・アントフィナンシャルは、アリババの金融部門ではなく、金融プラットフォームである
・アリババは、既存の金融機関とはすみわけをする。(これをインクルーシブ・ファイナンスといっています)
・既存の金融機関が上記20%を対象とするならば、インクルーシブ・ファイナンスは、のこりの80%を対象とする。だからアント⇒蟻。ロングテールで稼ぐ。
スマホ決済、しかもスマホカメラで対応できる安価なQRコードを使う
信用市場がなかった中国に新しいマーケットを作った。裁判所での対応も与信に組み込んでいる。
・アリペイ 決済
・余額宝 資産運用
・保険
・花唄、仮唄 マイクロクレジット
・芝麻信用 信用情報
膨大なビッグデータと、AIを背景に金融クラウド
セキュリティ(生体認証)、リスク管理(個人ごとに金融商品の金額を算定)
DX:単なる言葉ではなく、たくさんの入力項目を必要とする金融商品の申し込みを、口座名とパスワードだけで実現
融資は、4分で完結
すぐ借りられて、すぐ返せるしくみ 等
目次は以下
はじめに
第1部 ゲームチェンジャー・アリペイ
第1章 アリペイの誕生
第2章 アリペイの野心
第2部 アリが夢見るインクルーシブファイナンス
第3章 余額宝がもたらす資産運用革命
第4章 インターネット時代の零細企業融資
第5章 信用を財産に
第3部 金融の勢力図を塗り替える
第6章 1匹のアリが作る新金融エコシステム
第7章 グローバルな発展の未来図
第8章 農村金融の荒野を開墾する
第9章 オープンプラットフォーム
あとがき
Posted by ブクログ
アリババの決済部門を担うアントフィナンシャルの立ち上げから現在に至るまでを詳細に解説した本。
独身の日における凄まじい量の決済データをクリアするため、OSやデータベースソフトまで自前で作り出してしまうパワーは今の日本企業に無いものです。
企業が歩んできた事実を中核メンバー1人ひとりの個性も絡めて著しているので、迫力のある企業小説のように読むことができます。
Posted by ブクログ
アリペイを提供するアントフィナンシャルの本。
あまり日本では知られてない・報道されてない内容に思う。
圧倒的に先をいっている。
テックフィン企業。
小さなところへの集中。
信用。
Posted by ブクログ
結構、ボリューミーな一冊。アントの中核事業である信用部門のビジョン・ミッションが「信用の空白を埋めるということが芝間信用の役割」であることが良く分か。同社が個人情報保護のSIOも取得していたことを知らなかった。意味不明な理由で中国叩きをする人にこうしたChina Digitalの側面を知ってほしい。
Posted by ブクログ
技術後進国がイノベーションによって一気に技術立国になることがある。レガシーのジレンマがなく最新技術をフル活用できるからだ。アントフィナンシャルの躍進はまさにそれであろう。本書で描かれる蟻たちの集合体は世界最先端の金融エコシステムであり、農村金融のようにテクノロジーで裾野まで拾い上げる様はこれまで金融が挑戦して成し得なかった領域をも開拓しつつある。
中国というとどうしても国家統制の計画経済を思い描いてしまい、アリババもアントも膨大な中国内需があるから成長できており国家擁護のもと成長した企業と勝手に思っていたが、本書で描かれるアントは規制と果敢に向かい合いユーザーファーストで泥臭くトライ&エラーを繰り返すスタートアップそのものだ。彼女らの凄まじいアジャイルに驚かされる。
IT/AIの業界ではシリコンバレーではなく深圳のほうが進んでいる領域が幾つもあるが、金融もそのうちのひとつだろう。TechFin企業としてのアントフィナンシャルの凄さはもとより、米国が中国を恐れる理由、中国の底力を理解できる良著である。
Posted by ブクログ
廉薇、辺慧、蘇向輝、曹鵬程著、永井麻生子訳『アントフィナンシャル 1匹のアリがつくる新金融エコシステム』(みすず書房、2019年)はアリババ・グループの金融関連会社「アントフィナンシャル」を取り上げた書籍である。アントフィナンシャルはキャッシュレス化など中国の金融を大きく変えている。
アントフィナンシャルは様々なサービスを展開している。決済サービス「アリペイ」(支付宝)は日本でも有名である。中国のサービスを日本企業が後追いしている。余額宝は1元から資産運用ができるMMF(Money Market Fund)。芝麻信用は個人や企業の信用度をスコアリングする。網商銀行はマイクロクレジットのインターネット銀行。
これらのサービスは既存の金融機関が対象にしていなかった人々が金融サービスを利用できるようにした。たとえば芝麻信用で高スコアの者は敷金なしで賃貸住宅を借りることを可能にする。
日本では敷金や礼金を出せない貧困層をターゲットにしたゼロゼロ物件が貧困ビジネスとして社会問題になった。敷金礼金ゼロで物件を借りられるが、違約金や退室立会費など様々な名目で費用を徴収し、搾取する。貧困層の弱みに付け込んで搾取する日本の貧困ビジネスとITを活用して業界の常識を壊すサービスを生み出す中国のIT企業。その差は大きい。
SDGs(持続可能な開発目標)のターゲット1.4は「2030年までに、貧困層及び脆弱層をはじめ、全ての男性及び女性が、基礎的サービスへのアクセス、土地及びその他の形態の財産に対する所有権と管理権限、相続財産、天然資源、適切な新技術、マイクロファイナンスを含む金融サービスに加え、経済的資源についても平等な権利を持つことができるように確保する」と定める(総務省仮訳)。アントフィナンシャルの活動はSDGsの実践である。
20世紀は社会課題の解決と言えば、規制や福祉など公的権力の拡大によって実現するイメージが強かった。しかし、ハイエクが看破したように公務員の不正や無能、非効率が起こり、政府の失敗を引き起こすことも多々あった。民間企業が消費者感覚でサービスをローンチさせて世の中を変えていくことは素晴らしい。民間感覚や消費者感覚の点で日本は中国よりも遅れているのではないか。
Posted by ブクログ
・アントフォーチュン
・芝麻信用
・保険の内容
などなど、実際にあまり知られていない部分がよくまとまっていた。やっぱり、若いうちは早めに中国か東南アジアの成長領域にいかないとってほんとに思った。
Posted by ブクログ
アリババグループが率いるアント・フィナンシャルの事業については、信用評価サービス「ジーマ・クレジット」が取りざたされることが多い。しかし、最初期の金融サービスである決済の「アリペイ」を始めとして、様々な金融領域に拡大した彼らの事業について、なかなか全貌をつかむのは難しい。本書は、北京大学のデジタル金融研究センターに所属する研究者集団によるアント・フィナンシャルの新金融エコシステムについてまとめた論考集であり、恐らく日本語で読める類書の中では、既に多くの評者が指摘しているように最高の一冊である。
高い経済成長を誇っているとはいえ、都市部と農村の経済格差が大きい中国においては、全ての国民が等しく金融サービスへのアクセスを持てているわけではない。そうした環境下で、融資や投資などの金融サービスを等しく全てのユーザに対して提供するアント・フィナンシャルの事業は、いわゆるファイナンシャル・インクルージョン(金融包摂)の典型例として理解することができる。特にその一例として脅威深かったのは地方における農業従事者をターゲットとしたサプライチェーンファイナンスや融資などの一連の金融サービスである。日本においても、農業ビジネスの大規模化・高度化を図るにあたって金融×農業の意味合いは非常に大きいのではないかという仮説を考えていた自身にとって、その仮説を既にビジネスとして成立させている中国の取組は極めて示唆深かった。
Posted by ブクログ
まず書籍としての品質が高い。調査して、正しく書籍として書かれている印象を受ける。アメリカのバスワード一発なワイヤードな感じの書籍より数倍情報量があり、読み応えがある。また、途中のエピソードで、squareに学びに行って学びが何もなかったと言うものがあるけれど、その通り、ファイナンス分野で、グラミンのように包摂的で、その上でテクノロジーに結びつき、明らかに世界の最先端を走っている企業の話としてよく書かれている。プラットフォーム企業としてのあり方も、アメリカの先行企業に対して一つレベルの高い哲学を持っているように感じられる。中国だから、と言うことで、多分政府に情報を全て持って行かれているだろうと言うような印象操作だけでこの企業の物語を見逃すと大変まずい。まあ実際にどうなのか?はわからないけれど。