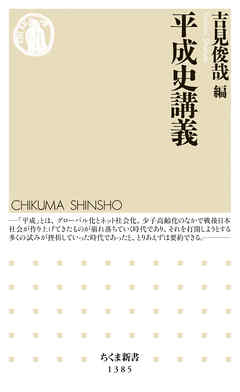感情タグBEST3
Posted by ブクログ
【本来ならば未来への道程が見通せなくなったときには、その未来への自らの構想力を改めて鍛え上げなければならない。それは、それまで当たり前と思われていることを問い直し、既存の安易な解決法を拒絶して、困難でも未来につながる道を選ぶ跳躍力を必要とする。これが、日本社会には存在しなかった】(文中より引用)
平成とはいったいどういった時代であったのかを、政治や経済、教育や外交といった多角的な側面から分析した作品。著者は、東京大学大学院情報学環教授を務める吉見俊哉他。
豊富なデータとともに、平成への一つの見方を提供してくれる一冊。一つの時代の輪郭を大まかになぞるのではなく、その時代を構成する様々な要素ごとに眺めていくため、幅広いジャンルに興味を持つ方にオススメです。
全体的に暗めのトーンでしたが☆5つ
Posted by ブクログ
昭和天皇の死去と平成天皇の即位は、歴史の流れとは全く別の、特定個人の物語であるが、平成の始まりは、冷戦の終結やバブルの崩壊と不思議に重なっており、「平成史」というものを語る根拠となっているように感じる。
本書は平成の30年間を、色々な論者が、色々な側面(例えば、政治・経済・若者・教育、等)から論じたものを1冊にまとめたものである。1つ1つの論文は興味深いものもあれば、全然面白くないものもあるが、全体として平成時代の動きを想起させてくれる。
平成とは総じて言えばどういう時代であったのかについて、編者が述べている部分が何カ所かあるので、ここに引用しておきたい。
■総じて平成は失敗の30年であった。この30年の間のバブル崩壊や一連の企業破綻、震災対応や原発政策の誤りが生んだ甚大な損失を振り返れば、絶頂から奈落の底へとここまで失敗を重ねた時代は過去の日本にそう多くはない。
■つまり「平成」とは、グローバル化とネット社会化、少子高齢化のなかで戦後日本社会が作り上げてきたものが崩れ落ちていく時代であり、それを打開しようとする多くの試みが挫折していった時代であったと、とりあえずは要約できる。平成史とは、多幸症的なバブル景気に始まりながらも、崩壊、挫折、失敗、縮小、危機によって特徴づけられていく苦難の30年間であったのだ。
よく言われることであるが、平成以降の、この約30年間で、日本の平均雇用者所得は全く増えていないばかりか、減っている。その間に、消費税は上がり、社会保険料はあがり、最近は物価も大きく上がりつつあるので、実質の可処分所得は平均すれば、大きく減っているはずである。しかし、それは「皆が一律に」所得を減らしたわけではなく、所得の低い階層が増えた一方で、所得を増やした階層もあり、所得を中心とした「格差」は広がっていると言われている。また、先進国の中で所得がこのような状態になっているのは日本だけであり、他国はそれなりに所得を伸ばしている。言えば、「一人負け」の状態なのである。
と、ここまで書いてきて、気持ちは沈んでくる。
しかし、最も気持ちが暗くなるのは、現在の状態が悪い状態であるということではなく、これらが良くなるきざしが見えないことだ。
多角的評論で読ませる
平成という最早元号で区切ることに、象徴以外での意図がなくなった初めての時代をあえて区切り、変化を評論する一冊。
正直必ず出てくると思っていたジャンルであり、様々な形でこれからも出てくるだろうが、本書は結論ありきな部分はありながらも、筋道を立てつつ難解なこの時代に名前をつけようとしてくれている。
平成時代を低迷や失敗が誰の目にも明らかとし、その原因に戦後形成された成功モデルが破綻し次策を構築できない経済や政治、官僚システムを挙げている。昭和後期からの兆候など納得できる点も多いが、あの時代だからこそ成功した特殊モデルであることは強調して欲しかった。無論著者たちは分かっているのだろうが、現在の失敗を注視するあまり対比となる「戦後昭和の成功」が書かれすぎているように感じる。
また複数の学者から広く集めている故か、一部の学者の評論からは平成時代のグローバリズムの混沌さの上昇と対比するように、昭和時代の秩序ぶりを書いているがそんなことはないと思う。例えば6章のメディア論からは昭和の新聞は討議を重ねる場があったとするが、当時だって話題性優先の報道はあっただろうし、ネット上だからこその世代身分を問わない議論の価値はあるはずだ。
もちろん多角的著者の視点は良いところもあり、訳に個人的に7章の文は面白かった。評論というと違うかも知れないが、漠然と物事を一元化してはいけない考える姿勢の重要性が伝わる。
総じて良い部分、悪い部分を自分で考えられる評論集。世代を問わず平成の日本を生きた方は一読しても良いと思う。
Posted by ブクログ
北田暁大の「平成リベラルの消長と功罪」には、重要な意味がある。
実態が伴わない中、マスコミが55年体制的な分析、言説を垂れ流す中、政治を支える意識の環境は、あっという間に、いつのまにか、アップデートしたようである。
新倉貴仁の「中間層の空洞化」は、重要な指摘をする。
2018年の「国民生活の世論調査」においても、人々は、約9割以上の人が、自身を中流と位置付けているのである。
これらから窺えるのは、一面的にしか報じないマスコミの崩壊である。
Posted by ブクログ
2019年2月に出版された「平成史」の本。
「令和」は、2019年5月からなので、厳密には「平成」は終わってないうちにこういう本がでるのもなんか変だが、令和5年になっても、「平成」とはなんだったのかを考えるための必要な新たな資料が公開されたりするわけでもないから、これはこれで良いのかもしれない。
ということは、この本は歴史というより、社会学的に30年くらいの時代の変化を読み取っていくというアプローチが中心になる。
テーマごとに著者が分かれる編著で、しかもテーマが現在進行中のものも多いので、全体としての統一感は少ないが、なるほどそんなこともあったな、とか、あれとこれはそう繋がっていたのかと頭の整理にはなった。
頭の整理以上に面白かったのは、編著者の吉見俊哉さんの第1章「昭和の終焉」と第10章「アメリカの後退・日本の漂流」。これらの論考は、世界大でのマクロトレンドを踏まえつつ、構造のなかでの日本の位置をおさえつつ、一つの物語に収束しない、複数の物語の可能性を提示しているように思える。
こうしたスタンスが、まだまだ近い過去に対して、わたしたちが取りうる有効な視点なのかもしれない。
あとは、平成における政治の流れを概括する第2章「「改革」の帰結」、そして社会学的なアプローチで意味の変容を読み解く第7章「平成リベラルの消長と功罪」、第8章「中間層の空洞化」あたりが面白かったかな。
あくまでも、これから考えための素材として捉えるべき本だと思った。