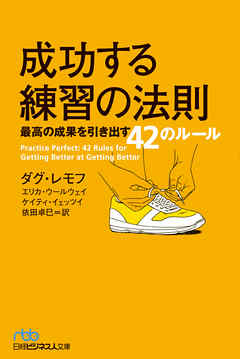感情タグBEST3
Posted by ブクログ
成功する練習の法則
最高の成果を引き出す42のルール
難解な書、いかに短期間で、正しい練習を行い自分のものにするかを語った書
帯に、「あらゆるスキル上達の最短距離、古い常識を捨て、最強メソッドを学べ!」とある
教育というものは、幾つものパラメータが複雑に絡まった行為との印象があり、その章が何をいいたいのかが
その章の冒頭に書いているが、難解である
一定の方向性、意味をもつ動作であるが、言語化することはむずかしく、まして、イメージ化しにくい。
観察をして
本書は、こうした、非言語化行為を、比喩であらわそうという努力がややかけているように感じました
気になったのは、以下です。
■結果を出すための練習とは
本書は、伝説のUCLAのバスケットボールコーチである、ジョン・ウッデンを出発点としている。彼は、20世紀でもっとも偉大なコーチと言われた人物である。
・彼は、靴下とバスケットシューズのはき方から練習させた。
・すべての練習をカードに書き留めた
①何がうまくいったか
②何がうまくなかったか
③次のどうしたらもっとうまくできるか。
④書いて将来のために保管した
・彼の練習の基本は、
× 試合を再現する実戦練習
〇 試合を変形して特定スキルを習得する、反復練習
・練習の進め方
ボールを使わない指導 ⇒ 徐々にむずかしくしていく
選手が習得して体が自然に動くようになるまで、反復練習をする
常に正しく練習することにこだわる
⇒地味っで細かい練習の積み重ねが、技術の習得につながる
⇒1分1秒を大切に、いかに効率よく時間を使うかにこだわる
・理解と実行のギャップ
あるべきことは理解している ⇒ でもそれを確実には実行できない
一つのこと修正すると ⇒ 別のことができなくなる
同時にことがおきていると ⇒ ひとつのテクニックに集中できない
つまり 理解していても、知っているだけでは、実行ができない
■練習の思い込みを見直そう
・間違った練習をすれば、ゴールはどんどん遠ざかってしまう
⇒質のよい「すばらしい」練習をする必要がある
⇒質の低い、多めの練習よりも、好ましい結果が得られている
01 成功を体感できるものにする
練習を観察して正しくやっているかを確認する
彼らがやり方を習得するまで、教えたとは言わない
02 最大の価値を生む20%に集中して取り組む
最大の価値を生む20%に練習を集中する
たんに習得するのではなく、きわめてうまくなることが目標
03 無意識にできるようになるまで徹底する
無意識にできるようになるまで徹底的に習得させる
複雑なスキルを積み上げ、能動的に考えなくても複雑な作業ができるようにさせる
基本的な作業を自動化するとともに、複雑化した作業も自動化できないかを考える
04 無意識いできるようになれば、創造性が解き放たれる
反復回数を増やせば創造性と個性が引き出される
05 目標を目的に置き換える
①目標は計測できる
②目標は管理できる
③加えて、専門的な指導がつき、ごく少数の項目を正しくやることに集中する
④効果的な目標は練習前に決めておく
06 得意分野を見つけて磨きをかける
すごくうまくできることを、集中的に練習し、さらにうまくなって大きな価値を生み出す
07 実戦練習ではなく、反復練習でこそ上達する
現実を変形した設定で、ひとつのスキルに最大限集中し、意図的に磨きをかける
実戦のために、既に習得したスキルを統合するための反復練習を行う
08 批評でなく、正しい方法でやり直しを求める
修正であって批評ではない。できるだけすぐに、具体的なよりよい方法でやり直させる
■どんな練習にするか
・練習に入るまえに、すぐれた成果に必要なことを正確に知る
・作戦を何度も立てて練習する、細かい点を確認しながら準備する
・わかりにくいテクニックや失敗に、名前をつけて分かりやすくする
・反復練習の再設計、範囲の見直し
09 ゲームを分析する
練習方法について、一番重要なルールとは、卓越するために何が必要なのかを知ること
主要な瞬間を分析しつづけ、法則性を発見する、さらに必要にスキルへ分解する
データを分析し、最高の教師を見つける。ビデオをみて、共通するテクニックを抽出する
10 スキルを分離して個別に練習する
手順を分離したら、個別のスキルをひとつづつ身につける
最終的には、個別のスキルを合わせて、統合的に使えるようにすること
11 スキルに名前をつけて共有する
スキルの識別、命名の組み合わせが効果的な練習の設計につながる
スキル開発の略語となり、同時に、効率よい管理ツールになる
12 スキルを統合して練習を本番に近づける
個別のスキルを練習し終えたら、複雑さを加えて、スキルを統合する
習得には、さまざまな反復練習が効果的だ
①本番さながらのシナリオでスキルを練習する
②正しいときに、正しいテクニックをマッチングさせる
③練習を本番の環境で行う
13 練習計画を立てて修正する
①データにもとづく目標を念頭において計画する
②最後の1分まで計画する
③計画をリハーサルして修正する
14 1分1秒を大切にする
ホイッスルや、手をたたくを導入する 3回手を叩けば皆きけ、2回たたけば、練習中断
<何すべきか、わからない> 予備の活動を用意しておくなど
<待ち時間> グループ分けして、事前練習
<長い指示> 反復練習を設計して、名前を付ける、同じ反復練習にバリエーションを加える
<注意不足> 最初から期待する行動を教えておく
<議論好き> 議論を短く
<こまぎれ時間> 割り当てられた時間だけが練習だという意識をかける
■手本を活用する
・スキルのモデル化⇒お手本
・リーダ・コーチが実際にやってみせる
15 手本と手順書の両方を使う
工夫された手順書と手本をうまくつかう
重要な判断が必要なときに、手順書を参考にする
16 事前にすべきことを伝える
手本を示すまえに、あらかじめ、何をみるべきかを相手に伝えておく
<学びの場>ショットをメールする
17 できそうと思わせる手本を示す
手本は高度のテクニックだけでなく、現実的で信じられる映像にしなければならない
学習者が見て、できそうだという手本でなければならない
18 完全な手本を示す
学習者に実践してほしいやり方で手本を示す
教えたいスキルの手本を示すとともに、最終的に学んでほしい他のスキルも手本を示す
19 手本をそのまま、まねさせる
手本をそのまま、まねさせることは、テクニックの完全に正しい学び方だということを知っておく
20 分解して手本を示し、繰り返す
手本を分解して、各部に名前をつける。各部ごとに手本、もしくはやって見せて、すぐ試してもらう
21 手本に近づく道筋を示す
テクニックによっては、手本を見せるだけでなく、手順を説明し、見せる必要がある
図を書き、メモをとり、ことばを交わす。手順をそってステップにそって、成果と手順、双方の手本を示す
あるいは、不完全でもかまわないので手本をまねて、フィードバックを受けながら、改善していく
22 ビデオを活用する
30秒単位で編集、質もそうだが、量を増やす
■フィードバック
・早く上達するためには、フィードバックの改善が必要
・1度にたくさん、フィードバックしないこと
・フィードバックの質を高めれば、個人にも、組織に並外れた力がつく
・フィードバックを習慣にする
23 フィードバックを取り入れて練習する
フィードバックは何度も繰り返す、そしてすぐ伝える
ビジネスでは、計画、実行しかない。教育では、計画、学習、練習、実行となる
24 フィードバックをまず活用し、あとで考える
フィードバックを活用し、練習したら、あとから考えればいい
練習⇒フィードバック⇒やり直し⇒なんどか繰り返す⇒できたら、考える
25 フィードバックのループを短くする
フィードバックでは、スピードがきわめて重要、行動を変えたいなら、すぐ伝え、すぐ実行する
26 フィードバックの「ポジティブな力」を使う
3つの方法で手助けする ①認識のことば ②繰り返しのことば ③応用のことば
27 小数のポイントに集中する
たくさんあっても、2つのポイントに集中する
フィードバックに一貫性を持たせること
28 フィードバックを日常のことにする
頻繁にフィードバックすれば、あたえまえに感じられるようになる
29 問題ではなく解決策を説明する
解決策はやるべきことを伝えるだけでなく、あいまいな指示を超えるものでなければならない
30 フィードバックを定着させる
3つのツールを使う
①フィードバックの要約
②フィードバックの優先順位
③次の行動
■練習できる組織を作る
・練習しやすい設備や環境を作る
・練習と一貫した改善の文化を作る
・練習の大切さを伝える
31 まちがいを練習の一部にする
失敗する練習をする
①ころぶのは普通である、スキルの欠如ではない
②スキルの限界ですべりつづけることでさらにうまくなれる
32 練習の障害を打ち破る
練習は生理的苦痛になりうる
身体的反応、心理的反応
自分をながめるもう一人の自分が批評する
①障害を見つけて名前をつける
②練習による克服を支援する
③その件について話すのもうやめよう
33 練習を楽しくする
練習は懲罰であってはならない、練習はがぜん楽しくやる気がわくものにする
仲間意識を活用する
34 全員が挑戦する
リーダが自ら手本になり、練習に打ちこむ
35 仲間同士の責任感を強める
メンバーが集中して取り組みたい具体的なスキルと分野を特定させる
メンバーが相互に責任を持ち合う環境を作る
36 練習のための人材を選ぶ
模擬授業をみせてもらう必要がある
フィードバックをどう受け止めて、自分の指導をどう取り入れるか
37 仕事をほめる
×性質(たち)をほめると成績がおちる場合がある ⇒性質は自力ではどうにもならない
〇行動をほめると、行動を変えれば、結果に影響を及ぼすことができる
■練習は終わらない リーダスキルの向上について
・リーダが新しいパフォーマンスを改善しようとしてもできない
せっかく研修をうけても、習慣化していないので、スキルが定着しない
38 できているかどうか観察する
スキルを切り分けて練習したあと、本番を観察し、練習した個別のスキルについてフィードバックを伝える
練習したスキルに合わせて、本番の観察に役立つツールを作る
39 本番中には教えず、思い出させる
本番中のコーチングには役立つが、本番中に教えるのは、気が散るので、逆効果だ
40 練習中に絶えず話し合う
練習中に共通のことばが定着したあと、練習した内容についてできるだけ多くの方法で話し合う
41 支援と要求のバランスをとる
練習の原則 練習は失敗しても影響のない無処罰の場であるべきである
42 成功を計測する
練習の有効性 練習でできていることを本番でもできるか
正しいことを練習しているか パフォーマンス向上に必要な練習をしているか
著:ダグ・レモフ
著:エリカ・ウールウェイ
著:ケイティ・イェッツイ
紙版
日経ビジネス人文庫 B れ-1-1
ISBN:9784532198725
出版社:日本経済新聞出版社
判型:文庫
ページ数:400ページ
定価:850円(本体)
発売日:2018年09月03日第1刷
Posted by ブクログ
やっと読み終わりました。
読み終えるのになかなか骨の折れる本ですσ^_^;
「練習でパーフェクトになるのではない」
「練習でパーマネントになるのだ」
練習はあくまでも実践の一部を切り出して行うので完璧になることはないと思います。
ただ反復練習を繰り返すことで練習で身につけたことが自然と出るようになります。
「練習→上達」
やらないと上手くならないです。
単なる繰り返しではなく本物の練習を行えているかどうか。
問題は上達しているかどうかを見るとわかります。
「意図的に上達するための反復練習」
実戦練習とは違う反復練習を繰り返すことで身につくことがたくさんあると思います。
「成功を体感できるものにする」
「最大の価値を生む20%に集中する」
ダラダラとムダなことに力を注ぎ込んでも成功は体感できません。
不要なものを捨てる勇気も必要とのことです。
「わかるじゃなく身につくまでやる」
息を吸って吐くように無意識にできるまでやることが最終的には求められるんやと思います。
「練習の有効性」
「正しいことを練習しているか」
最終的に計測できるのは自分しかいないんやと思います。
練習の時からちゃんと考えてやることが大切やとわかる本でした。
Posted by ブクログ
とても内容の濃い、真面目な練習についての本。仕事を身につけ、向上させていくための本と言ってもいい。読み飛ばすような本ではない。しっかりゆっくり実践しながら読む本。