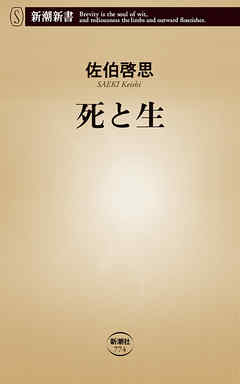感情タグBEST3
Posted by ブクログ
経済学の大家が書いた「死と生」
ギリシア・キリスト・西洋文明そして、東洋文明、日本文明の情報を駆使しての「死と生」、論理的でメチャクチャ解りやすく、自分なりに理解できました。
丁度、般若心経の写経を継続しており、その一字一句の奥深さがよりはっきりしてきました。
西部邁さんの「自死」にいたる経過も含め、少なからず影響を受けられてと思います。
経済学者の日本文明の解析、ますますの進化を期待している所です。
Posted by ブクログ
経済学者・思想家である佐伯啓思が、月刊『新潮45』に連載する「反・幸福論」の2017年7月~2018年4月発表分をまとめたもの。同連載の書籍化は本書が8冊目で、いずれもその時々の時流を勘案したテーマを論じている。
本書は、日本が、もはやモノを増やして、生活の物質的な向上を求めるような経済段階ではない“高齢化社会”、換言すれば、長い人生の生の意味づけや、やがてすべての人に訪れる死への準備へと人々の関心が向けられるべき “成熟社会”に直面する中で、著者としての“死生観”を様々な角度から語りつくしたものである。
内容は、仏教的な死生観を中心に、トルストイが『人生論』で表した死生観のほか、三木清、ソクラテス、ショーペンハウエル、ハイデガー、『葉隠』、西行、平田篤胤、『方丈記』、鈴木大拙、セネカ、モンテーニュなどの思想を部分的に紹介しつつ考察が展開され、最終章は以下のように結ばれている。
「「生も死も無意味だ」から出発して、その「無意味さ」こそが、自我への執着を否定したうえで、現実世界をそのまま自然に受け止めることを可能にするのです。われわれは、草木のように土から生まれ、また土に戻ってゆき、そしてまた別の命が芽をだす。すべての存在がこうした植物的な循環のなかにあることをそのまま受け止めるほかありません。・・・とすれば、われわれは特に霊魂はあるのかないのか、あるいは来世はあるのかどうか、などということに悩まされる必要はない。確かに、生も死もどちらでもよい、などと達観することはできません。しかし、この達観に接近しようとしたのが日本的な死生観のひとつの大きな特徴だったのであり、それは現代のわれわれにも決して無縁ではないでしょう。」
そして、死を論じることの大切さについて、「人間は死すべき存在である、という命題はまた、人間は死を意識しつつ死へ向かって生きる、ということを意味し、これはまさに生き方を論じることでもあるのです。」と付言されている。
私は、本書の中で繰り返し「私は、人間は死ねばただ土にかえるだけで「無」だと思っています」と述べている著者と同様に、死ねばすべてが終わりで死後には何もないとと考えるタイプである。また、三木清が『人生論ノート』に書いている「死は観念である」ということ、即ち、人は誰も死を経験することはできないということだけは、おそらく普遍的な事実である。それを踏まえて、どのようにして「死」に意味付けをするのか、そして、それを「生」に活かしていくのか、様々な示唆を与えてくれた一冊である。
(2018年8月了)
Posted by ブクログ
個人的にはもうちょっと突っ込んだ内容が欲しかった。
「死」に対しての、宗教や文化の違いを例示するなど、様々な考え方があっていいはずで、それらを示しながら、あなたはどう死ぬか?(どう生きるか?)を考える内容かと思って読んだら、少し肩透かしだった。
比較的、著者の意見が真っすぐに書かれていた本でした。
人生100年時代だ。
なかなか死ねない我々。
そして、死に方を容易に自分では選べない我々。
快活に生きることはどういうことなのか?
死に方を考えることは、生き方を考えることだ。
私の死生観はこれに尽きる。
「死ぬ気になって生きろ!」どうせ死は訪れる。
ダラダラしている暇はない。
愚痴ばかり言っている暇もない。
「死の恐怖」すらも忘れられるくらい、一生懸命に突っ走れ!
ただそれだけだ。
(2018/7/15)