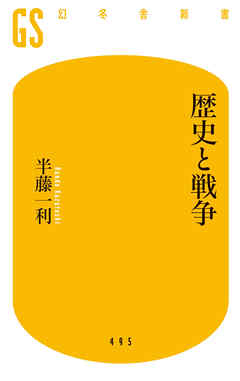感情タグBEST3
Posted by ブクログ
「日本のいちばん長い日」の半藤一利。彼の著書の中での言葉を、時間軸に整理して並べたある意味著作集。
知っていた話もあれば、もちろん知らなかった話も。
「昭和史」も読まなきゃって積読になっているけど、早く読まないと。
後世に伝えなきゃいけないっていう言葉もたくさんあります。新書ですが、これは永久保存版にしようと思います。
Posted by ブクログ
半藤利一氏の著作から切り貼り でも半分ぐらいは気持ちを新たに勉強になった
戦争は悲惨なのは当然 問題は責任が明確になっていないこと
「勝海舟」の評価高い 私も当然と思う 無血開城に加え、日清戦争に大反対
大義なき戦は、結局国を滅ぼす その通りになった
国家を滅ぼした戦犯は
山縣有朋 官僚制度 統帥権の独立 帷幄上奏権 治安維持法 現人神思想
伊藤博文は歴史に残せなかった
近衛文麿 蒋介石を相手にせず ずるずると国費20兆円、人命50万人
東條英機 戦陣訓の罪 超形式主義
→忠義の士が国を潰す[勝海舟]
ノモンハン事件の5つの教訓
①陸軍エリートの根拠なき自己過信
②驕慢なる無知
③エリート意識と出世欲
④偏差値優等生
⑤底知れない「無責任」 →私はこれが一番と思う
それにしても読めば読むほど腹が立ってくる
Posted by ブクログ
数ある半藤一利さんの著作の中から、日本の近現代史に関するものをまとめた本。
「歴史探偵」として、主に日本の近現代史を追っていた半藤一利さん。80冊以上ある半藤一利さんの著作から、主に戦争に関連することをまとめたのが本書になります。
本書を読むと、日本は果たして過去の失敗から何かを学んだのだろうかと疑問に感じてきます。
本書には終戦後、陸軍や新聞社が資料を燃やした話が出てきます。つい最近も似たような話がありましたね。こちらは燃やしたのではなく、裁断したり消去したりしたのですが・・・。
Posted by ブクログ
文春新書の「父が子に教える昭和史 あの戦争36のなぜ?」を読んだ後に、本書を読んだ。ある程度、戦争に関する知識の下地ができたうえで本書を読めたことが非常によかったと思う。
本書は、昭和5年生まれ(今年で90歳)の著者・半藤一利氏の著書から、本書のテーマ「歴史と戦争」にあった文章をセレクトして、一書に編集されたものだ。幕末・維新・明治から近代にいたるまで、特に近代では一年ごとに、その時を述べた著者の文章がセレクトされている。
著者のすべての著書の中から、文章をセレクトし、それを時系列にプロットしつつ、全体として一つの読み物として完成させる、この膨大な作業に対し編集者に敬意を表するとともに、その完成度の高さにも感謝を述べたい気持ちだ。
セレクトされた文書のすべてのその出典が示されているので、著者の原書に戻ってもみたくなる。
ダイジェスト的でありながら、様々な角度から学びが得られる。知識としての発見もあれば、考え方に対する新たな気づきが得られることもある。
例えば満州事変の発端となった「柳条湖事件」。我々が習った頃は「柳条溝事件」と教科書に書かれていた。この一文字の「ん?」が、その訂正された理由とか、この事件が日本の関東軍の自作自演だったことなどを再確認するきっかけとなった。
零戦の戦闘能力が高かったのは、人命を軽視して、機体の軽量化を図ったこと、同様に戦艦大和が攻撃力は世界一だったにも関わらず、対空防御に弱かったことなど、戦時中の思想が異常へと傾いていたことを知ることができる。
真珠湾攻撃での奇襲で戦果を得たことを、小林秀雄や亀井勝一郎や横山利一など日本を代表する作家がもろ手を挙げて大喜びしていたという事実を知り、どんな人であれ環境に翻弄されてしまうものなんだなぁと驚きさえあった。
その背景には情報操作というものがあった。当時のマスコミは、人心をコントロールするためのツールでしかなかったような印象を受ける。
「ノモンハン事件」が、陸軍エリートの過信や驕慢や無知から引き起こされた無責任な事件であったことを知る。
フランスの社会心理学者ル・ボンの「群集心理」を引用し、個人が群集にることで集団精神というものが生まれ、衝動的となり、動揺しやすくなり、興奮しやすくなり、暗示を受けやすくなり・・・と、当時の狂気の思想が成り立つ仕組みを解説してくれる。
日米戦の真実を語る石原莞爾の言葉。「この戦争は負けますなぁ。財布に千円しかないのに一万円の買い物をしようとしてるんだから負けるに決まってる。アメリカは百万円を持ってて一万円の買い物をしている」
なぜ「終戦」と呼ぶのか。「敗戦」という表現を嫌ったから。毎年、「終戦記念日」という言葉になんの違和感もなしに過ごしてきたが、そこにはそんな秘密があったのだと知った。しかし、著者はむしろ、民衆にとっては「戦争が終わった」という意味で、この言葉は良かったと述べている。
東京大空襲を指揮した男(米・空軍大将カーチス・イー・ルメイ)に旭日大綬章が授与されている事実を本書で取り上げ指摘している。推薦したのは小泉純一郎の父・当時の防衛庁長官・小泉純也らしい。カーチス。ルメイは、原爆投下についても、戦争を早く終結で来たメリットをいうような男でもある。
こういう半藤氏の視点に共感を覚えるのであり、氏の著書には読後の後味が非常に良く感じる。
最後に印象に残った著者の言葉二つ。考えさせられる言葉である。
・戦前や戦中は、「人間いかに生くべきか」ではなく、政治や軍事が人間をいかに強引に動かしたかの物語であった。
・反省のない元軍人に対し、勝海舟の次の言葉を引用していた。「忠義の士というものがあって、国をつぶすのだ」
Posted by ブクログ
お盆の時期なので何か戦争に関する本を読みたいが、子どもの遊びにも付き合わねばならないから分厚いものは無理だなあと考えながら、本屋で見つけたのが本書。半藤氏の過去の著作からの短い引用が、戦前〜戦中〜戦後の順に並べてあり、時代をざっと概観するには良かった。次は引用元である著作のどれかをじっくり読んでみたい。
以下、面白かった点。
P16-17
人工的な神国意識や天皇観。
P20
新旧両思想に帰依せず『宙吊りの孤独に堪えねばならなかった』勝海舟。
P34
日露戦争で日本兵の精神的弱さが認識されていたにもかかわらず、戦史には残されなかった。
P44-45
「非常時」の掛け声の下の軍国化。
P46
売るために積極的に戦争を煽った新聞。
P133
資料の整理保存が国家の仕事。
P142-144
石原莞爾の平和主義と人間味。
P146
東条英機の形式主義。
P151-152
『人間そのものから考えずに、機械や組織や権力や制度や数字といった人間とは別のものから考える傾向』『非人間的ーそのことがすなわち「戦争」』『大本営の学校秀才的参謀どもの机上でたてた作戦計画』
P185
日本はもう現状維持でいい。
Posted by ブクログ
幕末・明治維新からの日本近代化の歩みは、戦争の歴史でもあった。文藝春秋の編集長や役員を経て、歴史作家の半藤一利氏の80冊以上の著作から厳選した半藤日本史のエッセンスがここに!
Posted by ブクログ
半藤さんの今までの著書のまとめを歴史順に摘んだ図書でした。半藤ファンや昭和史の好きな方にはお勧めします。私は初心者ですのでもっと勉強して再度読み返したい。
Posted by ブクログ
実際に戦前から戦後を生きた方の、なんとも重たい言葉の数々。
特に東京大空襲の体験は衝撃的ですし、戦後に戦中の将校たちにインタビューを行い書いている文もすごく印象的。
この本は半藤氏のたくさんある著書から印象的な部分を引用してできているものなので、氏の著書を多く読んできた方なら物足りなく感じるだろうと思いますが、私みたいな初めて入る人にとっては最適だと思いました。
Posted by ブクログ
これは、タイトルがよくない!と心から言いたい。
うわーい新作!と思って読むと、とってもがっかりするので。
要は、過去の書籍からの抜粋、まとめなんですよね。
これはこれでよく出来てるの。
抜粋でもはっとする文があるし、全部出典がついてるからこの本読んでみたい!ってなるし。
半藤作品をあんまり読んだことない人にむけてのお試しガイドとしては素晴らしいと思うの。
でも、でもね!
新作を楽しみにしてたんだよー!
せめてタイトルにね、「過去作品集」とか「オムニバス」(使い方あってる?)とか入ってたらよかったのに…。
それでも気になる本がいくつか出てきたので、またいつか読んでみたいと思います。
でももう、新作は二度と読めないんだなあ…寂しい。
Posted by ブクログ
歴史に関する様々な作品がある著者の、幕末以降、戦争にまつわる作品を選び、著者の言葉をまとめたもの。
著者の作品は何冊か読みましたが、このよな編集になっているとは知らず手に取ったため、本全体としての主張などは分かりません。この中から気になるフレーズを探し、実際に原典にあたるためのガイドブック的なものとしてとらえればいいのかなと思っています。
個人的に気になった部分をメモしてみました。
・「フランスの社会心理学者ル・ボンは『群集心理』(創元文庫)という名著を、十九世紀末に書いているが、かれはいう。『群集の最も大きな特色はつぎの点にある。それを構成する個々の人の種類を問わず、また、かれらの生活様式や職業や性格や知能の異同を問わず、その個人個人が集まって群衆になったというだけで集団精神をもつようになり、そのおかげで、個人でいるのとはまったく別の感じ方や行動をする』そして群集の特色を、かれは鋭く定義している-衝動的で、動揺しやすく、昂奮しやすく、暗示を受けやすく、物事を軽々しく信じる、と。そして群集の感情は誇張的で、単純であり、偏狭さを保守的傾向をもっている、と。昭和十五年から海鮮への道程における日本人の、新しい戦争を期待する国民感情の流れとは、ル・ボンのいうそのままといっていいような気がする。それもそのときの政府や軍部が冷静な計算で操作していったというようなものではない。日本にはヒトラーのような独裁者もいなかったし、強力で狡猾なファシストもいなかった。」(『昭和・戦争・失敗の本質』)
・「戦争をいうものの恐ろしさの本質はそこにある。非人間的になっていることにぜんぜん気付かない。当然のことをいうが、戦争とは人が無残に虐殺されることである。」(『B面昭和史』)
・「よく『軍人はつねに過去の戦争を戦う』といわれる。先頭の技術や方式の急激な変化を予測することは、たしかに非常なる困難なことに違いない。が、戦いがはじまってそれをまのあたりに見せつけられながら、なお『過去の戦争』を日本人は戦っていた。その悲しき象徴が戦艦大和・武蔵なのであった。」(『歴史探偵かんじん帳』)
・「本当に日本人は歴史に対するしっかりとした責任というものを持たない民族なんですね。軍部だけではない。みんなが燃やしちゃったんですから。」(『「東京裁判」を読む』(保阪正康氏・井上亮氏との鼎談で))
・「『一億総懺悔』は、そう影響がなかったと言う人もいますが、その後の日本人の精神や日本の歩みを見ても必ずしもそうではないように思えるんです。みんなして悪かったんだからお互いに責めるのはよそうじゃないかという『なあなあ主義』につながりもし、同時に、この言葉のなかに、トップ層の、結局は戦前戦中と変わらない国民指導の理念が垣間見えるからです。つまりこれが、『戦後どういう日本をつくるか』をわれわれがしっかり考えるための大きな障害になったと言いますか、むしろわれわれにそれを考えさせないようにした、という気がするんです。そしてこの先、皆がなんとなしに『そういうもんか』と、責任を追及しなくなったような印象があるのです。」(『昭和史 戦後編 1945-1989』)
・「まったく戦争というのはいつの時代でも儲かるのです。新聞雑誌もそうです。だから変なことを考えるやつが絶えないのです。」(『昭和史 戦後編 1945-1989』)
・「政治的とは、人間がいかに動かされるか、動かされたか、を考えることであろう。戦前の昭和史はまさしく政治、いや軍事が人間をいかに強引に動かしたかの物語であった。戦後の昭和はそれから脱却し、いかに私たちが自主的に動こうとしてきたかの物語である。しかし、これからの日本にまた、むりに人間を動かさねば…という時代がくるやもしれない。そんな予感がする。」(『昭和史 戦後編 1945-1989』)
・「戦争は、ある日突然に天から降ってくるものではない。長い長いわれわれの『知らん顔』の道程の果てに起こるものなんである。(中略)いくら非戦をとなえようが、それはムダと思ってはいけないのである。そうした『あきらめ』が戦争を招き寄せるものなんである。」(『墨子よみがえる』)
・「この元軍人には反省という言葉はないと、そのとき思った。そして勝海舟の言葉『忠義の士というものがあって、国をつぶすのだ』とそっとつぶやいたことであった。」(『B面昭和史』)
<目次>
第1章 幕末・維新・明治をながめて
第2章 大正・昭和前期を見つめて
第3章 戦争の時代を生きて
第4章 戦後を歩んで
第5章 じっさい見たこと、聞いたこと
Posted by ブクログ
客観的に歴史を振り返れば振り返るほど、日本人ほど熱しやすく冷めやすい民族はないのではないか?いずれまた近いうちに間違いなくこの国は戦争に熱狂してしまうような気がしてしまう…。
ご本人も去ることながら、石田陽子さんに脱帽。