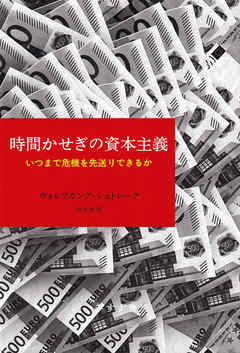感情タグBEST3
Posted by ブクログ
近年読んだ本のなかで一番面白かったです。星6つ、7つの評価です。本文もそうですが、文末の訳者の解説も改めて頭の整理が出来たので非常に重宝しました。本書で主に議論の対象としているのは欧州と米国といういわゆる「西側」の民主主義的資本主義国家群です。そしてこれらの国々での資本主義が第二次世界大戦後どう変化してきたか、ということで、1970年頃を境に大転換が起こったと見ています。戦後から70年頃まではいわゆるケインズ的な介入主義的資本主義ですが、ブレトンウッズ体制の崩壊をきっかけに、新自由主義的転換を経て、ハイエク的な市場主義的資本主義へと転換してきたと分析しています。そこでは資本主義と民主主義という本来は相性が必ずしも良くない2つがどう折り合ってきたか、そして現在起こっているのは、(1)経済の脱民主主義化(2)民主主義の脱経済化、であって両者が分離しようとしているという分析をされています。そこでは国家に加えて「市場の民(資産からの利潤を要求するレントシーカー)」と「国家の民(労働賃金で生活する人々)」の対立があり、2つの民が国家に対して自身の権利を主張しているわけです(※現在のところ圧倒的に市場の民に軍配が上がっている)。これはあたかも経営が危うくなってきた企業に対して、従業員、債権者、株主が、「俺への支払をまず済ませろ!」と叫んでいるかのようです(※もちろん企業の場合は弁済順位が法律で決まっていますが、国の場合はそうではない)。
さらに著者は、ハイエク的な市場主義的資本主義が1970年代以降行ってきたことは単なる時間稼ぎであって根本的な解決になっていないと述べています。つまり「市場の民」と「国家の民」の両方を満足させるために、貨幣の増刷(インフレ)、国家債務、家計債務が行われてきたわけですが、これはまったく根本的な解決にはなっておらず、特に国家の民の大きな犠牲の上に成り立っているという意味で、どちらかと言えば市場の民を利する動きであるわけです。そのような天秤の大きなブレを是正すべく最終章では著者の提言も多少書かれていますが、提言箇所については著者自身も述べているように参考程度としたほうが良いでしょう。むしろ世界経済の現状認識という点で非常に勉強になりました。
Posted by ブクログ
正統の経済学とは違った視点からの資本主義の貴重な分析。著者のバックグラウンドは社会学とのことだが、そういった異なる分野からの経済の検討は大切にしていかなければいけないのではないか。
Posted by ブクログ
ケインズ的混合経済に代わってハイエク的自由主義経済が本流に腰を据えた70年代以降、「インフレ」「国家債務」「家計債務」と手段を変えつつファイナンス原資を確保し、果実を恣(ほしいまま)にしてきたファナティックな市場主義者=資本家。本書は彼らに対する糾弾の書である。金融危機の余波も覚めやらぬ2012年の著述だが、むしろ世界がコロナウイルルスに翻弄される現在(2020年3月)こそ読み返されるべき。著者は経済専門家ではなくフランクフルト学派の流れを汲む社会学者であり、所々で社会学のタームが顔を出すが、基本的にマクロ経済の知識があれば問題無く読める。
政府が、国債を保有する債権者たる資本家に配慮するあまり、国民の主権が蔑ろにされてきた。はたしてこのような資本家に帰属する収益に「正当性」はあるのか?というのが著者の問題提起。「計画された自由放任主義(カール・ポランニー)」に基づく、各国の個別事情を顧みない単一市場/単一通貨の押し付けは、過剰債務に陥った国家に「内的切り下げ(国債利回り低下をもたらす通貨切り下げのかわりに、労働市場の流動化や低賃金、低福祉による競争力回復)」を強いるものであり、主権の所在である国民より国際資本を利するものだとする。
たとえば、財政出動(や減税)は、それに伴う国債増発が、国債に投資する資本家への利払い抑制ではなく、将来の増税や年金抑制につながるため、国民は結果的に相対的な財のシェアを失う。これは名目所得の増加で実質所得の目減りをマスクし、資本家に有利な形で富の分配がなされることにほかならない。また、減税は資本家の投下資本の回収局面における回収原資の増大につながる。いざというときの課税余地を確保することになるからだ。
かかる状況を打破し新自由主義的成長から排除され、虜囚となったた人々を救うため、著者はラディカルな提言を行う。すなわち、国家がこのまま脱民主化された政治経済への移行を看過し主権行使を留保し続けるならば、いっそポピュリズムや反成長主義の汚名に甘んじても破壊的な抗議行動を選択すべし、というのだ。具体的には通貨切り下げという本来国家に備わった主権行使手段を取り戻すという、現代版ブレトンウッズ体制への回帰だ。ナショナリズムはハイエク主義に比べれば危険ではない、というのはずいぶん過激な物言いだが、プリンシパル(主権者=国民)とエージェント(政府)の主従転倒にもどかしい思いを抱く著者の思いが伝わってくる。その後イタリアやフランス、そして何よりイギリスで起こったことに照らせば著者の主張も故なしとは言えないだろう。それでも解決どころか益々混迷の度合いを深めつつあるのがEUの抱える問題の根の深いところだが。
なお、本書の主張に沿えば市場は国家に国債価格の維持=財政健全化を要求するはずだが、現実にはそのようになっておらずむしろ市場は自らの利子収入の阻害要因となるはずの公的債務の膨張を懸念するどころか歓迎しているように見える。しかしこれについても、もはや金融危機後は家計債務の増大トレンドを維持できずかつてのようにインフレや国家債務膨張にしか頼れないと気づいた資本家サイドが、MMTのような公的債務過多のリスクを過小視する「理論」を持ち出すことにより、国家のバランスシート肥大リスクを不可視化して国債の減価を顕在化させまいとして流布するプロバガンダの顕れだと考えれば、鮮やかに現実と整合する。
たかだか景気に多少の減速の兆候がみられるからといって脊髄反射的に財政出動を叫ぶ国民は、その移転支出が果たして己れへの実質的な富の移転なのか、それとも名目的なものに過ぎず、国家債務膨張による投資機会増加で果実を掠め取る者が他にいるのかということについて、本書の主張に耳を傾けて意識的になるべきだ。また政府・中央銀行についても、市場の要求に過度に応えてしまい小規模な資産価格調整局面で金融緩和の大盤振る舞いを繰り返すと、いざコロナショックのような重大局面が起こったときにもはや弾切れ、という笑えない事態が今まさに起きつつあることを認識してほしいと思う。
Posted by ブクログ
本書で著者は、フリードリッヒ・ハイエクが描いた自由主義的市場経済が世界を如何に変貌させていくかの予言を受けて、租税国家→債務国家→財政再建国家という道筋をなぞりながら、その恐ろしいまでの正しさを確認していく。通読すれば、何故政府が立場の弱い労働者に甘言を弄して彼らを不安定雇用へと追いやるのか、何故生活困窮者にとどめを刺すように社会保障費を切り詰めていくのかといった現在観測される様々な不条理がことごとく解き明かされる。