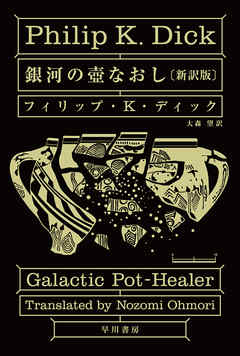感情タグBEST3
Posted by ブクログ
「銀河の壺なおし」…なんだかあまりおもしろそうなタイトルではないなぁと思いつつ手に取りましたが、これがどうした、意外と楽しめました。
そもそも壺なおしってなんだよ、というところから入りますが、主人公ファーンライトは陶器修理の職人家。しかしながら、陶器がプラスチックにとってかわられた昨今、陶器を修理するひとはどこにもいない。そんな彼のもとに待望の仕事が舞い込む。シリウス星系のグリマングからの巨額オファーは、海底に沈む大聖堂ヘルズカラを引き揚げるというもので…
相変わらずな設定ですが、展開も明後日な方向に進みます。ただ、どこか象徴的な場面が多く、頭に映像として強く焼き付くシーンもちらほらと。個人的には、プラウマンズ・プラネットの海中での出来事とその後のグリマングの死闘あたりは特に印象深い。また、ぐいぐいと引き込まれるテンポのよい展開はなにかのアトラクションに乗っているよう。最後もたぶん前向き(?)な終わり方でしたし、総じて楽しめた作品でした。
Posted by ブクログ
質問や命令に対して「ウィリス○○しろ」
というルールを頑なに守ろうとしながら
人間(状況)に合わせて、苛立ちながら妥協したり、
実は□□になる夢を持っていたり、脇役ながら光る。
まさにいま「OKグーグル」で反応する世界を予言。
葛藤があるあたり、当時は違ったかもしれないが
現在からすると風刺・パロディーの様でクスリとする。
で、物語自体は、色とりどりだが
ぶっ飛んだところも少なく、薄味な印象。
何もすることはなく、体制に生かされているだけの
どん底の人間が、何かに必要とされ、そのなかで
他人が敷いたレール:予言に抗い、
自分を見つめなおした先にある再生が
結局のところラスト一文の今回の日本語訳に
落ち着くのだろう、と私は(解説を読んで)思う。
いや、もしかするとそれすら他言語への翻訳を
もういちど元の言語に訳したゲームの結果
でしかないのかもしれない。
Posted by ブクログ
楽しい!ある意味ナンセンス。
Wikipediaを見ようとして通信制限にかかるとか、機械翻訳の再翻訳誤謬ゲームもそうだし、OK, Googleって言わないと反応しないAIみたいなのとかなんで’60年代に思いつくのか。しかもそのチョイスが微妙すぎる。
Posted by ブクログ
おー、確かにセリフが違うぞ。
旧訳より読みやすく感じたのは、既にストーリーが頭に入っていたからか、自分が年取ったせいなのか、訳者の優劣かは謎。
Posted by ブクログ
SF。
ディックはけっこう苦手で、長編を読むのは初めて。
個人的なディックに対するイメージと違って、意外とユニークでコミカルな作品。
シュールな雰囲気とコミカルな雰囲気が混在し、独特の読み心地。
訳者あとがきにもある通り、ラスト一行が色々と解釈出来て、読後感まで不思議な感じ。
Posted by ブクログ
タイトルから受ける印象通りの、へんてこりんな世界観。序盤こそディストピア的な管理社会を描いているが、仕事を受けて地球を飛び出し、未知の星へ降り立った後から始まる冒険はSFというよりファンタジー。これは好みが分かれそう。自分はストーリーについては今一つ楽しめなかったものの、部分部分で興味をひかれる要素がちらばっており、全体としては面白かったと思う。
特に面白いのは、英語の小説や映画のタイトルを外国のコンピュータに音声入力して外国語に翻訳させ、それをもう一度コンピュータ英訳したフレーズから、もとのタイトルを当てるゲームが登場すること。少し前までネットの自動翻訳で面白い訳を目にしていた我々の世代には既視感があるが、これを1960年代に考えていたディックの先見性たるや。
Posted by ブクログ
話としては少し古さは感じるものの、のびのびしたSFって感じがして楽しめた。
ただ、ディックの原文が問題なのか大森さんの訳なのか、今ひとつのめり込めない話だった。勿論、あくまで僕には合わなかった、という話だけど。
説の引きは凄く上手いのに、数日に分けてちびちび読めるくらい(本当に気に入った本は、勿体ないからと脇に置いても、気になってすぐに続きを読み始めてしまう)にしか惹かれなかった。ただ半ば過ぎた辺りからは、一息に読んだので、面白く感じたんだろうと思う。
展開的には凄く盛り上がってるはずだし、ビジュアルも結構浮かぶんだけど、なんだかこう身に迫ってこない感じ。ただ、話が本格的に動き出すまでが遅くて、ちゃんと完結するのか不安に思っていたら、後半ぐいぐいと話をまとめあげていたところは好きだった。その辺の話とか展開としては好きなんだけど、やっぱり読んでいて興奮とかはしなかったんだよなぁ。
現実との繋がりを感じさせるタイプのSFではなくて、全体的に話の規模は大きく、小さなものに着目している場合でも、そこから哲学的な方向に話が発展していく。そういう話を中心として展開し始める辺りから、ぐんぐん面白くなってはいった。ガジェットや世界設定でなく、テーマとしてアンドロイドが好きなら、気にいるかも。
のめり込めなかった原因の一つが会話文で、お互いの話を聞こうとしていないのか、かなりの箇所で、唐突だったり噛み合っていない印象を受けた。
それから、訳者も指摘しているけど、現行の技術を彷彿とさせる設定が登場するのには、非常に感銘を受けた。読んでいて、これってあれっぽいな、と思う技術が結構出て来る。また、描かれる地球の設定も、はっきりとは見えてこないものの、どことなく退廃的で、好きな人は好きかも。
感想を書いていて思ったのは、作中の設定を地の文で詳らかにするってことを、ディックはあんまりやってないのかも、ていうこと。アンドロイド、高い城を読んだのは随分前になるし、漠然と思ったので実際は的外れなのかも知れないけれど、冒頭の地球の生活とかは特に、出てきた事象については作中におけるシチュエーションでしか知ることができず、その全容をあんまり掴むことができない気がした。語り手が、その状況に置かれた一個人であると言う前提からするとそれは凄く正しい書き方なんだと思うけど、なんだか個人的にはもやもやした。
Posted by ブクログ
翻訳ミステリ札幌読書会に初めて参加させて頂く機会を得たのだが、最初の課題本が何とこれ。ミステリでもなければ、ディックの代表作品でもなく、どちらかと言えばゲテモノ扱いされる異色作。
初めて会う方ばかりだったが、ぼくのテーブルにはロバート・クレイスの翻訳者である高橋恭美子さんや、ヒギンズの大ファン氏でありながら何故かディックにも詳しい方がおひとりいて、この作品の位置づけを教えて頂けた。
どちらかと言えば、傑作を二つ三つものにした後の疲労回復のために肩の力を抜いて書いた作者のお遊び的作品なのではないか、という辺りで、多くの読者の感覚は落ち着いたのだが、まさに自由気ままに浮かび上がるイマジネーションを主人公である壺なおしのジョー・ファーンライトを軸に、展開して遊び抜いた、一言でいえばおもちゃ箱のような一冊である。
しかしディックのことだから、ともすれば深淵な意味合いが込められた奥行きのある哲学的書物であるということも考えられなくはない、という見方もあながち空想的と言い切れない。どうも怪しげなスタンスに立つ難物の作品であるようである、少なくともディックの研究家にとっては。
しかし、ぼく自身SFから十代で足を洗い、その後現実や歴史に即した人間の内部に迫る小説を好んで読んできた経緯もあって、ディック作品も初である。映画『ブレイドランナー』信者ではあるが、あれの原作者がディックということくらいしか持ち合わせない知識で、あの映画自体もぼくはハードボイルドとして観たという主観が強く、本作のような銀河の果てに出かける冒険譚というのは、極めて異色の読書経験なのである。
前段が極端な管理社会の中で生きる意味を失うジョーの虚無的な日々が描かれる。思考まで他人に読み取られ、歩行速度まで監視され警告される、度の超えた管理社会。そこは2046年のクリーブランド。作品が書かれたのが1969年だから、77年後の想像された地球である。
そこから自分の生きる意味を見つける冒険の機会を得て、壺なおしという極めて専門的な技術を持つ職人のジョーは、地球を後にして遥かな星の海洋から神殿を引き揚げるという大作業に集められた者たちと行動を共にする。異星では、仲間となる異質な生命体たちや、ロボット、雇用主たる巨大な変容体生命グリマングなどと出会ってゆく。
ロボットとの奇妙で滑稽な会話や、仲間のクールで奇妙な女性との恋愛、仲間たちとの対立や迷いなどの末に、大団円を迎える大冒険の果てに待つのは、何と……。
SFというジャンル故に産み出せる、とても奇妙な小説。これが半世紀ぶりに読むSF作品として相応しいか否かはともかく、ここまであらゆる理解を拒む、あるいはあらゆる自由理解を受容する作品を選んだ読書会主催者の発想にこそ拍手を送りたい。