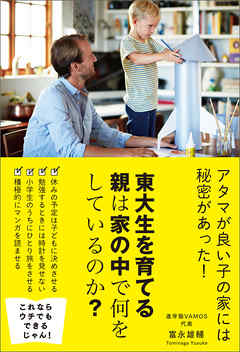感情タグBEST3
Posted by ブクログ
読んでよかった!
勉強を嫌いにさせない、肯定する、仕掛けをする、適度な目標設定と達成後に満足させきらない声がけなど、本当に面白かった。
子供はまだ2歳だから、数年後にまた読み返します!
Posted by ブクログ
すごくよかった! 付箋貼りまくり。メモと納得コーナーを最後に記載。
著者、先着順・入塾テストなしの塾経営、それで進学率80%の凄腕。
子どももそうだけど、親の傾向をよく見ていて、東大に入れる親はこう、というエッセンス満載。親の学歴、収入にかかわらず、子どもへのかかわり方いかんでは子どもが伸びる、と勇気づけられる一冊!
著者自身の、子どもの見方や伸ばすやり方に愛情と熱意をひしひし感じる。子は宝。未来。
memo&納得↓
p29
苦手と得意の科目について、先に苦手を叩きがちだけど、得意の方を10点伸ばして勉強の楽しさを感じられるようにする。
次に、まあまあ得意の科目。自信と、点数を上げるコツをつかんで、最後に苦手科目に行く
p35
家の中に勝負の空気を作る
家族で競う。親と子の勝負。ハンデをつけると勝った時の喜びがあまり感じられないので、オセロなどで努力次第で子どもが勝つ可能性のあるものにする。
p45
自分で考え、自分で解決するという自立心を持っている子どもというのは、どんな分野でも大きく成長します。
例えば、少年サッカーでは荷物がきちんと整理できているチームほど強いという人がいる。
ただ、それはコーチが怖いからというだけのこともある。塾でちゃんとし手家でだらしないなら見せかけの自立である可能性が高い。規律が厳しければ逆に自立が阻害されることもあるよう。家庭で育つのが自立。
必要なものは自分で準備する。自分が使ったものは自分で片付ける。それだけでよい。甘えと厳しさが同居していること。
p50
お母さんが夕飯を準備している横で知らんぷり。お皿やお箸に並べるようなお手伝いをしていない子が増えている。食事の準備を手伝わない子は成績も伸びません。
準備することの大切さを教えられる。
片付け,ふきんで拭く、献立を確認して、必要な食器を並べる。家族がテーブルに着く前にご飯をよそっておく。
1つ1つの作業は単純ですが、うまくやらないとお皿が足りない、フォークの方が食べやすかったなど小さなトラブルが起きる。失敗に戸惑っても、次第にできるようになる
p54
東大生の多くは大変な読書家。かばんにもいつも本。家庭でも小さいころからたくさんの本に囲まれているが、小さいころから自分の好きな本ばかり読んでいたという人が多い。
延びる子は自ら本を選ぶ。本屋で子どもを自由にし、どんな本でも買ってあげる。漫画でもいい。興味があるものを読んで夢中になることが、学びたいという意欲につながっていく。
読んできた本を並べるのも楽しい
p76
模試の結果が悪くて子どもが落ち込んだら、親はネガティブな言葉を出さない。落ち込んだ気持ちに拍車をかけない。
逆に良くても、これはあくまで模試よとクールダウンするような言葉をかける。子どもは慢心せず、本来の目標に向かうことができる。
p85
ピンチから逃げ出そうとする子6割、ピンチをピンチだと気付かない子2割、残り2割がピンチと戦える子(東大)に入る子。
塾、野球、サッカー、ピアノ。子どもにとってピンチは、今の実力以上の環境や課題と戦わざるを得ない状況。まあ自分はこんなもんだ、できなくて当たりまえ、などと負け癖をつけてしまいがち。でもピンチと戦える子は、そういう状況でも決してあきらめず本気で戦おうとする意欲がある。一人旅を経験させるのも手。やればできると自信を得る。小学生のうちに一人旅を経験させるとよい
p93
今日勉強した内容の60%を100%理解しなさいと言っている。
全体の60%の内容を確実に、100%理解することを続けて行けば、確実に成績は伸びていく。
10問のうちの6問を完璧に解ける実力を身につけて、その6問だけを相手にすることを続けて行けばいい。残りの4問はその時点でほっておいても、自分の理解力が高まっていけば、自然に解けるようになる。
p94
延びる子は、塾で難しい応用問題の解説が始まっても、「今の自分にその問題は無理だ」と判断し、自分で切り捨てる潔さがあります。親も、現時点で理解できない内容があることに対して非常に寛大。すべて理解しようとして全部中途半端になる人がいる。
p97
勉強の積み残しのように、成績優秀の子の親ほど、子どもの端緒をありのままに受け入れている。むしろそれをあえて治そうとはせず、笑いとばすようなおおらかさがある。短所は、成長とともにしっかりみについてしまったもの。それをむりやり変えようとするのは、その子の生き方を否定することにもつながりかねない。萎縮、自己否定、プライドが傷つく。東大生の多くは、自分の短所をネタにする。「自分にはこういうところがあるけど、仕方ないじゃん」と言い切れる強さ。小さいころから親が,その短所とうまくつきあっていくように仕向けた結果。
p115
親夫婦の意見がすりあわせられない人が多い
母親がイニシアティブをとるとうまく行くことが多い。
p117
日記をつけさせると、大変だから、続けることがつらいことだと認識させてしまう。習慣は、誰かに強制されなくてもできること。
p119
小学校低学年の子どもは毎日5分の計算ドリルや漢字ドリルを習慣化するといい。短い時間だけど、子どもにとっては大変で、習慣化するとしめたもの!
いろんな種類のものを並べて好きなものをやる、とすると変化がついて続く。とにかく継続させることが重要。
継続力さえつけば、少しづつ負荷をかけていくこともできる。気が付けば5分が10分。
p132
成績が伸びる子は、成功しても失敗しえも、自分で選んだ目標に対する責任を自分で負える子。自分で決めるという段取りをきちんと踏むこと。
p134
ダラダラの1時間より集中の5分。いかに密度の濃い勉強をさせるか。
p138
手が勝手に動くほどの集中力をつける。簡単にできる問題をスピーティーにとくこと。手の動きが止まらないような勉強。漢字ドリルや計算ドリルの優しい問題を解いていく
p141
東大生は、休むことの大切さを教えられてきている
ゲームに夢中な子の親が、週に1回だけゲームをとことんやっていい日を作ったら、集中してやるからだんだん時間が短くなった。
p150
リビングで家族それぞれが静かに集中して作業をする。集中している人の邪魔をしないというマナーも学べる。孤独にさせない。
p179
一日に2時間の勉強、としてもまとめて2時間にこだわらず、朝食前の10分、出る前の5分、…と隙間時間を活用する。東大生講師も、隙間時間にこまごまとした雑務をするなど、処理能力にたけている。短い時間でも頭を切り替えて取り組める集中力。
p184
スマホでいつでも調べもの
p196
模試の日に本番と同じ朝食、弁当、服装で動く
本番はいつものでりらくすできる
p200
受験は戦争ではない。勝ち負けではない。受験に挑んだという経験は無駄にならない。
最後は感動すらする。良本。
Posted by ブクログ
個人的には凄く読みやすく、ハマった本。自分は父親としてそこまで息子に構えていないような気がしているが、余裕を持って支えたり、導いていければと思う。競争を楽しむ、というのは確かに大事な概念。
Posted by ブクログ
しっくりくる内容が多かったです。「大事なのは挑戦するというプロセス」。周りを見ても、中学受験してる人達は地頭がいいように思っているので、中学受験に挑戦するのもいいのかな…と思うようになりました。
Posted by ブクログ
子どもに夢を持たせるために、テレビやマンガを遠ざけない。集中力を高めるためには、ゲームを利用するのもあり。休みの日にはダラダラする(習い事を減らしてでも)。オフのダラダラが、オンの集中につながる、など、目からウロコの内容が多々。
特に参考にしたいと思ったのは、「ピンチを戦える子」にするために、あえて厳しい環境に子どもを放り込むということ。自分の実力よりちょっと上のレベルの限界を超えられたという経験の積み重ねが大事だと改めて実感。
また「リビング学習」では、親は別の作業に集中し、「親の時間はすべて自分のためのもの」という甘えを断ち切らせるということ。すぐに実践したいと思います。
Posted by ブクログ
『東大生』を育てるためというよりも、もっと幅広で視座の高い、子育てメソッド本。
特に幼児から小学低学年までの子を持つ親にとってはとても有益な一冊だと思います。
活字の分量は決して多くはないですが、内容がぎゅぎゅっと詰まっています。
以下、個人的に参考になった21個のダイジェスト。
1.
小さい頃は、あらゆるところに注目して、ほめ続けることが大事。
普段からほめ言葉をさりげなくかけてもらっている子どもは、自己肯定感を自然と得ることができる。
伸びしろのある子とは、「自分はやればできる」という強い自信を持っている子。
2.
小学3〜4年生以上であれば、表面的な点数ではなく、子どもの満足度に合わせて褒めることが大切。
例えば、同じ60点でも、その60点が精一杯頑張った結果で、本人の満足度が80%くらいあるなら、80%分しっかりほめる。
褒め方のさじ加減が重要。
3.
得意科目は自信がある分、さらに点数を積み上げることがそれほど難しくない。
点数があがればますます自信がつくし、そのうち点数を上げるコツも掴んでいく。
子どもが勉強の楽しさを感じるのはこうした過程。
勉強の楽しさを少しでも感じてきたら、次はまあまあ得意な科目の点数を上げるという課題に挑戦する。
そうして「自分はできる!」という自信と点数を上げるコツを掴んだら、苦手科目に少しずつ挑戦すると良い。
4.
勝負の楽しさを知らない子は、勝負の経験が乏しい。
逆に勝負できるの子は、その楽しさを知っている子。
多くの子が挑戦しない傾向にあるから、勝負好きというだけで、大きなアドバンテージになる。
5.
家の中に勝負の空気を作る。
たまに遊ぶという程度では、勝負の楽しさを知るには至らない。
日常生活の中に沢山の勝負を持ち込むことが大事。
例えば、駅までどっちが早く着くか、誰が早く片付けられるか、誰が最初に外出の準備ができるか等。
あらゆることで勝ち負けや序列をつける。
勝負したがらない子の中には、失敗や負けを過剰に恐れる子がいる。
負ける経験を十分に積んでこなかった。
親がゲームで手加減をする、子どもが負けそうな競争には参加させないといった配慮はおすすめしない。
大事のは、負ける経験を十分に積ませ、同時に負けた悔しさをしっかりと受け止めさせること。
そしてその悔しさを跳ね返すために、次にどんなアクションを起こすのか自分で考えさせること。
6.
子どもがまだ小さい時に、特に大事にしたいのが、親子で入るお風呂の時間。
お風呂は心も身体も裸になるから、心身ともにリラックスできる時間。
そういう時間は、自尊心を養うのにうってつけ。
なぜなら、心からリラックスしている分、すんなりと厳しさを受け入れるから。
湯船に浸かっている間は思い切り甘えさせる。
その一方で、身体は自分で洗わせて、使った石鹸やタオルは元の場所にきちんと戻させる。
それを当たり前に繰り返す。
7.
自分で決めることがやる気につながる。
子どもがまだ小学校低学年くらいで、選べないと思っても、選択肢は与えるべき。
それも3冊とか5冊ではなく、20冊くらいの候補から1冊を選ばせる。
8.
子どもがまだ小さい場合でも、「これをしよう!」と大人の提案に従わせるのではなく、子どもの意志を尊重させる。
例えば公園で遊ぶ時も、いくつかの遊び道具を持って行って決めさせる。
決めるトレーニングをする。
9.
伸びる子は常にハングリー。
喜や楽の時、すなわち子どもが満足している時に、親がどう対応するかが、子どもを伸ばす鍵となる。
伸びる子は、それなりに自信はあるが、同時に満足するにはまだ何かが足りないという感覚(ハングリー精神)が持てる子。
だから、成果に相応しい褒め方が絶対に必要。
大いに褒める瞬間があったとしても、それはまだゴールではないのだと子どもにら感じさせる。
「よく頑張ったね。さあ、これで90点を目指す準備ができた」
良い意味で水を差す。
10.
旅が子どもを大きくする。
たとえ隣町までの一人旅でも、親に連れられていく隣町と、1人で行く隣町とでは、その子が見る景色は全く違う。
自分の限界をちょっと越えればクリアできるレベルを設定する。
限界を超えた経験を与える。
11.
上手くいく家庭は母親主導
夫婦どちらかがイニシアティブを取り、もう1人はフォローに回る体制の方が、子どもは勉強に集中できる。
子どもの教育に関しては、お母さんがイニシアティブを取る方がうまくいく可能性が高い。
一般的に子供と接している時間が長いお母さんの方が、子どもの性格や気持ちを正確に把握しているし、母性の関係性の強さを考えれば、母親に分がある。
12.
子どもの情報は夫婦で共有しつつも、お父さんは勉強のことには直接口を出さない。
でも塾の送迎はお父さんがやる。休みの日には一緒にスポーツをする。
それくらいの関わり方がベスト。
13.
小さい頃に積ませておきたいのは、「続けられる」という成功体験。
子どもが小学一年生の頃から、タイプの違う計算ドリルを5冊用意していた。
そして、そこから自分の好きなものを選んで毎日5分取り組む、と言うテーマを与えた。
また、子どもは単調さを1番嫌うから、1冊の問題集でも、好きなページからやって良いというルールを設定するだけで継続させやすくなる。
内容よりも、とにかく継続させることが大事。
14.
モチベーションの維持に必要なのは、「自分で決める」という段取りを確実に踏ませること。
「集中力」を鍛えるには、1時間の勉強を不定期にやるよりも、5分の勉強を毎日続けること。
時間が短くても、100%の集中力で取り組ませること。
15.
子どものテストの点数は、難しい問題ばかりやらせても良くならない。
簡単な問題を繰り返し解くことで、高い処理能力を身につけさせれば、難しい問題も少しずつ解けるようになる。
解ける応用問題のバリエーションを増やすよりわどんな問題にも対応できる基礎力をつけることの方が大事。
16.
どんなことであれ、夢中になった経験が乏しいと勉強の集中力も弱くなる。
だから、子どもの学力を伸ばしたいなら、勉強以外の何かに夢中になるような経験を意識的に積ませる必要がある。
集中する感覚を掴む。
17.
リビングを勉強の場にする。
孤独と無縁にする。
理想的なのは、お父さんは読書、お母さんは家計簿というように、同じリビングのテーブルで、それぞれが別の作業に集中している状態。
これは、集中ひている人の邪魔をしないというマナーを学ばせるのに良い方法。
また、親の時間は全て自分のためのものという甘えを断ち切らせるにも有効。
親が仕事をする姿は、子どものやる気を刺激する。
18.
どんな叱り方をするか。
それは、徹底的に戦うこと。
戦うとは、力で抑えるのではなく、徹底的に子どもと向き合うこと。
子どもと戦うために必要なこと、それは子どもにきちんと言い訳をさせること。
子どもが十分納得していないうちは、戦いをやめてはいけない。
何時間かかろうと議論して、納得させて終わることが大事。
19.
失敗の原因が能力不足なのか、努力不足なのか。
単純なミスは注意すれば防げたものだから努力不足。
それは厳しく叱らないといけない。
仕方ないことでは叱られない、でも努力しなかったら叱られるというルールを親子で持つ。
20.
1日のうちはやるべきことをホワイトボードに書き出し、やったものから消していく、という方法を子どもに提案。
それぞれの課題は5-10分程度で終わるもので、それをいつやるかは本人の自由。
21.
東大生が育つ家の最大の特徴は「仕掛け」。
家中のあらゆる場所に、勉強につながるものがさりげなく置かれている。
テレビのそばに世界地図や地球儀、ソファのそばにタブレット。
同じ参考書を2冊用意して、1冊は本棚に、残りの1冊は家の中の別の場所に置いておく。
トイレに薄い問題集と鉛筆をセットしておく。
壁に漢字の一覧表を貼る。
お風呂に日本地図を貼る。
自然と視界に入ってくる、手を伸ばせばすぐそこにある、という環境を作る。
Posted by ブクログ
自分の親がやってくれていたことが多数あったので、両親もこういう本を読んでくれたのかと思った。東大生にはなれてないけど、そこそこ健康でぼちぼち頑張ってるからいいってことで(笑)
Posted by ブクログ
【東大にはそんなに興味なくてもいい。
何かでグンと「伸びる」子になってほしい、小学生の親に】
「この子は伸びるな」という子の親はどのように子どもの基礎人間力を高めているのか。
本のタイトルはキャッチーだが、ガリ勉の話ではない。自己肯定感や、小さな自信、モチベーションを高めてあげられる声かけ・環境作りの具体例がわかりやすく紹介されている。
例:
・伸びる子は、自分で決めることができる。「どっちでもいいー」とばかり言わない。
←自分で決めるトレーニングを普段から行っている。月に一度、旅費から行程まで子どもに週末プランを任せる日を作るなど。
・伸びる子は、「もうちょっとやればできる」と思える。
←自分の少し上のレベルに挑戦して乗り越える経験を積んでいる。
Posted by ブクログ
東大に入れようという野心みたいなものはないのですが「自分で何かを決断させる力」を子どもに身につかせてあげたいと考えている方は一度読んでおいて損はないかと思いました。
Posted by ブクログ
読んで実行しよう思ったことのメモです。
自立が大切だなーと思いました。
・何事も自分で決めさせる
・できるだけ自分のことは自分で
・子供が欲しい本はできるだけ買う
・準備と片付けも参加させる
・家でダラダラできる時間をつくる
Posted by ブクログ
無理せずに取り組めることや、親の姿勢を学べた。
東大いかせずとも参考になる本だとおもう。
5分でもいいから勉強させる。
苦手なことはカバーさせる方向にシフトチェンジして、直させない(忘れ物が多いならいっそまるごとキャリーバッグで持ち運び)等
目次だけでも参考になることが多かった。
子どもが、受験する場合はこの著者の別な本も参考にしたいと思った。(男の子 女の子別のは、勉強に特化してる内容だった)
Posted by ブクログ
主体性を持つ子供、自分の意思で決断を出来る子供。そういう子になるために親がどう接するか。ヒントが書かれている。
ここの項目は納得できるが、読む側の注意は満点を目指そうとしないこと。ここに書かれている事を全部できる人はいないはず。出来ること、納得できることを一つずつやっていくのがいいと思う。
Posted by ブクログ
Unlimitedで読みました。
進学塾の方が著者なので実際の子供の例が多く納得するところが多かったです。以下は特に意識したいなと。
子供に決めさせる(決めたことは責任を持つ)
自分のことは自分でやらせる
集中する経験をさせる
納得しないと気持ち悪いように親子で言い争う
85点とったら90点目指せるじゃないとリード
Posted by ブクログ
あまり周りの人の子供への教育の向き合い方を見たり聞いたりする事はないので参考になった。子供によって効果のある接し方はそれぞれだと思うが、子供が勉強に興味を持って継続してもらうための接し方のヒントが記載されていたと思う。
Posted by ブクログ
子供との意思疎通の仕方ももちろん書いてあるが、親として子供を伸ばすためのスタンスが、毎回丁寧に書いてあるのか良かった。
私の子供はまだ2歳ではあるものの、偏差値的な考え方で他の子と比べるよりも、子供自身の変化、成長を見落とさない。
子供の好き嫌い、を見ながらいかに伸びる仕掛け作りが出来るかは、親の腕の見せ所だと感じた。
将来の子育てが、楽しみになりました。
努力は順位や偏差値に反映されるものではない。
努力が反映されるところに着目すること。
ゴールに辿り着くには子供数だけやり方がある。
こういった考え方は、自分の仕事にも活きてくるなと強く感じました。
Posted by ブクログ
東大生になることではなく自分で努力して挑戦してそれが受験であったり東大合格であったりするだけで、自分で努力して挑戦することができる子供にするためにどういう工夫ができるかということが書かれている本だと思う。
うちの愚息はまだ三歳なので参考にはできないがためにはなった。
Posted by ブクログ
読みやすく育児全般に使えるアイディアが載っていた。月1で休日のプランを子どもに決めさせるのは良さそう。子どもがもう少し大きくなったらまた読みたい。
Posted by ブクログ
題名には東大という文字が入っているが東大に限らず勉強に対する心意気が学べた。教育について考えさせられた。「負けず嫌いにする」「勝負する子に育てる」のは大人になって社会に出ても大事なことだと思う。
Posted by ブクログ
テストテストで忙しい子どもですが、その結果に一喜一憂してはいけないのだなということが良く分かった。
60点取ったら、取れなかった40点を考えるのではなく、次どうしたら70点取れるか考えるとか、偏差値や順位は相対的なものなので、気にしないとか。あくまでライバルは子ども自身。勉強の課題は子ども自身が解決すべき。色々参考になった。子どもとの関わり方を変えていきたい。
Posted by ブクログ
伸びる子供を育てる親は、子供とちゃんと向き合って勝負したり、話し合ったり、議論したりして子供の気持ちを置き去りにしない。また、東大に入ることが目的ではなく、受験というものを通して、自身を成長させる環境を作ることが大事
Posted by ブクログ
参考になる考え方がいくつもあった。
ベースは、自発的で自己肯定感が強い子に育つように、子供の人生と人格を尊重し、日々「決めさせる」ことが大事ということ。
各論として、以下の内容が参考になった。
●子が失敗に落ちこむ時には「今経験できて良かった」と前を向かせ、子が成功して有頂天の時には次の挑戦を示して良い意味で水を差す
●本当に大事なことを叱るときには、第三者を交えることで重要性をわからせることが有効
●子どもに自覚が十分になさそうな時には、理詰めよりもたっぷりの愛情を前提とした感情的な叱り方もアリ
●60%のことを100%理解するのが大事。
Posted by ブクログ
東大生、すなわち更なる高みを目指し、自分で選択した目標に向かって進める人の家庭はどんな傾向があるのか書いた本。親が手取り足取り子供をサポートするのでなく、人生を子と親で切り分けることも大事である。子供の言い訳は面倒だけど、戦うことで子供が納得し、今後の何故を追求できる子供になることが勉強になった。
Posted by ブクログ
勉強時間は一度にまとめて2時間取ろうとするのではなく、細切れであってもトータルで2時間、という風に時間を見つけるというやり方は参考にしたいと思った。
Posted by ブクログ
キャッチーなタイトルに惹かれて読んでみた。
なるほど、と納得できることが多かったように思う。
東大かそうじやないに関わらず、良い子育てだなと思った。すべてを実践できるわけではないけど、できるだけ取り入れてみたいな。
こどもの褒め方について、褒めたほうが良いというのが一般的で、自分もできるたけそうしてきたのだけど、褒め方にコツというか、何でもかんでも褒めるのは違うらしい。本書以外でもそういった記事を多数読んできたのだけど、なかなか自分でも線引きが分からず褒め下手な親だと実感はしてる。
今回改めてこの本を読んでみて、目的を意識するのが大切なのかなと思った。
小さい頃褒めるのは自己肯定感を持って欲しいから。でもできて当然のことを褒めても自己肯定感にはつながらない。それよりもできなくて悔しい気持ちに寄り添ったり、ひとつ上の段階を一緒に目差したり。。。ということを意識すればよいのかな!?と。
これってもしかしたらいたって普通のことのんだろうけど、数ある育児書の字面の上辺でしか理解してなかった私には貴重な気づきだった。
以下、読書メモ
・子どもの満足度に合わせて褒める
・得意なことを徹底的に伸ばす
そのためには現状把握(何が得意で何が苦手か)が大切
自信がつけば、他の教科も自然についてくる
・日常生活に勝負をたくさん取り入れる(負けず嫌い)
・負ける悔しさを経験させる
くやしさをしっかり受け止めさせる
・自分でできることは自分でやらせる(自立心)
・食事の準備をさせる(てきれば料理も)
・読む本は自分で選ばせる
・休日のプランを子どもに決めさせる
決められた予算内ならどこでも行ける日を月に1回
予算を抑える工夫、交渉力、情報収集、比較検討
自分の意思で決定するというトレーニング
・テレビやマンガはユメの宝庫
将来のビジョンを明確にイメージできる(リアル)
・子どもの人生は子どもが主役
・感情をうまく切り替える(感情のコントロール)
親は、小学校高学年くらいまでに、うまく切り替えられる方法を試行錯誤してみつけておく(言葉でないケースや、親以外の言葉というケースも)
・ハングリー精神(褒めすぎない)
・小学生のうちにひとり旅をさせる
自分の限界を超えられたという経験
・勉強を100%理解させようとしない
6割目安、積み残しがあってもオッケー
・短所を直すのではなくうまく付き合っていく
まずは短所と長所の把握、認識が必要
・こどもの教育は母親主導がうまくいくケースが多い
・ライバルは自分自身(他人、順位、偏差値を気にしない)
努力が反映される数値に注目(点数など)
・続けられるという成功体験を与える(ツライものはさせない。続けやすいものを選択)
・本物に触れさせる
夢に対するモチベーションが下がる中学生時代にも効果的
・何事も自分で決めさせる
自分の意思がなければ続かない
自分で選んたことに責任を負う
・たとえ時間が短くても100%の集中力で取り組ませる
5分でもオッケー
・スピードと基本を大事にする
処理能力が求められる問題も多い
・休みの日はダラダラもオッケー
伸びる子ほど休みが必要
メリハリが大切
・習い事のしすぎは注意
週に1日は完全休業日を入れ、シンプルに
ポジティブにダラダラしてもらう
・勉強以外の何かに夢中になる経験
ゲームでもオッケー
集中力を高める
・リビング学習が効果的(おもちゃがない環境、孤独じゃない)
親も読書や仕事など
勉強中は時計を見せない(終了時刻までのカウントダウン防止)
・言い訳をさせる(論理思考)
子どもも納得することが大切
・能力不足か努力不足かを見極めて、適切に叱ったり、一緒に悩む(次にどう活かすのか)
・ときには感情的に叱っても良い
でもしかりっぱなしにしない(スキンシップなど)
・人として野間違いは徹底的に叱る
・10分のスキマ時間を大事にする
トータルで○○時間と考える
集中できる
心理的ハードルが下がる
・家の中にたくさんの仕掛けを作る
世界地図、地球儀、タブレット、漢字表、日本地図、四字熟語、年表
必ず手にするものに細工する(冷蔵庫、お風呂、ボール、ソファ)
・成績の上下に一喜一憂しない
・模試の復習はさせない
やり直しグセがつく(本番とと同じ気持ちで)
解けなくて良い問題もある
・受験で大事なのは合格することでなく園経験を通じて何が得られたか
・こどもの意思を尊重、親のエゴを押し付けない
Posted by ブクログ
34の習慣が書かれており、オーソドックスなものから、いいかもと思えるものまで様々。東大というブランドにこだわらなくても使えるノウハウも多数。
能力不足か努力不足か、単純なミスをするのは努力不足。厳しく叱ることと書かれている。努力不足は叱られるに値するのだそうだ。これはなるほどと感じた。勉強中は時計を見せない。「手が勝手に動く」ほどの集中力をつける、などなど。
しかし、週に1日はゲームを飽きるまでやれる日を作って集中力をあげるトレーニングをする。これは中程度の子には実はとても危険な発想であることを私は知っている。ゲームの集中力を勉強の集中力に変化できるほど甘くはないのが、中程度の人間。
Posted by ブクログ
タイトルに惹かれて読んでみましたが・・・
実際に東大に合格した子を育てた親の共通点。うーん。といった感じ。
実は我が家にも東大生がおり、高校や中学受験塾時代の同級(塾)生にも東大生はゴロゴロ。当然、親の知り合いも多いですが、当てはまるかといえば、そうでもない。
子育てでたしかに大事なことではあるけれど、東大に限らないのではないかと思いました。
Posted by ブクログ
東大生全般、というよりは東大にも受かってしまうし人間として何か魅力のある人、を育てる家庭の話である。たとえ東大に入れることを主眼にしていない人が子育て本として読んだとしても、本の根底に流れる主張は「魅力的な子供は魅力的な人から育つ」と言っているようで、自分が魅力的な人間でないとわかっている者にはなんとも耳の痛い内容だった。そこで捻くれず、せめて模倣できるように頑張流べきなのだろうが。
Posted by ブクログ
3歳でまだ親の膝に座って食事をする我が子に危機感を覚えてふと手にしてみたら、自立心をどう育てるか、ということに対する提案が非常に参考になった。乳幼児向けの育児本にも共通して書かれていることではなるが、甘えと厳しさが同居していることが大事。叱ってばかりの育児は最低だけれども、甘やかしてばかりの育児も問題がある。甘えを最大限に受け入れ、許し、その中で「こうやろうね」と指導していく、もうそれが鉄則でしかない。
保育園や幼稚園、学校ではできていて、家庭でできていないのであれば、それは本当の自立ではない。
子どもをどう育てるか、何を目標に子育てをしていくか、試案しているところで、ちょっとした輪郭を創るきっかけになった。
・好きなことや熱中できることを見つけて、それを職業にできるような道を見つける。
・他人の人生を生きるのではなく、自分の人生を生きてもらいたい、だから褒められたり、叱られたり、強制されたり、賞賛されるから何かをやるのではなく、自らの想いで「自分がやりたいからやる」ということをベースに生きていってもらいたい。