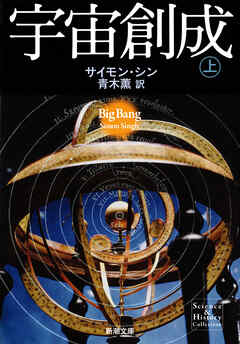感情タグBEST3
Posted by ブクログ
今まで読んだ理科の本には書かれていない、ビックバンや星が何でできているのか、など歴史とともにその理由が書かれていて、、わかりやすく理解&納得できました。
行ったこともない星の成分がわかるのはなぜ?
宇宙の始まり
膨張し続ける
など
面白い
Posted by ブクログ
フェルマーの最終定理が非常に面白かったので、同じ著者のこちらも購入。
相変わらずの難解な内容を分かりやすく伝える文章力と、謎が解明されていくプロセスをドラマティックに描き出す演出に感心させながら一気に読ませてくれた。
上巻は紀元前の古代ギリシャの哲学者が宇宙という天上世界の解明に足を踏み入れたところから始まり、コペルニクス、ガリレオによる地動説、アインシュタインの相対性理論、ハッブルによる赤方偏移による宇宙膨張の観測までが描かれる。
ここに至るまでも様々な議論や、長年真とされている価値観を変えたくない保守層の妨害を経た上で、実験、理論、観測等による検証を繰り返しながら、今当たり前とされている宇宙の現象が事実として確立されてきた紆余曲折の歴史がある。
未知の領域が少しずつ時を経て解決されていく過程と、それに挑もうとする人間たちのドラマは本当に目頭が熱くなった。このカタルシスを是非体験してほしい。
下巻からはビッグ・バン宇宙派と定常宇宙派の議論が白熱する。
Posted by ブクログ
ようやく読み終わった「宇宙創成」。なかなかのボリュームで内容もかなり難しい部分もあったが非常に質の高い作品で面白かった。
宇宙に関する人類の考察の歴史がよく分かり、今までは何となく言葉だけ知っていたビッグバンについてより正しく理解することが出来た。これ1冊読めば現代の宇宙物理学まで全部理解できるという優れもの。
それにしても「フェルマーの最終定理」といい、難しい学問を素人にも分かり易く表現できるサイモン・シンの力量には感服するばかり。
Posted by ブクログ
宇宙の性質や構造の仕組みを解き明かすドキュメンタリー番組を見ているようだった。個人的に面白いと感じたのはその時代の風潮が科学の発展に大きく影響することである。
本書では、アインシュタインとニュートン宇宙理論のストーリーがそれに当てはまる。年齢を重ねた人がいなくなると、古い理論を支持する人が減り、新たな理論が相対的に受け入れられやすくなるのである。古い理論を簡単に捨て去ることができないのは、新しい理論が正しい場合、古い理論を用いた実験結果は全て使えなくなってしまうからである。しかし、それ以上にその人が築き上げてきた結果とプライドによるところが大きいと思う。
上巻では宇宙の起源を発見するまでをたどっている。プトレマイオスモデルを覆すコペルニクス、地動説を復活させるガリレオ・ガリレイ、光の特性を明らかにしたアインシュタイン、ビックバン理論提唱の材料をそろえたエドウィン・ハップル。どれかが無くても今日の宇宙理論が成り立たなかったのだと考えるととても感慨深いものがある。
Posted by ブクログ
地動説の正しさを主張したコペルニクスやガリレオにしても、より正確な重力理論を提唱したアインシュタインにしても、一番の敵は科学それ自身ではなく、宗教や有力な科学者など、その時代の権威であったことがよく分かる。だからこそ科学にドラマが生まれたのだ。
Posted by ブクログ
ギリシャ神話から始まり、アインシュタインの特殊相対性理論ができあがるまで、科学者の関わりやそれまで常識と思われていたことに対する理論を作り、実験にて証拠を揃え、確立していく流れが描かれている。一般性相対理論が発表され、もっと微小な世界に目を向けていく流れが少し書かれ、下巻に続く。
科学者の名前を覚えるにはちょうど良い。理論そのものの説明があるわけではない。
Posted by ブクログ
科学史の本はいくつか読んだけれど、これが1番面白い。あまりに面白くて読んでいる最中に立ち上がってしまった。
古代ギリシャ時代から、ビッグバンモデルの完成した現代まで、宇宙の研究を追う。
我々が存在するこの宇宙がどうなっているのか、それを知りたくて、人類は寒空のもと望遠鏡を覗き、よりよい設備のための金策に奔走し、ときには隊を組んで観測遠征に赴く。
ただ宇宙研究発展の歴史を綴るのではなく、探究心に突き動かされた人間の営みにスポットを当てる。観測中のハーシェルを支えた妹(彼女も優れた天文学者)や計算部隊として活躍した家政婦(後に博士号を得る)、専門の写真家など、本題を追うだけなら省略してもいいような貢献者もしっかり取り上げられているのがいい。ノーベル賞を受賞するような人だけで成果を出せるものではない。
また、誰が何の研究をして、何が分かって、人類の知はどう進んだか、というのが全くの素人にも分かるように書かれている。サイモン・シンの解説は分かりやすいうえ、本書には章のまとめや用語集もあって、読後は少し賢くなった気がした。
Posted by ブクログ
「天才科学者達のバトル集」
天動説vs地動説
ニュートンvsアインシュタイン
静的宇宙vs動的宇宙
など、新しい説が古い説を打ち砕いていくストーリー的な面白さもあるし、
理論、実験、背景のエピソードなど、しっかり解説されているのに読みやすい。サイモンシンさん凄すぎるとしか言いようがない。
Posted by ブクログ
上巻の最後で鳥肌が立った。本書はまさに人類の夢と苦闘を描き出した大傑作である。中盤では、アルベルト・アインシュタイン氏が輝きを放ち、終盤はエドウィン・ハッブル氏が自身を開花させ、ビッグバンが仮説ではない証拠を見つけ出す。要所要所に計算式が出てくるが、親切に要訳してくれており、計算式のすべてを理解しなくても十分楽しめる。寝る前に宇宙の彼方を想像しては、ワクワクし過ぎて寝付けなかった。
以下、本書よりお気に入りの箇所を抜粋。
「『オッカムの剃刀』は、2つの競合する理論があるならば、よりシンプルなもののほうが正しい可能性が高いというものである」
「聖書は天国への行き方を教えるものであって、天の仕組みを教えるものではありません」ガリレオ
「理論の良し悪しを判定するとき、私はこう自問します。もしも私が神だったなら、世界をこんなふうに作るだろうかと」アインシュタイン
Posted by ブクログ
既に海外ノンフィクション部門のゴールデンコンビとなっているサイモン・シンと青木薫のタッグは宇宙論という分野にも確かな爪痕を残しました。
うまい安い早いが吉牛なら、うまい、わかりやすい、ためになるがこのコンビの特徴です。
サイモン・シンの展開する科学的な知見をスムーズに理解するには、読んでいてストレスを感じさせない日本語訳があってこそです。
その内容は、科学者や天文学者、さらには物理学者や数学者などを総動員した知の格闘による新たな発見のアウフヘーベン(ある解釈を否定して、さらに高みを目指す思考方法)の蓄積の歴史です。
そして天文学とは我々の存在理由をも決定するという科学的な哲学だということがよくわかります。
我々もよく知る偉人の名前と業績が手際よく紹介され、その後の新たな事実によって否定され、より真実に近づいていくプロセスは簡にして要を得る見事な筆さばきです。
現在では、本命とされるビッグバンモデルも、つい最近まで定常宇宙モデルと激しい主導権争いが繰り返されていたことやその論争の歴史の中で新たな発見があるたびに両者の客観的評価をまとめた表を都度掲載することで、難解な理論の変遷をわかりやすくしています。
「ビッグバンから1秒の内に超高温だった宇宙は膨張して劇的に冷え、温度は数兆度から数十億度まで下がった。その頃の宇宙は、主として陽子と中性子と電子からなり、すべては光の海に浸されていた。それから数分の内に、陽子は他の粒子と反応して、ヘリウムなどの軽い原子核を形成した。この最初の数分間で、宇宙に存在する水素とヘリウムの比率はほぼ決定され、その値は今日観測されるものとよく一致している。宇宙はその後も膨張して冷え続けた。このころの宇宙には、簡単な原子核とエネルギッシュに飛び回る電子と、膨大な光が存在しそれらが互いにぶつかり合って跳ね飛ばされていた。そして、およそ30万年が経過したとき、温度が十分に下がり電子の速度が落ちて原子核につかまり原子が形成された。この時以降光はほぼ何にも邪魔されずに宇宙をまっすぐ進めるようになった。こうして生じた自由な光こそ宇宙マイクロ波背景放射で、これは光によるビッグバンのこだまなのだ」(P298下巻)
さて、ここでビッグバンモデルと旧約聖書の出だしとの類似性に気づきます。
創世記曰く、初めに、神は天地を創造された。地は混とんであって、闇が深淵の面にあり、神の魂が水の面を動いていた。神は言われた、光あれ、こうして光があった。・・
聖書では神は7日間ですべてを創造したわけですが、ビッグバンモデルでは最初の1秒と数分で宇宙の原型ができたという大きな時間的な差異はありますが、秒や分という概念がない時代を考慮すればむしろ光が主役だという点に注目すべきでしょう。
もちろん、本書でも教会と科学との対立と受容の歴史にも触れています。
宇宙はどのように始まったのか?という真相に近づくにつれ、では我々が住む地球が生命体にとってかくも理想な形で成り立っているのはがなぜだろうという次の疑問が湧いてくるのは当然です。
そして、マーティン・ルースは6つの数値(重力、核力、宇宙密度、反重力、重力と静止エネルギー比、次元数)が宇宙の形を決定しており、6つの中の1つでも今と違った数値だったなら、宇宙の進化自体に深刻な影響がでていたという理由で人間中心原理に行きついたのも興味深い。(P316下巻)
最後に、訳者の青木薫は2006年に単行本のあとがきで、「本書は宇宙のことをよく知らない読者のために書かれた」と記し、内容は専門的だがわかりやすい点を強調していましたが、2008年の文庫本のあとがきでは「宇宙論についての最新の知見を紹介することよりも、科学的方法の喜びを味わってほしいために書かれた本」という言い直しをしていますが、まさに詰め込みの学校教育では味わえないアカデミックな知的興奮を味わえる1冊となっています。
やはり、宇宙には深遠な魅力、いや魔力があるようです。
Posted by ブクログ
本書では、宇宙創成の謎に挑戦してきた人類史、科学史にスポットを当てる。古代ギリシャに始まった天文学。地球、月、太陽の大きさや距離を推定した古代天文学者に始まり、暗黒の中世での停滞を乗り越え、天動説を覆したコペルニクス、ガリレオ。初期地動説が生み出す誤差を解消する理論を打ち出したケプラー。ニュートン力学を超え、相対性理論を生み出したアインシュタイン。彼の生涯2つの誤りの一つである静的宇宙モデルを覆したビッグバン宇宙モデルの設立まで、事細かに解説する。 さすがサイモン・シンと思わせる見事な描写は、読むものを引き付けて離さない。本書で書かれていることは、すべて良く知られた事実であるにもかかわらず、それを一同に系統立てて説明する手法は流れるような心地よいリズムを生み出し、一気に読まずには入られない。すばらしい。
Posted by ブクログ
理論と観測の双方で対立したり補完したりしながら進んできた宇宙論の歴史が非常にわかりやすい。
20世紀に入り、一般相対性理論が発表されている時代でもアンドロメダが銀河系の外にあるとわかっておらず、そんなギャップがあったことに驚きつつも面白いと思った。逆にこの時代の宇宙論の目まぐるしい進化を感じてみたかった。
下巻も楽しみ。
Posted by ブクログ
ギリシャ時代の宇宙認識から膨張する宇宙を示唆するハッブルが提出した観測結果まで。各時代で人々がどのように宇宙に対する認識を深めていったのかを追体験できる。非常に骨太で面白い。
実験と理論が如何にお互いを補いつつ科学の世界を広げていったのかを感じ取れる良書。
単なる事実の羅列でなく、著者の科学に対する深い理解も垣間見れる。
Posted by ブクログ
「宇宙はいつ、どのように始まったのか」。
かつて神話で説明されていたその謎に対して、現代科学は観測結果で裏付けされた理論を手にしている。
アルベルト・アインシュタインの「宇宙についてもっとも理解しがたいのは、宇宙が理解可能だということだ」という言葉のとおり、宇宙に比べて極めて小さく、歴史も浅い人類が、その謎を解き明かそうとしているその事実に改めて畏敬の念を感じる。
『ビッグバンモデル』は誰か一人の発明なのではなく、モデル構築、観測、実験、理論計算に貢献した多くの人々の、人類の叡智の結晶なのだということが分かった。
Posted by ブクログ
現代において「地球は宇宙の中心に存在する」と言おうものなら変な宗教でもやってんのかと心配されるが、宇宙の中心でないことを証明できる人は、一体どれだけいるだろうか。
夜空に浮かぶ星に辿り着こうとするなら「光の速さで何年もかかる」ということに疑いを持つ人は少ないが、それを証明できないなら、それは星が遠くにあることを「知っている」でも「わかっている」でもなく、ただそう「信じている」だけだ。
アンドロメダが星雲でなく、90万光年よりも遠くに存在する別の銀河であることが「わかる」までに、どれだけの研鑽が必要だったのか。天文学の軌跡は科学のそれと同じく、予測と観測の共進化であった。
人類は『光る点の動きを追い続ける』ことしか出来ない単純な観測方法を複雑に積み重ね、コペルニクスの地動説はケプラーの方程式とティコの膨大な観測データにより天動説を打ち破り、アインシュタインの相対性理論はエディントンの観測隊によりニュートンの重力理論を飛び越え、膨張宇宙論はハッブルの観測によりアインシュタインの静的宇宙観を破り、ついに星々は距離に比例する速度で遠ざかっていることまで証明された。
こうして星の全てが遠ざかっていることがわかったとき、一つの疑問に辿り着く。『全てが遠ざかり始める前の一地点では、一体何が起こったのか?』宇宙創世の真実への道のりは、下巻に続く。
Posted by ブクログ
フェルマーの最終定理に引き続き、サイモン・シンの宇宙創成読んだ。
世界は神が創られたと神話が信じられていた時代から、いかにして世界の真理を知り、ビッグバンの存在を突き止めるに至るかが紀元前の歴史から順を追って記されている。
下巻よりも上巻が面白い。特に天動説から地動説にパラダイムシフトが起きる時代の論争と、アインシュタインの登場とともに特殊、一般相対性理論が構築されてからの世界の変わり様と言ったら、めちゃくちゃシビれるドラマが味わえる。
■メモ
Ⅰ:神話の時代
①自然現象の始まりは紀元前6世紀のζの哲学者達
・実験、観測、論理、理論、数学によって地球、太陽、月の大きさと距離を図ることに成功→天動説の確立
・地球中心モデルでは不十分、プトレマイオスの周転円による惑星の逆光運動
②16世紀、太陽中心モデルが勃興
・コペルニクスが太陽中心モデルを構築
→宗教上の主流派による抑圧
・ケプラーにより円軌道が楕円軌道に修正
・ガリレオが木星衛星、太陽黒点、金星満ち欠けを発見
Ⅱ:宇宙の理論
①光の早さ
・レーマーにより光の速度が有限であることが発見された
・光の速度の有限性を説明するためにエーテル理論が勃興
・実験と観測によりエーテルの存在は否定された、その後、アインシュタインが特殊相対性理論を構築(1905年)空間と時間(時空)はともに伸び縮みし、光の速度は観測者に対して一定であることを主張
②重力
・その10年後に一般相対性理論が構築、ニュートンを超える正しい重力理論が打ち立てられた
・その結果、宇宙は収縮するという問題に対して、宇宙定数という間違った概念を持ち出し静的で永遠な宇宙という誤ったモデルを構築した
・フリードマンとルメートルは動的な宇宙を志向、膨張する宇宙を考えた
Ⅲ:大論争
①観測の進化
・1700年代に天の川銀河が発見された、銀河は天の川しか無いのか?
・1912年にヘンリエッタリーヴィットがケフェウス型変光星を発見、宇宙を測定するものさしを手に入れた
・ハッブルが遥か彼方の銀河を観測し、銀河は無数にあることが示された
②ビッグバンへの足がかり
・ドップラー効果により赤方偏移、青方偏移が起きる、星の光を調べることで成分がわかる
・銀河は遠ざかっていることがわかった。常に膨張しているのだ。だとすれば始原はどうなっていた…?
Posted by ブクログ
宇宙とは人類にとって最大の未知ではないだろうか。 本書は天才アインシュタインと宇宙の関係であったりビッグバン理論など、宇宙解明のこれまでの一歩一歩が描かれている。 一歩一歩というよりも一進一退という方が正しいかもしれない。 これだけ科学技術が発達したにも関わらず、まだまだ謎に包まれている壮大な宇宙。 下巻がどう展開されるか楽しみ。
Posted by ブクログ
昔から少しは宇宙に興味があったのでとても面白かった。
全く何も分からないところから色々な壁や先入観などを乗り越えてだんだんと今わかっている宇宙に近づいていく感じでとても楽しかった。
また、よく知られている学者(コペルニクス、ニュートン、アインシュタイン、ハップルなど)が出てきて読むまでその人たちの名前しか知らなかったことが恥ずかしくなった。
しかしわかりやすいが1つずつ理解していかなければいけない本なので時間がかかって疲れた。
Posted by ブクログ
ビッグバン理論についての本。科学は間違うということが壮大なテーマとなっており,いつものサイモンシンのように人物が生き生きと描かれている。
科学的素養がなくても身近な比喩で説明を進めているのすごい。
Posted by ブクログ
フェルマーの最終定理同様、読者が自然と引き込まれるような構成になっている。電車の中で読んだが、2時間くらいあっという間に経ってしまった。サイエンス系の本だと、読んでいても何が書いてあるか分からず、飽きてしまうケースが少なくないのだが、サイモン・シンはそのあたりが本当に上手だ。難しい数式なども出てこないので、予備知識がほとんどない状態でも読み進めることができる。宇宙論は数学や物理学を用いて詳細に説明しようとすればいくらでもできると思うのだが、読み物として読まれることを意識しているのだろう。それでいて、分かりやすく宇宙に関する歴史の概略を理解することが出来る。面白い。
Posted by ブクログ
あまりの面白さに連続で読み続けているサイモン・シンによる宇宙の謎を巡るドキュメンタリー。
本書を読むまで、自身が宇宙に関して抱いていた興味は「なぜ、ブラックミュージックは宇宙へと接近するのか?Sun RaやFunkadelic/Parliament,etc」というもので、この点については野田努の労作『ブラックマシンミュージック ディスコ、ハウス、デトロイトテクノ』を読むことですっきりしたのだが、全く別の角度から(当たり前だが)、宇宙について知ることができた。
上巻では古代ギリシャの天文学から、コペルニクス、ケプラー、ガリレオらによる地動説の誕生、ニュートン~アインシュタインによる物理学と宇宙の関わり、そして様々な仮説が検証されたハッブルによる宇宙観測までがまとめられている。
本書全体の大きなテーマは翻訳者が丁寧にまとめているように、「科学が進化する/パラダイムが変わる際に、いかに仮説としての理論が構築され、その仮説を観測という行為で検証されていくか」という、科学的思考プロセスが壮大な時間軸で書かれている点にある。そして、アインシュタインのような偉大な存在でも誤りを犯すのであり、ひたすら理論仮説を観測(これを実験という言葉に置き換えても良い)により検証していくプロセスをどれだけ真摯に繰り返せるかが、科学の進化の大きなポイントであることを実感できる。そうした点で、教育的価値も高く、なおかつリーダビリティも高い一冊。
Posted by ブクログ
上巻では、紀元前6世紀ごろの中国、アイスランド、アフリカなどの宇宙に対する神話から始まり、コペルニクスやケプラー、ガリレオ、レーマー、アインシュタイン、ハッブル等々、宇宙の観測、数学、物理学に人生をささげた人たちがお互いの主張を補完しあいながら、宇宙が膨張していることを示しているところまで。
紀元前3世紀から19世紀前半までで、地動説から天動説、太陽の大きさや地球からの距離、惑星の軌道、光の速さや重力、波長、ドップラー効果などから、銀河の存在とそれらが遠ざかっていくことまでがわかったが、宇宙の起源についてがそのあとのテーマに。
下巻より上巻のほうが読みやすい感じではあります。本書の題名のビッグバンの解明への前段といった感じ。
Posted by ブクログ
『フェルマーの最終定理』、『暗号解読』と読んだけど今回は宇宙がテーマのサイモンシン、これまた非常に面白い。青木薫さんの訳がいいのもあって、洋書で比較的硬い内容にも関わらずすらすらと読める(好きなジャンルだからかも知れないが)。理系、というより宇宙とか自然科学好きならたまらない内容だと思う。上巻は古代の天動説から古典物理による地動説への変遷、楕円運動の解析、望遠鏡やら分光器やらによる赤方偏移の発見辺りまで。ちょいちょい相対論も出てきて、さてどうなる下巻。
今読んでも相当面白いけど、出来れば高校生くらいのときに読みたかった。。。
Posted by ブクログ
星の運行から宇宙の成り立ちまでを探る天文学者と物理学/数学者の科学史。
しかし天文学者の観察精度を得るための努力と忍耐には尊敬を通り越して呆れかえるばかり。
Posted by ブクログ
良いなぁ~宇宙って。神話の時代から、相対性理論、ビッグバン・・・どんどん発展してきた宇宙論。でもまだまだ謎だらけ。人間が知っている事なんて、ホントに限られた事だけなんだなぁ。
Posted by ブクログ
ローマ時代から天動説、そして現在のビッグバン理論まで、宇宙というものが数多くの研究者によって少しずつ解き明かされてきた歴史を知ることができる。このシリーズは好きです。
Posted by ブクログ
宇宙の平均密度を計算してみると、地球1000個分の体積にわずか1グラムというものだった。宇宙の大部分はからっぽの空間なのである。惑星、恒星、銀河などは例外的に多くの物質が集中しているところであって、極めて異例な場所ってことになる。
下記の話は『人類が知っていることすべての短い歴史(上) 』のレビュー
「原子のサイズを理解するために、原子の幅を1ミリと仮定してみる、そうすると一枚の紙の厚さがエンパアステートビルに相当する。その極めて極小の原子を大聖堂の大きさまで拡大してみる、すると原子核はハエほどの大きさにしかならないらしい」って同じこと言ってる気がする。
Posted by ブクログ
何度読んでも途中で寝てしまうこいつに再チャレンジ。長い長い話、いつになったらビッグバンにたどり着けるのか。
アリスタルコス太陽中心モデル、プトレマイオス地球中心モデル、コペルニクス太陽中心モデル回転について、ケプラー楕円、ガリレオ望遠鏡。レーマー光の速度は有限、エーテル、アインシュタイン相対性理論、宇宙定数、フリードマン・ルメートル膨張する宇宙。メシエ星雲、銀河、ハッブル、赤方偏移の観測。