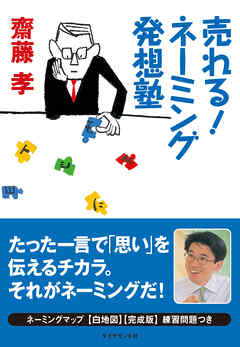感情タグBEST3
Posted by ブクログ
今まで読んだネーミングの本で一番いい。わかりやすい体系化と各分類の特徴(受けるターゲットなど)、自分で考えるときに使えるネーミングマップなど。
Posted by ブクログ
『声に出して読みたい日本語』で有名な斎藤孝先生のネーミングに関する本。これは面白いや。ネーミングは説明系とイメージ系に分類できる。それらを複数の型に落とし込むネーミングマップは秀逸。アイデアは思い付きではなく必然的に導くべき、ということで。
Posted by ブクログ
マーケティング関係者は必読。
商品づくり、ブランディングの観点ではネーミングってものすごい大事なのは誰しも認めるところなんだけど、これはタイトルのつけ方とかも同じことで、齋藤先生の観点で幾つかにジャンル分けしているこの本は極めてわかりやすい。まぁ、一部こういう分け方だと重複があるよね、という点もあるわけですが…
やっぱり小林製薬はすごい、という結論。
Posted by ブクログ
ネーミングという作業を、「穴埋め」作業に落としこんでくれる、素晴らしい発想。最近、人の共感を呼ぶネーミングやキャッチコピーの重要性に遅ればせながら気づき、久しぶりに読み返してみた。穴埋め用のネーミングマップにはとても価値がある、と思う。
Posted by ブクログ
何かのWebサービスを開発していた頃に買った本。サービスのネーミングって、とっても難しくて、まさにネーミングの発想法のテキストとして買ったことだけは覚えている。でも、内容は思い出せない。
Posted by ブクログ
齋藤孝は、整理し、その意味を体系づけると言う能力がすぐれているのだね。
編集能力がある。たくさんのネーミングを、腑分けすることができる。
だからといって、これが、役に立つかと言うと ふむ と思う。
商品の特徴を正確につかむことの方が重要だと思うが。
商品の特徴を絞り出すこと。小林製薬はそれがすぐれているのかな。
『ネーミング』だけにしぼってしまうところが、残念かな。
『練り上げる』『ネーミング作業のすすめかた』『ずらす』『つなげる』の
四つのポイントかな。たしかに、ネーミングマップはすぐれている。
このネーミング法は、結構手間がかかる。
ネーミングマップに、ひたすら書き込む作業をして、それから選ぶ。
大学の先生らしく、まったく 真面目なのである。
問題は、それを どう選ぶかという判断基準がまったくない。
これで、どうやって 『ゴリラの鼻くそ』がえらばれるのか?解明できない。
日本企業が 遊びがないのは、大学の先生の真面目さが災いしているのではなかろうか?
齋藤孝先生がネーミングして、『うれている』実績は あるのだろうか。
いや。私は 学者であって、そのようなことはしない というかな。
『座右のネーミング』って、うれるかな。
Posted by ブクログ
■概要
製品の名前を考えるプロセスについて書かれています。
製品名はやみくもに考えるのではなく、パターンごとに考えましょうというものです。
製品名は、「系」と「型」にカテゴライズできる。
その「系」×「型」ごとに考え、最もいいものを選択する。
という簡単なプロセスでも充分効果があると書かれています。
【系】
イメージ系(Fire/Boss) と 説明系(16茶/生茶)の2種類
【型】
擬人化型(ガリガリ君、タフマン)、ダジャレ型(イコカ、大清快)、外国語型(セフィーロ、とらばーゆ)などなど多数
■仕事に役立つ点
「系」「型」の考えは、サービス名や製品名を考える際の、1つの軸として活用できる。
製品の種類毎にネーミングの傾向があることが
わかったので、売れている類似品がどのようなネーミングなのかも気にしていきたい。
<あし>