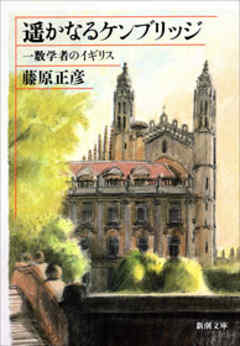感情タグBEST3
Posted by ブクログ
大学の推薦図書として高校3年生の時一度は手に取ったものの、ほとんど読み進めませんでした。
それから8年ほど経ったでしょうか、いつの間にか母親になった今、実家に帰った際ふと目に留まり、家に持ち帰りまた読み始めました。
すると、藤原節の面白いこと、面白いこと!
あっという間に完読してしまいました。
1980年代と少々前の話ですが、イギリスの歴史、地理、天候などから来ると思われるイギリス人の思考や行動が実に興味深くユーモラスに描かれています。
年代も国も職業も、自分の世界とかけ離れた人の生活を覗けるのは非常に貴重でありがたいですね(^^)
Posted by ブクログ
1209年創立。日本で言えば鎌倉時代。
そんな由緒正しきケンブリッジ大学に、文部省の長期在外研究員として我らが(⁉︎)藤原氏が乗り込んだ。
氏の著書はどれも(笑えるという意味でも)面白く、共感ポイントもすこぶる多い。しかしケンブリッジ滞在時の記録をしたためた本書だけがなかなか手に入らず、今回ようやく悲願達成に至った!
藤原氏が客員教授として初めに招致されたのがアメリカのコロラド州。その頃のエピソードの記憶が濃厚だったから、毛色の違う英国ライフは自分にとっても新鮮だった。
労働者階級やニュースで流れるイギリス英語に苦戦しつつも、大学で他の教授と互角に渡り合う氏に惚れ惚れ。英語力もしかり、あとは度胸に3年のアメリカ生活で培ったユーモアと、見習いたい点が山ほどあった。(イジメにあった次男くんに「何でやり返さない」と「藤原家伝来の戦法」を叩き込んだ点には感心出来なかったが…)
「数学者」と副題にあるので(頭を抱えたくなるような)数式や定理を連想するかもしれないが、他著同様心配ご無用。登場はするが軽く流せる程度だ。
それに教授方も人の子。各々の人生・家族・人間らしい悩みetc.が寄り集まり、さながら一つの文学作品だった。(本書自体もどちらかと言えば文学的要素が強い!) 彼らの教養の高さもグッと作品を味わい深いものにしており、それだけでも読む価値がある。
イギリス人をどこか特異な集団だと感知しながら上手く説明できずにいたが、謎を解く鍵の一つが彼らの、これまた特異なユーモアにあったと言うのが一番腑に落ちた。
George Wellsの『タイム・マシン』よろしく、今昔の作品を行き来してユーモアから探っていくのもアリだな。。今年と言わず、今からでも!
■フレーズメモ↓↓(氏の著書を読んだ際は何かしらメモってしまう…)
「戦争の真実を頭で知ること、そして心で感じることが、若者にとっていま最も重要なことと思います。人間が理性だけで、戦争を廃絶することは不可能なのですから」
…氏の英国ライフを助けてくれたブライアンのお父さんの証言。第二次大戦で独軍と闘った経験を語る中で出てきたものだが、心が大きく揺らいだ。
「人品というのは、洋の東西を問わず、一目瞭然である」
…ここでもまた共感ポイントを発見!思わずメモる。紳士淑女の集まりに出席した際さすがの氏も気後れしたみたいだが、「日本人だから何だ」とジョインしに行ったと聞いて思わず拍手を送った。(買い被り過ぎ?笑)
Posted by ブクログ
著者の1987年の1年のケンブリッジ大学での客員研究員としての生活を描いているが、1年とは思えないほど濃い内容でとても良かった。またイギリスやイギリス人についての説明が興味深く、イギリスやヨーロッパに対する理解が深まった。ただ自分のいったジョークが受けた、的な自慢めいた記載も多く少し鼻につく。メインは次男が学校でいじめられた時の父親としての心境、行動だろうが。このあたり、子供も心配だが仕事も重くてなかなかそこまで手が回らないなど同じ父として非常に共感するものがあった。
ルース・ローレンスという15歳で博士論文を書いている天才少女の話が出てきた。これに対して著者は、こうした天才児は時々報道されるがその後大成したとういう報道は一度も聞いたことがない、と否定的な感想を述べている。実際、このころから25年ほどたっているが、ルース・ローレンスさんはイスラエルの大学の准教授であり、それほど目立った業績を上げている様子はない。著者は数学ばかりやってきた彼女にたいし、野山を駆けまわったり、恋をしたり、文学や音楽に感動するなどといった経験を通して得られる情緒なくして良い研究ができるのだろうか、と心配する。このあたりも共感した。
Posted by ブクログ
イギリスに住んでいた人の目線から見た、風変わりなイギリス人のものの考え方や日本との文化の差についての言及が非常に多く、観光者としてではなく居住者としてその土地の人びとと関わらないと見えてこない外国の側面が描写されており、非常に興味深く読むことができた。特に第十二章でイギリス特有のユーモア感覚について書かれた箇所は一読の価値がある。イギリスの料理はおいしくないという話は所々で耳にするが、この本でもイギリス料理に関しては辛辣に評していて実際に確かめてみたくなった。
この本をより特徴づけているのは、なんといっても著者が数学者であるということだ。数学者という言葉にはどこか自分のいる世界とは違うところにいる人という印象を受けてしまうが、この本に登場する様々な数学者もまた人間であり、ジョークを飛ばしあったりそりが合わない相手もいたりと彼らの日常にも自分たちに近しいものがあると感じた。
基本的に面白おかしく、時に考えさせられるというエッセイとしてのみならず読み物としてとても優れていると思う。
Posted by ブクログ
私にはイギリス人が、何もかもを知ったうえで、美しい熟年を送ろうとしているように見えた。彼等は、年輪を重ねた自分達が、テニスチャンピオンになったり、マラソンで世界新記録を樹立することが、できないのを知っている。ならば、騒々しく、生き馬の目を抜くような、軽重浮薄で貪婪な若者であるより、気品あり、知恵もある熟年でありたい。それは繁栄、富、成功、勝利、栄光などの先に横たわる物を、既に見てしまった者の生き方だった。
それは丁度、ベルリンの壁が壊され、東欧諸国が次々に解放され、自由を得た歓喜に人々が酔い、涙を流すのを、茶の間のテレビで見たいた時の複雑な気分に似ている。暗いトンネルを抜け出た彼等は、きらめくような自由の光に眩んでいた。しかし我々は、このめくるめく光の向こうに理想郷がないことを、もう知っている。自由を標榜する各国で、自由の名の下でかつての道徳や情緒は低下し、社会や人心の荒廃がもたらされたのを、目の辺りにしてきた。
イギリス人は何もかも見てしまった人々である。かつて来た道を、また歩こうとは思わない。食物や衣料への出費は切り詰めているが、精神的余裕の中に、静かな喜びを見出している。不便な田舎の家の裏庭で、樹木や草花の小さな変化に大自然を感じ、屋根裏をひっかき回して探してきた、曾祖父の用いた家具に歴史を感じながら、自分を大切にした日々を送っている。もちろん悲しみや淋しさを胸一杯に抱えてはいるが、人前ではそれをユーモアで笑い飛ばす。シェイクスピアの「片目に喜び、片目に涙」である。
いかなる組織においても、最も重要な判断は人事である。人事さえうまく行き、有能な人間が集まれば、あとは自然に良い方向へ流れていく。人事を司る人間に必要なものは、何と言ってもすぐれた大局観と公平さである。この二つを兼ね備えた人間がいれば、その人に人事を一任するのが最もよい。民主主義とは多数決であるから、しばしば力関係が反映され過ぎ公平を欠くし、大局観も平均値的レベルにしかなり得ない。学内人事におけるすぐれた大局観とは、その学問分野全体を展望する広い視野と、これからの潮流を流行にとらわれずに見通す洞察力である。公平とは無私である。
この二つを兼ね備えた人間を探すのは、考えるほど容易でない。たとえいたとしても、民主主義花盛りの現今では、その人間に一任とはなりにくい。そこで通常は、学問的業績の高い人とか政治能力の高い人、人格の高い人、派閥の長などが民主的会議の場で実権を握ることになる。ところが、このような人が、上に述べた二つの資質を持っているとは限らないのである。学問的業績が高いということは、細分化された現在の学問では、それだけ自らの専門への傾斜が強かったということは意味しても、すぐれた大局観を必ずしも意味しない。人格や政治能力が学問的見識と無関係なのは言うまでもない。
日本の大学がうまく機能しない、最も重要な原因は、この学内民主主義にあると思う。世界中で最もうまく運営されている、と思われるアメリカの大学では、日本のような直接民主主義をとらず、間接民主主義をとっている、民主的選挙によって選ばれた学科主任、学部長、学長などが、権力を握るのである、例えば学科主任は、学科の人事はもちろん、給料の決定にまで、強い影響を及ばせる立場にある、主任の意志でほとんどのことが決まるだけに、主任の責任はそれだけ重くなる。日本の大学における長が、権力も責任もないのと、対照的である。
イギリスの大学は、どちらかと言うと日本の大学に似ている。近代民主主義を発明した国だけに、仕方ないのかもしれないが、それだけ大学の活性化は遅れているし、運営もうまく行ってない。
Posted by ブクログ
数学だけではなく、文化的な事柄にも通じている著者のことがよくわかった。
217ページ付近には、この本がバブルの頃に書かれたことが理解され、その頃のイギリスの状況が将来の日本であると予言し、かなり的中している。
Posted by ブクログ
イギリスもののエッセイに凝っていた時期に手に取った1冊で、とても大好きな作品。
大学教授ならではの視点でイギリス人やイギリス文化について触れており、一方で文は平易なので読みやすい。再読したい。
Posted by ブクログ
数学者である著者の、1980年代の英国ケンブリッジ滞在記。
藤原氏は、故新田次郎と『流れる星は生きている』の著者藤原ていの二男。
『若き数学者のアメリカ』で日本エッセイスト・クラブ賞(1978年)を受賞し、『国家の品格』は2006年の年間ベストセラー1位となっている。
米国滞在から10年以上を経て、今回は夫人と3人の子供と共に滞在した英国での波乱万丈の日々を、変わらぬバイタリティとユーモアで乗り切る姿が描かれている。
以後の作品でもしばしば登場することになる、夫人との掛け合いがまた楽しい。
(2007年10月了)
Posted by ブクログ
藤原正彦は、最近の発言にはちょっと気をつけるべき点があると思うが、この初期の頃の随筆は非常によい。解説で南木佳士が述べているように、この本と『若き数学者のアメリカ』は一級の随筆である。ただ、相変わらず愛国調は鼻につくけれど。
ケンブリッジ大学に派遣留学した経験が描かれている。イギリスという国とその人々の様子がなかなか生々しく、それが臨場感を与えている。イギリスは一筋縄ではいかないな、と思わせる。それが大英帝国の記憶を持つ国なのだろう。
古いものを大切にするお国柄であるが、これを読む限りでは、とても慕わしいものの、慣れない内はずいぶん不便だろうなぁ。特に冬の寒さやお風呂の貧弱さは辛そうだ。それでも、アメリカよりは落ち着きがありそうで、私は好きだ。
いつか暮らしてみたいと個人的に思う国はイギリスなのだが、その実情を教えてくれて、興味深い。よい本だ。
Posted by ブクログ
本の中で「ケンブリッジファイブ」のことをさりげなく触れているのですが、この部分を膨らませてほしかった。もちろん、話に聞いたこと、伝説として伝わっている事柄が多くなりそうですが、興味をもってその部分を読ませてもらいました。著者の文章の持つ磁力の強さ、上手さは言うまでもありません。
Posted by ブクログ
「一応ノーベル賞はもらっている」こんな学者が闊歩する伝統の学府ケンブリッジ。家族と共に始めた一年間の研究滞在は平穏無事・・・どころではない波乱万丈の日々だった。通じない英語、まずい食事、変人めいた教授陣とレイシズムの思わぬ噴出──だが、身を投げ出してイギリスと格闘するうちに見えてきたのは、奥深く美しい文化と人間の姿だった。
筆者のイギリスでの研究生活を題材にしたエッセイ集で、異国の地で暮らすことの大変さ、息子たちの学校でのいじめなど、様々な問題に体当たりでぶつかる筆者の姿に好感が持てた。
ただ一つ、息子のいじめに対する筆者の父親代からの考え方には、いささか疑問を感じざるを得ない部分もあった。そういう意味では、今どき珍しいくらい古風な考え方をする中年男性というふうにも見える。
Posted by ブクログ
お世話になった方が藤原正彦さんのファンだったことを思い出して手にとった本。
昼休みに少しずつ読んだが、読みやすく、あっという間に読んでしまった。
イギリスの文化や人々の生き方、アメリカや日本との根本的にある考え方の違いが、藤原さんの実体験を通して書かれていた。紳士の国、イギリス。いつか訪れて見たい。
Posted by ブクログ
アメリカ英語がペラペラの著者がイギリスに行った当初はイギリス英語にとまどった、という話を聞いてから、興味が引かれていた一冊。研究生活以外にも、オックスブリッジの人たちの考え方も垣間見れておもしろい☆
Posted by ブクログ
数学者の著者のケンブリッジ大学研修滞在記。
教授連は「ノーベル賞」くらいはもっている変わり者、厳しい階級社会、異国でクラス日本人たちは日本嫌いになるか極端な愛国者になるか…。
著者藤原正彦さんは、新田次郎氏と藤原ていさんの次男。
作者近影が新田次郎さんによっく似ている!!
藤原ていさんが「夫がシベリアへ連れ去られ、満州から三人の子供を背負って必死で帰った」時の次男なんですよね。
近年では「国家の品格」ですっかりお堅い学者のイメージですが、ご本人の著書や新田氏のエッセイではお茶目な次男坊の貌が感じられます。
Posted by ブクログ
国家の品格で有名になった藤原正彦さんのエッセイ。ケンブリッジ大学に留学し、必死で数学に打ち込む生活をしながら、父親として夫として奮闘する著者の姿は、読んでいて何とも言えない共感を呼びます。日本とは違うカレッジ制度を取るイギリスの大学教育(スーバーヴィジョン)は、非常に興味深いですし、著者と奥さんの漫才のような掛け合いも、軽妙で楽しいです。日本人にとって、何かと神秘的な雰囲気を持つイギリスを等身大で味わいたい人には絶好の本でしょう。
Posted by ブクログ
藤原正彦先生の家族同伴イギリス留学記。先生はけっして右翼ではないのだが、海外生活をすると必ず右翼的な感覚を体現してしまう自分がいるらしい。そういえば長男も留学から帰国後にSAPIOを読み、よしりんにハマリ、わたしも含め家族に多大な影響を与えるに至る。いまだその影響下にあり(笑
Posted by ブクログ
近は国粋主義者として鳴らしている氏の若い頃、数学者としてケンブリッジで過ごした中の1年間をまとめた旅行記兼エッセイ集。
英国の根底に存在する生活や文化や思想等の考察も交えながら、身の回りの出来事を等身大でありのままに活き活きと描写してある、個人的旅行記のベスト。何度読んでも面白いので、たまに読んでしまう。国家の品格以降そういう系の啓発本しか出してない氏だけど、またこういう本書いてくれないかなぁ。
Posted by ブクログ
イギリス人、というものがどうであるか、どのような特徴を持っているか、ということが数学者としての経験、というよりかは一人間として見た点が描かれている。
そしてそれがとても腑に落ちるものであった。
外国で生活するには「自国の知識」が必要だし、「相手の国の知識」も最低限知っておかないといけないし、とにかく言語の問題以前に教養の必要性を感じさせられた
Posted by ブクログ
前作「若い数学者のアメリカ」が大変よかったので、2作目である本作品も期待して読んでみれば、期待にたがわぬ素晴らしい出来栄えだった。
1987-88年にケンブリッジ大学クイーンズ・カレッジで研究を行った著者の生活記。
外国へ行くと極端に日本擁護派になってしまう藤原氏の前のめりな姿勢に時には苦笑しつつも、客観的で冷静なイギリス人分析力はさすがの一言に尽きる。
「敵を知り、己を知れば百戦危うからず」という格言通り、次第次第に周囲と打ち解けていき素晴らしい人間関係を気付いていく彼の人の良さには感動すら覚えてしまう。
数学者とは思えないほどの文才も前作に引き続き冴えわたっている。まさに一級品のルポルタージュである。
個人的には5つ星でも差支えないのだが、前作があまりに出来が良かったため星1つ減らした。
おもしろさは請け合いますぜ。
Posted by ブクログ
私は心の中で「行け」と鋭く号令を掛けた。
静まり返った中を、彼女が弦に当てた弓をすーっと引いた。物凄いとはこのことだった。
「圧勝だ」と思った。
〜
私は音楽的感動と愛国的感動の波に手荒くもまれながら、じっとしていた。
〜中略〜
「すごかった。ものの十秒で日本の圧勝を確信した」
〜中略〜
よし今度は自分が蹴散らしてやろう、と思った。
海外にいて自国の人間の活躍を観たときの気持ち。
凄く良くわかる。
Posted by ブクログ
藤原正彦さんの英国滞在記。
著者の本は今までアメリカに関するものしか読んでなかったから、読んでて純粋にイギリスという国の勉強になりました(と言ってももう20年以上前の内容だけど)。
数学の天才のはずなのに相変わらず僕のように凡人にとっても読み易く、ひいては楽しく読ませてくれる文章の達人です。
内容はというと、僕はイギリス行ったことない上にアメリカ育ちというのもあって、
「やっぱり英米間の隔たりって深いんだなぁ」
ってしみじみ感じました。
きっとイギリスで僕は米語を話しません。
でも一度は行っとかないとね!
Posted by ブクログ
「若き数学者のアメリカ」から歳月を経て、今度は妻子連れで渡ったイギリス。何もかもが物珍しく好奇心いっぱいに飛び込んだアメリカに比べ、少し距離を置いてイギリスを見ている感じが興味深い。好みや年齢や社会的立場の違いもあるだろうけれど、若い時に最初に出会った国というのが、その後、ある種のスタンダードになるのかもしれないな、と感じる。
Posted by ブクログ
【156冊目】ケンブリッジにいる間に読んでおかなければと思って読んだ本。期待したとおり、イギリスの文化・歴史に対する豊富な知識と、日米との比較が非常に勉強になった。
>オックスフォードは世界が自分のものであるかのように振る舞うが、ケンブリッジは世界が誰のものであってもかまわないというように振る舞う。
……こういうところ、結構大好きです。ちなみに体感では、ケンブリッジ生はToryよりもLabour支持派の方が多い気がする。
>数学に限らず、イギリスでは一般に、抽象的で論理的な議論はフランス人のもの、と不信感さえ持てれてきた。だから哲学において、形而上学はイギリスでは育たなかった。自ら経験した事実に頼るというのが、ベーコン以来のイギリス哲学の主流だった。(p.232)
……非常によく分かる。おそらくcivil lawとcommon lawの法体系の違いもここから発生しているのだろう。なお、フランシス・ベーコンはTrinity college出身。
>彼らの精神的ふくよかさは、イギリス病とか斜陽といった、経済指標によった名称からは、想像できないものである。日本は、イギリスのいつか歩いた道を歩んでいる。イギリスは日本のいつか歩むであろう道を歩んでいる。(p.261、なお本書は1987〜1988年の留学記である)
……これは僕が常に言っていること。日本はよくも悪くもイギリス(と、韓国)から学ぶべき点が複数あるように思う。
Posted by ブクログ
同著者の「若き数学者のアメリカ」が素晴らしかったので購入。
「若き~」ほどではないが面白い。
若干引くエピソードも有り。「国家の品格」の片鱗有り。
Posted by ブクログ
古いものが素晴らしいとされるイギリス文化。そんな気質が色濃く残るケンブリッジの留学記。ケンブリッジ体験記も面白かったが海外留学に家族を連れていくことの大変さがよく伝わってきて、印象に残った。特に子供の教育問題は人種差別の問題も相まって悩みの深さが伺える。時代は少し進んだけども海外で働く人に読ませれば共感する部分が多いのだろうなと思う。
Posted by ブクログ
四苦八苦しながらイギリス社会に入っていく氏の姿が歯切れよく描かれていてよろしいのだが,所々で見える「ドヤ感」に少々萎える。高校の校長先生にもらった一冊。
Posted by ブクログ
何冊目かの藤原正彦氏の本だけど、内容云々じゃなく非常にサクサクサクといけるカナッペみたいな文章が好き。
正直言えば氏の思想やイギリスに興味がない方が引っ掛からず楽しめるかも。