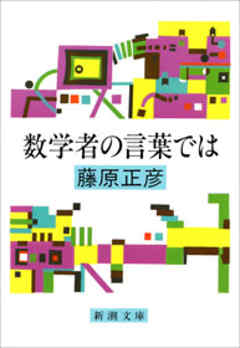感情タグBEST3
Posted by ブクログ
数学者藤原正彦氏のエッセイ集。とても読みやすいし淡々としたユーモアが心地良い。学者の視点から語られる学問への考え方、数学と文学の対比など内容は多彩だったけれど、何だかんだで新婚旅行記が一番面白かった気はする。ところどころそれはどうかなという意見もあったものの、数学者というのは普段こんなことを考えているのかあという思いで始終楽しく読めました。薦めてくれた友人に感謝。
Posted by ブクログ
かつてコロラド大学で教えた女子学生から挫折の手紙が届いた。筆者は彼女を激励しつつ、学問の困難さを懇々と説く。だが、困難とはいえ数学には、複雑な部分部分が張りつめた糸で結ばれた、芸術ともいうべき美の極致がある。また、父・新田次郎に励まされた文章修業、数学と文学の間を行き来しながら思うことなど、若き数学者が真摯な情熱とさりげないユーモアで綴るエッセイ集。
数学者である筆者が、数学者として、一人の人間として、父親として、夫としての、様々な素顔を曝け出しているところがおもしろい。
巻末には父・新田次郎に関するエッセイも多く、筆者にとっていかに父親の存在が大きいものであるかを感じられる。
Posted by ブクログ
数学者、藤原先生の強烈な個性爆発。『若き数学者のアメリカ』と一部重複する箇所があるように思うが、どのはなしも面白く読める。自分が日本人であると感じたいなら外国へ行くことだ。それも旅行程度の日程ではなく長期滞在をするに限る。日本人と自覚することでその後の人生にどんな影響があるのか、海外体験がプラスに働くことを願いたい。
Posted by ブクログ
厳密な論理にもとづく科学。その中でも厳密な数学。その中でも基礎である数論は数学の女王とまで呼ばれる。科学を専門とする人間は変わったキャラクターを持つ人間が多い。曖昧な世界で生きる人と論理性の世界で生きる人間の世界に対する見方・取り組み方の違いが出るのであろうか。著者も数論を専門とする数学者で最近は本職よりも様々な文化論・国家論で有名。論理も行ききってしまうと逆に世界に対する諦観が生まれるのであろうか、一途なキャラクターも人間味を感じる。
Posted by ブクログ
「国家の品格」の著者として有名な方だけど、実はそれ以前から「若き数学者のアメリカ」を読んで知っていた。今回は(失礼ながら)神戸・元町の高架下の何屋さんか分からない店で入手した古本だったけど、一気に読んでしまった。面白い。コクがある文章表現に、ユーモアと深い考察が並立した世界。こんなエッセイを書いてみたいもの。
Posted by ブクログ
内容:新田次郎と藤原ていの息子の数学者藤原正彦のエッセイ。小川洋子が「博士」を書くきっかけになった人でもある。日本エッセイストクラブの賞を取ってたり。そして、高校の同級生の親父だったりもする。内容はアメリカ時代の話や日本論などいろいろ収拾がつかないけど、たぶんばらばらに連載した細切れを集めた本だからではないか?
感想:今ひとつ。でもそれはこの人が好きで、期待値が高かったからだと思う。気楽な面白さが随所にあったけど、密度が薄かった。でも、やっぱりこの人ぐらいの明快さと気楽さが一番いい。頭を使わずに読書したいときで、外れのない本が読みたいときにオススメ(ただし、他の本、例えば『遥かなるケンブリッジ』のほうがよい)。
Posted by ブクログ
なんとなく、この人のエッセイを読んでしまう。
たぶん頑固親父に説教されたい願望があるのだろうと思われる。
結構私はきんぱち先生がすきなのである。
エッセイを読んで、そうだ!そうだ!と思うことが多い。
次はイギリスについての考察の本を読んでみたいと思う。
Posted by ブクログ
若き数学者・・に続く藤原正彦氏の著作。アメリカでの生活に限定されず、学者とは何ぞや、数学者とは何ぞや、アメリカ人とは、情緒とは・・等々について書かれている。数学者に限らず、学者が如何に苦しい生き方なのかという部分が垣間見えつつも、氏独特のユーモアにあふれていてる。