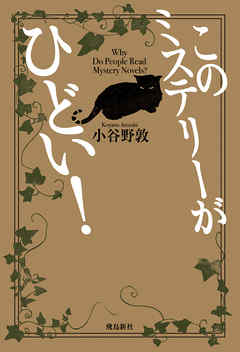感情タグBEST3
Posted by ブクログ
いつも思うのだけど、なぜ小谷野敦は全方向に敵を作るような書き方をするのか。
推理小説嫌いと言いながら、それなりには読んでいるのだ。
そしてほぼボロクソにけなしている。
嫌いなら読まなきゃいいのに。
彼は純文学の人だ。
だからトリックのためにストーリーやら人物造形やらが不自然にゆがめられるのが許せない。
好き嫌いはしょうがないと思う。
私も結構毒舌を吐くし、気持ちはわかる。
だけどどうにも彼の書く文章は品性に欠けるような気がする。
“『赤毛のアン』が好きなのは、二流大学卒の女子あたりが中心だろうと書いたのだが、これが何だかバカにしていると思われて、いまだに話題になる。(中略)だいたい、私自身が『赤毛のアン』が好きで言っているのに、なんちゅうひがみ根性であろうか。”
もし本気でこの文章を書いたのだとしたら、作家をやめればいい。
この文章を読んで、「『赤毛のアン』が好きなんて、趣味が合いますね」と握手を求めてくる人はいないだろう。
意図した読ませ方ができない自分を嗤うがいい。
そして“『赤毛のアン』が好きなのは”ではなく“『赤毛のアン』を好きなのは”と書くほうが文章的に正しいのではないでしょうか。
と、ついこちらも厭味ったらしい文章を書いてしまうくらい、えげつない文章が続く。
そして、つるっとネタバレ。
そしてタイトルには表れていないが、純文学にもSFにもファンタジーにも毒を吐いております。
私よりはるかに大量の本を読んでいながら、その9割に不満爆発なのは、不幸なことなんじゃないかな。
ちなみに著者の推理小説ベスト
1位 西村京太郎『天使の傷痕』
1位 筒井康隆『ロートレック荘事件』
3位 貴志祐介『硝子のハンマー』
4位 ヘレン・マクロイ『殺す者と殺される者』
5位 中町信『模倣の殺意』
6位 北村薫『六の宮の姫君』
7位 折原一『倒錯のロンド』
だそうです。
『六の宮の姫君』しか読んだことないや。
『未来少年コナン』と『機動戦士ガンダム』と『風の谷のナウシカ』と広瀬正をほめてくれたのはうれしく思います。
最後は気持ちよく読み終わりたいもんねえ。
Posted by ブクログ
ミステリ愛好家としてはかなり構えて読んだのだが、意外にもうなずけるところが多い。
ねちねちしたところのないさっぱりとした「面白くない」の断定は、ときにユーモアも感じられ、小谷野節健在だなあとニヤリとさせられる。ここ数冊の著書の中では最高の質なんじゃないかなあ。
にしても「俗謡に合わせて人が死ぬと何が面白いのであろうか」には吹き出してしまった。えー!面白いじゃん!むちゃくちゃ面白いじゃん!
そこの感覚の有無が、ミステリ好きになるか否かの分水嶺になるような気がするな。
Posted by ブクログ
ミステリファンのうるさいひとり言と思ってください。
ご不快になられたのならごめんなさい。まず謝っておきます。
まず、単純な事実誤認が多すぎます。
例えば、『興奮』の主人公は「コックニー訛り」ではなく「オーストラリア訛り」、『シャム双子の秘密』でクローズドサークルになった理由は「火山の噴火」ではなく「山火事」(噴火だと『月光ゲーム』ですよ)、『砂の器』の真相部分に触れたところに大きな事実誤認、『魔女が笑う夜』に出てくる像の名前は「わらう後家」ではなく「ばくれん後家」(『わらう後家』はポケミス版のタイトル)、などなど。これではどこを信用していいのかわかりません。
つまらない面白いという評価が書いてあればいいほうで、あらすじしか書いていない、評価がなされていない作家・作品も多く目につきます。
「何が面白いのか説明してほしい」的な文章が散見されますが、どこがつまらなかったか、あるいは理解できなかったかを具体的に書いてもらわないと、読者はそれらを漠然と察するしかなく、説明をするにしても曖昧になってしまいます。
「クリスティーはストーリーテリングが下手」「連城三紀彦は小説が下手」「グレアム・グリーンは二流作家」「泡坂妻夫はバカミスの帝王」「横溝正史は乱歩の亜流の二流作家」「フィリップ・マーロウは『ワル』」など……「純文学作家」・「比較文学者」が読めばそうなのかもしれませんが、一般の評価とはかなり離れていて、独自の視点をお持ちなんだなと思いました。
あと一点、エラリー・クイーンの「読者への挑戦状」を批判していましたが、本作で触れられている『シャム双子の秘密』『日本樫鳥の秘密』『Yの悲劇』には「挑戦状」はついていません。シャムは国名シリーズで唯一「挑戦状」がついていない作品として有名なのでは? あえて「挑戦状」がついていない作品を選んだ可能性も考えました(著者は小説の知識が豊富ですし)。国名シリーズでも有名な、ギリシャ・オランダ・エジプトあたりを読まれていたら、本文で触れていてもおかしくないと思うのですが……。もしそれらを読まれていないのであれば(読んでいるとは思いますが)、学生向け雑誌の付録のみでクイーンの「挑戦状」を批判するのはフェアではないと思います。
『推理小説の美学』でエドマンド・ウィルスンの評論を読まれているなら、ドロシー・L・セイヤーズのミステリの歴史についての記述も読んでいるはずなのですが……。古典的寓話や神話、戯曲などにミステリ的要素があるのはその当時から指摘されていることで、ジュリアン・シモンズが『ブラッディ・マーダー 探偵小説から犯罪小説への歴史』のなかで、推理小説がポーを始祖とするかとともに仔細に検討しています。その本を読んでおいてほしいとはつゆにも思いませんが、そのようなものに触れた人は大体思いつくことです。
ミステリというジャンルを嫌いな方がいらっしゃるのは当然のことですし、そのこと自体は全然かまいません。批判のないジャンルは衰退しますが、「文学者」が雑に読んで(「読み飛ばした」、映像のみ、などが頻出するので)、雑に論評するのは、ファンとしてはいい気分はしないな、と思いました。お金を払って居酒屋で知らない酔っ払いの戯れ言を聞かされている感覚です(お酒をたしなまれるかは存じ上げないですが)。
あと随所に「中学生レベル」といった感じの言葉が出てきますが、中学生もミステリファンもバカにしている印象を受け、なんだかなぁと思いました。
それと、直木賞や芥川賞、作者の最終学歴などにこだわりすぎる印象を持ちました。それぞれの作者紹介でこんなに最終学歴が掲載されているのを読んだのははじめてかもしれません。学歴には詳しくはなりましたが、作家としての素質と何か関係があるのだろうか? といぶかしんでしまいました。
ただ、意外にある程度ミステリについて納得できる点や、文学界の人間関係、作品に関するうんちく、ミステリ嫌いの人がどう考えているかなど、参考になる部分はあったので、読んで損とまではいかなかったです。
最後に。私小説的ミステリなら、ジェイムズ・エルロイの『ブラック・ダリア』を推薦します。悪人しか出てこないノワール小説なので、勧善懲悪が好みの著者の趣味とは離れているだろうとは思いますが。
Posted by ブクログ
ただつらつらとミステリのタイトルが並べられて、よくない、わからない、わからないとはつまらなかったということだ、などのぼやきが続くばかりなんだけどさ。読み進めていくと、これが意外と面白い。膨大な量のタイトルが出てきて、中には雑読みしたり、途中でやめたり、読んだけどわすれてしまった、というのもあるものの、それだけの本を手に取るだけでも今どき珍しい人ともいえるだろう。作品をとりあげ、こまかく評するのも面白いこともあるけど、こうやってざっくりとただひたすらタイトルと〇か×かだけを並べるだけ、というのもわかりやすくてよい。
自分で読んで、あ、やっぱりつまんなかったんだ、という本もあれば、えー?あれ、そんなにダメかなというものもある。そういうものだと思う。本を読んで感じるものなんて、人それぞれちがうんだからさ。
本について、ああでもない、こうでもないという話を聞く楽しみを味わえたね。
Posted by ブクログ
バシバシ斬りまくるのでドキドキしますが、最初のあたり、あら!私と好み一緒なのね!と、つい嬉しくなったり(笑)
私も小学生の時、ポブラ文庫のルパンが大好きで繰り返し読んでたんだけど、ホームズと少年探偵団にはピンと来なかったんだよな〜。
あとヒカルの碁が好きってのも。
アンナ・カレーニナ好きじゃないのは残念だわ…
とりあえず、あんま難しいこと考えずにもっと自由に感想言っていいよね、と励まされました。
Posted by ブクログ
何とまあ正直な人だこと。あちこち怒らせるようなことをかまわず書くのが著者のスタイルではあるけれど、なかなかこうは書けないだろう。ミステリって読者も評論家も多い。傑作・名作と言われるものを読んで面白くなかったら、自分がちゃんと読めてないのかしら?と思って黙っとく。あるいは著者が言うように「私の好みじゃないです」と言っとく。つまらないのをほめている評を見ると、あの程度のを喜ぶなんて低レベルだなーとか思ったりする。ミステリファンって小うるさいものだ。(SFファンほどじゃないか)
そんな思惑などものともせず、自分の主観で、名だたる「名作」や近年のヒット作などを「まったくつまらん」とメッタ斬り。一方で筒井康隆の「ロートレック荘事件」を最高傑作と絶賛。え?あれって特に珍しくもないワンアイデアのトリックもので…と目をパチパチさせてしまった。まあ、これは個々の作品とかについてどうこう言うものではなくて、天下御免の言いたい放題を芸として楽しむものなのだろう。
とは言え、随所になるほどなあという指摘もある。最近の文芸作品の傾向を「ノワール化とスイーツ化」としているところなど納得である。また、高級官僚が好きな作家を尋ねられて「宮部みゆきさんです」と答えていたそうだが、確かに少し前なら「高尚な」純文学作家の名が上がったはずで、「そういう時代」なのだろう。
どうにもこうにも
不出来な小説が売れてる現状に異議申し立てをしてるが、本は商品なのだから、売れなければ出す意味がない。本が売れることで、出版社は潤い、作家は印税で生活が出来る。それの何が悪いのか?売れない本は商品として失格。菊池寛の文章を借りると、読まれない文芸などは、飛べない飛行機と同じものである。
「そして誰もいなくなった」ピーター・コリンソン版の映画をつまらないと評すが、1945年のルネ・クレール版が最初の映画なので、それを観て評価するべし。
正義の味方の方がいいに決まっているとあるが、そんなこと誰が決めたのか?どういう人物に魅力を感じるかは読んだ人の勝手である。
著者がつまらない・バカだと決めつけているミステリは、出版されてから何十年も経っているのに読み継がれているのだから大したものである。逆に小谷野のものも含めて、現代小説の殆どがつまらなく、五年も経てば消えるだろう。