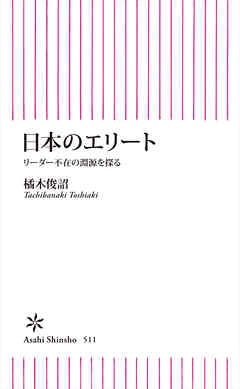感情タグBEST3
Posted by ブクログ
明治維新から始まる高級軍人・官僚登用の仕組みや実績、日本の政治家や経営者、ガリレオやニュートン、マルクスなど世界の知的エリート達の生涯など、エリートに関する論。
特に日本での学業重視傾向は、昔からの特徴であるが、幼年学校からの囲い込みによる、視野の狭い人材育成・登用をしたが故に、破滅の道を歩んだ日本陸軍や、海外留学など世界を見据えての人材育成により、アメリカとの戦争回避に傾いていた海軍の良心など、読みどころが抜群でした。
官僚においても、明治維新以降の富国強兵政策のもと、身分にとらわれず優秀な人材を登用するために、地方の貧しい秀才を有力地主が婿養子にとり、帝国大学の学費の面倒をみて立身出世するなど。また帝国大学と慶應など私学との競争もあり。
エリートというより、近代の日本建設のための人材育成の歴史を知ることができました。
そういう意味で、知的エリートとして登場した諸外国の偉人達は、本書の構成上、余分だったかも知れません。
Posted by ブクログ
「日本のエリート」
はじめに「エリートとは、社会の先頭に立って社会や組織の指導者として、人々を牽引していく人のことである。」と定義している。
軍人、官僚、政治家、経営者、そして社会に大きな影響を与えた知識人をエリートとして考え、明治以降のそれぞれの時代に必要とされたエリートとその功罪について議論している。特に陸・海軍士官学校から軍人、帝国大学(東大)から官僚に関してはかなり詳しく議論している。そして、身分を問わず実力で栄達できたと言うことは評価すべき点だといえる。中でも明治から脈々と続く東大の強さがよくわかる。
しかし、本書では特に議論していないがエリートが人格高潔で社会正義に敏感であるということとはまったく関係がないわけで、エリートとして社会を牛耳るならば、それ相応の責任を負う必要性も議論しても良いように思う。
著者は最後にエリート不在と言われる現代でエリートは育てられるか、学校教育でエリートが輩出できるかを議論しているが、最後にはエリートからリーダーという言い方に微妙に変わっているところが気になる。既にエリートという言葉は死語になりつつあるのかも知れない。