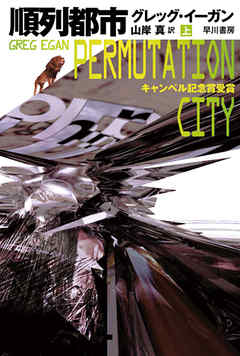感情タグBEST3
Posted by ブクログ
この難解な本が理解できるようなり、この本を通して自分の成長を感じる。
読まないからと売ったり捨てたりせずに残してて良かった。
はっきり言って、用語について調べながら読まなければ、面白さよりも苦しさが勝ると思う。
私がこの本を購入したのは、7年前。私はまだ高校生でした。当時放送が始まったソードアートオンラインをきっかけに「仮想世界」について興味をもち、この分野について調べていくうちにグレッグイーガンに辿り着きました。
Posted by ブクログ
うーん、とても難解だった!w それでも総体として面白かったという印象を残すのだから、やっぱりグレッグ・イーガンはすごい。
オートヴァース内の化学的な描写は、正直なところ難しくて飛ばし読みしてしまった。あと、コピーのポールが真相?に至るまでの考察も。
だけど、そんな初心者をも楽しませてくれるのだから、イーガンはすごい。上級者向けの細部を披露しつつも、初心者を振り落とさない。しっかりとストーリーの道案内をしてくれる。
だから読んでいる方も必死になってしがみつくことができて、タフな読書体験を獲得できる。
話の核となるのは、人間のコピーを作成してコンピュータ上で走らせるというもの。
単なるSF的アイデアの披露に留まらないのは、話が多層的だからだ。コピーという存在について、経済・法律・哲学などの複数の視点から語られる。だから、のめり込んでしまう。
コピー以外にも、ささやかなSF的エッセンスが散りばめられている。手の込んだ迷惑メールとか、新しいライブ鑑賞のスタイルとか。それ単体で短編小説になり得るレベルのギミックが差し込まれる。SF小説として非常に贅沢。
また、上巻としての終わり方がすごくサスペンスドラマ的で下巻が気になってしまう感じ。
Posted by ブクログ
イーガン凄い!コピーの権利の問題やフェッセンデンの宇宙をガチに理論化した様な世界のシュミレーションや塵から生まれる意識やらそれらが量子論や哲学等多方面から検討される。ダラムやマリア、登場人物たちの議論や悩み、問題が来るべき世界を先取りしてる様で知的に刺激されます!
Posted by ブクログ
普通に面白い。難しいというよりも、専門用語が多いだけでそれを知らなくても内容は理解できるくらい作中で丁寧というかしつこく説明きてくれている。下巻を読まないと内容に関する感想はかけないけれども、これは期待できる。
Posted by ブクログ
とにかく好き。理屈じゃないんだ、理屈あっての小説だけどでも理屈じゃないんだ。「創造主が創造物に否定される」ってのはシビアながら笑いどころのような気もする。で、私の考え方は90年代生まれのママンに似ている…年上だから当たり前。
Posted by ブクログ
え、そんな展開!?そんな理屈!?
という、意外性の連続な展開が非常に面白い。
SFって世界設定の理屈付けがどれだけしっかりしていて、なおかつ驚愕を誘うものかがひとつの面白さの基準だと思うのだが、見事にそれを満たしている一冊。
Posted by ブクログ
被検体の時間をスライスしてシャッフルしてシミュレートするってことは未来を予測する処理が必要だと思うけど、その結果が対照標準と一致することはありえない気がする。
Posted by ブクログ
SF作家の中でイーガンは特に興味があり、最初に読むものとしてこの初期作品を選んだ。イーガンは「難解」と言われたりするが、彼が作品中で設定している根本的なロジックさえ納得できれば、読み進める事はそれほど難しいとは思わなかった。この作品では主人公が「塵理論」を元に純粋な情報のレベルで世界を作るというもので、線型代数学の基礎知識がある程度の私だがなんとなく理解はできた。作者が設定するロジックを面白いと感じるかどうかが好き嫌いの分け目かと思う。私はこういったロジカルな作風はSF表現の一つとしてとても面白いと思う。
Posted by ブクログ
分かりにくいがその世界に入れば第一部はなかなかいい
表紙 5点小阪 淳 山岸 真訳
展開 7点1994年著作
文章 6点
内容 725点
合計 743点
Posted by ブクログ
2016/09/07-2016/09/10
星4.5
「グレッグ・イーガンのSFがおもしろい」というのを風の噂で聞いたので読んだ。ハヤカワ文庫SFの中ではこれが最初の単行本だが、日本語訳されているイーガンの長編の中では2番目らしい。創元SF文庫から出ている『宇宙消失』が最初。Wikipediaによると更にそれより前に "An Unusual Angle" というのがあるらしい。
物語の背景として主軸にあるのは、物理・情報科学・生物の知識。物理に偏ることも情報科学に偏ることもなく、基礎原理から生物的性質まで幅広く設定され考察されているのには、想像力の広さを感じた。
今まで僕はいわゆる「強いAI」の世界観に違和感を覚えていたのだが、そんな僕にでも「強いAI」が存在する世界をリアリスティックに感じられるくらいの構成だった。
また、科学を志すものとして、「オッカムの剃刀」についてちょっとした考え違いをしていたことに気づけたのも大きかった。SFを読むと自分の視野の狭さに気づけるので面白い。
Posted by ブクログ
どうやって人間をサイバー空間に送り込むか? という問題については、つまりこの順列都市の「スキャン」って方法で解決できちゃうのかも。身体構造をまるごと写しとって、仮想世界に用意した真っ白いインテリアの部屋にぶちこめばいい。魂というものがない限り、人間はそれで問題なく動くかも。
この小説で面白いのは、その「スキャン」の発想と、ダラムの展開する「塵理論」。なんだけど、その解釈が難しいのでこれが塵理論かな? と思うのを二つ書いておく。
塵理論その①
主人公の一人であるダラムは妻によって一度仮想世界を体験し、自身をコピーと思い込んだ。その結果、「ベッドで眠る自分」と「コピーとしての自分」という二つの自分を経験した。それはどちらも実在するダラムだった。ということは、ダラムにとって世界は二つあったことになる。ダラムは自分がパラレルワールドを体現したことを悟る。人間の意識を起点として世界が存在するのなら、時間は必ずしも連続していなくていいし、不連続な空間は人間の認識によって溶接出来る。つまり、塵理論は「永遠は無限に散らばった極小の空間の接続で実現できる」ということ。
塵理論その②
もうひとつは、塵理論は「プログラムのなかのプログラム」そのものという話。現実世界におけるサーバーのパワー不足が問題なら、仮想空間のサーバーを使えばいいじゃない。情報という実態のない「塵」から無限の空間が生まれる。だから塵理論。鈴木光司の「リング」三部作でも同じような話があった。
個人的にはその①かなあと思ってるけど、よくわかっていない。塵の存在であるプログラムの中のプログラム(TVC宇宙)に永遠の時間が分割されて存在し人間の意識によって溶接される、それ全体を指してというのが今の認識に一番近いかも。
また、コンピューター上で世界で起こりうるすべてのパラレルを無限に計算し、それを観測者の認識によってこよりのようにより合わせ永遠に実在化し続けるのが塵理論という考え方もあるけど、個人的にはしっくりこない。
下巻に入り、シャワー室でダラムが自殺してから、とたんにパワーダウンを感じる。TVC宇宙の人間のファッションとかどうでもいいし。ラストのオートヴァース世界がTVC宇宙に影響するというのは面白いなあと思ったけど、それってアリか? オートヴァースとTVC宇宙の基盤になるプログラムは違うんじゃないの? とも思う。
Posted by ブクログ
タイトルからは全く内容を想像することが出来ないSF。上下巻に分かれており、上巻だけでは全く話をつかむことが出来ないし、どこに着地するのかを想像することもできない・・・・。
あらすじはこんな感じ。
近未来、人類は神経系を全てスキャンすることで、肉体がなくなった後もコンピューター上に「データ」として生き続けることが出来るようになった。コンピューター上の人格は現実とコミュニケーションをとることもできるし、企業に干渉することもできる。ただし、コンピューターを動かし続けるには資産が必要であり、それを手もっていないものはゆっくりとしか時間を過ごすことが出来ずにいた。
主人公の女性プログラマーはそのような巨大リソースの中で趣味のオートマトン遊びを繰り返している時に信じられないような発見をし、そしてそれをきっかけに「順列都市」の計画に巻き込まれていくのだった・・・。
こうかくと一本道のような話に聞こえるが、実際には複数の主人公の話が複雑に絡んでいる群像劇で、上巻は人間関係を把握するだけで終わってしまうようなところがある。上巻でも後半に入ると少しずつ話が動き出しておもしろくなるが、その前に力尽きると全く何の話かわからないまま。★4つは上下巻あわせての評価。
Posted by ブクログ
コンピュータの性能が上がり、脳のシミュレーションさえもが可能になった社会を舞台にしたSF。結構難しいところもあるが、やはりおもしろい。下巻がとても楽しみ。
Posted by ブクログ
生化学も物理もITもさっぱりな私でもなんだか面白かったです。人格をデータとして保存することで生き延びたと言えるのか?完璧な世界を作り上げることは可能なのか、意味はあるのか。いろいろ考えてしまいました。マリアとお母さんの会話が一番印象に残った。死を受け入れたことを神に(神が何を動かしたわけではないが)感謝する。その気持ちは一番美しく見えます。
Posted by ブクログ
ハードSF極北の一つ。上巻だけ読んでいる時は、設定と展開が斬新すぎて何が何だかよくわからなかった。下巻の訳者解説を読んで、そういう話だったのかと思って、上巻再度読み直し。それでようやくわかったような感じの名作。
Posted by ブクログ
グレッグ・イーガン著。90年代を代表するSF作家だそうな。
SFというニッチなジャンルでありながらその中でも有名、と言う事で程よい読みやすさかと。
読みやすいだけでなく面白さも折り紙付き、つまみ食いのつもりが気付いた時には二周目だった。
宇宙系のSFに比べるとサイバー系は「トンデモ超理論」が出にくい気がします(偏見)が、これの屑理論は珠玉。わけわかんねえ。
最早サイバーパンクが「パンク」とは呼べない時代になってきておりますが、確実にギブスン、ひいてはディックの精神を感じ取れるのが好印象。
そういや「ターミナル・エクスペリメント」なんつーのもありましたねえ。
Posted by ブクログ
一度読んだけれどもう一度再読しようと心に誓っている。
グレッグ・イーガンの作品は、
初めて本格的にSFに挑戦しようと「ディアスポラ」を一番最初に読んで意識が飛びかかった思い出がある。
この作品を読んでコンピュータ上に人格を移すというアイディアがやっとつながった。
「ディアスポラ」を読む前に読みたかった。
Posted by ブクログ
人間の精神をスキャンしてデジタルの世界に送り込むことが可能になった世界。ある画期的な理論を考案した主人公(?)がデジタルに住まう「コピー」たちに、文字通りの永遠の存在を約束する話が前半のメイン。
コピーたちはハードウェアの制約で現実の17分の1の速さでしか活動できなかったりするのが面白いですが、コピーの人権を認めない法律が成立しようとしていたりで、存在としての基盤が揺らいでいるのを背景に話が展開していきます。
後半は、ある理由があって「…そして7000年後」
アイディアの核はなんとも説明しがたい「塵理論」とセル・オートマトンモデル生命なんですが、この二つが結びついたとき主観的宇宙論の本作におけるアプローチが理解できると言う構図。なんと言っても塵理論の片鱗でも分かったつもりにならないと面白くないわけですが、話が綺麗にできているから、SFの素養がある人で、あんまり突き詰めて考えない人はイーガンの長編だったらこれがとっつきやすいような気がします。
ベースの世界観(というか基本設定)はディアスポラや他の短編とも一緒のように見えるので、ディアスポラを読む前に世界をイメージするのにはよいかも。
Posted by ブクログ
一言で言うと難解。
仮想現実の中で実体をスキャンして、それを元にしてコピーとして生きる人々。コピーなのに感情を持ち、あたかも生きているように振る舞う。
更に人工宇宙まで作り出し、そこに惑星と生命を作り出し、進化させるとは。
これだけのことをこなすコンピュータパワーがあるとは現状を考えると考えづらい。そして電力も。
でも、コピーとして生き続け、実体のある人々を支配している?と言う姿はある意味ホラーでしかないかもね。
そんな未来が来るのか?と思いながら読んだので、内容が今ひとつ入ってこなかった。
Posted by ブクログ
自分をスキャンし、架空都市に配置した「コピー」の人格は自分なのか。処理速度の低下で17分の1に、30分の1に、5万分の1の「主観時間」で遅くなった、さらに逆再生、ランダム化された意識は、自分の体感と思考は、自分のままなのか。分子より大きな段階でモデル化され学習され調整された「反応」と「行動」は、果たして本当の自分なのか。
コピーされた自我とオリジナルの同一性で悩む人々。オートヴァースで再現された進化生活環。真の目的と、永遠の自我。将来たしかにこういう技術が生まれ、こういう問題が起きるかもしれない。
それを考えるのも楽しいけど、問題に直面した人の心理的な葛藤よりも、その技術を元にどんな社会と大衆の行動が生まれるのか、そういうSFを読みたいのです。
Posted by ブクログ
細かい論理は正直、理解の範疇をこえてる。誰かわかりやすいパワポとか作ってほしい。でも、オートヴァースが生み出す仮想生命は、他のSF作家によるスピンオフが見てみたい。複数の登場人物の視点で書かれる本作だが、それぞれが絡み合っていく過程は秀逸。
Posted by ブクログ
自分をスキャンして電脳空間で永遠に生きる時代を描いたもの
我々の意識は過去→未来へと流れていくように思えるが、それは本当なのか(記憶を失いつつ過去に戻ることと区別がつかない)、全く同じ神経回路が複写された時、自意識はどこにいくのか、などの哲学的な問題についても著者の関心の赴くままに書かれている
Posted by ブクログ
仮想現実に自分の”コピー”を創造することでコンピュータのリソースが続き、ソフトウェアが止まらない限り半永久的に生きられるようになった世界。
そんな中で一人の男がとある計画のために動き出す――。
認知科学とか、機械工学とかに精通している人は問題ないかと思うがそうでないとなかなか入っていくのに時間がかかる。
だが、読み込んでいくうちにどんどん深みにはまり、気がつけばイーガンの作中に沈んでいる自分に気付く。
上下巻分かれているわけだが、上巻の終わり方が卑怯すぎる。もちろん、いい意味でだが。
生命とは?自我とは?
常に問いかけ続けてくる。
Posted by ブクログ
人物のスキャンが可能となり、電脳世界で生き長らえることが出来るようになった世界で、自己とは何か、生きるとは何を意味するかに迫る物語。『順列都市』の世界において鍵となるのは、次に挙げる三つの概念である。第一に、現実。これはボトムアップ型の概念であり、素粒子のスケールから計算された物理法則に従う世界を指す。これをコンピュータ上で再現するには膨大な計算力が必要で、『順列都市』の世界においても不可能である。第二に、コピー。これは現実の生理学をブラックボックス化することで、計算を単純化し仮想現実を可能にするトップダウン型の概念である。世界中の富豪たちが自らのコピーを作り、死ぬ間際にスキャンすることで、その存在を半永久的なものにしていた。そして第三に、オートヴァース。これはオートマトン(逐次的に状態が遷移する数学的なモデル)の一種であり、現実とは異なる物理法則で動くが、その法則は原始的なレベルから巨視的なレベルにまで作用し、その全てを統率する。一方で現実とは異なり計算量が小さく、コンピュータ上で再現可能な概念である。
上巻では複数の人々による群像劇として話が構成されている。コピーによる実験を行うポールとダラム、莫大な資産を担保にコピーとして存在し続けるトマス、オートヴァースに魅了されたマリア、そして何かを企てるカーター、ピー、ケイト。それぞれの物語が鍋の底で燻り続ける泡のように現れるも、本書では未だその全容は分からない。下巻において、散らばった数々の伏線はどのように回収されていくのだろうか。
下巻の解説を垣間見て、塵という単語が目に入った。塵理論についてはよく分からないが、私が本書を読み感じたのは解釈に関する問題である。無秩序に並ぶデータをどう解釈するのか。その方法によりその内容が決まり、そこに意味が生まれる。形式と内容、シンタックスとセマンティクスの対応が、本書で鍵となる概念なのではないだろうか。原子の並びに意味は無く、そこにメモリ上の電子情報との差異はない。異同があるとすれば、それは解釈する側の問題で、解釈することに意味があり、意志があるのだと。
本書では章毎に色々な人物に視点が映るので、最初は戸惑うかもしれない。世界観にとって重要な用語や概念も、後に説明される場合があるので気軽に読み進めても問題ない。ただオートヴァースは分かりにくいので、この本を読む前にセル・オートマトン、ライフゲーム等について調べると良い。分かりやすい動画がネットには豊富に存在するので、それを参考にすると想像しやすいだろう。
Posted by ブクログ
・2040年代のアメリカが舞台のハードSF。
・ジャンルはサイバースペースもの。発達した仮想現実に意識をコピーし、コピーたちはほぼ人間と同じ生活を送る。コンピュータ資源の制限から、コピーの活動速度は実時間の1/17以下となっており、支払い能力のない者はさらに低速での生活を強いられる。
・コンピュータ資源は有限なので、「コピー」たちには常に停止=死の恐怖があるが、ある人物がその悩みへの対処を売り込み、主役のプログラマに広大な仮想惑星系の開発を依頼。そこに警察の詐欺捜査班も加わり…というのが上巻の流れ。
Posted by ブクログ
申し訳ない。
ハードSFの傑作に、私自身がついて行けませんでした。
グレッグ・イーガン、すごい天才だと思う。
でも、理解するのが難しい。
許してくれー。
ジョン・W・キャンベル記念賞受賞作。
ディトマー賞受賞作。
Posted by ブクログ
本作は1994年刊行。イーガンは現代電脳SFの最右翼とされている。
「人格を電脳空間にダウンロードして不死を得」という設定は、先日読んだ同じ作者の 「ディアスポラ」1997と共通している。
「ディアスポラ」は、宇宙の真実を解明するために旅するというようなテーマだったのに対して、「順列都市」は自分達専用の異次元空間を作り出して、宇宙の終りが来ようとも不死である。という物凄い話。
出発点の世界は、電脳空間で「大富豪」は自分専用のプロセッサでのびのび暮らせるけれど、大多数の電脳人間は公共ネットワークの余った計算資源で細々と計算されている存在という世界。なにしろ生前の「投資の利息」で細々とCPU時間を買っているのだから、社会情勢のわずかな変化にも敏感にならざるを得ない生活。原理的には不死なのに。
そこで、わずかなコストで現実世界がどうひっくり返ろうと無限に生きられる環境を提供しようと言う男「ダラム」が登場する。
「ダラム」の提供する環境を「TVC宇宙」という。
それはチューリングとフォンノイマンの弟子が開発した物理的に自己複製可能な「二次元チューリングマシン」装置をチャンという人物がN次元に拡張したというもの。このバージョンでは 「6次元万能チューリングマシン」が稼動する。
最も基本的な「チューリングマシン」は、一本(1次元)の磁気テープ(データと命令を格納する) と読み書きヘッドを持った記憶装置を有したコンピュータのモデルで、無限に長いテープを使えば万能コンピュータが出来るという概念。
現代のコンピュータは、ランダムアクセス可能なシリコンのメモリや、HDD、光ディスクを使うけれど、チューリングマシンの概念は生きている。
チューリングマシンの論理的限界は、無限に長いテープには無限に長いアクセス時間がかかるということ。それがシリコンに置き換わって2次元や3次元になっても物理的なアクセス限界が存在することは避けられない。
ところが、「N次元空間にコンピュータを組み立てる、Nはいくら大きくても良い」なんて言うと、高次元な空間にメモリとCPUを折りたたむように組み立てることで無限に複雑なコンピュータを無限に小さなN次元空間に組み立てる事が出来る。
つまり、複雑さの限界を無視できる。
コンピュータ・サイエンスに興味がある人には刺激的な設定だ。
しかしここには、とてつもない論理の飛躍がある。
N次元空間の実在について何も説明が無いし、「自己複製的コンピュータ」が有ると仮定しても、材料やエネルギーが無から生じるわけではないし、現実の 3次元宇宙が滅びた後も、N次元のコンピュータのシミュレートされた世界は永遠に生き延びる とか、そのへんの話は 100%ファンタジーである。少なくともSF世界を構築する為に必要なだけの説明が無い。
ナノマシン好きのイーガン的には、N次元コンピュータを構成する「セル・コンピュータ」の一つ一つがナノマシン的に自己複製を繰り返して無限に増殖するイメージを書いているらしいが、やっぱり、イーガンのナノマシンは魔法領域のガジェットで、これが出てくるとSFというより ハード・ファンタジーになってしまう。
とはいうものの、その世界の上で動くシミュレーション世界は興味深い。
この世界の人間が住む仮想空間は、精神活動をシミュレートするもので、物理法則とは直接関係していない。
これは「ディアスポラ」で書いていた世界が原子一つ一つをまるごとシミュレートすることで成り立っているのと比べると、今のコンピュータの世界に近い。
ところが、人間たちが動くコンピュータ世界のほかに「実世界を簡略化した物理法則」を用いることによって、原子レベルまでシミュレートした世界を、作るところがこの「順列都市」の特徴だ。
原子レベルを扱う「ミニチュア宇宙」と、物理法則とは無縁の「シミュレート宇宙」の二つが「TVC宇宙」というハードウェアの上で走る。
シミュレート宇宙の住人たちは「永遠に生きる」ことを目指しているが、永遠とは「不変」に繋がる。永遠不変は「死」に近いという哲学的な思考も生まれる。
だから、不死の住人たちは「ミニチュア宇宙」に生命の種をまき、その宇宙の物理法則の中で進化していく命を見守ることで永遠不変の人生に変化を見出そうとする、これは壮大な娯楽装置として企画された宇宙だったわけだ。
ところが、ミニチュア宇宙で発生した生命が知性を持って「素粒子論」とか「宇宙論」を考えるようになると、様子が変わってくる。
ミニチュア宇宙は、シミュレート宇宙の住人が初期設定したものだから、彼らが「宇宙の始まり」について考えると、それ以上遡れない、説明不能の状態に陥るはず。
つまり、正解は「この宇宙は神様が創造したのだ」ということ。
でも、科学者は「神」を否定して、観測可能な事実から合理的な宇宙論を構築しようと取り組む。
このへんの成り行きを我々の宇宙の成り立ちと神様に当てはめて考えてみるのは面白い。現実の物理学者の中にも「宇宙の始まりに神の存在を信じる」という人が最近は結構居るらしい。
しかしイーガンは「本当に神様が作った世界」の住人たちが、それを信じないで世界の内側の論理を組み立てて何とか「整合性の有る宇宙論」を作り上げる。
ここからがまた「イーガンの世界」で、住人が宇宙論を完成すると、「TVC宇宙」が壊れる。
これってイーガンが書いた「万物理論」と同じネタですね。
要するに頭で考えたことが本当になる。これも科学というより「ファンタジー」。
面白かったけれど、サイエンスとファンタジーの混在が「座りの悪い」感じがする作品だ。