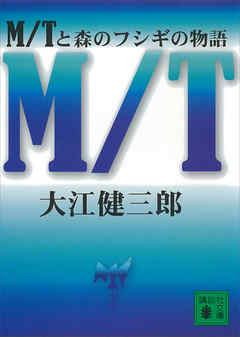感情タグBEST3
Posted by ブクログ
大江の本の中で、エロも酷薄な殺人(描写)も出てこない、珍しい作品。だからこの文庫の裏に紹介されているように「海外で最も読まれている大江作品」なんだな。乱歩が少年探偵ものに自作を書き換えたようなところがあって、もとの『同時代ゲーム』とくらべると、熱がなく、こじんまりとまとまってしまっている感がある。ただ、語り直しだけあって、こちらの方がメッセージはよりダイレクトに伝わってくる気がする。それが文学作品としていいのか悪いのかは何とも言えないが。いずれにせよ、一番読みやすいし、何か一冊読んでみたい人にはこの作品がまずは入り口としてはいいと思う。
岩波文庫版も持っていて、漢字の読みなどの確認のため(岩波文庫版の方がルビが多い)時々参照しているのだが、ちょっとした言い回しやあてる漢字に違いがあったりするのが興味深い。例えば、酷たらしい→酷い(岩 p.144)とか、訊ねる→質ねる(岩 p.249)、影→翳(岩 p.277)、昏れて→暮れて(岩 p.286)、背負い子→背負子(しょいこ)(岩 p.294)、赭ら顔→赤ら顔(岩 p.324)、ついてきて→ついて来て(岩 p.373)、大ズック靴→大きいズック靴(岩 p.373)、頂き→頂(岩 p.373)、魂となって戻り、銘助さんに→魂となって昇り、銘助さんの魂に(岩 p.374)、浮びあがる→浮かびあがる(岩 p.374)、おなごりおしい→お名残惜しい(岩 p.375)、三角に皮膚を畳んだような眼→三角に皮膚を畳んだ目(岩 p.385)、亀ね→亀です(岩 p.385)、別れの告げ方→別れ方(岩 p.386)、ヒソヒソ話したことは→ヒソヒソ話したのは(岩 p.386)、同意もえた→同意も得た(岩 p.388)、ためらっていたのです→ためらったのです(岩 p.388)、いってあげられた→言ってあげられた(岩 p.388)、神隠し→神誘い(岩 p.390)、夜中に紅で→夜中に私の鏡台から取った紅で(岩 p.390)、利発そうな眼→利発そうな目(岩 p.391)、経て→へて(岩 p.391)、働きはじめる→働き始める(岩 p.392)、実際の話です→事実です(岩 p.392)、神隠しに会った時→神隠しにあった時(岩 p.393)、なかでもとくに、→なかでも、とくに(岩 p.394)、脱ぎすてました、→脱ぎ棄てました(岩 p.394)、手さぐりであるものをとりあげ、脇にかかえると→手さぐりで、あるものをとりあげ、脇に抱えると(岩 p.394)、鏡台の抽斗でした。→鏡台の抽斗。(岩 p.394)、塗りたくっていった→塗りたくって行った(岩 p.395)、惧れて→恐れて(岩 p.395)、みたした→満たした(岩 p.395)、という気持ちでした→という感じでした(岩 p.397)、いたるところレーザー光線が→いたるところ、今でいえばレーザー光線が(岩 p.397)、サワガニに心を→サワガニに空腹の身体と心を(岩 p.397)、移しかえたもの→移しかえてのもの(岩 p.398)、つもりです→つもりでいます(岩 p.399)、になって来た→担って来た(岩 p.399)、登って→昇って(岩 p.400)、おちついて→落ち着いて(岩 p.400)、みちたりて→充ち足りて(岩 p.402)、ふるうた→奮うた(岩 p.403)、はじまった→始まった(岩 p.403)、いたり→至り(岩 p.404)、ありながら、今日現在→ありながら今日現在(岩 p.405)、開く→拓く(岩 p.405)、塊り→塊(岩 p.405)、あやまって→過って(岩 p.405)、そなえる→加える(岩 p.405)、したくないの→しないの(岩 p.407)、紐→凧糸/糸(岩 p.407)、かえって厄介→厄介(岩 p.407)、みちたりた→充ちたりた(岩 p.409)、別れて→分かれて(岩 p.410)、生簀→生け簀(岩 p.410)、空けて→開けて(岩 p.410)、しておるのがな→しておる。それがな(岩 p.410)、集って→集まって(岩 p.410)、訴える→うったえる(岩 p.412)、向う→向こう(岩 p.412)、じゃからそうであって→じゃから、そうであって(岩 p.413)、はるかな→遥かな(岩 p.413)、毎日な→毎日(岩 p.413)、聴こえて→聞こえて(岩 p.414)、してな→しましてな(岩 p.414)、思いきめて→思い決めて(岩 p.414)、なごりおしい→名残惜しい(岩 p.415)、思いなして、生きて→思うて生きて(岩 p.415)、滑稽なような、腹立たしいような→滑稽なような・腹立たしいような(岩 p.415)、眼→目(岩 p.415)、聴こえて(た)→聞こえて(た)(岩 p.415)、思いでおりました→思いがしました(岩 p.416)、しあわせなことでした→しあわせでした(岩 p.416)、しあわせなことでした→しあわせでした(岩 p.416)、何の心配も→なんの心配も(岩 p.416)、おおもとにあるところの意味を、はじめて示されたように感じるのです→おおもと(傍点)にあるところの意味を示されたように感じます(岩 p.417)、いくつも→幾つも(岩 p.417)、など。
Posted by ブクログ
まつろわぬ人・大江健三郎が
地元に語り継がれてきたとされる(ホントかな?)伝承を
モデルとして書いた小説作品
具体的な地名は伏せられていたり変更されていたりして
いちおう創作のスタンスを保っているが
もろもろから察するに
宇和島藩の城下町を追放となったならず者たちが
宇和海賊の娘から船を借り
佐田岬半島を迂回して肱川河口からさかのぼっていって
新天地を発見するといった筋書きだろう
ならず者のリーダーは「壊す人」と呼ばれ
神がかり的な力を発揮する
また
村の創建者たちが「故郷でありふれた人生を送っている自分」を
夢に見ながら消滅するというエピソードには
アナザーワールドの可能性も感じられるのだった
やがていろいろあって、なし崩し的に
外の世界と併合されてしまった村は「二重戸籍」のからくりによる
税金のごまかしが露見したことを発端に、大日本帝国との
全面戦争へ突入する
Mとはメイトリアークの頭文字で、母なる存在を意味し
Tはトリックスターを示している
「森のフシギ」は、森にさまざまな怪現象をひきおこす謎の存在
それはときおり音というかたちで顕現し
最終的には
新時代のトリックスター・語り手の息子(大江光)によって
音楽へと昇華される
まあ、大江が我が子を不憫に思う気持ちは伝わってくるのだけど
オウムと少年Aの時代を経て
ふたたび検証されるべきところはあるだろう
Posted by ブクログ
今までにない魅力のある本。四国の山間の村に伝わる神話と幕末の歴史及び、作者が何故これに深く関わるか?が書かれた本。
作者が神隠しに会い、神秘的な体験を通して、村の物語の継承者として選ばれた理由。また、作者の知能障害の息子と村の繋がり。
人の一生は産まれたときから死ぬときではなく、「かれがふくみこまれている人びとの輪の、大きな翳のなかに生まれてきて、そして死んだあともなんらかの、続いていくものがあるはず」というメッセージが美しく響く小説
Posted by ブクログ
こんなにも自由なイメージを喚起させるように描けるものなんだなぁと感心しました。
おとぎ話風の語りですが、森の中は村人達だけでの裁判(昔から限界状況での自治ってモチーフはよく出ますね)や、なんだか超絶に大きな人がいたり、少年としての著者が出て来たり。
少し異色ですが、個人的には好きです。
あの、「どこか木のうろからブーーンという音がして」とか
そういうイメージの植え付けは素晴らしいと思います。
絶対にない、しかも新しい物や気分を教えてくれる点では翁は素晴らしいと思います。
海外不条理映画とはちょっと違う。
D.クローネンバーグ的といえばそうなるかも知れません。