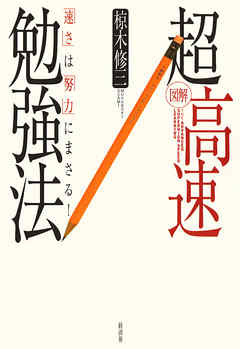感情タグBEST3
Posted by ブクログ
横着に勉強をして成果を上げるための「勉強のしかた」を伝授するための本です。
速読と精読はどちらがいいかと考えてしまいますが、全体を理解するための勉強の本は、どちらかというと速読を何度もくりかえしながら学習したほうが効果的であるという主張に賛成です。
ぼんやりと全体を理解することは、著書もいっていますが、効果があると思います。小説は精読でいいと思います。大書は、何回かぼんやり読んだあとに、精読してもいいかなと読みながらそう感じました。
気になった点は、以下です。
・心から欲していなければ、本気でなければ、実現力はぐんと落ちます。モチベーションは高まらず、集中は持続せず、勉強が進むはずはありません。
・超高速勉強法の第一歩は、集中力の養成と持続です。集中力に最高の効果があるのが、自己暗示です。
・自分に暗示をかける暗示語は、特別な言葉でなくてかまいません。①行動が変わる言葉、②行動に移せる言葉、③行動が増す言葉、でさえあればいいのです。
・永平寺でまず、修行僧に教えることは、「我見を捨てよ」だそうです。よけいな字がを切り捨て、ひたすら、「形」の中に自分をはめていくのです。自分を否定し、否定しきって、なお、最後に残るのが、仏教でいう「真の自己」というわけです。
・ピカソは、「目に見えるいっさいのムダを切り捨てて、最後に残ったものが真の芸術である」と喝破したといいます。
・言葉やイメージは、具体的でなければなりません。
・あれもこれもと意識を分散せず、これだけは確実にやるものにしぼってやること。
・努力すればするほど悪化する これを、「努力逆転現象」といいます。
・「いいかげんにしよう」という暗示語を使うとよい。「いいかげん」とは、本来「ほどよい」というプラスの意味です
・「長い時間」より「多くの時間」を見つけよう
・一般的に人間は、時間通りにピタッと終わらなければ、あとは、ズルズルとなりがちです。そんな非効率的な時間をすごすより、目標に達してなくても、時間がきたらピタリをやめましょう。
・読書時間は、主に次の5つです。①朝のトイレタイム、②出勤時の電車、③昼休み、④帰宅時の電車、⑤就寝前のふとん
・チャンスは「人と違う」ことにある
・わからなくてもいいから前に進む です。短時間に試験に合格するとか、専門知識を高速で蓄えるとかの場合の、前倒し勉強法です
・凡事徹底:平凡なことを徹底してやることで、非凡な人間になれるという意味です。
・記憶力を高めるには、「記憶する前に、まず整理する時間をつくる」ことが大切です。
・わかったことはおぼえらます。でも、わからないことでも、①共通点はないか、②どこかに法則はないか、③どこかパターン化したものはないか、などで覚えることができます。
・テキストは、薄いものを使う
・勉強をする時も、自分は、プラス思考が強いのか、マイナス思考が強いのかで、勉強の計画の立て方は違います。プラス思考が強いタイプは、不得意分野を優先、マイナス思考の強いタイプは、得意分野をまずやって自信をつけてから不得意分野をやるのがいいです。
・継続は力:わからないものはわからないままにしとけといっているのではなく、めげずに継続していくことでわかる日がやっているということです。
・脳は使えば使うほど進化する
・勉強嫌い:心理的抵抗感があれば、知識は定着しない
・楽しいことは続けられるシステムにする。①わかる⇒②できるで自信をもつ⇒③できたという達成感⇒④だから、おもしろい、
・前半を速読すると、後半を想像することができるようになる。あっていようがいまいが、想像すれば、記憶が固定化して知識として定着していく効果がある
・記憶力を増強する4つの絶対法則 ①反復する、②関連付ける、③整理する、④思い出すクセをつける
・シンプルな勉強法 ①問題集一冊のみ、②機械的にやる、③テキストは必要なところだけ目を通す
・記憶ポイント ①鉛筆は、Bか2B,②問題集は、試験まで最低5回くりかえす
・要領の悪い人は全体が見えていない
・速読の基本は、わからなくても読破する
・本の読みかたは、5通り ①素読、②精読、③熟読、④瞬読、⑤速読
・早く理解したかったら、図解せよ
・勉強法として、「くり返し」はいいが、「時間延長」はいけない
・速読速解ができる人は、視読力がつよい。視読とは、文字を音声化することなしに、理解する力である。
・迷う人は本番に必ず弱い
・凡事徹底をするには、①平凡さ、②シンプルさ が大切
・ど忘れ防止法、勉強したら十分に眠ること、これだけでかなり効果がある。それと、きっかけになるものを用意する。「基礎結合法」という。
・自分はここが限界といえは、そこが限界となる。だめでいいからやってみる。できなくていいからやってみる、ムリでいいからやってみる。と考える。
目次
はじめに
1章 「あせり」をうまく使え
「成功暗示」から始めよう
怠け心を封じ込める
「無力な努力」をなくしていく
集中力の疲れをこまめにとる
2章 「長時間」の損に気づこう
終わらなくても定刻でやめる
「みんなも」発想を嫌え
準備に時間を使うことで時間を増やす
3章 「平均点」は上げなくていい
「自信をつける」を指針にする
頭が固くなったと誤解している人に
「瞬間理解力」を深めよう
4章 「目次」を暗記せよ
教科書より問題集が記憶には効く
「逆に考える」ことで回路が太くなる
おぼえにくいものをおぼえる法
5章 「わからない」ままを恐れるな
自分を「多読家」につくり変える
速度を上げて理解度を下げないために
常に「いいスピード」を保つ
6章 頭はリラックスでより強くなる
「要領力」をつけよう
「ど忘れ」防止法
速く回復する頭になる
これで「合格力」に絶対の自信がつく
おわりに
Posted by ブクログ
作者の経歴とかレビューとか一切見なくて良いから、とにかく読んでみて欲しい。先入観なんて持たないで、バカ正直に適当に読み始めると案外引き込まれる。受験生、とくに浪人生におすすめ。学校や塾では当たり前過ぎて教えてくれないような勉強への「姿勢」を教えてくれます。そしてそれを実践させてくれます。自分は後10回は熟読すると思う。
Posted by ブクログ
勉強が苦手と思っている人に勇気をくれる本。不器用でも不器用なりに自分にあった勉強法が探せ気るがしてくるし、自分の動きを変えてみたいと思える。何度か読み直してみたい。
Posted by ブクログ
一通り読んで、「なるほど」と思う部分がかなりあった。
ちょっと試してみたくなる方法もたくさん。
勉強に近道はないと知って、淡々と継続するのが いいんでしょうね。
Posted by ブクログ
・テキストは薄いもの
・パワポで1日10問自分の問題集作り
・新聞コラムトレーニング
・章決め 機械的に
・ペンキ屋方式
・問題、解答、理由、例外
・目標と願望の違い
・はりつけ法
いままで勉強の仕方を教わった事が無かったので、非常に読んでよかったなって思える一冊。
いままでなんとなくわかっていたことがこのように本になっていることで、自分の中で言語化することができた。その結果、勉強に対する自信が深まったように感じる。
あとは実践するのみ!
Posted by ブクログ
とりあえず参考にすること。
勉強法に関しては複数書籍よんでいる。
この本は多分2.3回読んでるけど、改めて読んでみるとほとんどが記憶になく新しいもののように感じた。
※一度もアウトプットしてない。
・自己暗示
・勉強のあれこれ(複数テキスト等)をなくす
→他の勉強法のサイトで二冊くらいならいけんじゃね。って言ってる上に、自分も二冊くらいまでならいいだろって感じなので二冊までとする。
・じっくりは言い訳
→これは同感。勉強期間を長く取ってじっくりとか言ってるのは完璧主義者のやることだ。
資格勉強真っ最中だが、以前長期間取って勉強したおかげで、最初の方にやった勉強は余裕で忘れてた。
大切なのは短期で勉強して復習回数を増やすことだ。
Posted by ブクログ
勉強法の様々なノウハウをぎゅっと詰め込んだ本。
これまで色々な勉強本、ブログ等を読んできたけど、
そのほとんどがこの一冊に書かれている印象。
①集中力を保つための時間配分
②勉強計画の立て方
③記憶の保持の仕方
④メンタル面の整え方・細かいテクニック
大まかにこの四つの観点で書かれているのかな、と。
切り口やテクニックがいろいろありすぎて、
全部一度に取り込むのは混乱しそう。
以下は個人的に実践するための、忘備録。
★勉強の基本
効率のいい勉強とは、「集中力を最大限保ち、かつ、
記憶への定着が良い勉強」ということ。
長時間だらだら続けたり、
教材が沢山ありすぎる、などの状態は
集中力低下につながり、
その結果、勉強時間の無駄な消費や
勉強時間が足りない、といった状態を招く。
時間を決める、教材を決める。
意識を分散させず、確実にやることだけ決めて
取り組むことが、集中力の安定につながる。
この土台の上に、記憶力アップのテクニックが
生きてくる。
★計画の基本
まずは試験日を把握する。
試験日までにどれだけ期間があるのか把握する。
その上で、どの教材で勉強するのか決める。
絞り込んだら、教材の目次を読み、
勉強する内容の全体の流れをつかむ。
教材が全部で何章あるのかを把握したら、
それをいつまでにやればいいのか、
月、週、日単位で割り振る。
こうして締切りを設定することで、
1ヶ月あたり、1週間あたり、1日あたりの目標が
明確になり、集中力を生む。
立てた計画通り進めていないのなら、
勉強計画の再考が必要。
一日の予定と実際にどんな差異があるか。
計画に無理はないか、プライベートや睡眠の時間も
ちゃんと確保出来ているのか、
要はメリハリつけてストレスためずに
取り組めているのか、といった点も
勉強に集中して取り組む上で大事。
★記憶の基本
・反復する、関連づける、整理する、思い出す、
が基本。
・記憶+想起=勉強時間。
整理
・共通点や法則、パターン化出来るならする。
・文章で覚えるのではなく、図や表にして整理する。
関連付け
・身近なものや言葉に紐づける。
・勉強した知識通しの繋がりを見つける。
思い出す
・自分で問題を作って解いてみる
これらを反復する。
さらに、以下の点も注意。
・長時間ではなく短時間。
記憶に20分、想起に10分のセット。
・瓦屋式ではなくペンキ屋式のイメージで覚える。
細かい知識から詰め込むのではなく、
大枠や概要をざっと理解した上で、細かいところを
補填する。
・プレッシャーは記憶の邪魔になる。
努力しよう、しようと思うほど、
それがプレッシャーになり、
交感神経を強く刺激する結果、
自律神経が乱れて集中力が低下する。
音楽流しながらなどで
適度にリラックスしながらやるとよい。
Posted by ブクログ
実は勉強法に関する本を読むのは人生初かもしれない。
とりあえず内容がわからなくても問題集を解き進めるという勉強法は、新鮮な考え方でありつつもそういえば仕事を覚えるプロセスに似ているなぁと思ったりもした。
まずは今やっている資格勉強で実践してみよう。
Posted by ブクログ
マインドマップ的読書感想文でのベストセラーらしく読んでみた。
勉強法を知りたいという切実な状態ではなく、将来娘のために勉強本を一冊選びたい、という動機で読む。
そういう意味で、本書のターゲットは、学生だけでなく、社会人も広く対象としており、重要視しているのは、勉強したいという意欲であり、目的である。
その点が少々不満。
・教材はできるだけ厳選して。少なく。
・能力開発に役立つクラシック音楽リスト
・勉強時間=記憶時間+想起時間。思い出す時間が必ず必要。
・間違った箇所は、消さずに、正解を書き直す。
・目次を暗記して、全体の中での立ち位置をつかむ。
・朝型に移行するためには、12時前に寝ること。
・勉強したらさっさと寝る。
[more]
(目次)
1章 「あせり」をうまく使え!―集中力が自然に増強するテクニック
2章 「長時間」の損に気づこう―常に良質な勉強時間を保つコツ
3章 「平均点」は上げなくてもいい!―自信一つで合格力は十分に高まる
4章 「目次」を暗記せよ―データは形さえ整えば大量におぼえられる
5章 「わからないまま」を恐れるな―速読術を訓練なしで身につける法
6章 頭はリラックスでより強くなる―疲れない頭になる意外な生活習慣
Posted by ブクログ
勉強の目的を明確にする。暗示語にする。それを思えば勉強したくなる。
あれもこれも、ではなくこれだけは確実にやる、ものを決める。それと月割り、週割、日割りにする。
集中できるのは最初の30分だけ。
雑念は犬と同じ。逃げるから追いかけてくる。ながら勉強。聞き流すだけ。覚えようとはしない。アナログ時計の音を聞く。
部屋をきれいにする。観葉植物を置く。
クラッシック音楽
不安感の解消=ショパン/スケルツォ第1番、ブラームス/ハンガリー舞曲第5番、ブラームス/交響曲第4番第2楽章、ドヴォルザーク/チェロ協奏曲第2楽章、モーツアルト/ピアノ協奏曲、
記憶力向上=バッツィーニ/要請の踊り、ヘンデル/ラールゴー、バッハ/G線上のアリア、パルティータ、
集中力強化=チャイコフスキー/憂うつなセレナード、バッヘルベル/カノン、ヘンデル/ラールゴー、メヌエット、チャイコフスキー/ヴァイオリン協奏曲第2楽章、
自身をつける=チャイコフスキー/交響曲第6番悲愴第1,2楽章、ベートーベン/交響曲第9番第1,2楽章、ワーグナー/ロー円グリーン第1幕への前奏曲、ジークフリート牧歌、
何かを覚えるには最低20分間。10~20分で覚えて、5~10分で想起する。勉強は記憶と想起が含まれていなければならない。
太く短く、ではなく細かく長く、勉強する。
20分経ったら途中であってもやめて、想起に取り掛かる。
時間を切ってやめることが悔しさにつながる。
チャンスは人と違うところにある。時間差出勤、辛いと思うものは面白い、と思う。失敗しても落ち込まない。人が困難や苦痛を感じるとき、自分は乗り越える喜びを発見する。
わからなくてもいいから前に進む。
わからないことは覚えにくい。覚えることは理解して整理すること。記憶術は整理術。
記憶のためには、反復、関連付け、整理、思い出す癖をつける。
これ一冊、のうすい問題集を使う。問題集が主、テキストが従。鉛筆で何回も繰り返す。
5回反復法。3回目から仕上げ、5回目で完成。
自分で問題集を作る。パワーポイントで一日10題。
形から入る。完全主義のワナに気を付ける。
繰り返しの魔術=最初は速読5分、2回目はじっくり30分、4回目は重要語句を、4回目は思い出す。時間延長はしない。
新聞コラムを書き写す。半分読んで残りを予想する。コラムのタイトルをつける。
2桁数字変換表=2桁の数字で語呂合わせを作る。
記憶の呼び水=モノに記憶をアンカリングする。
マーカーで色分けする。問題は赤、解答は緑、理由は青、例外は黄色。例外は受験のヘソになる。
勉強したら寝る。
自分を信じる。モハメドアリは自分の手を眺めては「この手の中に何かあるはずだ」と思い続けた。
ダメでもいいからやってみる。できなくてもいいからやってみる。
身のほど、は高く持つ。
創造的生活チェックシート=課題と毎日のチェック欄のあるもの。
Posted by ブクログ
この手の本が必要な人にはお勧め。
問題集5回反復法。1回目回答を見ながらともかく最後まで解く。2回目回答を見ながら解く。最後まで読破する。わからない単語のチェック(テキスト参照)。3回目自分で問題を解く。わからない問題に□をつける。何をなぜ間違ったか、何がわからなかったのかをチェック(ふせん?)。4回目□のついた問題を中心に解く。出来たものは半分塗りつぶす。出来なかったものは□そのまま。テキストなどで再確認する。5回目□と半分塗りつぶした□をやる。4回目でできて5回目もできたものは■にする。時間があれば□と半分塗りつぶしについて勉強し、6回目やる。わからない箇所があってもいいから回答を見ながら最後までやり通し、(その人にとっての)テキストの主要部分をつかみ、攻略する。
1週間前にタイムスケジュール確認。計画チェックシート。12時前に寝る時間調整。体調を整える。朝食、昼食後の昼寝。
Posted by ブクログ
【忘備録(引用)】
・わからなくてもいいから前に進む
・凡事徹底
・機械的にやる。感情を使うなということ。
・最初は大雑把に記憶し、だんだん記憶を固定していく。
・要領の悪い人は全体が見えていない。
・速く理解するには早く図解せよ。
Posted by ブクログ
言っていることはほぼ「7回読み」と同じような感じと感じる部分もありました(明らかにこちらの方が先行でしょうが)。自分の勉強の仕方には非常にfitしそうです。
Posted by ブクログ
勉強のための勉強本として大変参考になります。勉強する方法から勉強に取り組む心がけまで網羅されています。この本で学んだことを活かして、本来の勉強に活かしたいものです。
Posted by ブクログ
速読から自己暗示まで幅広く超高速勉強法についてまとまっている本。特に目新しい知識はないが、改めて読むと色々と忘れていて、知識が生かせていないなーと反省しつつ、再度試してみようと思う。
Posted by ブクログ
かなり売れている本らしいので購入。精神論や根性論に陥らず人間の弱さをちゃんと分かっている人が書いた勉強法の本。勉強をする上で土台となる考え方のように思うのでこういうことを学校で教えて欲しかったです。特に意識したいことは以下7つ。資格の勉強とかしたくなりました。
①具体的に勉強の目的を考える
②勉強=記憶+想起なので想起訓練必須
③完全レベルを下げる
④分かるところからやってエンジンに
⑤問題集はざっとやって5回反復
⑥テキストから読むのではなく問題から解く
⑦分からないのは気にしない。止まらないこと。
Posted by ブクログ
【概要】勉強術(やる気・記憶・速読)のコツの宝庫
【感想】具体的なコツが多数あり、すぐに実践できそう。主張を絞り込んで薄い本にすれば爆発的に売れる予感
○
・終わらなくても定刻でやめる
・記憶の四法則(反復・関連付け・整理・想起クセ)
・その他、工夫は多数あり
×
・目次と内容が合わないのが残念
Posted by ブクログ
勉強のノウハウが負担無く読めるようよくまとめられている。
受験向けであったり、日頃から意識いれば特筆することではない項目もあるので、取捨選択は必要か。
この中だと、簡易な速読術は利用している。
Posted by ブクログ
自分に暗示をかける暗示語は、特別な言葉でなくてかまいません。 ①行動が変わる言葉 ②行動に移せる言葉 ③行動が増す言葉 でさえあればよいのです。 言葉は思い(念)を強めます。念の強さは行動の変容をうながし、驚くほど集中力を高めてきます。簡単にいえば、念の強さと集中力は比例するということです。 その意味からすると、暗示語は何でもよいといえます。中でも、「見返してやる」「やってやる!」「気合いだあ ~っ」 などといった「生身の言葉」が最適といえるかもしれません。
  三分割する場合は、勉強時間は二十分間、記憶時間が十五分間、想起時間が五分間、勉強科目は三科目です。 ◆「やらねば!」より「やめたら?」で発想しよう ここで、一時間二分割二科目の勉強のエクササイズをしましょう。 わかりやすいように、次の空欄に記入してください。 ①( )を( )ページから( )ページまで勉強する 記入したら、そのページを二十分間勉強します。
自分の勉強の中に「楽しいことは続けられる」システムをつくればいいのです。 ①「わかる」から始めるシステム ②「できる」という自信を持たせる流れ ③「できた」という達成感を持てる仕組み ④最後に「おもしろい」という興味と動機をうながす これに沿って勉強をしていけば、ランナーズハイのような快感物質が脳内に出て、「勉強は大変だけどやりたい」「勉強はおもしろい」といった感情を持つようになるのです。
二回反復だけでは、あいまいな部分が残り、急場はしのげますが、記憶の固定には届きません。三回目、四回目に、記憶の固定化が急速に進み、五回目には、簡単なことがらなら、確実に記憶できます。
Posted by ブクログ
学生向きのような体裁だと思っていたが、後半がなかなか面白い。当たり前のことだが、シンプルに言い回してある。
そして一番の障壁は実行に移せるか。これは平凡に毎日コツコツとしかない。どんなに気分が乗らない日でもコツコツと。
じっくりは凡才のいいわけ
迷う人は本番に弱い
速さはあなたの人生を変える
目の前の小さな目標をやり通すことで、とんでもないことができるようなになる。Byイチロー
Posted by ブクログ
①集中力を増すコツは?
・部屋の掃除+観葉植物
・音楽活用
・20-30分の隙間時間で勉強
②良質な勉強時間のコツは?
・ながら勉強法
③気づき
・試験は要領
・ピカソ「目に見える一切の無駄を切り捨てて、最後に残ったものが真の芸術」
・週1回2時間より、15分毎日の方がよい
・継続は無理のないように
・記憶術は整理術
・プラス思考の人⇒不得意分野の勉強優先
・マイナス思考の人⇒得意分野の勉強優先
・理解力は頭の状態より心の状態
・記憶は反復
・学校では勉強を教えてくれますが、勉強のやり方は教えてくれない
・× テキスト理解⇒問題解く⇒テスト
・〇 問題解く⇒テキスト理解⇒テスト
・勉強後は寝る
Posted by ブクログ
タイトル通り効率的な勉強法の話しを展開しているが、奇をてらった感はなく、正当派で参考になる本だと思う。
ただ、いろんな本を読んできた自分としては既知の内容が多かった。情報の整理をいかに行うか、いかに時間を捻出するか、どのような順序で何を優先して行うべきか、また速読の考え方、などなど、まっとうな内容が記載されている。
<メモ>
・集中力の付け方 瞑想法 一点集中法 呼吸法 リラクゼーション法 道具法 時間設定法 自己暗示法 筋肉弛緩法
・凡事徹底 平凡なことを徹底してやることで、非凡な人間になれるという意味。
・整理法の一つ 文章を図にすること
・心の姿勢は体の姿勢をつくり、体の姿勢は心の姿勢をつくる。
→形から入ることで自信がつくこともある
Posted by ブクログ
基本的な心構えなどについて書いてあった。
試験日を目標として紙に書く。
全体予定表と月間予定表を作る。
そういったことから始めようと思う。
Posted by ブクログ
ある書評ブログのアフィランキングで3年連続トップ3にに入っているというのでどんなものかと気になって購入してしまった。
内容は当たり前のことばかりだったが、勉強法は意識することが大切であるので、そういう意味では得るものはあった。
こういった類の本を読むのは受験生以来で、タイミングはよかった。
Posted by ブクログ
全体的にオッサン臭く、どこかで聞いたような内容だったが
心に残ったことが若干あったのでまとめておく
・ゆっくり読んでも早く読んでも理解度にそれほど差がつかない
1回ゆっくり読むより、早く3回読むほうがよいことが多い
試験中もそれくらいのスピードで判断することが求められるので
日頃から早く処理することに慣れておいたほうがいい
・勉強で重要なのはインプットよりもむしろアウトプット
必要なことを必要なタイミングでアウトプットできるようになることを意識する
・20分などの細切れの時間でも集中すれば成果は出せる
Posted by ブクログ
どちらかというと速読できる本だと思う。
聞いたことのある、考えたことのある勉強法を整理するために便利な本。ただし、成果が上がるか否かは自分自身の実践にかかっている。
Posted by ブクログ
勉強法に関する本はたくさんありますが、ある書評サイトで高い評価だったこの本を読むことにしました。
近いうちに、資格を勉強するわけではありませんが、このような知識はどんなときであっても参考になるものです。
この本は、スピードを優先にした効率的な勉強法を紹介するものであり、限られた時間の中で結果を出そうとする人には、結果に直結するノウハウがつめられています。
単なる勉強法にとどまらず、記憶術や速読術にも言及しており、実践的な1冊といえるでしょう。
特に、時間設定については非常に参考になる内容でした。
今後、本当に勉強をしなければならない場面になったら、ぜひ実行してみたいと思います。
<この本から得られた気づきとアクション>
・何事にも時間の有効活用が最重要ポイントとなる
・集中力の低下を考えると、最初からテキストを読むのではなく、逆から読むことも行ってみる
・詰め込むだけでなく、思い出すための時間を意識的にとる。これはアウトプットを意識した読書にも通じるかも
・最低限の速読の技術は、知的作業の基礎となる。本書指摘のように意識すべき。倍の早さで2回読んだほうが理解度が高まるという考え方は応用できることが多い
<目次>
1章 「あせり」をうまく使え!―集中力が自然に増強するテクニック
2章 「長時間」の損に気づこう―常に良質な勉強時間を保つコツ
3章 「平均点」は上げなくてもいい!―自信一つで合格力は十分に高まる
4章 「目次」を暗記せよ―データは形さえ整えば大量におぼえられる
5章 「わからないまま」を恐れるな―速読術を訓練なしで身につける法
6章 頭はリラックスでより強くなる―疲れない頭になる意外な生活習慣