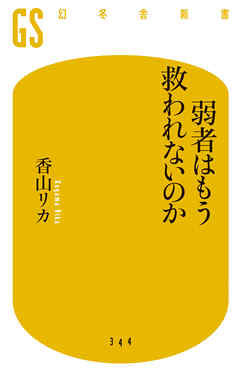感情タグBEST3
Posted by ブクログ
著者が子どもの時分の回想から、現在日々の診察室で感じる格差の拡大。
そもそも明治時代の中葉までは、貧民という概念は存在すらなかったらしい。高度成長からバブル、新自由主義へと弱者の切り捨てに至る時代の変化。
自分自身の思いを問い詰め、リベラル知識人の責任や、そもそも弱者を救済すべき根拠があるのかにまで思いを馳せる。宗教それとも倫理であろうか。
弱肉強食の適者生存で進んできた今日、答えは見つからないとしつつ、それでも我々は手を差し伸べてきたと結ぶのである。
Posted by ブクログ
困ってる人がいたら、傷ついている人がいたら、助けたい、なんとかしたいと思うのは当たり前で自然なことじゃないですか、という結論。
大道廃れて仁義あり、を思いだす。
Posted by ブクログ
「弱者切り捨て」のグローバリズムに席巻された新自由主義の潮流の中で、「自由と公正を柱とする福祉国家」のモデルは崩壊してしまうのか。
「弱者にやさしい社会」が失われつつあることを危惧する著者が、精神科医としての実体験も交えながら「『神なしのヒューマニズム』は果たして可能か」「なぜ、弱者を救わなければならないのか」と問う。
「大きな物語の終焉」に際して、「新しい物語」を求める社会の要請に応えられなかった自身を含む「リベラル派知識人」の不作為責任を指摘する第3章は必読。当時「わかってくれるクレバーな人にだけわかってもらえればよい」という著者が抱いた印象は、そのまま日本の教会が固持してきた姿勢にも適用できる。
小樽で教会学校に通い、キリスト教にも親近感を覚え、教会にもたびたび足を運びながら、洗礼を受けることには抵抗を感じてきたという複雑な胸の内が読み取れる。
著者自らが導き出した最後の結論は、実にシンプル。「弱い人や困っている人を救うのに、理由なんて何もない」。(松ちゃん)
Posted by ブクログ
香山リカさんの実力が垣間見えたような、そんな感じ。
いつものふわっとゆるく、やさしいメッセージをくれる本とは一味違う。タイトル、目次を見ても、そんな感じは最初からしていたけど。
前半はいまの日本がどのような状況にあるのかを書いていて、後半から「他者を救う意味」というところを宗教や哲学の立場から検討していて、まさにこの後半がおもしろい。
最終的には、「ひとを救うことに理由はいらない」やって、ポップな結論ですが、これがすごく好きでした。
Posted by ブクログ
はじまりは前橋市に届いた伊達直人のランドセル。最終的には、全国で何千人もの伊達直人が現れ、恵まれない子供たちのため善行に走った。最初にランドセルを贈った伊達直人は決してお金に余裕があったわけでもない。不幸な境遇にある子供たちの力になりたいとの一心に突き動かされての行為であったという。東北大震災では車椅子の女性を助け、自身は津波に流された女学生もいた。本書では精神分析、思想、経済、様々な視点からわが身をさしおいても弱者を救済する行動について論考する。あとがきには社会的公正や恵まれない子供たちのため世界を飛び回るドゥダメル氏の言葉が引用されている。「弱い人や困っている人を救うのは自然で当然のこと。理由などない」。けだし胸いっぱいに広がる清しい名言である。
Posted by ブクログ
社会的弱者救済を実現しようとしてきた戦後日本が、世界的潮流およびグローバル化の流れの中で、弱者切り捨て、弱者の自己責任へと、舵を切ろうとしている、と著者は指摘する。
そして、内外の著作を取り上げ、弱者救済の理屈付け、理論づけを探求するが、いずれも正解といえる答えは見いだせない。
最後は、理由なんてない、と爽やかに言い切る覚悟を持てるかどうかだ、と結論付ける。
常に、社会的に弱い立場の人、努力しても報われることの叶えられない人、の心情を忖度して発言する著者の姿勢に、敬意を表したい。