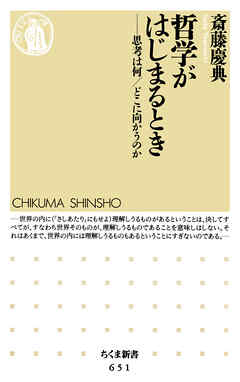感情タグBEST3
Posted by ブクログ
思考とは反復であり、反復の中核をなすのは偏差(ずれ)である。
「思考とは何であるか」と問うことに始まり、哲学の意味、存在や時間などの形而上学について細分化され書かれている。
最初は具体的な例も挙げられていて内容を理解することが出来たけど、徐々に抽象的な話になってきて完全に消化出来なかった。
ぼんやりと考えていたこと言語化すると、こんな風になるのかなぁと思った。
でもやっぱり今の私には少し難解なので、もう少し哲学に深く踏み入れることが出来るようになってから再読してみたいと思う。
Posted by ブクログ
著者が、「哲学」と呼ばれる思索の営みの始まりから、「存在」そのものを問う形而上学への歩みを読者の前で実演して見せた本です。
著者は、世界に対する当惑から「どうして?」という問いが始まるとき、「哲学」と呼ばれる営みが開始されることになると論じています。「どうして?」という問いは、理由や根拠、意味や本質への問いかけを含んでいますが、とりわけ「存在とは何か」という世界全体への問いかけがおこなわれるとき、われわれはそれを「形而上学」と呼ぶと著者はいいます。
その上で著者は、「存在とは何か」という問いは果たして可能なのだろうかと、改めて問いかけます。ライプニッツは「なぜ世界は存在するのであって、むしろ無ではないのか」と問いましたが、パルメニデスが主張したように、「あるものはある、ないものはない」のであれば、「無とは何か」と問うことができないように、「存在」そのものを問うこともできないように思えます。しかし著者は、そのような仕方でわれわれは「存在」の外部の「無」に触れてしまっているのではないかと反問します。
さらに著者は、パルメニデスにしたがうならばけっして移ろうことも分割することもない「存在」の中に、時間と空間、さらには概念の象りによって「距離化」ないし「疎隔化」が生じて、「あるものはある、ないものはない」という空虚な充満でしかない「存在」の中に「何か」が生まれてくる機序を解き明かします。そのうえでカントの「超越論的統覚」に関する思索を手がかりにして、そうした「何か」が生まれてくる場に居合わせる「私」のあり方を論じ、西田幾多郎の「場所」の思想を手がかりにして、「何か」が「私」や「他者」たちによって述語づけられることでそれが「何か」を十全に示すようになることについて考察を展開しています。
本書を通じて、「存在そのもの」を問う思索の「途方もなさ」に触れることができたような気がします。