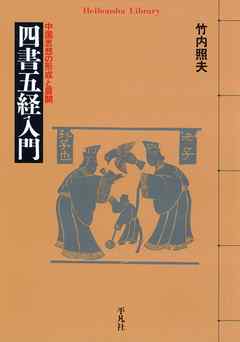感情タグBEST3
Posted by ブクログ
四書五経を勉強しようと思い、勉強を始める前にまずは入門書を読んでみました。
本書では、以下の順番でそれぞれに何が書いてあるかの概要がまとまっています。
書経、易経、礼記、詩経、春秋
論語、孟子、大学、中庸
また、中国や日本でどのように四書五経が歴史的に位置付けられてきたのかがありました。
これは、結構面白いです。
日本では、素読を通じて、幼少の頃から勉強されてきたとありましたが、四書五経の素読ってなかなかすごい勉強法だったんだなあと思いました。
実際に四書五経の勉強を始めて少し時間がたってから、この入門書の価値をいつか改めてレビューしてみようと思います。
Posted by ブクログ
この本で紹介されている四書五経は
四書・・・『論語』『孟子』『大学』『中庸』
五経・・・『書経』『易経』『礼記』『詩経』『春秋』
一つもまともに読んだことがない。
恥ずかしいかぎり。
Posted by ブクログ
題名通りの入門書で,それぞれの書物についての要点についてまとめられており,成立した背景から理解することができる。多数の人々に染み付いている思想を知る第一歩である。
Posted by ブクログ
四書五経の全体像を俯瞰できるところが良かった。『論語』ばかりが取り上げられることが多いが、それぞれ役割をもっており、全体で一つということがよく分かる。そもそも『大学』『中庸』は『礼記』の一篇だったことからもそれが分かる。
四書五経が日本、中国の思想史に与えた影響の章はなかなかの読み応えがあり、これだけで十分一冊の本にできるぐらいの内容があった。日中共にかなりの影響を受けているが、日本においては既に日本的な考え方がほぼ固まっているところに、朱子学、陽明学として四書五経の考え方が入ってきたこともあって、相当の影響は受けているものの、上手く受け流している印象がある。一方で中国は染まっているといっても過言ではない。殷、周のころから儒者が普及に努め、隋で科挙となり、それが清まで続いたのだから染まっていないはずがない。また、四書五経が絶対視されそれ以外の考え方を拒絶する態度が近代化を遅らせたという指摘は、日本の明治維新と対比させてみるとそれなりの説得力がある。
四書五経をどう読むか。それは成立についてのかなり面倒な状況を見れば明らか。散逸、紛失、焚書を経て記憶を元に再編集され、『論語』の朱註のように註釈が重要視され、その註釈に註釈が付くような状況。さらにその註釈もあらゆる文に解説を付け意味をもたせてしまっている厄介さを併せ持っている。そして科挙に組み込まれるに至り為政者の思惑も入り込んでいるであろう。そのため現在読むことのできるこれら文献は書いた本人の意図をどれだけ伝えているか定かではない。元の文が失われている以上は目の前にある文を読むしかない。四書五経をどう読むか。まずは感じたままを受け入れるのがいいだろう。どうしても分からなければ註釈を読むのもいいが、そういう考え方もある、という程度に留めておくべきだろう。
Posted by ブクログ
「美しい妻がほしいならば、読書するがよい。」
いわゆる四書五経について簡単に説明している本。
これを読み、興味を持った書物を読むのも良いと思う。
読み応えがあり、また、新たな興味を喚起する本である。
Posted by ブクログ
・その人の以(な)す所を視、由る所を観、安んずる所を察すれば、人いずくんぞかくさんや、人いずくんぞかくさんや。
(まず行為・行動を見る。次に行為の動機を調べる。次にその人が真に楽しみを感ずるらしいのは、何に対してであるか、どうした時においてであるか、生活の根本信条を見る。)
・人の過つや、各々その党に於いてす。過ちを観てここに仁を知る。(党は類で、類型とか性格とかの意。過失を犯すにしてもそこに人物の特徴がでるものである)
―この二つは人を観るのに至言ですね。人を見るには背中を見よと言った経営者がいましたが、言葉や顔立ちや表情に気を取られるから本質が見えないのかも知れません。正面から見ると動きが大きいから逆に騙されますね。