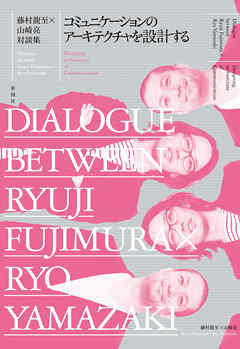感情タグBEST3
Posted by ブクログ
藤村さんと山崎さんの違いに興味を持ちましたが、本書ではそれほど深く追求されてはいません。広義の目標は共通でも、方法論やスタイルにおいて違う点があると感じますし、その違いを中心に今後もお二人の活動に関心を持ち続けていきたいと思います。
Posted by ブクログ
studio-L山崎さんの対談本。政治とアーキテクトの取り組んでいる課題は、共通点もある割にアウトプットの美しさが異なってしまうという点は、実はIT業界でもアウトプットへのこだわりという部分では近いものがあるかなと思いました。あと、お金は関係性を切ってしまうという点も共感したところで、確かに「これは貸しだからね」「こないだの借りを返すよ」っていうやりとりはお金を介在させないからこそ楽しくなる部分もあるなぁと思いました。自分の伝え方、コミュニケーションの質についてはまだまだケアするべき点がありますね。
Posted by ブクログ
最近ちょっと注目している藤村龍至とコミュニティデザインでおなじみの山崎亮の対談なので、面白そうだと思って読んでみた。
ハードものを作らなくても、地域の課題を乗り越えていく手助けを仕事にしている山崎さんが、「つくる仕事」を知らないと「つくらない仕事」はできない、「つくらない」といってもフィジカルなものは作らないというだけで、クリエイティブという意味ではたくさん創っていると語っていたのが印象深かった。
また、「住民参加」のスキルは相当上がってきているのに、行政側の公共事業への参加の仕方が20世紀型。あたかも公共事業は全部行政ができるかのようにふるまってきた。行政が全部公共的な事業を抱えるというのはほとんど不可能なんなだから、住民にも支えてもらわなければいけない、というのは耳が痛いがその通りだと思う。もっと現場の担当者に裁量を与えて、臨機応変に対応すべきなんだと思うし、そういう方向に向かいつつあるが、長年しみ込んだ組織マインドはなかなか変わらないというのが実感。
それに、建築設計に携わった人は、いったん決めたことは後戻りしないということが染みついているから、住民のワークショップでも、ひとつひとつフィックスさせていって議論を積み重ねて結論を引き出すっていうのは、大事なこと。心しなければならない点だと感じた。
これまでの山崎さんや藤村さんの言っていることと重なっている部分も多々あり、とりわけ目新しい発言をしているわけではないが、それらを再確認するという意味でも面白い対談集でした。
Posted by ブクログ
コミュニケーションのアーキテクチュアを設計する。
「何を目的として」「誰のために」「どうやって」、それぞれについての二人の意見、主張、哲学が悉く異なっているのに、何か共通するものを感じるのは何故なのか。
同じことを繰り返したり、言い換えたり、アプローチを変えてみたり、テーマをスライドさせたり、何というか・・・小賢しい印象が強いです。
二人が歩み寄ろうとしているからこそ、そうなってしまうのでしょうか。
最もしっくりきたのは「物語性」を重視するという点において、二人が楽しみながらそれぞれの仕事をしているし、また建築家やデザイナーは、その部分をこそ語る熱意・技術を持つべきであるというところ。
ハッピーエンド、ネバーエンディングを目指すには、あらゆる箇所を整合、統括させていく必要があって、それこそ建築・アーキテクトだよね、みたいな。
とてもインテリな本でした。
Posted by ブクログ
コミュニティから建築へと進んだ藤村さん、建築からコミュニティへ進んだ山崎さんの、つくることと、つくらないことについての対談集。
学生の頃、有名建築家の設計した建物を見に行き「建築を勉強してるんです」と言うと、たいていそこで働く方が建物の使い心地などを話してくれた。学生だという気安さからか、建物の悪口も多かった。いくら形がカッコ良くても、使う人たちが不便ならば、その建物は存在する意味があるのだろうか?というようなことを考えていたような記憶がある。本書を読んで、その頃のことを思い出した。
すでに建物を建てれば地域の課題が解決できる時代ではないし、公共建築の数は減る一方だ。建築家は、つくらない世の中に恐々とするのではなく、その専門知識と能力をつくらないことにも発揮できるという。そのためには、政治や社会などの広い知識も必要なのだろう。でないと、説得力ないからなぁ。
Posted by ブクログ
コミュニティデザイナー・山崎亮さんと建築家・藤村龍二さんの対談で構成される本である。
お二人とも建築業界の方なのだが読み進めるほど福祉の視点から学ぶことがたくさんあり、今回はそれを簡単にまとめる
●多様な要素を統合してビジョンを描く
ものをつくれば売れた時代は終わり、今は「作る」「造る」のではなく「創る」時代。そんな時代に前者を専門としてきた建築家(アーキテクト)は何ができるのか。山崎さんはこう述べる
テクネ―に、設備や法規や予算を代入して、それらを一つに美しく統合(アーク)していく職能が建築家だと言われてきました。アーキテクトだと言われてきました。しかし、これからはものが建たない時代になる。そうであれば、テクネーの部分に「八百屋のおばちゃんの意見」や「漁師のおっちゃんの意見」「行政の意見」など、ばらばらな意見を代入し、それらを美しく統合してビジョンを示すのも、アークテクトの役割じゃないかなと思うんです。
いろんな要素を活かしてビジョンを示す。
それってソーシャルワークそのものじゃないか!
ミクロソーシャルワークではクライエントの経済・心身・生活状況・ニーズ・社会資源を統合して、クライエントがエンパワメントされるような長期・短期目標を提示する。
メゾソーシャルワークでは多様な価値観や立場、特性から生み出されるコミュニティのビジョンを描く。
マクロソーシャルワークではインクルーシブな社会の姿を具体的に社会に訴え、社会変革を起こしていく。
授業で「ビジョンを描くことの重要性」を言われたことはなくいつもプロセス重視だけど、プロセスをよりよいものにするためにも福祉には「美しくてわくわくするビジョン」が必須だし、ビジョンを描くスキルを身に着けていかなくてはならないんだ。あらゆる要素を統合してビジョンを描くスキルは、建築から学べるのかもしれない。
●福祉はもっとクリエイティブに
むしろ、人のつながりが弱くなってきたために顕在化した問題、教育や福祉の問題にこそ、クリエイティブな発想を取り入れていかないと、「前例に沿って」「制度に従って」という対応策では、教育も福祉も課題を突破できません
p172
なんだか耳が痛い(笑)
ソーシャルワークは長年対人援助が中心で、社会福祉士という国家資格は既存の制度への理解度を図るものでしかないから、福祉分野は今でも「前例に沿って」「制度に沿って」ということが多いと思う
でも今、社会問題がたくさんあるのだから、今にすがったって根本的な解決にはまったく至らない。
メゾ・マクロソーシャルワークにおいてはもっとクリエイティブに、ソーシャルワーカーはクリエイティブな発想をもてるようにならなきゃなんだ
●クリエイターと力をあわせよう
じゃあどうしたらクリエイティブな発想をもてるようになるのか
それは社会課題に取り組むクリエイター、デザイナーの活動を知ることから始まる
「ものをつくれば売れた時代」ではなくなった今、建築やジュエリーやファッションでもなんでも、社会課題の解決に繋げて専門性を発揮しようとしているのだとこの本から学ぶことができた。社会課題を解決しようとする波が広がっているならば、社会課題に取り組むクリエイター、デザイナーは私が想像するより多いし増えていくのだろう
障害者アートは昨今の福祉のトレンドでもある気がするが、それでもまだ福祉とクリエイターの間には距離がある気がする
ソーシャルワーカーはクリエイティビティを学ぶために、クリエイターやデザイナーも含めた多職種連携を図っていくことが必要不可欠だ
Posted by ブクログ
【一:定義・これからのあり方】
アーキ・テクト→ものごとを統合していく仕事。
物質的に恵まれた今後の日本においては
隣人とのつながりを生むための方法を、ものをつくることに限らず創出していくことが必要。
【二:これまでの経緯】
【三:現在の方法】
話を拡散も収束もでき、かつ収束させるべきタイミングで話を固めて、決定を積み重ねていける能力が必要。
【四:これからの教育】
目的のために、手段を使う。
思考的ジャンプと技術力の両方が必要。
エデュケート→人々の中に本来ある価値を引き出す。