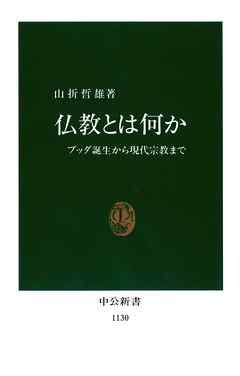感情タグBEST3
Posted by ブクログ
全体を通して日本の仏教界への問題提起がなされているので、知りたいこととズレがあった。
1993年当時の仏教に対する世間の印象と、昨今の仏教ブームとの差異も少なからずあるし、在家からすると自明のことのように感じることが、それこそ大袈裟に書かれていたりもして、世襲坊主、袈裟坊主の連中が読んだら説法も少しは面白くなるんじゃないか。
アリス・ミラーの『魂の殺人』という本は面白そうなので、読んでみたい。
著者の仏教に対する所見を述べた本。
Posted by ブクログ
仏教の歴史や現代的課題について解説しています。民衆の精神史という広い文脈のなかで日本仏教の意義をとらえなおすべきだという著者の観点が、積極的に押し出されている解説書です。
釈尊は入滅に際して、人びとが望むならば長くこの世にとどまって教えを広めようということを弟子のアーナンダにほのめかしましたが、悪魔にとりつかれていたアーナンダは、釈尊の真意に気づかず、その言葉を聞き流してしまいます。彼の態度を見た釈尊は、悪魔の誘いに応じて3ヶ月後に入滅することを決意します。著者は、『大般涅槃経』に記されているこうしたエピソードを紹介し、ここには仏教徒の釈尊に対する裏切りという問題があるといいます。その後の仏教の歴史は裏切りの歴史であり、現代の私たちもまた「アーナンダの徒」として、釈尊の真意を捉え損ねているとされます。そのうえで、「アーナンダの徒」である私たちは何をするべきなのか考えなければならないと主張します。
また、日本仏教の特徴についても、著者自身の見解が示されています。日本仏教の黄金期とされる鎌倉仏教は、親鸞や道元といったカリスマ的指導者と彼らを取り巻く少数のエリート信者による知識人的宗教であり、民衆の生活に根ざした宗教とはいえないと著者は主張します。そして、仏教が本当の意味で日本の民衆に根づいたのは、山岳信仰、他界=浄土観、遺骨信仰との習合がいきわたった15世紀ないし16世紀以降であり、先祖崇拝や死者儀礼を中心とする現代の仏教のあり方のなかに日本人の宗教意識がしっかりと根を張っていることを認めなければならないと主張しています。
Posted by ブクログ
読者の「仏教とは何か」という問いに応えようという本ではなく、
著者が思い描いている「仏教とは何か」について書いた本だと思う。
仏教についてさほどくわしくない人にとっては、決してわかりやすくは
ないだろうし、やや独断的な傾向が見られる本であるだろうことは
決して否定しない。
だが大学生当時に著者の講義を受けたこともあって、私は山折哲雄に
ついては無条件に信頼している節があり、この本も素直に楽しく読む
ことができた。
1993年発行のこの本に続き、2011年発行の本を読もうと思っている。
どう変化しているか、少しだけ楽しみ。
Posted by ブクログ
一口に仏教と言っても、日本で論ずるときには注意が必要だ。まず釈迦の考えた「仏教」があり、弟子達が考えた「仏教」があり、日本で文化的・世俗的に融合された「仏教」がある。また統一的な教典を持たない仏教は解釈が多様で、実質仏教と定義できるものはないといっていいだろう。
また筆者は現代における宗教の役割について懐疑的だが、それは自分も同感。「神様」「天国」を無垢に信じることのできた時代の信仰と「科学」の進んだ時代の信仰とは自ずと性格が違ってくるだろう。新書故にそこまで突っ込んで深く論じてはいないが、宗教論はその点を含んで研究しないと意味がなくなるだろう。
Posted by ブクログ
遺骨の供養にかかずらうなと言ったブッダの教えに背いたアーナンダにはじまり、仏教はときにはブッダの言葉を裏切りながら、様々な変化を経て現在へ続いている。その是非を問うよりかは、そのような現実を受け入れアーナンダの徒として我々はこれからいかに仏教と向き合うか。新しい時代で仏教はどの様にあるか。おそらくそのような内容の本。
個人的には日本において仏教が日本固有の山岳信仰、浄土観、遺骨信仰と結びついて独自の発達をしたという日本仏教の個性という章と、民族仏教の背景という章が印象に残った。神道もまざってひっちゃかめっちゃかであり、とても興味深い。
しかし入門書としてはあまりおすすめしない。