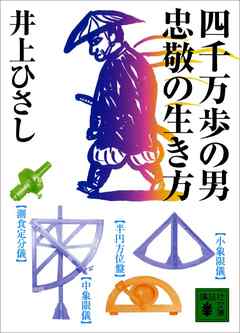感情タグBEST3
Posted by ブクログ
「四千万歩の男」では一年間の物語だが、その執筆過程で伊能忠敬の足跡を追うとともに、その時代の大きな流れの中で伊能忠敬が果たした役割が読み取れる。たいへん面白く、再度、読む機会を持ちたい。
Posted by ブクログ
長編小説『四千万歩の男』全5巻(講談社文庫)にかんする著者のインタヴュー記事などをまとめた本です。
本編は、忠敬が蝦夷地と伊豆・相模の測量の旅を終えるところまでがえがかれていますが、作品内での期間は1年半であり、一方著者がこの連載に7年の歳月を費やしたということで、けっきょく十七年におよぶ忠敬の行程をすべてえがき切るには百年かかるだろう、といったことが述べられています。また、富岡幸一郎がインタヴュアーを務めている対談では、「当時の人口が三千万人くらいですから、そのうちの、できたら一万人くらいには話をさせたかった」「岩波の日本史年表に忠敬が全部関係してくるということをやろうと思っていた」など、途方もないことばが見られます。
「これは、やりたいと思っていたことのほとんどをやらないでしまったという、へんな小説ですね」と著者自身が語っている通りで、まさに本作そのものがドン・キホーテのような企てであり、小説として成功しているかどうかはともかくとして、本作のような企図が試みられたということそれ自体に感銘を受けました。
Posted by ブクログ
あの日本で初めて地図を作った伊能忠敬を小説にした井上ひさし氏の「四千万歩の男は、全部で5巻完結であり、そのボリュームに恐れをなして、似たデザインの兄弟本に「四千万歩の男 忠敬の生き方」という本があるのを知り、少々弱腰でこちらを読むことにした。
ところがこちらは、小説でなく、上記小説についての著者の雑誌や新聞への寄稿文、あるいは講演記録、インタビュー記事などが編集された本であった。であるのでで小説の概要や、伊能忠敬の人物像については、この本で結構知ることはできた。しかし、小説の醍醐味、伊能忠敬になって日本全国を巡る臨場感的なものを期待するなら、小説本体のほうが断然すぐれているはずだ。
小説本体のほうの内容は、西暦1800年(寛政12年)の一年間の歩みについて書かれているようである。これに井上ひさしさんは5年かけて書かれた。そこで、井上さんと編集者は計算したそうだ。
伊能忠敬のの地図作りの旅は約17年間に及んでおり、このペースでいくと生涯を描き上げるには、5×17=85年を要すと。当時40歳だった井上は完結するには125歳まで書き続けねばならないということになり、断念したというエピソードが載っていた。
しかし、それほど井上氏は書きたかったようだし、伊能の一年分を5年かけて書いたその内容は、まさに一歩一歩の歩みについて濃厚に綴っていったようである。
巻末に関連年表が掲載されているが、1800年のところを見ると伊能忠敬の御年55歳。「蝦夷地を測量して実測地図をつくる(第1回測量)、間宮林蔵と会う。」とある。
伊能忠敬が55歳であることと、蝦夷地を測量しているところがポイントである。
それまで忠敬は商家の婿養子で、けっこう稼いだようだ。それが第一の人生。忠敬が測量を開始したのは隠居してからで、これが第二の人生。つまり忠敬は第二の人生において、日本初の地図を作るという偉業を成し遂げたのである。
それも当時は平均寿命が40歳くらいの時だから、もう皆が隠居しておとなしく余生を過ごそうというようなときに、一念発起してこれをやり遂げたわけだから、世の中の壮年世代に勇気と希望を与えてくれる人物であると言える。
これを始めるにあたり忠敬は19歳も年下の暦学家の高橋至時に師事し、西洋天文学を学び始め、自らも天体観測を行った。そして高橋至時の推薦で幕府の命をうけて、蝦夷東部および南部の測量を開始したのだ。この年齢における向学心もまた見習うべきところがある。
また、忠敬の師・高橋至時のその師がまた、麻田剛立という凄い学者だった。西洋でケプラーが惑星運動の法則を発見したのと時を同じくして、日本でも麻田剛立がほぼ同様の法則を解明していたというから、日本の天体観測技術は非常に先進的だったということだ。
この小説の中で井上氏は、同時代に生きた多くの碩学を登場させているようである。ここはフィクションとして。フィクションとはいえ、物語はとても面白くなるだろう。
碩学たちについて、本書では「忠敬と同時代人」という章を設け、志築忠雄、関孝和、林子平、高田屋嘉兵衛、平賀源内、二宮尊徳、他多くの登場人物を紹介している。
併せて当時の測量道具なども特集的に紹介されており、こんな道具をもって測量していたのかと、非常に興味深い。
本書を先に読んで、前知識をもって小説に入るのもよいかもしれないし、小説を楽しんだ後に、「復習とまとめ」の位置づけで本書を読むのもよいかもしれない。
井上ひさし氏が当時もくろんでいたNHK大河ドラマ化が、そろそろ実現してもよいように思うのだが・・・。
Posted by ブクログ
5/19に誕生日を迎えた時の誕生日記念読書の1冊。56歳になった私は、あの地図で有名な伊能忠敬が、婿養子で財を成し、実は隠居になった56歳から日本地図を作るために全国を歩いたと聞いて、その生きざまをぜひとも読みたかったのです。まあ、とにかく商売では、そこまで財を成したのだからあくどい面もあったのかもしれないけど(笑)、自分の歩幅で正確な日本地図を作ると言うのは、まさに愚直そのものです。私なんか今から「日本を歩いてまわって地図を作ってね」って政府から言われてもお断りするから(笑)
この本は井上ひさしさんの「四千万歩の男」の外堀の本です。本丸はやっぱりその本を読まないといけないけど、ちょっと長いから引いちゃっている時点で、もう負けていますね(伊能忠敬と勝負する気はないけど)。
しかし、この時代、シーボルト(ふぉんしーふぉるとの娘は読んでいたので)関連や天地明察関連が出てきて面白いですね。本当に大河ドラマになるといいのにって思いました。
Posted by ブクログ
伊能忠敬を見つめる井上ひさしの視線がいい。
「忠敬さんは、いい意味で愚直」
そういいきってくれて
おろかな毎日を過ごす、
でもそれを決して嫌っていない
私自身の生き方も認められたような気がする。
生きているはずのない伊能忠敬の3番目の奥さんと
対談をしたり、
伊能忠敬本人とも話をしている
そういうユニークさを持ちながらも
非常にまともな対談もありで
飽きない。
肝心の小説『四千万歩の男』には
まだ手をつけていないけれど、
予備知識として、読んでおくのもいいかも知れない。
さぁ、凶と出るか、吉と出るか
いよいよ伊能忠敬ワールドに入ることになりそうだ。