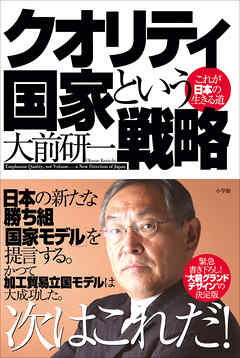感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
最近の大前さんの著作は昔のような勢いがなくなってきたなぁと思っていましたが、この本は違いました。
「民主主義は啓蒙された人間でなければ維持できない。啓蒙されていない人間が投票すると衆愚政治になる。」
という言葉は、現在の日本を的確に表していると思う。
韓国とフィンランドの教育方針に現れているように
クオリティ国家として進むためには、教育の位置づけは
非常に重要だと思う。
僕も常々、日本の教育がビジネスに直結していないこと
を問題と感じていた。本書を読んでクオリティ国家を
目指すべき日本にとっては、世界で通用するリーダー
を輩出する教育が重要なのだと改めて感じた。
Posted by ブクログ
少子高齢化や多額の国債などの問題を抱えながら、今の延長線上に豊かな日本を想像できる人は少ないのではないでしょうか。本書は、他国の事例をあげて日本の進むべき道を説いています。賛否両論あるでしょうが、これだけ明確にかつ説得力のある内容で未来を描ける著者に感銘を受けました。企業運営のスペシャリストが考える国策ってやっぱり興味深いです。
Posted by ブクログ
道州制とは何をすることか、それを説く本。大きすぎて身動きの取れない日本の国家規模を分割して、北欧を目指そう。
「ものづくりの国:日本」だった時代は終わった。当時も日本のクオリティの高さがウリだったが、日本がこれから目指すクオリティはモノではない、「抽象的な何か」というクオリティである。
実体のないものを目指さないといけないから、非常に難しい。失敗もする。けれどそれを恐れずに行こう。
______
p18 日本の教育はサラリーマン用
日本の国家再生戦略にある「理系博士課程修了者の完全雇用」とか、工業立国しか考えられない人たちの作る目標である。せっかく博士課程まで修了したのにそれを活用できないのは問題だが、それを労働者にして狭い枠にはめようとするのも宝を腐らせるだけである。
日本の教育は成長していない。
いや、変えられない。日本にとって教育は戦争責任とか暗黒面があるせいか、アンタッチャブルな領域である。だから変えられない。変えたらどうなるかわからないから。
変われないなら、成長もない。それに気づかなければ。
p48 スイスの税制
法人税や所得税が安い。世界の有力企業や資産家を呼び込むためである。
p53 ブランドの考え方
日本はセイコーが1969年に小型クォーツ時計を作って欧米の時計を席巻した。日本はブランドを育てるのを「技術の向上」「生産の効率化」で付加価値をあげようとした。
スイスはファッショナブルな時計を作り、また世界の衰退ブランドを買い上げ磨きをかけて、「装飾性」「ステータス」で付加価値を高めた。
結果、日本の時計は価格競争で中国に敗れ、部品屋さんになってしまった。
p58 個の力
「ブランドを維持するためには、一人のプロデューサーがいればよい。」
日本の組織ではブランド・マネジメントも組織でやろうとする。遺伝子レベルで「みんなで力を合わせよう」の工業国の集団意識が根付いている。これではブランド戦略を柔軟に行えない。
スイスのようなブランドを育成できる国にするには、思い切って集団意識を捨てて、個の力に頼る勇気を手に入れなければいけない。
p69 日本とスイスは似ていた
スイス人のある人が言っていた、日本とスイスは天然資源がなく、国民が勤勉だという点が非常に似ていると学校で教わった。ところが今は違う。最も大きな違いは「国家の役割」である。
日本の場合は国家が何でもする。第二次大戦後の復興を早々と達成できたのは中央集権国家が効率よく機能したからだ。
スイスは連邦国家であり、地方の権力が強い。地方のことは地方で決められる。そこが違う。
p70 大学進学はクラフトマンシップを軽んじる
日本とスイスの違いはクラフトマンシップ(職人芸)に対する価値観である。
スイスの大学進学率は3割しかない。逆に日本は7割になる。高等教育に進まない若者は早くから職能教育を始める。だからスイスでは職人のステータスも高い。
一方日本の職人は今や大田区の零細工場のおっさんだけである。
この差が国力の差になる。
ものつくりの国:日本はどこへ行ったのか。
p77 民度の高さ
スイスには国民皆保険もなければ国民年金もない。それは自分で保険に入り、年金を積み立てるからである。こういうことも教育される。
日本はすべて国がやってくれる。だから教育されることもないし、責任感もない。
大きい政府と小さい政府の差が民度の違いになっている。
p87 シンガポールの変遷
60年代:1965年にマレーシアから独立。外資導入で輸出志向型工業化政策を導入、電化製品の組み立てなど労働集約型産業育成、海外企業誘致のため法人税引き下げ
70年代:コンピュータや機械などの付加価値の高い産業へシフト、労働集約型産業から脱皮
80・90年代:1985年にマイナス成長になった反省として金融や通信サービスの強化
00年代:知識集約型産業育成、電気・化学・通信・バイオ・医療サービスなど強化
10年代:アジアのハブとしての地位確立、都市ソリューションの開発、多様性のある人材の誘致・育成に注力
p105 中国の実態
中国は共産党の一党独裁で中央が強いのかと思いきや、地方の方が強い市もある。浙江省の温州市は北京のいうことを聞かないので有名である。福建省や広東省は華僑の中心地として東南アジアに強い力を持っていて、北京よりも強かったりする。
p120 中国が日本のカギになる
クオリティ国家は隣国の大国に依存する。北欧国家もドイツに進出して切磋琢磨する。アイルランドはイギリスに、台湾は中国に。
日本もこれを見習って、中国という巨大市場で勝負し利用すべきなのである。
利用するというと聞こえが悪いが、経済の勝利は「騙す」ことではない。よりよい「価値」を提供することである。自国よりも人口の多い国で、より多くの人に価値を提供する。そういう世界の優良国家になるべきということである。
p128 移民の質
日本では「移民を入れたら治安が悪化する」という理由で拒否される。しかし、スイスやシンガポールのクオリティ国家では治安が悪化していない。
例えば、シンガポールでは移民に学歴、職能などの条件を課している。優秀な外国人だけが来るなんて都合がいいように見えるが、実際シンガポールは人口を300万人から500万人に増やせている。
きちんと高いスキルを発揮して、成功できる場を作ってあげれば、優秀な移民をたくさん誘致できるのである。
日本人の考えでは、低賃金労働を移民に押し付けようとしているから、治安が悪化するという考えになるのである。そりゃ当然だ。差別されれば心も腐る。
移民に仕事をとられたくない保守的な考えがあるから日本では国家をあげての移民政策ができないのである。
p136 ボーディング・スクール
スイスには「ボーディング・スクール」という、海外勤務の子供のための全寮制の学校が整備されており、すんごい充実している。
スイスのグローバル企業では、若いうちに海外を転々として、キャリアを積んで国内で管理職になる。その時夫婦で海外で暮らし、子供はその学校に入る。長期休暇の時だけ親もとへ行く。そのうち留学したりする。
ちなみに、ル・ロゼという老舗BoardingSchoolは年間800万かかる。ちなみに年8か月の開校なので、実質月額100万円。
p145 「教える」の廃止
「考える教育」を目指すデンマークでは、学校とは「学ぶ」場所であり、「教える」という概念を追放した。
デンマークでは、先生はファシリテーターというラーンニングアドバイザーである。ファシリテーターは担当の生徒が学べるように、自分で考えて行動するので、学校全体が考える場になっているのである。
デンマークではPISAなどのテストでランキングが落ちたりして、これを見直そうという意見もあるが、この教育でちゃんと人材は育っている。
p161 詰め込みも学力が上がる
韓国や中国では詰め込み教育によって教育レベルを上げている。これほど徹底してやれば、そりゃあ実績も上がるだろう。そこで競争を勝ち抜いた一握りのエリートが世界で活躍して、国をひっぱるのだ。
ただ、絶対に大きな悪影響があると思う。
p163 韓国の英語力
韓国ではTOEICで800~900点という高いハードルを受験資格や採用資格に設けて英語力をあげた。
ちなみに日本の英語教員のTOEICの平均スコアは中学が560点、高校が620点である。このデータは非常に興味深い。
p180 解雇規制緩和→雇用援助の方が効果的だ
スイスなどのクオリティ国家では、従業員の首が切りやすい仕組みになっている。そのかわりセーフティネットが充実しているのである。失業給付や職業訓練が機能的で、給付を受けるには訓練を受けなければならず、訓練で能力強化されてどんどんほかの企業が採用していく。
この雇用の流動性の高さがあるから、新しい産業・企業が成長できる。
日本などの雇用の固定的な国ではこの仕組みの印象が悪い。だから政治家もこの仕組みを取り入れようという人が出てこない。
p186 日本のダメ
①日本の市場がデカかったから、海外進出の必要性がなかった
②コストダウン・技術革新で勝負していたが、もう限界
③技術開発は得意だが、ブランド価値の向上や新しいビジネスモデルの構築が苦手
④大企業や銀行などが経営不振になったら国が助けちゃう。中小企業もモラトリアム法で無駄な延命処置されてる
⑤外貨導入や外人採用ができない。劣等感からくる差別意識
⑥工業国モデルからの脱却ができない。教育システムが変えられないから
______
ちきりんの言ってることはこのまんまだ。
日本の規模が大きすぎるというのは凄くなっとくなんだよなぁ。この面積で1億人以上の人口がいるんだもんなぁ。
そりゃあ地方だけで1国家くらいの規模なんだから、そうするべきだ。
鎌倉幕府は1192~1333年の242年で戦乱になり、
室町幕府は1336~1573年の237年で戦国時代になり、
江戸幕府は1603~1867年の254年で維新が起こり、
明治政府は1868~現代まで146年経った。
100年くらい早いけれど、また統一国家の解体来るかな??
橋下は道州制についてきちんと勉強していて、大前さんにも師事したというが、実現できなさそうだしなぁ…。
安倍さんが命に代えて日本の行政機関を解体してほしいところです。