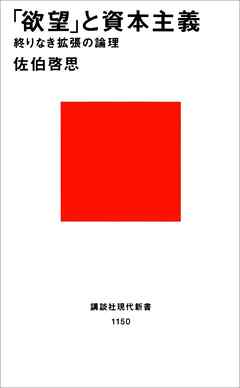感情タグBEST3
Posted by ブクログ
資本主義は
国外のフロンティア
→国内の大衆消費者
→人々のアイデンティティ
→広告で作られた実態のない「好奇心」
の順に欲望を拡張してきた、と言う話。
最近までを綺麗に書いてるなぁと思ったが、読み終わって奥付を見たら1993年出版でびっくりした。
日本の成功は、同質な品を大量生産する米国的製造から、より細かいニーズに添う生産にいち早く変えたから。
その後は「個々人」に寄り添うことが出来ず、広告代理店が「好奇心」を煽り実態のない消費を作った。
いまIT企業がイケイケなのは、テクノロジーで個々人に寄り添うことを実現したからか。
小麦の罠と一緒で、豊かになって増えるからより作らなきゃいけない。
でも、昨今世界的に突然少子化が進んでいるから、もう作らなくていいというフェーズになった。
これが「モノ消費」から「コト消費」への転換駆動力な気がするな。
30年前の本だけど、近年流行った「お金2.0」とか「モチベーション革命」とかと書いてあることは同質で、なんか気が抜けた…
人間言うことは流転するんだなぁ…
Posted by ブクログ
私自身は、イデオロギーやそれを軸とした経済システム、法体系というのは、人間の支配欲から成り立ち、それを統制するべく形成されたという立場である。著者は、経済史家のブローデルによりなされた資本主義と市場経済の区別を用いながら、資本主義の形成を、欧州が中東の舶来品を入手したいとする欲望から順を追って説明する。カール・ポランニーによる欲望の交換などの考察からすれば、些か手順に飛躍があり、資本主義の存在そのものを文明国に限った断定的な感が拭えないが、前提が受け入れさえすれば、著者の考察は理解しやすく、馴染みやすい。
また、欲望の条件は、客体に距離のある状態、すなわち分離された対象に価値を自覚する事、としたジンメルの欲望論を引いている。これについても、希少性や対象への競争が価値を高めるという説明だが、これも一つの条件に過ぎず、言葉の定義としては物足りない。労働を生み出す労働者の価値、商品の価値を限界効用に照らしながらも、では、普遍的価値とは何か、もう少し掘り下げられたかも知れない。
グダグダ述べたが、種々参考文献を引きながら、著者のように論理的に資本主義を考察するには、私自身には参照用のストックもなければ、事実関係を確かめる時間、実力もない。然るに、考察の助長として非常に有益な著作であると言える。
欲望の果てにあるもの。資本主義の終焉、それはシュンペーターの言う社会主義への移行では決してない。価値追求が即ち競争であるなら、その果てにあるのは、支配の許容、つまり究極の格差社会だ。支配欲の統制システムが瓦解するのだから、当然、支配世界が復活する。
Posted by ブクログ
「資本主義はニヒリズムか」の中で紹介されていた本作品を読んでみた。今日のこの高度に情報化し、グローバル化した社会で「資本主義」という概念をどのように理解すればよいのか、そして文明論的に、歴史的にみればどのような意味をもつのかを問う作品である。
第1章が、社会主義はなぜ崩壊したのかということで、「効率的」は自明的なことかを問いながらも、社会主義が欠けていたものを論証している。
第2章は、80年代と日本の成功について、理念なきテクノロジズム、歪んだ資本主義?としながらも、消費資本主義を誕生させたということで総括している。
第3章は資本主義という拡張運動ということで、ブローデルの三層理論、バタイユの発想、ジンメルの欲望論などを参照しながら、その時代時代の資本主義の変遷を語っている。
第4章は、「外」へ向かう資本主義ということで、ゾンバルトの説、産業革命とは何だったのかとして、それ以前のアジア・イスラムの商業活動に言及している。
第5章は「内」へ向かう資本主義として、20世紀アメリカが生み出した資本主義について分析を行った。
第6章はナルシズムの資本主義として、欲望のフロンティアのゆきづまり、浮遊する好奇心、情報資本主義における消費者といういままでになかったタイプの資本主義の到来について語っている。
第7章は、消費資本主義の病理で締めくくっている。ゆたかさの果てに、つまり、「成功するがゆえに没落する」資本主義について、シュンペーター、マルクス、ケインズらの予言を紹介している。
最後に、著者は以下のように締めくくった。
モノはほんらい、技術だけではなく文化の産物でもある。経済活動自体が、ほんらいは広い意味で文化という土壌と不可分なのである。今世紀の産業主義は、それを技術の次元に還元し、文化から切り離そうとした。いま限界にきているのはそうした今世紀の産業主義である。だが、その限界地点で、ようやく、欲望を産業技術のフロンティアの奴隷にすることから解放されようとしているのではないだろうか。欲望を文化的なイマジネーションの世界へ取り戻すことができるようになってきたのではないだろうか。わたしはといえば、やはりこの可能性にかけてみたいのである。
Posted by ブクログ
主に資本主義の歴史についてかいてあります。
「資本主義はその成功のために没落する」ってゆう言葉を聞いて思い当たりました。
それで日本こんな不自然なんですね。
あと、投機マネーのせいで石油が高いとかなんとかゆうてますが、
資本主義の恩恵にあやかっている限りそんなことを言う資格はありません。
Posted by ブクログ
資本主義は「欲望」によって成り立っている。人間の欲望はとどまるところを知らず、資本主義は欲望のフロンティアを拡張し続けていくというのが本書の内容。非常におもしろい。買ってよかったと思える一冊。
Posted by ブクログ
とても面白かった。出版されてからもう10近くになりますが、今までの経済の歴史を振り返って、今はどんな状況なのか、筆者の意見が出ています。本当は経済に分類したいのですが、内容的には思想だと思ったので思想に分類しました。
「外に向かう資本主義」「内に向かう資本主義」「ナルシズムの資本主義」の展開はかなり興奮です。
Posted by ブクログ
ヴェーバーのプロテスタンティズムの倫理と資本主義の成立を関連づけた議論ではなく、資本主義の成立をバタイユの蕩尽やゾンバルトの理論を援用しながら展開し、その特徴や病理をあぶり出している。
ヴェーバーに対して漠然と抱いていたモヤモヤ感が少し明快になる感じ。
Posted by ブクログ
資本主義を欲望によってフロンティアを拡大していく行為と捉え、どのように発展したか、何故成功し、社会主義は失敗したのかについての著者なりの答えが示されている。ペレストロイカは社会主義+市場の導入という形で立ちゆかなくなり、計画経済において権力側がコントロールしきれなかったことなどが興味深かった。アメリカの大量生産を可能にする大量消費(需要)の存在や、メルティングポットが故の大衆を相手にした資本主義なども納得できる(それは貴族主義などのヨーロッパには根付かなかった)。欲望とうまくつなげながら論じられている名著。
Posted by ブクログ
資本主義の歴史とその本質がよく分かる。
元来ポリネシアなどでみられた「交易」というものは「価値」のないものをぐるぐるまわす、その運動自体に意味があるものだった。そうすることで富を必要以上に蓄積することの危険を回避していた。しかしヨーロッパ人は違った。自分たちが持たないものを執拗に欲しがった。中国の茶、陶磁器、インドの砂糖や香辛料、南米の金、銀など。重要なのはそれらは「生活必需品」ではなく、「贅沢品」であること。つまり「欲望」が資本主義という運動をドライブさせ続けてきたのだ。あるときは武力に任せて強奪し、あるときは三角貿易によってアヘンや奴隷を介在させることで、非人道的に利潤を上げ続けた。
基本的に資本主義というのはここからそうかわっていない。「欲望」を作りだし続けることが成長のためには必要なのだ。当然のことながらそこには搾取する側とされる側の不均衡が必要になってくる。世界中が平準化したら資本主義という運動は止まってしまうだろう。
グローバリズムというものが貪欲さと離れがたいのはその本質が「欲望」であるからである。世界は自滅に向かっているようにしか思えないのだが…。
Posted by ブクログ
「消費者」という観点から資本主義を捉える
そこには「欲望」が存在し、距離が遠ければ遠いほど、深くなる
読み物的かと思ったら、説得力があって、歴史を新しい視点から振り替えることができた
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
資本主義の駆動力は何なのか。
ゆたかさの果て、新たなフロンティアはどに求められるのか。
差異・距離が生み出す人間の「欲望」の観点から、エンドレスな拡張運動の文明論的、歴史的な意味を探る。
[ 目次 ]
●資本主義という拡張運動
過剰の処理としての資本主義
「欲望」についての考察
●「外」へ向かう資本主義
産業革命とは何だったのか
●「内」へ向かう資本主義
20世紀アメリカが生みだした資本主義
●ナルシシズムの資本主義
モノの意味の変容
欲望のフロンティアのゆきづまり
●消費資本主義の病理
「ネオフィリア」の資本主義
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
1993年発行でそれから17年経つけれども色褪せないのは、欲望を軸においた資本主義論だから。ウォーラースタイン的な世界史観から行くと、水野和夫氏の著書と並べて読むと面白そうだ。
オーソドックスな経済学が構築してきたデカルト的な資本主義の見方から、欲望という人間らしさを軸とした有機的な見方へと、うまく読書を連れて行ってくれる。
また、外への拡張から内への拡張という欲望の話も面白かった。19世紀の帝国主義から20世紀のアメリカ型消費者主導社会へという動き。本書では触れられなかったがその後のアメリカ文化輸出型、ブレトンウッズ体制崩壊後の金融資本主義、という内から外への動きも興味深い。
それが崩壊した今、次なる動きは内向きか?今の流行りで行くと「正義」の消費か?
Posted by ブクログ
資本主義の本質を「欲望の拡張」と位置付けた本書。書かれたのが90年代前半だけあって、メディアの役割については「トレンディ」的なものを重視しすぎている感はあるが、70年代までの資本主義については上手く総括しているのではないかと思う。佐伯啓思の新書はどれも非常に読みごたえがあるので、お勧めです。
Posted by ブクログ
資本主義を「欲望」という観点から捉えて説明している。
社会主義と資本主義の違いというと、「競争があるかないか」の違いだと漠然と考えていた。
だけどそこに「消費者」が入っているかという違いでもある。
社会主義は、国が生産量・価格を決めるもので、そこに消費者の「欲望」は入ってないんだよね…
これに対して資本主義は、消費者の「欲望」がなければ成り立たない。
フォード生産方式と、トヨタのカンバン方式の違い(効率を重視か消費者重視か)、そこからトヨタがマーケティング部門に力を入れるようになったのだとか。
あと「欲望」というと、「無限」のものってイメージがあるけど、この本では逆に「過剰」ってとらえているのも印象的だった!
生き残るための最低限の欲望と、その他不必要(?)な欲望に分けて。
いかにして、「過剰」な欲望を引き出すか。
興味深かった…!!
社会主義・マーケティングについてももっと知りたくなりました
Posted by ブクログ
資本主義とは何だろうか?ここでは、もう一度資本主義を定義し直す。資本主義とは、人々の欲望を拡張し、それに対して物的な形を絶えず与えてゆく運動である、と。フロンティアの拡張運動としての欲望の分析。非常に面白く、マクロな視点が養われる。
タイトルに惹かれて
タイトルに惹かれ購入してみました。
内容的には面白くはあったが、少し物足りなく感じた。
前知識がなく、引用されている分についてふーんとしか思えなかった。もう少し知識があったらより面白く感じたかもしれない。
Posted by ブクログ
資本主義と、それを動かす動力である「欲望」について論じた本です。
「市場経済」という観念とその基礎にある「自由」の観念は、個人主義や自由主義、デモクラシーといった西欧の価値観と深く結びついています。しかし、資本主義の中から現われ出た「産業主義」は、むしろ西欧の社会を支える骨格に対する挑戦とみなされると著者は言います。
著者は、ヨーロッパに資本主義が生まれた歴史的経緯について考察をおこない、ヨーロッパの外にある文明への「欲望」が、資本主義を動かしてきたと論じています。しかし、資本主義の「外」が容易には見いだせなくなり、さらに大衆の顕示的消費さえもが魅力を薄めつつある現在、人びとは改めて、資本主義によって覆い隠されてきた文化や知識、価値といったものに気づくことになるのではないかと論じて、資本主義の危機が新たな可能性にもつながっていると語られます。
資本主義と欲望をめぐる歴史的経緯についての解説は、興味深く読みました。ただ、著者が最後に語っている資本主義の「後」の可能性については、多くの問題があるようにも思います。直接「文化」や「価値」といったものについて語るとき、私たちはどのようにしてそれらを調停すればよいのか、まだ具体的な手段を持っていないように思われるからです。現在の社会制度に即した手続き的な正当化以上のものを求めることはよしたほうがいいような気がするのですが。
Posted by ブクログ
資本主義とは何なのか?がこの本の主題。そしてこの本でいう資本主義は一般的な使い方と若干違うようなので注意が必要。市場経済とセットとは考えない。
社会主義も市場経済は導入していたが競争がなく、失敗をチェックする仕組みがない。消費者が存在しないことが失敗の原因だという。
資本主義は大きく分けてアジア等外側に欲望が向いていた産業革命周辺の時代、理想のアメリカ人像を求めた1880年代終盤から1900年代初期。欲望がメディア、広告によって人々の刹那的になり絶えず移り変わる現代(1980年代から1990年代)と分けられるとしている。すこし昔に書かれた本だが現代からを見てもまだまだ欲望に取りつかれていて文化、知識の領域は取り戻せていない。
著者は資本主義発生のメカニズムはゾンバルトを指示していてヴェーバーには一部を除いて否定的。
Posted by ブクログ
ヨーロッパの資本主義からアメリカの資本主義への変遷が、外向きの欲望から、マーケティング、広告により内向きにあおられる欲望により形成されたという節。
生産力などには一切触れず、欲望が生産を生み出していくかのように描かれている、ある意味珍説として受け止めた。
Posted by ブクログ
資本主義を「欲望」という観点から論じている。第4章「外」へ向かう資本主義における、ヨーロッパの消費革命についての記述が面白かった。また、書籍のテーマである「欲望」についても頷かされることが多い。昨今では、これに類似したテーマが扱われることが多いが、本著は20年以上も前に記されたものである。そのような点からみても一読の価値はあると思いました。
Posted by ブクログ
資本主義の精神の根源をたどる。
資本主義と欲望の関係を考察。
それらを歴史を絡めて描いていたので読みやすかったが、最後の方が少しずれてる気がしたのは僕だけ???
Posted by ブクログ
資本主義というものが、人間の無限の欲望を前提として形成されて来た歴史について解説した本。著者は資本主義を「人々の欲望を拡張し、それに対して物的なかたちをたえずあたえていく運動」と定義する。
また、著者は資本主義経済においては「過剰」に注目すべきであると説く。以前私は経済学を「有限の資源をいかに効率よく分配するかを考える学問」として「稀少性」に着目すべきだと理解していたが、これまでの人間社会の生産力からして供給過剰になりがちなため(生産物にもよるが)、この説はある意味で正しいだろう。
ミクロ経済学では個人は「効用」の最大化を目指すことを学んだが、本書では今までその効用がどのように形成されて来たのかが無視されがちであったことが指摘されている。その答えとしては、大航海時代以来の貴族の嗜好品や奢侈品への欲望(モノ自体や個人の枠にとどまらない、シンボルの消費)によるものが大きかったことが挙げられる。香辛料、金銀、茶などといったものがその代表例。
資本主義の歴史を語る上で優れた本だと思った。