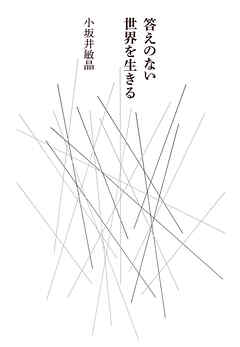感情タグBEST3
Posted by ブクログ
作者の思考されたものではなく思考の仕方が自伝がてら語られる。
答えのない、正しい答えが存在しない世界だからこそ問い続けなければならないこと、この世界を異端、異邦として見つめることで、画一化される正しさに疑義を与える。
今、この世界に生きるとき、大事な姿勢。
Posted by ブクログ
「解のない世界に人間は生きる。・・・
(中略)
・・・考えることの意味を知ることが重要だ。」
この世界で生きていく上での答えなどない。
自身の問いに向き合えているのか、そう著者に問われている気がした。
とても読みやすく、何度も読み直したい本だ。
Posted by ブクログ
同著者の『社会心理学講義』や『責任という虚構』読もうとしたが重かったので、ちょっと寄り道。紆余曲折の末にフランスで社会心理学者として教鞭を執った著者の半生を振り返った本。
異文化の中で培った普遍性を疑う感性から見た世界を綴る。
「文科系学問は役に立つのか」という章の〆の一文が象徴的だった。
「文科系学問が扱う問いには原理的に解が存在しない。そこに人文学の果たす役割がある。何が良いかは誰にも分からないからだ。いつになっても絶対に分からないからだ。(···)技術と同じ意味で文化系学問の意義を量ってはいけない。」
文科系学問の意義は「人間の原理的な限界に気づく」ことにあるいう。
その認知は知識の矛盾により生じるが、一方で知識は世界を疑うことを忘れさせる。文科系学問は絶対的な解がない故に、人をこの認知へと到達させる。ここまで理解して、この著者による今の人文学への批判を読んでみたいと思った。
「海外旅行をして人生観が変わった」とよく聞く体験談は、その感性が自身の文化を擦り合わせた末の「矛盾」によるものか、その土地の文化への「服従」によるものかによって全く違う意味を持つのだろうなとも感じた。
自己内である程度のアイデンティティを確立してはじめて、異文化や他者と触れた時に「矛盾」が生まれる。そうして初めて単体では成立するが共存し得ないロジックの存在を認知することができ、解がない問いの存在を理解する。
昨今の世界からは、その前提意識が抜け落ちているなと思うなどもした。
Posted by ブクログ
考えるとは悩むこと。
人は他人の頭で考えることができないのだから、借り物の知識だけでなく、”不思議だな”と思うことをしつこく追及していくしかない。しつこく悩み考えるなかにスッキリした瞬間があらわれる、たとえそれが大したことない”なーんだ、そんなこと当たり前じゃないか”と言えるものが、実は思考の結果だ。
劣等感と劣等は違う。理想と現実の乖離があるからこそ悩む。悩みが多いということは野心を持っているということだ。
本書を読んで、目の前が明るくスッキリしたという読者は少ないだろうが、確実に自分の体内に小坂井さんの毒素が回っていくとこは実感できる。
10年後にまた再読したい。
Posted by ブクログ
尊敬する出口治明氏が推薦しているので読んでみた。
近代以前ならば、物事の是非を判断するのは「神」だったが、近代では人間が決めなければならない。
「人間が決める以上、その先に待つのが〈正しい世界〉である保証はない。」
知識の欠如ではなく知識の過剰が理解の邪魔をする。ペルーの農村の話は分かりやすかった。
名言がたくさんあって、メモを取るのが忙しかった。
「行為が正しいかどうかは社会的・歴史的に決まる」という言葉に唯幻論を思い出してたら、中盤で岸田秀氏の名前が出てきて嬉しい。
難しいけどおもしろく読めた。血肉になるまで何度も読み返したい。
Posted by ブクログ
マイページ毎に脳震盪が直撃するような感覚になる稀有な本。
自分の頭で考えることの重要性を謳われて久しいが、真に考えるということを今までにないほど、ストレートにぶつけてくる。
自身の思考枠にヒビが入る。
それは痺れるような快感だ。
何なんだこの本は。
畢竟、独学に勝るものなし。
Posted by ブクログ
「世の中のあらゆることに、絶対的な正解などありはしない」と教える本です。半分は著者の自伝でもあります。
第一章「知識とは何か」、第二章「自分の頭で考えるために」まではまだ大人しいのですが、第三章「文化系学問は役に立つのか」の辺りから過激になっていきます。「大切なのは知識を積むことではない。教育の本質は常識の破壊にある(p92)」、「開かれた社会とは、社会内に生まれる逸脱者の正否を当該社会の論理では決められないという意味である。〔中略〕キリストもガンジーも社会秩序に反抗する逸脱者だった。対してヒトラーやスターリンは当初、国民の多くに支持された(p136)」、「犯罪と創造はどちらも多様性の同義語である(p138)」等々。
早稲田大学在学中にアルジェリアに渡り、その後フランスの大学で社会心理学を教えるようになった波乱万丈の経歴について語る第四~五章(「フランスへの道のり」~「フランス大学事情」)は、まるで小説みたいに面白いです。常識的な世界観に楔を打ち込み続ける著者の本の楽屋裏を覗くようでもあります。フランスの大学制度や大学人に向けられる批判も痛烈です。
これまでに読んだ著作(「人が人を裁くということ」、「責任という虚構」、「増補 民族という虚構」)から、小坂井敏晶さんに対して国際的な舞台でスマートに活躍する洗練された学者というイメージを私は勝手に作り上げていました。でも、この本を読んでそのイメージがすっかり壊されました。第六章「何がしたいのか、何ができるのか、何をすべきか」で明かされるとおり、著者は反骨精神旺盛で組織に馴染めず、学会の主流派からも距離を置いて、挫折したり悩んだり迷ったりしながら、でも自分のやりたいことをやってこられた人なのですね。
「国際人という言葉がある。〔中略〕私が目指したのは、その逆だ。フランスでも日本でも自然に生きられる国際人ではなく、どこに居ても周囲に常に違和感を覚える異邦人。グローバル人材の反対に位置する社会不適合者、非常識人間である(p253)」 ── この心意気は素晴らしい。大学で学ぶ人は、学ぶことの意味について考えるためにも、ぜひこの本を一度読めばいいと思います。普通の人が著者の生き方に憧れそのまねをしたら、きっと酷い目に遭うでしょうけど……
Posted by ブクログ
ライフネットの出口氏がゴリ押ししていた本書。国際人というのは、どこにいても自然に生きられる人であるのに対し、異邦人とは、どこにいても周囲に常に違和感を覚える人。普遍的な心理や正しい生き方など存在しないという前提のもとに、ひたすら問い考え続ける生き方について説く。主観と客観、内側と外側、人生におけるあらゆるフィールドで「線を引く」という行為について大いなる示唆をくれる本。
Posted by ブクログ
ライフネット生命の出口会長推薦の本。少し前から読みたいと思っていたが、出張の移動時間を利用して読むことができた。作者の学問へのスタイルを形成する要因となった後半部分の作者の半生が、かなりぶっちゃけた内容が続くので、ぐいぐい引き込まれていく。後半スピードアップする感じだ。面白いおっちゃんである。
自他ともに学際的だと思っているところもあり、色々な分野に置き換えて考えることができる内容がある。作者は自分自身の存在価値として、むしろ学際的であるべきとも考えており、まさにイノベーションの定義と同じだなと感じた。また「究極的真理や普遍的真理は存在しない」という現在の哲学の立ち位置を踏まえて、いかに問いを設定するのかというところが、他の方が書いた本を読んで感じることのないところである。
授業でなく、学ぶなら本を読めという話も通常の論調とは異なるけれども、根底の考えは出口さんが話されていることともつながっていると思うので、出口さんが評価されているのも分かる気がした。
当然と思われている前提を疑うところから斬新な理論が生まれる。無意識に前提としているものや、常識と思っていること、確証バイアスなどによる矛盾する情報の遮断など実践は難しい。私も日常の中で実践できるようにしていきたいと思った。
Posted by ブクログ
自分の頭で考え自分の言葉で話すこと、価値観の崩壊を恐れないこと、多面的にものごとを捉えるようにすること
人生を考え直す良いきっかけとなりました
人とたくさん議論を交わせるようにしていきたいです
Posted by ブクログ
第一章に記された「自分の頭で考えるためには、どうしたらよいか。専門用語を避けて平易な言葉で語る。これが第一歩だ。」という一文、
また第二章の「思考枠を感情が変える」の内容全体、
これらが、日常の忙しさにかまけて、早く(安易に)回答を知りたがる自分にとって、とても印象深いメッセージになりました。「うむ、読んで良かった!」という実感です。
ただし、構成には少し戸惑いました。
後半の第四章以降は、前半とはがらりと変わって著者の自叙伝のような内容。
私はこの本を手に取った動機が「筆者の主張を論理的に系統たてて読み解こう」であったので後半に入った時に退屈さを感じてしまいました。
しかし、その後半も読み進めていくと、筆者のアルジェリアとフランスでの実体験や心の動きが臨場感を持って感じられ、徐々に引き込まれて興味深く読むことができました。
大変僭越ながら、読み方としては、最初に後半の第四章以降から読み始めて、作者の「異邦人」としての思考を追いかけつつ、その後に第一章から第三章で、表題でもある「答えのない世界を生きる」ための切り口や考え方を発見していくと、より深く考えることができるのかなあと感じました。
Posted by ブクログ
根本論の話であり、非常に興味深く面白い一冊。
メモ
・勉強は知識の蓄積ではなく、壊すことの方が大切。慣れた思考枠を見直す。
・異質なぶつかり合いを通して矛盾に気づく。矛盾との格闘から新しい着想が生まれる。矛盾や対立がなければ常識を見直す躍動は起きない。
☆他人との比較で考えている時点で、そもそも独創的でない。
・答えでなく、問いを学ぶ。考え方自体を学ぶ。哲学や社会科学では。答えをすぐに出そうとすると現実を正視せず、根本的な問題から逃げてしまっていることがしばしば。
・自分の頭で考えるには、専門用語を避けて平易な言葉で語る。基礎的な事柄ほど難しい。
・型こそが自由な思考を可能にする。認識枠が共有されなければ、解釈は他者に伝達できない。
・わかるとは、理解とは、未知の事項や現象を既知の枠組みに取り込む行為。
・本から内容だけを読み取るのは消費者の発想。自ら生産する意思を持つものの眼には型が見える。学び方をメタレベルで学ぶということ
・枠組みを共有するからこそ、冒険に駆られ自由になれる。
・考えることの意味を問い直す。人間の原理的な限界に気づく。
Posted by ブクログ
『責任という虚構』を読み、小坂井氏の考えに強く惹かれて読むに至った、2冊目。
『責任という虚構』に比べると論旨は散逸しているが、第二部、小坂井氏のアルジェリアやフランスでの悩みや苦労話は、彼の考えを理解するにあたって大変興味深かった。
自分も海外での生活及び留学を経験したことがあるため、小坂井氏の悩みは身体的にも共感する部分が多々あった。海外で生活しないと分からない部分は多分にあり、また母国から距離を取ることによって見えるものもある。
常識は目を眩ませるが、だからこそ、常識の不条理に気づかされる異文化環境に生きることは、それ自体に意義がある、という点はその通りだと思う。
本書と『責任と言う虚構』のどちらにも記されていた、「地獄への道は善意で敷き詰められている」という言葉の趣旨が未だ掴めないため、引き続き彼の著作を読んでみたいと思う。
Posted by ブクログ
良著。
第六章は「何がしたいのか、何ができるのか、何をすべきか」。
割と頻繁に頭をかすめる問題。
全く考えがまとまることなく、そのままにしてしまって日々を過ごしてしまっているが。
著者は、どうそこに向かい合ってきたか、ということを記している。
終章は「異邦人のまなざし」。
具体的にどうした属性があれば「異邦人」であると決まるものではなく、違和感を覚え続けることが「異邦人」の要件であるとすれば、自分も「異邦人」であったのかもしれない。
幾つかの集団に属してきたが、ほぼ全ての集団において、その主流の価値観に染まることができずに来た。
朝日新聞など日本のマスメディアの主流となる論調、日教組的価値観に基づいた公立小学校教育への違和感から始まり、いろいろなものになじめずにきた。
そうした違和感をただやり過ごすだけでなく、考えを深めることで、すっきりした気持ちで生きていくことができるのかもしれないと感じた。
Posted by ブクログ
p3 世界から答えが消え去った。〜<正しさ>を定める源泉は、もはや失われた。
p4 遠くから眺めるか近づいて凝視するかによって、世界は異なる姿を現す。しかし〜異邦人という位置〜遠くにあると同時に近いところ〜境界的視野に現れる世界
p8 「答えのない世界に生きる」これは、混沌とする社会に生きながらも答えを探せというメッセージではない。
p9 「正しい世界に近づこう」「社会を少しでも良くしたい」この常識がそもそも問題だ。「地獄への道は善意で敷き詰められている」
p18 知識が思考の邪魔をする
p20 第三世界への技術導入がしばしば失敗に終わるのは、〜導入される異文化要素と互換性のない知恵があるからだ。
#異なる個体のタンパク質を拒絶するのに似ている?異文化の知恵を“アミノ酸“に分解して再合成すればよい?
p29 「アイデアは簡潔な形をとって突然にひらめき、絶対に正しいという確信を伴って現れる」ポアンカレは、こう指摘した。古い世界観の結晶構造が溶解し、絡み合っていた要素群が分解され、新しい結晶構造へと再編成される。
p32 矛盾に陥った時に〜矛盾はまさしく、従来の理論に問題があると示唆している。
p33 矛盾を前に妥協してはならない。〜矛盾を突き詰める姿勢から画期的なアイデアが生み出される。
p34 当然視されている前提を疑う方が斬新な新理論を生む。
p43 矛盾に対して安易な妥協を求めてはならない。逆に矛盾を極限まで突き詰める意思が世界観の再構成を胎動させる。
p46 独創性の呪縛から解放されよう。他人の目を気にせず、自分の疑問だけを追えばよい。〜自らの実存的問いを追い続ける人間も、答えを他の人が提示していないかと、まず、探す。〜しかし誰も満足な答えを与えてくれないから、仕方なしに自分で探すのである。
p48 大切なのは、答えよりも問いである。科学でも哲学でも常識と距離を取ることが最も重要だ。
p52 自らの問いを持つ大切さ。〜心の叫びに苦悩する者だけが宗教の道に進めばよい。〜自分で解かずにはいられない問題があるから自然と研究生活に入るのではないか。
p53 「いつしか日本のシッダールタか、現代の親鸞になりたい」〜「そんなものより、小坂井敏晶になれ」
#泣きそうだ!
p54 常識と戦う重要性〜常識を崩した後に、思考をどう紡ぐか。〜矛盾をどう解くか。妥協してはならない。〜「正言若反(真理は偽りのように響く)」
p58 そして禁止がなければ、ドラマは生まれない。
p63 日本の人口は百年ほどで総入れ替えされる。〜集団同一性がなぜ維持されるのか。
#これも動的平衡と呼べるか。全てが一日で入れ替わるなら同一性の保持は難しいのではないか。系の維持。有性生殖では世代が進むごとに遺伝情報は1/2となる。しかし家系では純血が維持される。
p81 こうして私は<開かれた社会>を把握した。社会には必ず逸脱者が生まれ、それが契機となり社会が変遷する。
p92 人文系学問は無駄だという世論が〜大切なのは知識を積むことではない。教育の本質は常識の破壊にある。それは真理が存在しないからだ。<正しい世界>という表現が無意味だからである。
p94 作家・坂口安吾は言った〜親がなきゃ、子供はもっと、立派に育つよ。
p101 教師は生徒を家畜と間違えているのか。
#相手に対する不安が「力」を発動させる。威張っている人ほど不安が大きい。
p136 社会は開かれたシステムである。異端視が必ず生まれ、社会を変える。開かれた社会という考えには誰でも賛成する。しかし、その意味〜「究極的真理や普遍的価値は存在しない」
p138 悪い行為だから非難されるのではない。我々が非難する行為が悪と呼ばれるのである。
〜何が正しいかは結果論だ。社会の支配的価値に対して逸脱者・少数派が反旗を翻す。安定した環境に楔を打ち込み、システムを不安定な状態にする。〜次なる安定状態が生まれ、社会が変遷する。
p139 普遍的価値は<閉ざされた社会>に現れる心綺楼だ。
#本質を語る人々はこの苦い薬を飲まねばならない。
p140 「正しい答えが存在しないから、正しい世界の姿が絶対にわからないからこそ、人間社会のあり方を問い続けなければならない」
p202 人間の運命など、ほんの小さなきっかけで変わる。今居る位置を自分で選びとったと考えること自体、尊大な態度である。
p206 「立派な役立たずになれるよう、俺も頑張ろう」
p207 「迷う必要などない。迷うような人間はそもそも俳優になど絶対になれないから」〜才能なんて関係ない。理由はわからないが、やらずにいられない。他にやることがない。だからやる。そんな人が俳優になるのだろう。
p247 考えるとは迷うことであり、身体運動である。
p254 「魚の目に水見えず」常識が目を眩ませる。
p259 人生に成功するとはどういうことか。〜成功していないと感じるのは、自分のやりたいことができていないからに違いない。
p298 どうしても解けない問題は世の中にたくさんある。なぜ貧困家庭に生まれたのか、〜なぜ、他でもない我が子が殺されねばならなかったのか。〜貧富の差を減らす政策を練る〜、法制度の厳罰化を通して犯罪防止に〜。しかし、そのような答えでは問題の本質に到底届かない。
#本質が出てきた。。
p301 人間社会は二種類の最終原因を捏造した。一つは<外部>に投影される神や天である。〜そして近代が創出した、もう一つの最終原因が自由意志だ。神を殺し、<外部>に最終原因を見失った近代は、自由意志と称する別の主体を<内部>に捏造する。これが自己責任という呪文の正体である。
p303 私がぶつかった問題には、先達がすでに答えを出していた。〜だが、それでよいではないか。時間が許す限り、力のある限り自らの疑問につき合えばよい。プラトンが、あるいは仏教がすでに答えていたと、人生を終える時に気づいたってよい。
p349 私は大学に一応勤めてはいるけれど、同僚と関心が離れていく〜結局、同僚とは違う職業に就いていると気づきました。〜自分の好きに生きる。〜皆が皆同じことをする必要はありません。〜出世コースを歩む道もあるし、他のやり方もある。〜そんな当たり前のことに、やっと最近気づきました。
Posted by ブクログ
どうして自分にとってという志向・思考がそこまで重要になるのかがわかるように書いてくれるとありがたいんだが。こりゃ生きずらい話になりそうで、しんどい。
Posted by ブクログ
専門家じゃないから、高学歴じゃないから、白人じゃないから、卑屈になって出来ないと言うのは、本当にそうか。
この本を読み、こうあるべきと決めているのは、社会ではなく、自分自身ではないのか、と感じた。