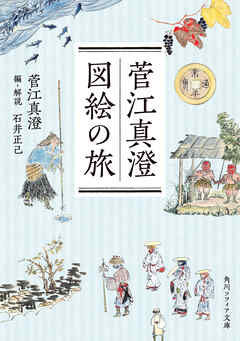感情タグBEST3
Posted by ブクログ
個人的な話。
初めて青森県の山内丸山遺跡に行った時。史料展示室の壁にはかなり長大な等尺年表があった。山内丸山は縄文期から平安期頃まで人の住む地だったので、そこまでの時代については記載が多い。等尺年表なので、その後は昭和の発掘調査まで、ほぼ真っ白。空白。ところが、
……江戸期に記載がある!
それが菅江真澄の記録。土偶や土器片をスケッチし、土地の人からの聞き書きを残している。しかも克明に。
菅江真澄がすごいのは、江戸後期に北海道へ渡って越冬もしている。そしてアイヌの人々の文物•文化•言語なども記録に残したこと。アイヌ語には"文字"がないので、聞き書きのアイヌの言葉の記録は貴重だ。現在、アイヌ語がわかる人が読むと、当時のアイヌの人々の風習がわかるそうだ。
平凡社東洋文庫で出ていた『菅江真澄遊覧記』は白黒だった。しかし菅江真澄の記録は、本人の描くカラフルな記録画があって初めて真価を発揮する。この「図絵の旅」はカラー図版が豊富に載っている。偉いぞ角川ソフィア文庫!ちょっとお高いけど、許す。
そして本書では触れていないが、菅江真澄の記録には謎の空白期間がある。津軽藩滞在時の日記だけがごっそりと欠けているのだ。およそ40年にわたって記録されたものに欠落があるのは何故か。
歴史の教科書には出てこない、地方に住む民衆の、しかも忘れられてしまった記録をこうして目にする機会がある私達は幸せだ。
Posted by ブクログ
最初は借りた。目当てはアイヌの図絵だった。処が、全部で112図絵ある中の最初の七夕人形の記事で既に魅了されていた。ヤバいなあ。購入するべきなのだろうか?絵も凄いし、民俗学的にも貴重。
結局、昨年4月に購入した。その後、半年ほど文庫本が行方不明になったが、この春からまたぼちぼち読み始めて、ようやく読み終わった。いつか長い長い東北旅を敢行するとき、この文庫本を持ち歩き、「これが真澄の描いた八郎潟、これが大間の浦か」と驚き、郷土博物館に行って民俗遺物を眺めながら「200年前に普通の農家の庭先にあったのだ」と想像することだろう。
菅江真澄。1754年おそらく三河・岡崎の生まれ。国学と本草学を学んだのち、83年、30歳で旅立つ。信濃、越後、出羽、陸奥を通って北海道松前に至り、下北や津軽を経て秋田に滞在した。その間一度も故郷に帰らず、多大な日誌、地誌、和歌と図絵を残した。1829年、秋田にて没。民俗学の先駆者というのだけでなく、もっと新しい生き方の手本みたいなものがあるような気がする。
菅江真澄の図絵をカラーで112も紹介したのは、文庫本はおろか、単行本でも極めて珍しいようだ。柳田国男は「真澄の図絵は見事であるだけに、かえって覆刻を妨げた」と述べた。全て覆刻すれば、あまりにも高額になるためだけでなく、詳細な考証が必要なためだろう。今のところ2400点の図絵のうち1割ほど載せた本が最大らしい。その本の発行も1989年である。真澄の図絵の民俗学研究は、つい最近始まったばかりだ。
以下は、純粋わたしの「覚え」である。無視してください。
・(2)1783年本洗馬(長野県塩尻市)「七夕人形」。木で作った人形(ひとがた)の可愛いこと。男はちゃんと帯刀しているし、その下には膳に酒食が供えられる。なんと丁寧で細やかで美しい祭りだこと。
・(3)1783年姨捨(長野県千曲市)「姨捨山の月見」。この頃既に姨捨山伝説はあるのだが、それ以上に月見の名所であり「百人」もの人たちがわざわざ月見に集まり、漢詩・和歌・俳諧を楽しんで酒宴を開いていたということが興味深い。真澄も、姥捨山の絵ではなく、酒宴の美しい絵を描いている。
・(16)1792年松屋が崎(北海道茅部郡森町)「磯廻船路の図」。地形図は図絵の方がわかりやすい。かなり詳しく縮尺は正確ではないが、その分わかりやすく描いている。鳥から見た景色であり、狩野忠敬の地図は見ていたのかもしれない。
・(17)1792年物岱(北海道八雲町)「アイヌの家と村」。貴重な江戸時代アイヌの村の景色。
・(19)1792年ケボロオイ(北海道小幌)「多数のイルカ」。小幌のイルカ漁の絵。50頭ほどのイルカを2人乗り小舟2隻で追って、紐付きモリ(ハナリ)で撃っている。完全に技術として確立している。
・(26)1794年田名部(青森県むつ市)「藤九郎の予祝」。下北半島の民俗。小正月において、豊作を願う形。
・(32)1797年童子(青森県東津軽郡)「平内の雪景」。柳田国男「雪国の春」で模写して口絵に置き賞賛された図絵。家々がすっぽり雪に埋もれている。
・(38)からは1801年より(48-歳)の菅江真澄が秋田県(内のみ)旅した図を載せている。結局1829年76歳で亡くなるまでの28年間を秋田領で過ごしたらしい。1801年岩舘の浦(秋田県八峰町)。鰰(はたはた)が藻に産みつけたぶりこ(卵)を大荒れの岩場で金熊手のような道具でかき寄せて獲っている様を描く。民俗的にも貴重だが、絵的にも素晴らしい。
・(39)1801年岩舘の浦。鰰の雌と雄の詳細画。リアルで尚且つ存在感がある。
・(46)1803年2月、真澄は大館市の大滝温泉を訪ねた。ここには「ススキの出湯」という湯元がある。翁が卵の殻に湯を詰めて、ススキで包んで置くと、そこからふつふつと温泉が湧き始めた由。以来、湯元にススキが生い茂るようになった。今でもそうなのだろうか。図のような素朴なところなのか、行って確かめてみたい。
・(49)1804年8月、寒風山から眺める、未だ干拓されていない頃の雄大な八郎潟。現在の景色と比べたいものだ。
・(53)1805年8月、仁鮒の森に5社を祀る鳥居左の谷陰に、連理の銀杏と一本の大銀杏がある。本嬬木(もとめぎ)は周囲12メートル、枝に乳袋を吊して米と銭を投げ入れ、母乳の乏しい女性が祈るという。連理の銀杏は、男木、女木に見立てその下を通って参るという。今もあるのか、確かめたい。
・(56)1807年4月、鳥形(熊代市)往来に「やまづと」を見つけスケッチしている。山男が初めて杣(そま)入りする時に、祀るものだという。山男の家の庭の高い木の枝を弓のように引き絞って掛け、それに藁の脛巾(はばき)を弓弦のように張って、太いしりくべ縄、一本の矢、スリコギ、しゃもじを添える。で、酒宴をして山唄を歌って出て行くという。このような詳細な文字の記録と共に、記録に徹した図会を残すところに、単なる旅画家ではなく、民俗事例を学問として残そうとした真澄の先進性がある。ホントに凄い。
・(57)1807年5月、小雪沢(大館市)にあった、簡素な小屋に置かれた人形ニ体。避疫神である。編者によれば、現在でも雪沢の新沢地区には、木製のドンジン様ニ体が立てられているそう。
・(60)谷内中。1810年正月。山の神の弊(へい)を木から吊るしている。謂わばしめ縄のようなもの。12日につくり、十二の節があり、それぞれの物を取り付ける。
・(61)八郎潟。1810年1月。氷の下の網引き漁。氷に穴を開けて、網を引く。図があるのだが、今ひとつわからなかった。
・(62)1810年芦崎の浦。伊勢詣の家の庭に、旅の安全を祈る習俗があった。これは絵を見るとよくわかる。御幣を5本立て、しめ縄を引き巡らして弊をかけ、四乳の草鞋一足を家の方に向けて置く。足の裏の左右の中心に小石をのせて、それに水をかけて清める。これは庭中の阿須波の神に小柴を捧げて斎き祀った古俗であり、家の主人が伊勢の内宮と外宮に詣でている証拠。同様のことは「万葉集」防人の歌に見える。防人歌では、旅の安全を祈る神らしい。
・(69)1811年5月。岩瀬(秋田市)の田植えの習俗。葉盤(ひらで)を祀り忌を防ぐ。初田植えの日、かしわの葉を敷いて、海山の神饌を奉る。包飯は、風が吹かない呪いとして作り自在鉤に結びつける。綾襷(あやたすき)もつくる。赤飯はふしかね飯ともいう。色を更に赤くするために、五倍子(ふし)の粉を混ぜて小豆を煮る。かなり詳細な民俗図であり、興味深い。
・(74)1813年、菅江真澄(60歳)は秋田県6郡の『地誌』を編もうと考えた。これは泉の郷(秋田市)の万固山天徳寺の全景。広大な田んぼの山際に道沿いに滔々と川が流れ、其処に小橋を掛けて一際立派な寺が建つ。秋田藩主佐竹家の菩提寺。入母屋造りの本堂を両脇に書院と霊屋がある。当時の村の状況がとってもよくわかる。
・(77)1814年、泉沢村(湯沢市)の泉光院と左に妖怪潭のある面の図絵が載る。寺と云いながら庵である。生垣の外に、桜か梅が咲いて、趣きあり。面も中々造作が良い。
・(79)1824-26年、田村(横手市)の「燃える土」、つまり「根子(ねっこ)」という名の泥炭について記述し描いている。
・(80)1824-26年、下樋ノ口村(横手市)の荒処の弁天沼を俯瞰で描いている。元和年間(1615-24)、小さく深い水沼を、新田開発のために216mの堤を築いて大沼にした。これによって水田は150石になった。沼祭りで梵天を立てている様も描いている。この工事を主導した佐々木某は誰かわからないという。人間の素晴らしさはこういう所にあるのかもしれない。
・(86)描き年不詳。信濃御嶽山。疱瘡を病む子供を近くの山に連れ出して捨て置く様を描いている。御座をしき櫃・鍋・器を置き、コヤが近くにある。家族は絶対近くに寄らない。乞食が世話をし、快方すると物を与えたという。近代医療以前の感染症対策を知る上で貴重。
・(90-91)積雪時の用具や衣装の図絵を作っている。橇(そり)は、移動手段としても運搬手段としても必須で、対象年齢、対象用途に従って、此処には四種載っている。衣装のなかでは、目簾(めすだれ)というのが珍しい。雪から目を保護するものである。
・(92)所謂「かまくら」も描かれている。灯火を2箇所に灯し、数えたら赤ちゃん含めて18人の子供が入っていた(!)。家の前の道に作ってる。取り止めもない話をして夜がふける。
・(108)100〜110では「臼」の図いろいろを描く。ここでは、臼を回って「寝敷(ねしき)」という「夜尿の呪い」をしている。夜尿をすると、子供に夜具や枕を背負わせて、臼の回りを7回回らせたという。他の子供達が笛や太鼓で歌を歌いながら囃し立てる。そうすると、臼の神様が承知くださるという。勿論、当の子供には地獄の体験だろう。これで多くの子どもはやがて夜尿をやめたかもしれないが、トラウマになる子どもも居たかもしれない。しかし、それを含めて村の共同体では全員で病気を治そうとしたのだ。ln津軽や松前の民俗。
・(112)1820年頃の記録。橋桁村(大館市)の畑からは縄文土器が、いくらも出たそうだ。菅江真澄は、これを昔アイヌが住んでいて作ったのだろうと考えた。学術的には間違っているが、この土器が秋田・青森のみではなく北海道にもあると考えるのは重要な視点である。図絵の土器は、平底の大壺である。派手な紋様はなく、細かい縄文が付く。
Posted by ブクログ
・石井正己編「菅江真澄 図絵の旅」(角川文庫)は読んだといふより見たと言ふべきか。書名通り図絵中心の書である。真澄は三河の生まれの人だが、その絵は東北のものが多い。若い頃旅立つたまま、こちらに帰ることなく亡くなつたからである。彼の絵は独特のもので、その絵の「真澄独特の稚拙な表現は、文人の間に流行していた真景図とは違って、御伽草子絵に近い」(辻惟雄、331頁)ものであるらしい。風景画も多いが、民俗的な絵も多い。個人的にはこちらに興味がある。真澄は2400点ほどの絵を残してゐるとい ふ。それからすればここに載るのは112点、20分の1以下である。それでも色がついて細かなことまで 分かるやうになつたのはありがたい。
・真澄30歳、旅立つたばかりの頃の絵、七夕人形(26頁)、これはつるし雛である。伊那といつても松本に近い場所である。松本の押し絵雛のやうなものであらうか。軒端に7つの人形がぶら下がつてゐる。刀を差す人形もあるから、子供ではなく大人なのであらう。七夕行事の人形であるといふ。これにどのやうな 行事が伴つてゐたのか、残念ながら分からない。てるてる坊主もある。一気に北海道に飛ぶ。「てろてろぼ うず」(46頁)である。これは変はつてゐて、半分に切られたのが木にぶら下がつてゐる。しかも逆さまである。「雨が晴れると、このてろてろぼうずを一つに合わせて完全な形にし、御馳走をしてお礼を申すという。」(同前)かういふことをする地域が今でもあるのだらうか。これはアイヌの習俗ではないといふ。ついでにずつと後ろに飛ぶとおしらさま(258頁)がある。真澄晩年の絵である。多くの布に包まれた2体もあるが、男女や馬、鶏もある。馬娘婚姻譚と言ふから、馬と娘が多いのかと思へばさうでもないのであるらしい。真澄の時代も現在も変はりなく信仰されてゐるのはさすがと言ふべきか、19世紀初めのおしらさまを見ることができるのである。珍しいものをかうして描いて残してくれたのは本当に有り難い。関連して恐山がある。真澄40歳の頃の絵である。見開き2枚の絵が載る。左側75頁の絵は参道から地蔵堂を描 く。地蔵堂は小さいやうな気がする。今の地蔵堂はそこらの寺の本堂くらゐはある。ところがここのは、灯籠や石段と比べると、そんなに大きなものとは見えない。村の地蔵堂といふ感じであらうか。恐山といつたところで、現代のやうに人が多く行くやうな場所ではなかつた。これで良かつたのかもしれない。手前には 温泉がいくつか、これは現代と同じである。左手には煙が出ているところがいくつもある。昔も何とか地獄と言つたのであらうか。ここを更に行けば宇曽利湖なのだが、これは右の74頁にある。三途の川は丸木橋 である。人の姿が見えないのは実際に人がほとんどゐなかつたのであらうか。イタコの口寄せでもと思ふのだが、「この時代にはまだ(中略)イタコの口寄せは見られない。」(73頁)さうである。あれも人がゐてこそ成り立つ。さういふ事情であるかどうか。とまれ、恐山が昔から荒涼とした風景であつたことが分か る。その他、112点しかなくても十分におもしろく見ることができる。これがオールカラーで全点そろつ てゐたらと思ふ。壮観であらう。そして民俗や風景に関する多くのことを教へてくれるはずである。個人的には、真澄が若い頃に絵を描かなかつたのが残念でならない。若書きでも習作でも、三河周辺の絵が残つてゐればどれほどおもしろいことか。風景であれ民俗であれ、真澄の目は確かである。真澄の目で見た江戸の 三河の風景を見てみたいと思ふ。しかし、東北の風物で我慢するしかないのが残念である。