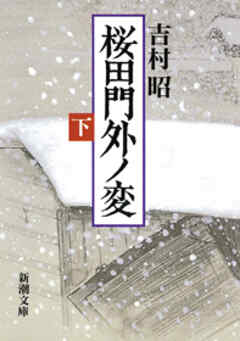感情タグBEST3
Posted by ブクログ
上巻の途中からはどんどん読める。
事件そのものの描写は100頁から133頁までしかない。
事件前後の緊迫した状況が、確かな筆致で描かれている。
Posted by ブクログ
桜田門外の変が、現場を指揮した水戸藩士関鉄之助の視点から訥々と語られている。膨大な資料を基に徹底的にリアルに描かれており、読みながら大老井伊直弼は生かしてはおけぬと思わされるほどである。桜田門外での井伊大老の襲撃シーンは、鉄之助の横で観ていたかのような映像記憶が残る。事変後は、鉄之助はじめ関与者の過酷な逃避行には胸が締め付けられた。吉村昭の筆力に感動する。★5つでは足りない。
Posted by ブクログ
☆☆☆2020年5月レビュー☆☆☆
非常に緊迫感の伝わってくる内容だった。
桜田門外の変、歴史を揺るがしたその時間が遂に起きる。
雪の中を、井伊直弼の行列に迫る水戸藩士たち。
P70~120ぐらいの、決行決定から井伊を斃すまでの展開は、本当に手に汗握る。自分がその場にいるような感覚に陥る。
そして、桜田門外の変のその後。
高橋、金子といった事変の主導者が次々と切腹、投獄の憂き目に。薩摩藩との連携は失敗。
桜田門外の変は確かに歴史を動かしたが、当の実行者には悲劇をもたらした。関鉄之助の逃避行。ここまで調べたか、作者の力量に恐れ入る。
Posted by ブクログ
吉村昭氏の書き方の物悲しさはなんだろう。
高野長英、この本の主人公関鉄之助然りあまりにも切ない。
しかし、世に無名の人が歴史を動かした張本人であったことを、ひしひしと感じさせるその綿密な調査のあとにはただ脱帽である。
世の中を変化させているのは、歴史的功績からすれば極一部の人かも知れない。
しかし、世の中を維持させる役割は、歴史にも残らない一般人である。
我々は、ついつい目立つ人々に目を囚われがちだが、世の中には数多の民がいて、それらは互いに支え合って生きている。
良いことも、悪いことも、その時の情勢で刻一刻と変化する。
ただ、世話になった人にお返しをしようという気持ちは、そう簡単には変化しない。
歴史の転換点では、その人間同士の温もりが、様々な大事件を起こすきっかけとなる。
吉村昭さんの筆蹟を辿ることは、人間とは何かを訪ねる旅である。
私は、最近そんなことを思っている。
Posted by ブクログ
旧暦の3月3日、その桜田門外の変の日は、雪だった。
その事件後のことも、くわしく展開される。
事件にかかわった水戸藩士に資金的に援助していたのが、こんにゃく商人であることも興味深い。今は群馬が名産のこんにゃくは、もともと茨城が名産だったよう。
Posted by ブクログ
決行準備からその後の逃亡生活を詳細に記している。
上下巻合わせて圧倒的なボリューム。
よくぞこれほどまで調べ上げ一つの読み物としてまとめたものです。
それにしても当初の予定が狂ったとはいえ、事件の後がお粗末ですね。
赤穂浪士みたいに全員で自害するって思いはなかったのかな。
Posted by ブクログ
ついに主人公関鉄之助を中心とする水戸藩士の井伊直弼大老暗殺、つまり桜田門外の変がようやく下巻にて達成。
しかし、この事件自体はわずか5分の出来事。小説内での描写もあっという間。その後、藩士たちは逃亡を続け、ほとんどが死を迎える。桜田門外の変は前フリで、作者が描きたかったのは、関鉄之助たちの逃亡生活だったのか。
桜田門外の変から2年、関鉄之助は水戸藩内で捕縛され、江戸に送られて処刑される。37歳だった。
Posted by ブクログ
上、下巻でとても読み応えがありました。
資料を取材して書かれているということで歴史を知る上でも大変勉強になりました。
暗殺に至るまでの時代の状況や経緯、そして暗殺、その後の諸藩の動き、逃亡生活、まさにドラマのようでした。
Posted by ブクログ
羆嵐がきっかけて吉村昭に嵌り込んだ。
読み始めて8作目にて初めての歴史小説。歴史小説はもう少し後でいいかと思っていたが、今度映画が公開されるということで、予習の為にも読んでみた。
歴史小説は元から割と好きな方で楽しみではあったが、勤勉で詳細な下調べはやはり吉村昭、といった感じ(まだまだ既読は少ないが)。安心して読み進められた。そして歴史的に有名な事件、『桜田門外の変』がどのようにして起ったか、その後どのように歴史の流れに繋がっているか、まったく知らなかったことに気付く。
硬質で無駄のない文章と緊張感がたまらない。
要するに歴史小説でも吉村昭は面白い、ということだ。
ますます好きになってしまった。
Posted by ブクログ
桜田門外の変は、幕府と水戸藩の対立、諸外国どの向き合い方をめぐる立場の違いを背景としている。この作品は、水戸藩士の関鉄之介を主人公に事件の詳細を描く。明治維新のたった8年前。歴史のネジを巻くことになった事件。
Posted by ブクログ
徐々に鉄之介が追い詰められていくのが、苦しい。体調不良、情勢の変化や追われる者の精神的疲労、苦痛。信じたことを行い、貫き通すことは、難しい。
多様性が叫ばれる現代。正義は、皆違う。何処に落とし所をつけるか。そのためには、他者理解やコミュニケーションが必要か。
Posted by ブクログ
尊王の志士を鼓舞し維新につなげた一大事変。一瞬の出来事。それは、長期に及ぶ構想と緻密な計画の基に成された。商人に身をやつしての密談。厳重な警戒の中、発覚しなかったのは奇跡。一瞬のタイミングとわずかな判断の差異で事は起きなかったかもしれぬ。大老の死を秘し、彦根藩・水戸藩とり潰しによる動乱を避けた事変後の幕府の判断。その後日本は独立を保つ。実行を指揮した関鉄之介の逃亡。2年を経ての捕縛。歴史は必然であったり、偶然が織りなす運命でもある。また、先人の意志が創り出した結果でもある。そう思い、今を生きる。
Posted by ブクログ
「これは映像になる」
と、どなたかが感知して映画になったのかどうか
2,3前に映画が完成しブレイクしいたのを思い出す
たしかに読んでいて
雪の霏々と舞う中の惨劇を絶えず思い浮かべてしまう小説
日本史の勉強で
「安政の大獄」1859年(安政6年)
「桜田門外の変」 1860年(蔓延1年)
と暗記した昔が懐かしい
けれどもたった2行の年表事項、試験が終われば忘れてしまう
その歴史的事実を忠実に吉村昭さんは小説になさった
ルポルタージュでもない、創作でもない作品
ましていわゆる時代小説でもない
しかし
感動を呼び起こし夢中にさせる筆力
それはなんだろうなぁ、誠実な筆運びというのかな
と、わたしは夢中で読んでしまったのであったが
さてさて、この事件を肯定する気にもなれない
歴史は人々を幾人殺せばいいのかと思う
人間は殺し合いという遺伝子をたれながしつつ滅亡に向かう
Posted by ブクログ
安政7年3月3日(1860年3月24日)の史実。
今から ほんの160年ほど前に起こった出来事
であることに 感無量の思いがする。
その時代に 生きていた人たちの息遣い
その時代に 生きていた人たちの無念さ
その時代に 生きていた人たちの吐息
が 伝わってくる。
筆者の吉村昭さんが
指摘されておられるように
あの「二二六事件」との類似性も
ものすごく気になるところである。
Posted by ブクログ
感想は上巻とほぼ同様なのだけど、事変に関しても現場から離れてみている関鉄之助の淡々とした記述であり、この徹底具合に驚いた。上巻でも書いた通り、これを情感たっぷりに書かれても何か違う気がして、この距離感だったからこそ、張り詰めた雰囲気が醸し出されているんではないかと思った。
Posted by ブクログ
熊嵐とか漂流とか、以前に読んだ作品の方が、より好きでした。もちろん、これがつまらないってことではなく。先日読んだ「四十七人の刺客」でも感じたことだけど、比較的史実に忠実に則って、かつマイナーな登場人物もかなり網羅してっていう風だと、免疫がないとどうしてもとっつきづらさを感じてしまいます。まあ素養のなさがそもそもの問題なんだけど、入門編としては最適ではない、っていうくらいの意味です。桜田門外の変は歴史の教科書で読んだくらい、ってレベルだと、なかなかついていくのが大変でした。ただ、事変がメインなんだけどクライマックスではなく、その後日談がかなりの紙面を使って書き込まれているのは読み応え大でした。むしろその部分こそ、個人的には一番楽しめたところかも。
Posted by ブクログ
忠臣蔵については、周到な準備があった経緯がよく知られている。桜田門外の変については、あまり知られていないと思う。この小説を読んで、経緯がよくわかった。毎度ながら、作者の調査の深さに驚く。
Posted by ブクログ
井伊大老暗殺決行。
いざ命のやりとりになると、道場稽古がまったく役に立たないあたり、二百六十年の泰平をむさぼった侍の体たらくといったら。
その割に自刃の仕方だけは堂に入ってるのがよくわからない。
追われる身となった暗殺実行者たちの多くが、郷里の水戸に戻ろうとしていたのが印象的だった。
単に、自分の味方が多いと思っていたからなのか、それともやはりふるさとに帰りたいと思うのだろうか。
Posted by ブクログ
映画になった時から読みたかった本。やっと読み終わりました。水戸藩側からというか、襲撃現場の指揮をとった関鉄之介の視点で書かれています。彼が多くの日記を残していたとのことで、いつもながら史実に忠実で淡々と描かれてなかなか読み辛い(眠くなる)けど、のめり込んでくると余分な装飾がないぶん、ものすごいリアル感があります。
Posted by ブクログ
井伊直弼暗殺の瞬間と、襲撃者たちのその後について。
井伊直弼が暗殺された後、幕府が水戸藩に対して進言した内容が印象的だった。
一、水戸家は将軍家の分家であり、本家である将軍家を補佐していた井伊大老の死を決して喜んではならないこと
互いに国を護ろうとしていた者同士の悲しい行く末。
関が逃げていくその様子は、絶望と哀愁が漂う。
Posted by ブクログ
桜田門外ノ変自体は数時間のものだろうからそれだけでこれだけの小説のテーマになるのかと思っていたら圧倒されました。
あとがきを読むと資料を丹念に読み砕き、現地に行き、そこでまた人と会い資料を得て、それを骨格として作り上げてその間を想像で補い紡いでいくという作業をしていることがよく分る。
著者は当日の雪がいつ止んだのか色々な文献をあたるが不明で、不明ではあるが気持ちが入っいくと想像できるというようなことを言っていた。本の中では午後2時に止んだとしている。
尊皇攘夷派は今になると分の悪い立場だが、安政の大獄の件を読むと事件を起こすのもやむなしかと思う。井伊直弼の弾圧は過酷を極めている。
襲撃の描写は息を呑む。剣の修行なんて関係ない。怖いので刀のつばぜり合いとなり、刀同士がぶつかったとこで刀を振るので鼻とか耳とか指が散乱していたなんてリアルだ。
井伊直弼は合図も兼ねていたピストルが腰にあたっていてその段階で襲撃は成功だったわけである。雪も幸いした。敵は刀が濡れないようにカバーをしているし、刀にサビがこないようにボロな刀を持っていた人もいて、結果、曲がった刀があちこちに落ちていたとある。
話はこれで終りかと思ったら、主人公の関鉄之介のその後の足取り、最後は逃走に移っていく。このタッチは大好きな「長英逃亡」に似ていて緊張感を呼ぶ。ここまで資料が残っているものかと思ったらあるんですね。
あまりの労作に圧倒されてページを閉じた。
Posted by ブクログ
学校で習った桜田門外の変や安政の大獄。
ただただ丸暗記してただけの歴史的事件が、複雑な人間関係を絡ませながら起こっていたことにびっくり。
読みながら何度も「そうやったんかー…。」の連続でした。
ほんとは映画を観に行く前に原作を…だったんだけど、原作で十分堪能できてしまった。
Posted by ブクログ
桜田門外の変の詳細が、残されていた各種の資料から精密に描き出されていた。襲撃した元水戸藩士のほとんどが直後に自刃などにより清冽な死を遂げる中、生き残った元藩士たちがどのように行動するのか、深く追求されている。歴史だけでなく、戦う者、藩邸に逃げ帰る者など、まるで現代に通じる人の生き様のようなものも感じた。
Posted by ブクログ
名作には違いないが、下巻は関鉄之助を中心とする生き残りメンバーの逃避行だけなので、途中でちょっと飽きてきた。ただ、緊張感が伝わってくる描写はさすが。
Posted by ブクログ
桜田門外の変については、井伊直弼が暗殺された事件。ぐらいの認識しかなかったが、事件に至る過程や関わった人達の気持ち、その後の動向が忠実に書かれていてとても勉強になりました。
Posted by ブクログ
桜田門外の変から明治維新までの8年。激動ですね。お殿様やお家のために家来は躊躇いもなく命を投げ出す。そんな古の時代から8年で近代国家。
幕府大老暗殺なんて日本史上の大事件を起こしながら、維新まで生き延びてよりによって警視庁勤務した奴までいるとは。英国公使館を焼き討ちした初代内閣総理大臣伊藤博文といい凄い時代です。
Posted by ブクログ
・井伊大老の初傷はピストルによる貫通銃創。
・襲撃時間は約3分程度。
・実際の斬り合いは剣術によるスマートなものは全くなく、泥臭い鍔元による押し合いで指、耳、鼻が斬られるケースが多く、襲撃後の現場にはそれらが散乱していた。
・幕府による逃亡者の逮捕捕獲技術の高さ。
Posted by ブクログ
歯医者さんの待ち時間・銀行・バス・寝る前・・・少しずつ読み続けていた吉村昭氏の桜田門外ノ変、やっと昨日読み終えました。2か月もかかってしまった。
そうだなあ・・・僕にとってはきつい一冊でした。どちらかと云えば忠実な、それは多分気が遠くなるような調査の上に書きあげたものだと思いますが、所謂、事実を述べたものです。作者の思いは殆ど入れなかったのではないでしょうか、あとは読者が自分で感じなさいと云うものです。
吉川英治の三国志がありますが、あの本は漢文から来ると思われる朗々とした流れが文から感じられます。そのことで状況描写や心理までをイメージする事が出来たような気が致します。
この桜田門外ノ変にも至る所に武家言葉が出てまいりますが、それは三国志に出てくるような漢文で無く、あくまでも武家言葉です。とは言え、主人公の関鉄之助は歌を詠む事が好きですので
”めぐり逢えて姿見えねど声そえてこは又いかにかかるなみだぞ”
などまたちがったものを感じる事が出来ます。
ペリー来航・不平等条約締結・開国云々の問題に対して、幕府が問題を処理できなかった状態が桜田門外の変を産み、日本は尊攘攘夷・尊王倒幕そして大政奉還と移っていったのです。
今の世の中にリンクするところが多々あり考えさせられました。
Posted by ブクログ
桜田門外の変について、劇的ではなく淡々と実行責任者関鉄之助の足跡をたどった内容。小説というよりもノンフィクションな感覚。
ハイライトであるであろう桜田門外の襲撃のシーンすら数ページでそっけない。歴史というのはきっと何かの瞬間のイベントではなく淡々とした事柄の連続であとから振り返ると劇的な瞬間があったということか。
あとがきにあった「桜田門外の変から明治政府樹立までわずか9年」、「226事件から太平洋戦争終結までも9年」。歴史的大転換はごく短期間に凝縮しておこる、というのに納得。いまはそういう時期なんだろうか?この2つに比べると、まだ凝縮して大事件が起きてる感じではないなあ。