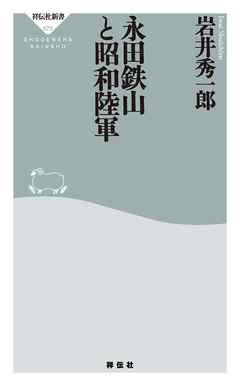感情タグBEST3
Posted by ブクログ
永田鉄山という人物は、いろんな風説が流れやすい人物であるが、改めて整理すると理論家で現実主義者で、天才肌でありながらも理知的で交渉も上手な切れ者という、ぐうの音も出ないほどの人材であったのが分かる。
昭和の陸軍は、かなりいろいろな問題を起こしているが、そんな中で永田鉄山は「総力戦」に備えながらも陸軍内部の統制に厳しく、決してそこから逸脱することはなかった。
いわゆる昭和陸軍が軍閥のように無茶苦茶になっていったのは、永田のようにこうした「国軍」としての陸軍のあり方から逸脱し、気づいた時には下克上と無秩序で支離滅裂になっていった要素が高い。
それは海軍も同じ事が言えるのだが、個人的に酷いと思ったのは永田を殺した相沢三郎はどうしようもないマジキチであり、結局のところ彼らは陸軍の落ちこぼれ仕官で、立身出世が出来ないからこそそれを破壊することを前提に動いていた醜悪な存在に過ぎなかったということ。
それに大川周明や北一輝のような、愚にも付かないようなインチキ思想家を担いでいったわけで、永田鉄山、そして渡辺錠太郎大将らが殺害されたことは昭和陸軍の終わりの始まりだったような気がしてならない。
Posted by ブクログ
永田鉄山について書かれた書籍は多数あるが、歴史研究家が事実に重きを置いて記載してきた物とくらべると、本書は歴史のifに触れる珍しい内容である。そこに面白さがあると言って良い。
永田鉄山は言わずと知れた昭和陸軍における最高峰の頭脳の持ち主で、「永田の前に永田なく、永田の後に永田なし」というフレーズを聞いた事のある読者も多いだろう。その考え方は極めて合理的、神係的な精神論で押し通す事の多い軍人の中で、一切そうした考え方を排除し、膨大な知識からなる状況分析と冷静な判断で渡り歩いた人物である。そして太平洋戦争の遥か以前から「国家総力戦」の重要性を説き、近代国家が避けて通れない大規模な戦争の勃発とその際の国の在り方について研究し、実践しようとした。道半ばにして相沢事件により斬殺されてしまうが、多くの歴史家が「もし永田が生きていれば」と論じたくなってしまうのも解るような、日本にとって欠かせない頭脳であった事は間違いない。国家総力戦については重要であるため永田の言葉を全文引用すると「国家総力戦とは有事の際国家を平時の態勢から戦時の態勢に移し、国家の権内にあるあらゆる人なり、物なり、金なり、あるいは機能なりの一切を挙げてこれを戦争遂行にもっとも都合の良いように按配する事業を指すのである。換言すれば国力全体を挙げ、国民の全能を絞り、これを適当に統合組織して軍の需要を満たすとともに、国家国民の生存を確保してもって戦勝を期する事柄がすなわち国家総動員である。」とし、欧米諸外国と比して後発国である日本が、技術的にも生産力的にも経済的にも遅れをとり、それでも尚、それらと戦禍を交えることになるなら、国を挙げて戦わなければ勝てない事に早くから警鐘を鳴らしていたという事である。事実、永田亡き後の日本は陸海軍の対立、陸軍内部の皇道派と統制派の対立、戦場である現場と指揮の中心にある大本営との考え方の乖離など、軍内部においても、とても挙国一致とはかけ離れた状態で戦争遂行せざるを得ず、各地で屍を晒す大敗という結末を迎える。なお永田の死後、軍を統率した東條英機や武藤章など評判が芳しく無い人物たちも永田の信奉者であり、いずれも官僚としても軍人としてもかつての独裁者、無能という評価を覆し、優秀な人材として見直されたが、永田が生きて彼らを統率できていれば敗戦の内容は随分変わったと考えたくなるのも仕方ない。
本書では永田自らも尊敬する渡辺錠太郎の逸話や、永田を斬殺した大佐の相沢三郎に関する生い立ちや経歴、考え方が醸成される過程など、永田を取り巻く人々についても多く触れられており、より俯瞰的に永田という人物像を捉えることが出来る。特に相沢と永田のやりとりはその後の惨殺シーンに至る以前の対立を臨場感を持って垣間見ることができ、手に汗握る内容になっている。
永田は知的な人物像とは裏腹に、酒も女も嗜み一体いつ何処でその頭脳に磨きをかけているのか、そうした疑問を抱く。政治的な問題も周囲と協調し、反対者すらも説き伏せ、協力を得ながら事を成そうとする姿は現代の会社組織を生きるビジネスパーソンにも大いに参考になる。
迫り来る事件当日を変えることの出来ない歴史の事実として、それでも尚どうにかならないものかという想いを抱きながらページをめくる自分がいる。
Posted by ブクログ
この作者は、主人公の遺族に会って見せてもらった写真や聞いた話を紹介するので、仕事以外の主人公の姿も見えてきて多少なりとも親近感が湧いてしまうという特徴がある。
この手法は好きである。人物を描くからには私的な面があって当然で本当の姿がそこにはあるし、また調査を行って書くということは空想小説ではないという証拠でもある。
永田鉄山は、相沢事件で刺殺され関係者に残念がられたとか、前後に人がいないなどの優秀ぶりが語られているが、それ以上の情報は乏しくよく分からなかったが、その辺りは本書でクリアになったと思う。
合理的だが対人折衝も上手で軍人以外にも理解者が多かったというのは、能力はあっても言動で難のつく才人が目に付く中で、難局でのリーダーにはふさわしいのかもしれない。
永田が生きていれば歴史が変わったかも、と言われるのもこの辺りを指していると考えれば、そうかもしれない。変わっていた歴史が良かったかどうかは別として、そう思わせるだけの人だったことは間違いない。
同じ議論が今後も果てしなく続くだろうが、本書を読んでスッキリしたので、そこはもういいやという気持ちが生まれているのがちょっと不思議な読後感である。