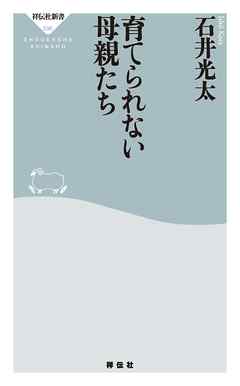感情タグBEST3
Posted by ブクログ
実例が現実感を持って胸に迫ってくる。
なるほど、こういう背景や事情で…と腑に落ちてしまうのが怖い。
こういうことが起きているということを知ることができる貴重な資料である。
Posted by ブクログ
事例が中心で読みやすかった。
いわゆる世間の価値観からずれていることを行えば、犯罪となったり、保護の対象となるが、その価値観は本当に当人たちにとって幸せなのだろうか、と福祉に関わっていたときは常に迷っていたのを思い出した。
何が普通なのか、何が幸せなのか、判断することは厳しいけれども、子どものために、自分の信じる正しいに従って周りが動くしかないのかも。
Posted by ブクログ
世の中にはまだまだ親の愛情をたくさん受けることができていない子どもが沢山いるということがわかった。発見されている分でもすごい件数なのに、発見されていない家庭もあると思うと、目も開けられないほど、悲しくなってしまう。
もっと沢山の世の中の人たちが日本にこんな現状があるということをしっかり理解して日本全体で支えていけるようになっていけばいいと思う。
Posted by ブクログ
これの反対に「育てられない父親たち」が読みたくなっ た。育てられない母親よりも相当な数がいると思うので。
両親揃ってまともに子育てしてれば虐待なんてそもそも起こらないと思う。作者が取材した養護施設に預けられてる子供が全員片親なことが現実なように。
元々生来の気質から「死にたい」と精神的に弱っているケース以外は救いようがあるけど、これは救いようがないのかなと思ってしまった。実親がどんなに頑張ろうとその方の精神は一向に病み続けているらしいので。
Posted by ブクログ
一つ2つではなく多くの理由で子供を育てられなくなる人がいることがわかる。
親だから産んだから愛情が湧くものではない。
母性は作られるもので、備わってはいないことを理解しなければせっかく生まれる子供を守れない。
男女問わず目を通してほしい本といえよう。
問題はそこしれなく、ひろがりもみえない。
人間がこれからどうしなければならないのか、考える時期に来ているのかもしれない。
Posted by ブクログ
石井光太さんの著書は何個か読みました。しっかりと取材され、現実と向き合い、私的に読みやすい。
毒親からの支配、希死念慮の衝動、性の違和感など自分に刺さった内容があった。「子育てに正解はない」なんてよく聞くけど、間違った子育てはある。少なからず間違った子育てで、トラウマを抱えたまま大人になる。間違った子育てを無くすよう、微力ながらも取り組んでいきたい。
Posted by ブクログ
石井光太さんの文体がすき。淡々と事実を教えてくれて、人への愛がある感じ。
この本もしんどいけど、つい手に取ってしまった。今も苦しんでいる子どもがいるかと思うと辛い。
Posted by ブクログ
教育者を目指しており、子どもが抱える様々な問題について理解を深めたく、こちらを購入。
事例を中心に書かれていることから、想像しやすくとても読みやすかった。心が痛み、涙が出た場面もあった。
虐待は決して許されない。しかし、育てられない親がいるというのは現実かなり多く、ニュースでもよく見かける。
教育者を目指す上で、そのような環境下の子どもの変化にいち早く気づき、関係機関と連携をとり、子どもを危険から救いたい。
虐待される子どもがどのような感情を抱き、どれほど傷ついているのか、私は体験していないから分からない点がほとんどだ。でも、子どもの話をよく聞き、寄り添い、自分にできることは全力でしたいと改めて感じた。
この世に生まれてくる子どもたち全員が安心してのびのび生きていくことのできる環境であってほしいし、救うことのできる日本になってほしいと心から思う。
Posted by ブクログ
読むのもつらい事例が多かったが、読むことをやめることもできなかった。
やはり感じるのは、いろんな皺寄せが今も女性と子どもという立場の人間に集まってしまうことだ。
育てられない母親たちというタイトルがついているが、問題は母親にあるわけではなく、一つ一つの事例が複雑な背景が絡み合っていて、これを解きほぐす仕事につかれている方には、本当に頭が下がる思いだ。
Posted by ブクログ
筆者の本をこのところ何冊か、読まさせていただいている。改めて考えさせられることが多い。連鎖。連鎖。負の連鎖、と言っては失礼だけど、愛されて、健やかに育つべき子どもたちが、こんなにも過酷な生活を強いられる。辛すぎるなあ。
Posted by ブクログ
子どもを育てられず施設に預けた親たちの、生い立ちや生活環境を書いた本。
そろそろ母親ではなく父親のほうに注目した『認知しない父親たち』『ヤリ逃げする男たち』というタイトルの本を出すライターが出てきてもいいのではないか。
Posted by ブクログ
虐待や育児放棄に至る原因はひとつではない。
収入の不安定・病気・障害・親も被虐待児だったために問題に対処する能力の欠落など。ゆえに支援しきれない。
また、施設に入った子の年齢により親に対する思いが違ってくるというのもあるらしい。
外国籍の親と言葉が通じない、というのもショッキングだった。
それほどコミュニケーションを取っていないということだ。
また性行為により誰かに求められる喜びを初めて知りのめりこんでしまい、結果望まぬ妊娠につながることもある。
避妊手術を受けられる、というのも支援の中にあっていいて思う。
Posted by ブクログ
子どもを虐待した母親たちの24のエピソード。始めのミュンヒハウゼン症候群以外の人は、母親以前に人としてダメな人ばかり。でもその人たちもこの社会の中での被害者であることが多い。負の連鎖。
他の本(確か熊本のコウノトリ揺かごに関する本)で、日本では児童養護施設に預けても、親と連絡が取れていたり、いつか迎えに来るという意思があれば、特養にはできないとあった。実際に迎えに来ることは少なく、子どもは愛情不十分のまま施設で過ごし、社会に出て行く。本書ではある施設では卒業していった子たちでしっかり仕事をして連絡が取れている人はほんの数人と書いてある。要は、施設を出たほとんどの子は裏社会、夜の世界へと行っている、と。
世の中には説得しても響かない人、そもそも何らかの障害を抱えていて人を育て上げることができない人がいる。そういう人たちでも人間の3大欲求である性欲は普通にあり、また避妊に対する知識が無かったり、性暴力によって子どもができてしまったりする。産まれた子どもたちが少しでも幸せになれる社会を大人は考えなければならない。
Posted by ブクログ
「身体的虐待」「性的虐待」「心理的虐待」「育児放棄」。4種類あるという虐待の事例が22。「複雑な家庭環境に育つ」という聞きなれた将にその通りストーリーが並ぶ。本書は取材報告であり、どうすればよいかという提案は示してくれない。著者の予告通り「気持ち良い読後感」では終わらない。答えは読者がみつけなければいけない。「自分がその場にいたら何か助けてあげたい」と思っても解決にはならない。苦しむ子供たちはたくさんいる。社会の仕組みを改善することを考えなければいけない。最終的には行政の手に委ねなければならない。もっとケアを手厚く。それしか答えはない。お金がかかる。貧困者に負担が重い増税はダメだ。緊縮ではダメだ。お金はある。国はお金をいくらでも作れる。問題は、人手と知恵だ。1人の被害児童を救うために多くの人の労力と知恵が必要だ。それで、解決できるのか、やってみないとわからない。嫌、一刻も早く手掛けなければいけない。この世に生を受けた1人の人間の一生がかかっているかもしれない。邪魔するのは緊縮財政。今できることは?そう、緊縮財政が誤っているということに早く気付くことだ。
Posted by ブクログ
さまざまなケースが出てくる。でも、暴力や育児放棄をする母親側も問題を抱えていて、子どもへと連鎖していく。
本では、地域で子どもを育てる必要性を訴えていた。
でも、もう一つ思ったのが、ここに出てくる話では、男性がすぐ逃げるケースが多い。男性側が逃げてしまえないシステムが欲しい。
Posted by ブクログ
育てられない母親がいても、育てられる父親がいれば、不幸にも命を落とす子供は少なくなるだろうなあ、と感じる。
「babyぽけっと」の活動は素晴らしいものだと思うし、特別養子縁組のシステムはもっともっと普及していって欲しいとは思う。
私にとって子育ては苦行の部分もあったし、そうでない部分もあった。
苦行でしかない時期もあったし、そうでない時期もあった。
なるようになる、どうにかなると、どうしてもっと早く対策しなかったの、どうして誰かに相談しなかったの、がない交ぜになるのが子育てのように思う。
どうやっても、この環境では健全な子育ては無理だ、という事態はあるのだということをこの本は教えてくれる。
親なら子供のためにどんなことでも我慢できるだろう?という常識が、どれほど人によって違うか、考えたことはあるだろうか。常日頃、考えてきたことがはっきりと、言語化されるように感じた。
Posted by ブクログ
本書は児童虐待の当事者である母親に主に焦点を当て、虐待が起きた背景を探る。
複雑化した問題を単純化することなく、地域支援の輪を作り出すことの重要性を主張する。
本書において、一つだけ注文をつけるなら、父親の存在あるいは父親の責任といったものがあまり見えてこないということ。
決して育てられない「母」を責めているわけではないし、取材対象が母親であるからだと推測はされる。
産まざるを得なかった母の苦悩に比べ、「俺は知らない」と逃げる父親や恋人、あるいは、客の無責任たるや。
代理ミュンヒハウゼン症候群の母親については、
最近発覚した虐待死事件でも同様の精神疾患によるものと考えられるものがあった。
その後の報道では母親の生育歴が明らかにされていた。
子供を手にかけたこと、傷つけたことは許されることではないが、彼女自身も救われるべき「子供」だった。
生育歴に問題があったことと虐待をすることは決してイコールではない。
また、知的障害や発達障害等があるから虐待をするわけではない。
だが、筆者が指摘するように、周囲の無理解や、援助のなさが孤立を招き、一番弱いところに行く。
決して人ごとではなく、誰しもが当事者たりうる。
性に対する理解が少ないのなら、学校、家庭、社会で教育・啓発を進めていく必要がある。
「寝た子を起こすな」の教育方針がどれだけ子供を傷つけるか。
子供たちに与えるべきは自分を守る術だ。
子供を守る人が足りないのなら、デジタル技術を最大限取り入れてほしい。
人が足りないのなら、人がやらなくてもいい作業はやらなくてもいい。
支援教育の場に向かうのならば、副業も認めてほしい。
さまざまな理由で子供を助けられる仕事を本業としていない有資格者は多いはずだ。
私も、自治体の支援センターに助けられた。
だから今度はその手を別の人につなげたい。
小さな意見かもしれないが、社会が変わることを、心から望んでいる。