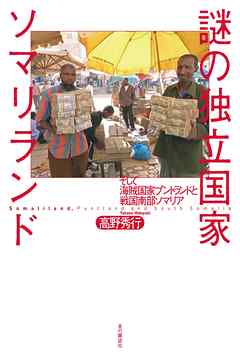感情タグBEST3
Posted by ブクログ
この人の本まじでおもろい。
行動力と探究心がカンストしてるだけで、基本怠惰で捻くれ者の早稲田卒のおじさんだから親しみ深いし同じ穴の狢って感じがする。故にシンプルに憧れる。この人の本全部読む。
あと金なさすぎて海賊雇おうとする件くそやばすぎておもろい。
Posted by ブクログ
2009年と2011年のソマリア--ソマリランド、プントランド、当時の暫定政権が一部を統治していた南部ソマリア--取材旅行をまとめた本。遠慮が無くカネにうるさく氏族を中心に考えるソマリ社会に著者同様に驚き呆れることの連続だった。
本書では主にソマリランドを中心に話が展開する。2度の内戦を経験しながら他のソマリ地域より平和で民主的な「国家」たり得ているソマリランドの歴史と政治体制は興味深い。氏族主義が浸透しているからこそ氏族単位では扱いきれない政治からは距離を置きつつ、氏族の長老たちが政治家たちを監視するシステムは画期的だが合理的だ。本書で幾度も触れるソマリ人の実利を重んじる性分にも合っているのだろう。
プントランドにて著者が半ば本気で海賊行為を立案し試算してみたり、言動や考え方が知らず知らずのうちに“ソマリ化”していたりとクスリと笑える箇所も多数。また、次の表現は本書で特に言い得て妙だと思った。
(前略)私が思うに、国際社会、もっと端的に言えば国連というのは、「高級な
会員制クラブ」みたいなものではないか。
人類普遍の理念に基づいた公平な組織と勘違いされることもあるが、実際には民
主主義とも人権とも直接関係がない。
なにしろ、このクラブは5人の理事の権限がひじょうに強く、理事の一人が反対
すれば、どんな素晴らしい提案も却下されてしまう。そこからして反民主主義的
だ。それに理事の一人である中国自体が人権や民主主義とは無縁だし、会員にも非
民主主義国家がたくさんある。
それはしょうがない。なんせ、第二次大戦の戦勝国によって任意に作られた会員
制クラブなのだから。公平や正義を期すほうが無理である。(後略)
※第7章8
2020年代のソマリ地域--ソマリランド、プントランド、ソマリアはどのようになっているのか、著者には引き続き取材してもらいたい。
Posted by ブクログ
ソマリランドが奇跡の国だということがよく分かりました。読み進めていく内に、ソマリ人に愛着をもっている自分がいました。カートは一度体験してみたいです。
Posted by ブクログ
ソマリアのソマリランド、プントランド、南部ソマリアについて書かれた本。
ソマリランドの内容を、日本の戦国時代になぞらえて書かれていたので、わかりやすかった。文章も小気味よくテンポ良く読めた。
紛争あったり、海賊あったり、大変だなーとこっちは勝手に思ってしまうが、住んでいる人たちはそんなことあまり思ってなさそうで、バイタリティ溢れている。
南部ソマリアで出会った、ハムディはかっこいい!
女性で若いので、何かと大変なこともあるかと思うが、本当に剛腕すぎる!!
テーディモの探検にも行ってほしい!
Posted by ブクログ
複雑で飲み込むのは難しいが、実際の旅行記と併せてソマリランドについて説明されており,面白かった。
臨場感があり、登場人物は皆面白い。
読むのに時間がかかったが,ソマリランドについて知るための貴重な資料だと感じた。
Posted by ブクログ
「氏族」という概念があるのを初めて知った。とても面白い仕組みで、さすがに細かな分類や経緯は読んでいて難しかったけれど氏族の何たるかやその掟(ヘール)についてはざっと理解できた。
筆者、バリバリカートやってるな。
ソマリ語ってどんなものなんだろうと思った。
写真がもっとあればより良かった。
Posted by ブクログ
ソマリランド、内戦可にあるソマリアのなかにありながらすごく治安がよいラピュタのような国(国としては認められていないが)。
以前未来世紀ジパングで特集していて上記のような程度の知識しかなかったが、高野氏の潜入・取材力によって、物語のようにソマリ人の特徴、またソマリランドの設立?の流れが色鮮やかに入ってきて本の分厚さが全く苦にならなかった。
ソマリランドにとどまらず、海賊国家プントランドとリアル北斗の拳の南部ソマリアも取材したことでより色濃くソマリの流れやそれぞれの氏族の言い分があり、多方面からの視点がとりあげられててよりソマリランドとは、ソマリ人とは、ということが浮き彫りになっている。
カート宴会のなかでヒアリングする力は素晴らしいし、氏の辺境地での経験値とイスラムの知識などからなる疑問ポイントも秀逸。
「国連は高級会員クラブみたいなもの」はたしかに、と深くうなずけた。その他もうなずけたり気づかされるポイントが多く、俯瞰と現場第一の両方からなるこのような視点をもっていたい。
別の国と仕事やそれ以外でもかかわるとき、これくらいの知識を身に着けていきたいし、それでもなお、わからない、というスタンスをもって接したいと思う。
Posted by ブクログ
この本でソマリランド、プントランドの存在を知った。著者の好奇心とソマリランド愛に引き込まれる。海賊がなくならない説明、海賊はビジネスって目からうろこだった。難民キャンプにいる人達が笑顔というくだりも印象的。実は皆生き生きして笑みを浮かべているそうだ。それは安心しているから。やせこけた、目がうつろな子供ばかりを難民キャンプの写真に添えるのはプロパガンダ。
著者は氏族について、日本の士族に置き換えて説明してくれているけど、それでも頭に入ってこない。だが、氏族政治が成り立っている仕組みは興味深い。行ってみたいなソマリランド。
Posted by ブクログ
ソマリランド、プントランド、南部ソマリアへと行った人の記録で、書き方が面白いのでグイグイ読ませる。
ソマリの文化に染まっていって日本の常識を相対化してくれる。
海賊の背景にあるもの、ソマリの文化と歴史、カート食べるとどうなるかとか、真面目な話からおふざけな話まで色々勉強になる。
Posted by ブクログ
これは、面白い!!
なかなかボリュームのある一冊だけど退屈とは無縁の読書タイム!ただの物珍しい・楽しい旅行記とは一線を画している。というのもソマリア(ソマリランド・プントランド・南部ソマリア)の歴史や氏族の仕組みなどを文献にあたるだけではなく現地でカート中毒になりながら質問に質問を重ねて詳しく調べ上げているあたり、著書の並々ならぬソマリランド愛を感じる。氏族を日本の戦国武将にたとえて説明してくれるのはナイスアイディアで大変わかりやすい!これがないと絶対挫折してた…。
Posted by ブクログ
欧米人や日本人の感覚としては、かなり危険を伴うことが予想される東アフリカのソマリアへ、著者が現地へ飛び込み、知り得た情報、現地人とのコミュニケーション、感じたことが綴られた渾身のルポルタージュ。
ソマリアが、北部から南部にかけて、ソマリランド・プントランド・ソマリアの3つに分断されているとは…、この本を読んで初めて知りました。
アメリカ映画の"ブラックホークダウン"程度のフィクションや、たまに伝えられる新聞記事で聞きかじる程度でしたが、この本からソマリアに関する様々な事を学びました。
ソマリアの歴史や現況を知るキーワードとして、"氏族"という概念がありますが、外国特有の用語や、様々な氏族の系統を、日本の歴史で登場する源氏・平氏・戦国大名・応仁の乱など有名な合戦名を駆使して比喩してくださったお陰で、かなりわかりやすく読み進めることが出来ました。
また著者は、分断されたソマリランドがなぜ争いがない民主主義が形成されているかという問いに対し、氏族間の規律、戦争を知るが故の相互抑制力、エネルギー・工業や商業・観光資源などがなく他国からの介入がなかったことを挙げてます。しかしながら、国連などの介入なしに、独自に氏族間の調整などボトムアップで民主主義体制を築き上げた点は、素晴らしいとも。
一読して感じるのは、アメリカや国連など第三者が介在することで生じる歪みの方が、ソマリランド内の氏族間の話し合いにより生じる歪みよりも、はるかに大きく、それを乗り越えるためのモチベーションも違うのだなと感じました。
グローバル化と逆行するかもしれませんが、意外と他国のお節介を焼くよりも、本当に支援が必要な時のみ、仲介に入る方が良いのではないかと。
ソマリアだけでなく、アフガニスタン、中東などの紛争の全てに双方の当事者を支えている国々がいるからです。
歴史は語る。
いい気付きを与えてくれた本書に感謝!
Posted by ブクログ
圧倒的に面白い…
久々に陶然たる読書体験であった。
国際社会では長らく無政府状態とされているソマリアの中にあって、独自の政治機構を有し、もはや浮世離れしていると言えるくらい、治安の良いハイパー民主主義独立国家・ソマリランド。
この存在を知った著者が、実際にソマリランドへと渡り、歴史・文化・風俗・土地・信仰など、あらゆる側面からその真実に迫っていくルポルタージュ。また、海賊国家プントランド・戦国南部ソマリアという、異なる軌跡を辿った旧ソマリア統一国時代の国々との比較から、なぜソマリランドだけがこのような国家を成立し得たのか、また三国に通底するソマリ社会とは一体どのようなものなのか、その謎を解き明かしていく。
徐々に全貌が解き明かされていくプロセスが、著者の熱量を持って筆致されており、もうとにかく興奮が止まらない。
また、著者が徐々にソマリ社会の一員と化していく様が面白可笑しく、また羨ましくもある。
「カラシニコフ」(松本仁一著)を読んでいても感じたことだが、著者は私が理想とする旅人像というか、記者像というか。
こんな旅がしたい。世界に対して、常に彼らのようなスタンスで向き合っていたい。読んでいて、尊敬と羨望、自分もこんな旅がしてみたいという憧憬が入り混じり、終始高揚感が止まらない、そんな一冊でした。
文句無しでオススメです!ソマリランド、行ってみたい!!!
Posted by ブクログ
事実と主観が意識的に書き分けられているので、とても読みやすい。
そしてエキサイティング。
人間くさいソマリ人に笑わされた直後、シビアな現実に考えさせられたり。
ボリュームが大きく歯ごたえがあるが、一読の価値あり。
Posted by ブクログ
ふとしたことでソマリアの情報が欲しくて、たまたま手に取った本だった。ソマリアの歴史と現状を高野氏が現場に入って手に入れた情報を元に執筆したものである。ソマリ人の内戦の歴史、多国籍軍や国際機関の介入、イスラム原理主義の台頭など複雑に絡み合う戦争の要因とその中で平和を維持するソマリランドの謎について日本人にわかり易い比喩を用いて説明している。一度読むと時間を忘れて読み進め、ソマリ人国家の現状が映像で流れているような錯覚を覚えた。国際協力に関心のある私にとって多国籍軍や国際機関の役割を考える上で役に立った本だった。
Posted by ブクログ
ほんとおもしろかった。ソマリアいえば世界一の失敗国家、そこら中で戦闘と海賊だらけというイメージでいたが、そこには人間がいて生活があってまさか自称民主主義国家があるなんて想像しなかった。
そして著者がすごい。よくここまで取材を重ねて、ソマリ社会に入り込んでしまうなんて。最後はちょっと感動させられた。
Posted by ブクログ
「およそ真実の探索者は、塵芥より控え目でなくてはならない。」 (ガンジー 『ガンジー自伝』)
読み終わると冒頭のこの一節が本当にその通りだなと痛感する。
これまで生きていた中でなんとなく"常識"として自分の中に埋め込まれてきたことが一歩外に出ると全然そうでなくて、ソマリアの人はソマリアの仕組みで生きてる。だからこそ外から介入があるとその仕組みは維持できなくなる恐れがある。そんな中で自分たちで上手く築き上げてきた奇跡のような国(認められてないが)がソマリランド。
ソマリランドとして平和を維持できているのが、農業や産業が盛んな南部ではなく、"何もない"北部なのが皮肉だけどリアルだなと思った。
「ソマリランドは貧しくて何もない国だから、利権もない。利権がないから汚職も少ない。土地や財産や権力をめぐる争いも熾烈でない。」
という言葉が印象的だった。
逆に、内戦が厳しいモガディシュでは
「"トラブル・イズ・マイビジネス"でトラブルを起こせば起こすだけ、カネが外から送られてくる。モガディシュはトラブル全般が基幹産業なのである。」
高野さんが現地に入り込み生活する中で知ることを共有してもらうことで、メディアではなかなか切り取られないリアルを少し知れた気がする。
明るくない内容もあるけど、高野さんの軽快な語り口調と愉快な登場人物のおかげで、すごく読みやすい。
毎度思うけど、高野さんの人物描写は面白おかしく魅力的に登場人物を描いていて、私が高野さんの著書を好きな理由の一つ。今回も「まじか?!」と思うエピソードもありつつ、魅力的なソマリアの人たちをたくさん知れてとてもおもしろかった。
Posted by ブクログ
本が分厚くて、読み応えがたっぷり。ソマリ愛溢れ、しかも全く未知の世界、文化。ソマリアというと紛争地帯で治安が悪いイメージだが、その中に存在するソマリランドという平和な民主主義を保つ独立国家。冒頭から沢木耕太郎の深夜特急でも読むようなワクワクが止まらない。その疾走感で突き抜ける読書。ソマリ人の早さ。カートをキメた明晰さ。
ソマリランドから海賊国家プントランドへ。旅を続ける中で、国や文化、氏族主義などの制度を学び、発見する著者。まるで文化人類学の領域。果ては、海賊ビジネスに手を染めようとしたり、地元メディアに登場したり。大麻みたいなカートを食いまくる様は写真の著者からは想像つかない。
そして、モガディショの剛腕姫との出会い。危険な南部ソマリアのホーン・ケーブルテレビ・モガディシオ支局長のハムディ。垢抜けて性格も男前な彼女は、別著『恋するソマリア』のカバーに写真があるが、想像通り。これは著者の表現力が素晴らしい。
色々と意識散漫だが、とにかくあちこち、著者と共にスリリングに楽しめる内容。
Posted by ブクログ
最初手に取った時、予想よりも分厚くて驚いた。
でもするすると読み進められてしまった。この本でソマリアがもはやひとつの国ではないことを初めて知った。ソマリアにプントランド、南部ソマリア。なかなか事情がややこしかったが、筆者の体験に沿って得られる驚きはまるでミステリを読んでるようだった。
氏族文化や、ソマリ人がどのような価値観で生きているのかなど、どれも新しい価値観で新鮮で面白かった。
Posted by ブクログ
高野秀行の体を張った渾身のルポ。世界から危険だと思われていたり、実際に危険だったりする場所に乗り込んで極力現地に馴染む。そういう手法が最大限活かされており、これまで日本はもちろん、旧宗主国という比較的なじみの深い国でも理解されていなかったことが書かれている。
何しろ我々には縁遠い場所だが、日本の読者のために用いられる比喩(リアル北斗の拳とか、イサック藤原氏など)が読者の理解を助けてくれる。
本書が書かれてからだいぶ時間も経ったが、いまどうなっているのかという興味をそそられる。
Posted by ブクログ
派閥や登場人物が多すぎて、敵になったり仲間になったり複雑で頭の中が大混乱。
途中からメモに図を描きながら、間違えて解釈しないよう一生懸命読んだ。
先進国が常識としていることが、この国では常識とは限らない。ここまでの取材力にただひたすら驚き。
Posted by ブクログ
・ソマリ人と一緒にラリって仲良くなって彼らの懐に入り、ソマリ社会の掟や常識を聞き出す著者の情報屋としての能力。ソマリ人以上にソマリ人へ変貌。この人の自然体っぷりはとっても魅力的。
・著者は取材生活の中でソマリ語を独学で習得していきメキメキ上達し不自由なく会話している
・人の話をちゃんと聞かないうるさいソマリ人。そんな彼らを相手に、「ソマリ論(日本人が好きな日本論のようなもの)」の議論になって、ソマリ人のネイティブ相手に「教えてやろうか、ソマリの歴史ってのはなあ…」と知識で相手を打ち負かすくだりは圧巻で、なんか泣けてくるものがある。
Posted by ブクログ
ソマリアという危険極まりない辺境の地で、奥深く完全に現地に溶け込んで取材したからこそ書ける圧倒的なリアリティのノンフィクション。
普通に面白く読める。
Posted by ブクログ
ソマリ世界の事象はとても複雑だが、作者が確認がてら同じような内容を何度も言及してくれるので、大きな混乱もなく読み進められて、なんかありがたい。
どの内容も新鮮な驚きにあふれていたが、「海賊を雇う際の損益計算」の具体例は圧巻。
実際に現地に行って生で見ないことにはわからない、というのは本当に仰る通りだと思います。
Posted by ブクログ
ソマリランドの存在は昔から知っていて、当然気になっていて読んでみました。
当たり前だが、日本の常識、欧米の常識が人間の常識ではない。
「氏族社会」、この本で初めてそれを知りました。
決して分かりやすく説明されてはいないけど、今のソマリアを知るうえでの信頼できる相当量な情報が書かれている一冊であることには間違いないだろう。
Posted by ブクログ
今までこうゆう本をあまり読まなかったけど、面白かった。情勢がころころと変わる場所なのだろうから、時々、ソマリランドはいまどうなってるのだろうと思いながら読んだ。
Posted by ブクログ
本当は「ハードボイルド室町時代」の方を読みたかったのだが、さすがにその前にこっちの有名本読んでないとまずいかなと。
異文化モノにカテゴライズしたけど「アフリカのこんな辺境にはこんな珍しい風習が…」といった世界ビックリ列伝みたいのではない。読んで、コミュニティデザインの参考書みたいと思った。この手の本ではよく、どこかの自治体のささやかな成功事例などを紹介してるが、こっちの本は共感や理解には程遠い気がするアフリカの、さらになんかヤバそうなソマリランドが舞台。ソマリ人社会は確かに日本人と全然違うのだが、にも関わらず、彼らの国の動かし方を知ると「ウチでも取り入れた方が」とか「こっちのやり方の方がいいんじゃないの?」とか思ってしまう。なんかソマリランドのやり方の方がシンプルで洗練されてる気がしてくる。民主国家のあり方、国とは何か、国と国民、なんて、普段は絶対に見向きもしないテーマが実はこの本の背骨になっていて、すごく自然とそういうお堅いとされる事を考えてる自分に気づく。なんか底知れないものがこの本には潜んでいます。
あと、遊牧民気質の私にはソマリ人は共感するところが多々あった。拉致文化にも納得してしまった。世界は長いこと欧米の尺度だけで出来事の良し悪しを決められてきたけど、さすがにその仕組みが疲弊してきた昨今、元々の地域にあったやり方というのが一番なじむのだろう。とすると全世界がまた鎖国化していくのもいいんじゃないかと思ったけど、日本の大黒屋からソマリランドに一瞬で送金できる利便性は否定できないなとも一方で思う。
Posted by ブクログ
ソマリランドというとそういや一時話題になってた。ソマリアとソマリランドじゃ全然違うんだとか、アグネス・チャンが行ったとかなんとか。まぁでも総じて、あそこヤベーって感じな煽りがメインで、でもなんか写真もないし、皆さん又聞きっぽいし、話半分って感じではあったけど、実際のところどうなんか、ってのはあった。まぁそんな深く考えて気にしてはなかったけど、こうやって読んでみると、とりあえずこのおっさんおもろいな、と。ソマリランドとか周辺のことが何となく分かるけど、結局のところはそれを楽しく読ませなきゃしょうがないんであって。文字で読む分には、ふーん、てとこだけど、実際に体験したら大変だったって次元じゃないな、って話もいっぱいあって、ちょいちょい面白いので、難しい文化的な話もなんとか読み切れた、かな。
てか麻薬的なものも、日本ではやったらやばそうだけど、禁止されてない海外でやるぶんには問題ないんだよなー、ってのが考えてみりゃ不思議だ。おっさんが楽し気に嗜んでるのを読んでると、自分も一発試してみたいなー、なんて思ってるのが恐ろしい。
Posted by ブクログ
ソマリアといえば映画「ブラックホーク・ダウン」のとおり、民兵がウヨウヨして無政府状態を想像するのだが、北部のジプチ・エチオピアの国境付近にソマリランドという独立国家がある。
大統領も議会もあり、方法は日本より進んでいるところもある。
著者は2度にわたり、ソマリア、ソマリランドを訪れ人々の生活やソマリアが今の混乱に至った経緯を現地人の目線で取材、ソマリア人に半分以上染まってしまった状態である。
ソマリアは氏族が支配する国だが、日本や欧米での報道では氏族がほとんど出てこないので「なぜ混乱が続くのか?」が理解しづらい。
著者は氏族を日本の武士にあてはめ、わかりやすく解説、終始氏族と切っても切れないソマリアの実態がわかり面白い
Posted by ブクログ
とても採算の合わない取材で、物好きと仲間に称される高野さん。
アフリカは人類の発祥の地、
広大な土地にまだ未確認の地下資源も。
人口の多さは、巨大な市場にも。
建前上、国家として認められているのに、
国内の一部(もしくは大半)が、
ぐちゃぐちゃというなら、イラクやアフガニスタンなど
他にもたくさんあるが、その逆というのは
聞いたことがない。まさに謎の国、地上の「ラピュタ」
ソマリランドの存在する地域は
今もなお無数の武装勢力に埋め尽くされ
戦国時代の様相.「リアル北斗の拳」
陸が「北斗の拳」なら、海は海賊が「リアルワンピース」
そんな崩壊国家の一角にそこだけ、十数年も
平和を維持している国それがソマリランド。
509ページという分厚いノンフィクション。
ヒリヒリするような危険を背にしながら
高野さんはいたってマイペース。
なんでもお金に換算し、ふっかけてくる輩に
自称「ネギカモ」とつぶやきながら
見たいこと聞きたいことに奥深くまで潜入する。
同じソマリ人でもソマリ人を語るには
部族ではなく氏族を整理しなくては理解しがたい。
また、その文化も途中どこの国の植民地だったかで、
本来の文化の失われ度が違い、性格も違う。
イスラム過激派が国にとっては
「亭主元気でするがいい」ならぬ
「イスラム過激派元気で留守(国内にいないこと)がいい」
国としての成長を考えると、とかく閉鎖的で、
発展から遠ざかる考え方の過激派。
だが、政敵や敵国を退けるには必要。
キリスト教国家が敵国に打撃を与えるために
原理主義(これは本来キリスト教のことばです)を利用し
また、統治に失敗した元政府が倒れた時
その反動としてこのようなイスラム過激派、原理主義が
はびこるが、これを熱狂的に指示するのは
高圧的で、厳しい禁止事項があってもなくても
同じ何も持たざる者(貧民)たちのみ。
元の政権が倒れ、一時的に受け入れても
その内容を見るや、逃げ出す人々が難民になる。
まぁ、長くはありますが面白い一冊です。