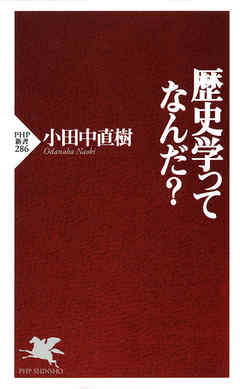感情タグBEST3
Posted by ブクログ
最近真面目に歴史の勉強を始めてからこっち、自分の中でぐるぐる渦巻いていた命題にたいして、数十年余分に行きてる先輩から分かりやすいビジョンを見せてもらえた、という感じでした。
まだまだ勉強不足で批判的に評価できてるかは分からないけど、私にとってこの本は足がかりの一つとして充分すぎる素晴らしい本でした。
出会えて良かったです。
私が持っていた命題に対して私が想像してた落とし所以上に思考を提示してくれました。
Posted by ブクログ
名著級です。歴史を「学問」とするものは何か? 歴史学と歴史小説とはどこが違うのか? 歴史学は社会に何を貢献できるのか? そういう素朴にして巨大な疑問に正面から立ち向かった本。
そもそも「歴史学は史実を明らかに出来るか」という疑問がある。現在から過去を推し量ることはどこまで可能か? 本当に正しいことにたどり着けるのか? 本著は構造主義のインパクトも織り込んだ新しい解釈で、この疑問に立ち向かっている。
さらに、「歴史がなんの役に立つのか?」という疑問についても真摯に追究している。「従軍慰安婦論争」を例に取り、「新自由主義史観」の主張なども交えて、「役に立つってどういうことなのか」という課題にじょじょに迫る手際は、木訥とした味わいながら、非常に納得できるものだった。
歴史を学ぶ、ということは、実は非常に現代的な課題をクリアにしない限りできない営みである。「自虐的な歴史ばかり教えるな、日本人として誇りを持てる歴史こそが必要なんだ」という立場もあるだろう。「当事者の数だけ真実があるのだ」という立場もあるだろう。その中で、自分はどんな「歴史」を語れるのか。どうすれば、自分なりの問題を設定でき、自分なりの結論にたどりつけるのか。「歴史学」を学ぼうとする者は、常に揺れ動き、ひんぱんにつまずくのだ。この本は、初学者にとっての頼れる足場を提供してくれるだけでなく、歴史学に迷いさすらうときの灯台としても、必ず役に立ってくれることだろう。
壮大な課題に対して、きちんと考えるための枠組みを与えてくれるばかりか、希望を与えてくれる本は初めて。しかもわずか、200ページの新書でそれを達成しているところがすごい。歴史学の読書ガイドとしても素晴らしいので、すべての人におすすめ……としたいところだけど、せめて大学で歴史を学ぶ人は絶対必読。
Posted by ブクログ
最近、あちこちで話題となっている歴史認識問題を易しく解説した本です。歴史学は暗記の学問だという思い込みをくつ返してくれるはずです。史学科に進学するまたは進学中の方は、ぜひ手に取ってみてください。
(九州大学 大学院生)
Posted by ブクログ
○歴史学ってなんだ?
小田中 直樹 著 PHP新書
タイトルを見て想像していたものよりずっと奥が深かった。(例えば構造主義だとか)
そうか、そう単純な問題ではないのか。
かなり考えさせられる本であった。
Posted by ブクログ
1963年生まれのフランス経済史を専門とする経済史学者・小田中直樹による2004年の著書。
著者は本書の内容について、序章で、歴史学の意義とは何かという疑問に答えるべく、①歴史学は歴史上の事実である「史実」にアクセスできるか、②歴史を知ることは役に立つか、役に立つとすれば、どんなとき、どんなかたちで役に立つか、③そもそも歴史学とは何か、という三つの問題を取り上げるとすると同時に、本書の目的について、あとがきで、①歴史学について、なるべく体系的に基本的な知識を整理すること、つまり、歴史学の入門書として機能すること、②歴史にかかわる優れた啓蒙書を紹介するブック・ガイドとして機能すること、③歴史を考える枠組みを再検討してみること、の三つと述べている。
本書の主な主張、及び私の印象に残った点は以下である。
◆歴史学の営みは、史実を明らかにすること、即ち「認識」と、認識した史実に意味を与え、ほかの史実と関連させ、その上でまとまったイメージである歴史像を描くこと、即ち「解釈」という、二つの作業から成る。
◆1970年代に現代思想家ジャン=フランソワ・リオタールは、「“大きな物語”は終わった」、即ち、歴史のトレンドを描き出すことは無意味になったと主張したが、実際には、“大きな物語”が終わったのではなく、それぞれの民族の歴史や大衆の歴史などの様々な“大きな物語”が併存するようになった、即ち、歴史の相対化の時代に入ったということである。従って、歴史家は、たとえ相対化されたものではあっても、より正しい「解釈」を求め続けることが使命である。
◆同様に、1970年代に言語学者フェルディナン・ド・ソシュールが展開した、「もの」、「意味」、「言葉」の三者の繋がりは恣意的なものにすぎないという構造主義の思想は、歴史の「認識」についても疑問を投げかけるものであったが、歴史学に求められているのは、コミュニケーションによって、多数の人々の間で正しいに違いないという「認識」に至ること、更に、そこからより正しい「解釈」に至ることである。
◆歴史学は、外国に関わる歴史像や、外国と日本の関係に関わる歴史像を提供し、我々の集団的なアイデンティティを相対化する際に重要な役割を果たす。しかし、第二次世界大戦に向けて、日本人の意識を統制したのが当時の歴史学を支配する考え方であったことなどを踏まえると、歴史学が「社会」の役に立つべきか否かという問題を考える際には、慎重さが求められる。むしろ、根拠がある史実に基づくという真実性を経由した上で、直接に「社会」の役に立とうとするのではなく、つまり、集団的なアイデンティティや記憶に介入しようとするのではなく、「個人」の日常生活に役立つ知識を提供しようとすることが大事である。
◆そもそも、様々な科学を学ぶことの意義は、自覚的にものを考える必要に迫られたときに「考え方のモデルのカタログ」として自分の役に立つ、地に足がついた知識としてのコモン・センスを体得することにある。そして、歴史学もその科学の中のひとつなのである。
若手の歴史学者が、現代思想の考え方を取り込みつつ、歴史学の意義と課題(更には限界)を率直に述べており、好感の持てる一冊である。
(2006年12月了)
Posted by ブクログ
歴史を学ぶ意味について、近年の研究の成果を取り入れつつ、簡便にまとめた入門書。あとがきで著者が触れているように、古典的名著が入手難であったり、文体が固く、専門外の読者には取りつきづらかったりするのに対し、内容が大分噛み砕かれており、歴史について生じ易い疑問である「史実は分かるか」「歴史は役に立つのか」という二つの主題について理解しやすい。
Posted by ブクログ
「歴史学で本当に史実を明らかにできるのか?」「歴史学は本当に役に立つのか?」という、「なぜ歴史学を学ぶのか」を考えるにあたって出てくる疑問についてガッツリ書いてくださっている本。
また、歴史教科書に対する批判もあり、「おおこの人もか!」と思ってしまった。ただ、小田中氏の場合は、倉山氏とはちょっと違って、教科書と言うよりも、教科書にそういう書かせ方をするシステムが問題と言う言い方をされていて、私もむしろこっちが問題だろうなと思いました。
Posted by ブクログ
これはなかなかに興味深かった。学問としての歴史学を歴史小説から区別し、では如何に違うのかを紐解いていく。○○年に何があった、って授業で習うけど、果たしてそれは事実なのか、っていう疑問立てから学問が始まる。そこに至るまでに色々検証された結果が、現在一般に理解されている史実だろうから、それが簡単にひっくり返ることはまああまりないだろうけど、それを細かく調べて検証し直すっていう部分に向く興味は、歴史好きの自分にも理解できるものでした。
Posted by ブクログ
何回か読み直しましたが、その都度考える機会をあたえてくれる是非ともお勧めしたい書籍です。あまりしないことですが、知人に何冊かお配りしました。
かつて、大塚久雄、丸山眞男、内田義彦などが文化系大学入学者の登竜門でした。色々な著作を読み、ゼミなどで自分の専門分野を深めていくいくにつれて、これらの書かれた啓蒙書の意味などがわかってきたように思われます。本書はいきなり理解できます。
本書は、タイトルのように歴史学とはいったいどういうものであるのか、あらねばならないのかを解説しています。だが、深いですね。社会、人文科学というものは科学たりえるのかという考察をしています。言葉の定義づけもしっかりされていて、齟齬,破綻もみうけられません。
歴史学の仕事の重要な要素として認識と解釈をあげらています。とっかかりとして、小説と歴史書の違いから始まります。それにまつわる具体的な話と抽象的な話をうまく関連づけされていて非常にわかりやすく書かれています。
歴史を学びたいが、小説ではと思っている方、学術書では大変だなと思っている方は、本書をお読みになって自分の学ぶ道筋をつけるのには絶好だと思います。
構造主義やポストモダンをわかりやす説明されていているので不勉強な私にとっては大変助けになりました。
「大きな物語は終わった」ということを知りたかった私は、とても収穫がありました。
従軍慰安婦問題を通して坂本多加雄、吉見義明、上野千鶴子の論争の話がでてきますが、学問のありかた、論争の意味など内容もりだくさんです。
一つの問題を考えると、また新たな問題がでてきますね。それをどのように処理していくのか、又、問題はどのような姿勢で考えていくべきなのかという重要なヒントがいっぱい詰まっている新書ですね。
蛇足ですが、出版社は、このような啓蒙書を新書としてだして欲しいものですね。それが、自分達の生き残りにつながると思うのですが。
Posted by ブクログ
他の新書に比べると平易な言葉と
口語表現によって論理展開がなされる本書は
とても理解しやすいものであった。
歴史学ってなんだ?
というタイトルからもあるように
歴史学の入門書として良書を探していた著者が
無いなら自分で書こうと至った作品
歴史学の入門書ということもあり
歴史学者が研究を行うプロセスを
より具体的に説明しようという姿勢が見て取れた。
Posted by ブクログ
講義の参考図書で、最終レポートを書くのに読んだ。歴史を学ぶのって義務的だなと思ってたところがあったけど、ちょっと意識が変わったかも。またちゃんと歴史学ぼうと思った。
Posted by ブクログ
本書は「素人のための歴史学入門講座」(「内容紹介」より)と銘打っているように、歴史を専門的に学んだことのない人々-特に、歴史は“暗記”であり、社会の役に立たない“虚学”だと思っている人々に向けた一冊である。
筆者が強調するのは、歴史学における“プロセス”の重要性である。それは、歴史家に必要な資質を「疑い、ためらい、行ったり来たりすること」(p.151)だと規定していることからも分かるだろう。つまり、教科書の記述(解釈)を暗記することが重要なのではなく、むしろ、その解釈を疑い、史料を通じて「より正しい解釈」を導き出す営みこそが、歴史学の本髄であると指摘する。さらに言えば、与えられた前提を疑い、使えるデータを批判的に解釈し、他の人々とのコミュニケーションを通じて、新しい解釈を打ち出すという作業は、歴史学に限らず、社会一般に役立つスキルであるとも言えよう。
その他にも、本書では様々な視点から歴史学という学問を分析していく。入門書という位置づけ故に、その記述の一部には、楽観的過ぎたり、簡略化し過ぎたりする部分がないわけではない。しかし、分かりやすさという点も含めて、これから歴史を学ぼうとする人(あるいは、歴史が嫌いになってしまった人)が最初に手にするべき一冊としてオススメしたい。
Posted by ブクログ
高校の教科書を見て、「歴史は何の役に立つのだろう」と思った人向けの本。
歴史学は過去の真実(史実)を明らかにする学問である。
そして、史実という事物の根源を知ることで、その問題に定義づけをすることができる。
物事を考える際には先ず問題を意識する必要があるが、その問題の定義づけをするのに歴史は非常に役立つのである。
Posted by ブクログ
「なぜ歴史を学ばなければならないのか」という問いは,多く聞かれる。筆者は歴史学がこれまで歩んだ経緯を示し,その存在意義を述べている。
歴史学が史料批判を通じ「より正しい解釈」に至ることの営みであることは,説得力がある。
近年の教科書問題にも通じ,その解決にも寄与する書だと思う。
Posted by ブクログ
この本では三つの問題を考えています。
①史実はわかるか?
②昔のことを知って社会の役に立つか?
③そもそも歴史学とは何か?
みんなで検討し、より正しいものを選び取っていく。現在の段階で最善を尽くし、史実をより正しく認識し、解釈し、よりよい歴史像を構築するべきことを考える。しかし将来どう評価されるかはわからない。
直接に社会の役に立とうとするのではなく、真実性を経由したうえで社会の役に立とうとすること。集団的な愛エンティティや記憶に介入しようとするのではなく、個人の日常生活に役立つ知識を提供しようとすること。役に立つはずだ。
Posted by ブクログ
とっても読みやすい入門書☆
Q史実を明らかにできるか
Q歴史学は社会の役に立つか
を軸に綴られている。
結論も納得w。
でも、歴史学ってより全ての学問に通じる結論だと思う。
社会科学、人文科学、自然科学…
曖昧さを肯定するには??的な。
Posted by ブクログ
歴史学は「史実を明らかにできるか」「社会の役に立つか」という二つの疑問に迫る。前者の問いの答えには結構納得させられる。歴史書と歴史小説の違いなども興味深い話題だ。
Posted by ブクログ
歴史学という学問のあり方を考察。歴史教科書問題や戦争認識問題に対するスタンスの参考になりますね。もちろん批判は大事だけれど、その土台作りには最適な本だと思う。
Posted by ブクログ
分かりやすい言葉で書かれた歴史学の入門書です。
そもそも歴史学とは何かという問いを立てるのであれば当然、史実の認識可能性についての議論に立ち入らなければなりません。本書でも、構造主義の源泉となったソシュールの言語論以降、私たちは歴史をあるがままに認識することができるのか、という深刻な問いにさらされたことに言及されています。さらに、上野千鶴子が構築主義の立場から従軍慰安婦論争に参戦した経緯などの例をあげて、歴史学者はどのようにして「史実」にアクセスできるのかという問題が、単なる歴史哲学上の理論的な問題にとどまらず、アクチュアルな意味を帯びた問題であることが浮き彫りにされています。
ただし著者は、歴史を一つの「物語」として相対化してしまうような極端な立場には与せず、たえず史料批判へと立ち戻ることで、絶対的な真理には到達できなくても、「コニュニケーショナルな正しさ」を追求することができるという立場を採ります。
歴史を学ぶ者がさしあたって歴史学という営みを続けてゆくことができるためには、そしてさまざまな民族や国家における歴史認識の断絶を克服するためには、いわば実践的な観点から「コミュニケーショナルな正しさ」の立場が欠かせません。本書では、そうした歴史学者にとっての歴史認識の方法論的考察が展開されていると言ってよいのではないかと思います。
Posted by ブクログ
再読です。授業を始めるにあたって、まさに「歴史学ってなんだ?」という確認がしたかったので、本棚から引っ張り出して来ました。著者は世界史が専門。いくつか具体例をあげながら、歴史を学び、伝えていく意義を模索します。答えは、①真実はわからないが、各自が真実だと思うことを持ち寄って、その納得点を見いだすこと ②①を踏まえて、個人の日常生活に役立つ知識を提供すること
だと言います。
再読なので飛ばし読みですが、そのままは使わずに、頭のなかでまとめ直して授業に臨みたいと思います。
Posted by ブクログ
高校(中学)時代、歴史の授業は好きだった。歴史学、歴史を科学するとは?
問題
1歴史学は歴史上の事実である「史実」にアクセスできるか。
2歴史を知ることは役に立つか、どんな時、どんな形で。
3そもそも歴史学とは何か。
27
歴史の資料を史実ととらえるか、作り話ととらえるかは作者(小説家、著者)の考え方次第、自分の信ずる通りの方法で良いだろう。史実を証明できるほど、人生は長くないだろう。
40
歴史学での定義、過去に本当にあった史実を明らかにすることを「認識」、認識した史実に意味を与え、連想させイメージを描く「解釈」
99
歴史学の対象は1つしかない「事実」ではなく各各の「現実」
170
既存の歴史学は「文書資料中心主義」「口承の歴史および口述証言」は用いない。
183
”自分の身近にあり,真偽を問わずとも役に立ちそうな過去は、「記憶」と呼ぶことができます”歴史は記憶である。
Posted by ブクログ
歴史学は「社会の役に立つか」という問に対しては、割合さっくり「役に立つ」と言いきっているので、へぇ、と思い、ふと自分の専門を振り返ったりもしたが、「社会の役に立とうとするべきか否か」とは別問題だというのに、いろいろ感じるところがあった。
Posted by ブクログ
大学1年時の授業で勧められた本。「史実を明らかにできるか」、「歴史学は社会の役に立つのか」、「歴史家は何をしているか」という3つのテーマでページが割かれている。
突き詰めると
・史料批判でコミュニケーショナルに正しい認識をすることでより正しい解釈に至る
・真実性を経由することで、「コミュニケーションの改善」、「教訓を得る」という形で個人の役に立つ
・歴史家の仕事は「テーマを設定する」→「史料を探して読み解く」→「そこから得た知識を文章化する」の三段階にわけられる
ということになります。従軍慰安婦をめぐる論争の根底に「歴史は物語(フィクション)であるか否か」という問いがあったこと、「倹約」、「謙譲」、「孝行」といった美徳が規範になったのは江戸時代で、その結果「日本人は勤勉」という共通認識が生まれたということは、当時としては印象的だった。
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
歴史は何のために学ばなければならないのか?そもそも、社会や個人の役に立つのだろうか?年号ばかり羅列する歴史教科書への疑念。
一方で相対主義や構造主義は、“歴史学の使命は終わった”とばかりに批判を浴びせる。
しかし歴史学には、コミュニケーション改善のツールや、常識を覆す魅力的な「知の技法」が隠されていたのだ!
歴史小説と歴史書のちがいや従軍慰安婦論争などを例に、日常に根ざした存在意義を模索する。
歴史家たちの仕事場を覗き「使える教養」の可能性を探る、素人のための歴史学入門講座。
[ 目次 ]
序章 悩める歴史学(「パパ、歴史は何の役に立つの」;シーン1・ある高校の教室で ほか)
第1章 史実を明らかにできるか(歴史書と歴史小説;「大きな物語」は消滅したか ほか)
第2章 歴史学は社会の役に立つか(従軍慰安婦論争と歴史学;歴史学の社会的な有用性)
第3章 歴史家は何をしているか(高校世界史の教科書を読みなおす;日本の歴史学の戦後史 ほか)
終章 歴史学の枠組みを考える(「物語と記憶」という枠組み;「通常科学」とは何か ほか)
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]