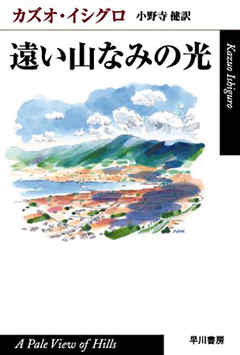感情タグBEST3
Posted by ブクログ
先に名前のインパクトのある、素直に素晴らしいだろうと思い実際に文学に触れた重篤感があり、なにより読み易い。なんだろうかこの感覚は、たしかに不思議な登場人物に終わらせ方に ラストもページ捲ってありゃまあニキのお見送りが終わりかいってなあーってこと。ニキもそうだが掴みきれずに 万里子も、うーむだし、景子の誕生シーンも二郎との別れもなかったが。それでも読み終わるのは要所要所に大切なものが詰まっていたから。あっ佐知子の伯父の家に戻らないのと自分がアメリカ行けないことを分かっているのに神戸に行くという場面が全く理解出来んのよ。これもう一度読むと違いがわかるんかなあー
Posted by ブクログ
カズオイシグロさん、生まれも育ちもイギリスだとおもってたけど、5歳までは日本に居たのね
足に絡まるロープがループするとこ怖
えつこさんがさちこさん、、?
Posted by ブクログ
戦後の諦めを含んだ前向きさとか、イデオロギーの急変による軋轢とか、親と子とか、後悔とか、折り合いとか。本当にすごい。
池澤夏樹の解説も良い。
250
「いまさら、むしかえしてみても始まらないわ」
Posted by ブクログ
後半に向かうにつれ、何を語っているのかが見えてきて、ぞくぞく恐ろしい。
原爆に遭い家族を亡くしたエツコの記憶の混同と異常性。
自分の生き方を肯定しながら、記憶の中で、上品で優しく明るい自分を作り上げながら生きてきたのであろうことも。
カズオイシグロ作品に多く見られる記憶の捏造。
記憶を作り替えなければ、とても生きられなかったのだ。
Posted by ブクログ
再読。いやこれめちゃくちゃ怖くない?なんで昔読んだときは気づかなかったんだろ?ぜんぜん女性の自立とか復興への希望みたいないい話じゃないじゃんか。解説書いた人トチ狂っとるんか?
「信用できない語り手」という補助線を引いて読むべきだった。語り手による語りは信用できないものだということは緒方さんの饒舌さが常に示唆している。
最初に万里子を探しにいくときに主人公の足に絡んだロープ、ブランコの夢、長崎の街を徘徊し児童を殺して木に吊るす殺人鬼、万里子を訪れ脅かす謎の女、神戸に旅立つ前夜に万里子を追いかけた主人公が手にしていたもの。終盤、大切な思い出についてさえ嘘をつくことで主人公自身が信用できないことは決定的になる。そのとき、景子は本当に自死だったのか?という疑念が限りなく黒に近いグレーで迫ってくるよね。いやほんとに怖いよこれ。
ニキはブーツを3足も持ってきてたって?そんなに履くものばかり持って何から走って逃げてきた?お前さんのパパはいったいどこにいったの?そしてなにより、穏やかに老いた風にしている優しいお母さん、「悦子」さん?アンタ一体何者なの?
Posted by ブクログ
女性の男性からの独立や、不条理なパラダイムシフトで没落した人々のもがきといった、複数のテーマが書かれている。
回想の中で過去と現在を行き来し、「いい母親」よりも非隷属的な、自立した女性になることを選んだ自己を、同じ選択をした過去の友人に重ね合わせる。友人に対する非難は、過去の自分からの、現在の自分に対する非難でもある。
また、友人や男尊女卑の古い価値観に囚われた人々との生活を思い出すことで、そのような従属的な環境の中にも幸福を見出していたことを確認する。
しかし、だからといって現在の主人公は、イギリスでの生活に不満を抱いているわけではない。
過去の自分による現在の自分に対する批判、そして独立した、現代的な女性である娘の言葉によっても行われる、現在の自分による過去の自分に対する批判。
この二つの批判を通して行われる、主人公の過去の精算こそ、この小説の真の主題なのかもしれない。
Posted by ブクログ
戦後の騒乱の中で生きた女性の物語。
戦前、戦中に良いとされていたものは覆され、戦後には戦前の地位や名誉はなんの意味もなくなる。
愛国主義を掲げて教壇に立っていた義理父は戦後、落伍者となり息子にも相手にされず、ひっそりと隠居生活を送る。
戦争で旦那を亡くした佐知子は、娘の万里子とともにアメリカ人の愛人とアメリカへ渡る夢を描く。
そういった出来事を、現在は英国人の旦那をもち、英国で暮らす主人公の悦子が、景子という娘を自殺で亡くしたことをきっかけに、過去のこととして回想する。
結局、佐知子や万里子は、自分であり景子だったのであろう。そう思わせる箇所は作中いくつかある。
悦子から見て、当時奔放に見えていた佐知子は、現在の悦子とシンクロする。
そう考えていくと、親のエゴに振り回された万里子は景子であり、結局は自殺する。
自殺の原因が自分にあるとは感じながら、その罪悪感に直視できず、歪んだ過去が佐知子と万里子になったのではないか。
ともあれ、これは日本人の血をひきながらも幼少から英国で育ち、日本語を母語としない著者の小説である。
他国からみた日本、といっても差し支えないと思うが、
「日本人には本能的な自殺願望がある」
という英国メディアの表記に驚いた。
他国から見て、日本人はそんな風に思われていたのか。
Posted by ブクログ
タイトルからは想像できない、薄暗くてちょっと不気味な小説。
現在居住するロンドンで自分の娘を自殺で亡くした悦子が、その体験をきっかけに、長崎に住んでいたときに出会った少し変わった母娘、佐知子と万里子との経験を回想するというもの。
大戦直後、まだ原爆からの復興も道半ばの長崎を舞台背景に、母娘との出来事を想起する形で綴られていく。
佐知子は、かつては東京でそれなりの生活を送っていたが、戦争で母娘二人きりになり、長崎へとやってきた。
東京で知り合ったアメリカ人の愛人のいい加減な言動に翻弄されながらも、そのアメリカ人がいまのみじめな生活を救ってくれると信じている。
娘の万里子は10歳くらいで癇癪持ち。そして時折とても不気味な発言をして悦子を当惑させる。
悦子は自身が身重でありながらも、この母娘に協力してあげようと必死に世話をする。
佐知子と悦子は価値観が全く異なる。主人公の悦子は戦前からの日本的価値観の持ち主。一方の佐知子は戦後アメリカから導入された民主主義的解放を信じた言動をする。
会話が全く噛み合わない。まず不気味さの一端はここにある。
本作のテーマの一つは、戦後流入した新たな価値観を自分のアイデンティティとして受け入れるというところにあるのだというところが随所に感じられる。
戦前価値観側の悦子、そして悦子の面倒をみた緒方さん。そして一方が悦子の夫で緒方さんの息子である二郎と、そして佐知子。
悦子が回想する時点では、既に彼女は新たな価値観の中で生きており、その受容過程が想起するエピソードに大きく影響を与えている。
そしてもう一つの大きなテーマ。これはカズオ・イシグロの多くの作品に共通するものであるが、記憶の曖昧さ。
物語のなかで、誰かが何かを想起するという場面はごまんとある。ただ、多くの場合それは記憶とはいえはっきりと語られる。
一方のカズオ・イシグロの作品は、記憶は、本来人間の持つ記憶と同じで、とても曖昧なもの、信頼ならないものとして物語に投入される。
そして、想起する人間のそのときの状態によって、記憶は適当につぎはぎされ、都合良く改編される。
劇場で聞いた実に立体的なオーケストラが、録音で聞いたら平面的になってしまうのと同じように、時系列的な奥行きが平面へと吸収され、3年前と1年前の出来事が同一平面の記憶として存在したりする。
いなくなった万里子をおいかけた悦子が、追いかける途中でサンダルに縄がからまる。でもその記憶が、最終盤、もう一度万里子をおいかけることになった経験のときにも混在している。
この場面、心底不気味なのだが、あとから振り返ると、人間の記憶を実にリアルに表している。
彼の代名詞的な表現技法として名高い「信頼のできない語り手」というのは、この処女長編からして確立している。
すごいと思う。ただほんと、薄気味悪い。
登場人物みんな薄気味悪い。カズオさん、ほとんど日本にいなかったと聞いているけど、よくまあこんな日本人特有の気味の悪さを抽出できたなと感心する。
ああ、そうか。あまり知らないからこそデフォルメできたのかもしれない。
や。面白い。薄気味悪いけど面白い。読みやすいし、おすすめですよ。薄気味悪いけど。
Posted by ブクログ
はじめてのカズオ・イシグロ作品。
幾度と出てくる自らの主張を正当化するちくはぐな噛み合わぬ会話から、戦後日本の価値観の移り変わりと混乱を感じる。
娘の自殺、離婚・異国への移住。大きな出来事の全ては語られず、過去の日常を回想することで、その背景に何があったのか、受け取り方が無数にある。読み取りきれていない行間がたくさんある気がして、読後パラパラと最初から読み返してしまった。
Posted by ブクログ
カズオ・イシグロ氏の作品、私はこれで二作目です。
私は前回『私を離さないで』を読み、そのディストピア的雰囲気と他人の為に命を供することを運命づける命、という存在に、意識のある家畜などを想起しました。まあとにかく、その設定に魂消た。
そして今回の作品も実は原作は40年前となかなか古め、そして不穏さがプンプン漂う中、釈然としない終了。模範解答が示されない! 友人知人に解釈を聞いて尋ねたくなるような展開でした。
【不穏①自殺した娘、景子】
本作は長崎時代の悦子と老年(50代後半)の悦子の状況が、行き来しつつ展開します。
冒頭では英国に渡り再婚した悦子から始まります。どうやら日本から連れてきた長女景子は自殺してしまった模様。他方英国に来てからの再婚後の子である次女ニキ。彼女と母の母娘の関係はもとよりニキと景子の姉妹関係もどうもしっくりいっていなかった様子。
こうした中、一体どうして景子が自死を選んだのかは明かされませんでした。英国が合わなかったのか、母との関係が良くなかったのか、或いは日本人の父親との間に何かあったのか等々、個人的には色々勘繰りました。一体どうして?
【不穏②再婚の経緯】
語り手である悦子が英国にて再婚したことは状況から分かります。でも、経緯については一切語られません。今現在、英国人の夫も亡くなり、その資産を受け継ぎ田舎に引っ込んでいるという事だけが分かります。
来し方を振り返り、戦後の結婚当初の日本人夫そして義父については振り返りますが、この英国人の夫については詳細が分かりません。こちらはどのような背景があったのかは全く分かりません。一体何があった?
【不穏③佐知子と万里子親子はいったい】
アメリカ人の情婦と思しき佐知子とその子である万里子(純ジャパ?)。
悦子が景子を亡くし、その後かつての長崎を想起する際、この母娘を思い出します。この佐知子・万里子親子は、没落貴族?のような風であり、プライドも高く、特に母は虚言癖の如く、米国人情婦のフランクとともに母子ともども米国へ移住すると何度となく悦子に告白(自慢?)します。
佐知子によるオオカミ少年的繰り返しの何度目かで、娘万里子が可愛がる猫がアメリカへは持っていけないと分かった万里子は、母親の反故にした点を佐知子にねちねち言ったところ、母親はとうとう猫を川に沈めて殺してしまった!?なんだこの母親!?
読者として、そんな病的な行為を後々振り返って考えると、実は英国での悦子というのは佐知子なのでは? そして英国で自殺した万里子とは景子のことでは?等と想像してしまいました。つまり佐知子は長崎でしった悦子(本物)を英国で思い出していた!?とか。
あるいは猫殺しやフランクへの執着から佐知子・万里子母娘の不仲が想定されましたが、実は景子とは佐知子から引き取った万里子のことで、悦子が英国へ連れて行ったのか等を想像しました。では長崎で孕んでいた悦子の子供はどうしたんだってことにもなりますが。
いずれにせよ、行間の広い、そして不穏な空気が美しく文語チックに描かれる様が美しい作品でした。
・・・
ということでイシグロ作品二作目でした。
今回は翻訳が非常にすばらしかったのですが、原典でも(お値段安かったら)読んでみたいなあと思いました。
純文学好き、英国好き、長崎好き等々にはお勧めできる作品です。
Posted by ブクログ
色んなことが分からないまま終わったけど、嫌じゃない。知りたかった結末もあるけど、ストーリー展開的に、分からないままでいいやって思えた。
謎っぽい書き方だから、続きが気になって、割とすぐ読めた、
Posted by ブクログ
イギリスの田舎町に住む「わたし」のところに、次女の「ニキ」がやってきた所から話は始まる。わたしは、二人で自殺した長女「景子」の話をしていると、生まれ育った長崎に戦後いた頃に出会った「佐知子」と「万里子」という母娘のこと思い出す。
万里子は、戦時中の東京で、近所に住む女性が、自分の赤ちゃんを水に沈めている光景を目にしてから、その女の幻影を話すようになったという。一番印象に残ったシーンは、母親の佐知子が、その万里子の飼っていた子猫を川に棄てるシーンだ。
母親の佐知子は、愛人を頼りにして、万里子とともにアメリカへ渡ることを夢見ていた。渡航の目処が立ち、佐知子は引っ越しの準備を始めるのだが、万里子は、どうしても子猫を連れて行きたいと言い出す。これに業を煮やした佐知子は、万里子の目の前で、子猫を箱に詰め、川へ連れて行き、一匹ずつ取り出して水に沈め、娘の方を振り返る。
娘のトラウマを、大事にしていた子猫で再現する母親の姿が恐怖だった。
この物語は、過去と現在の間で繰り返される様々な場面でこうした映像の重なりが現れる。全体を通した薄暗い雰囲気と合わさり、暗い現実が繰り返されるイメージを感じた。
手が込んでいて、もう一度読み直したくなる小説だった。
Posted by ブクログ
一旦読み終わったあと、また最初から読み返したくなる。
悦子が長女を失ったことについての心情や詳細な経緯は語られない。悦子の長崎時代の回想を通して、「多分こうだったんじゃないか」「きっとそうだ」と読者に思わせる表現になっている。
他の方のレビューでもあったけれど、そもそも語り手である悦子すら、本当のことを語っているのか、そこを疑ってみるのも面白い。長崎時代の回想は悦子が自身の罪から目を背けるために作り出した、事実と虚構の入り混じった「記憶」なのではないか。そのような見方ができる。そういう意味で、もう一回読んでみたくなる。
悦子と万里子母との間の会話は、普通の会話のように見えて、普通ではない。噛み合っていない。そこが狂気を感じさせていて、「これって悦子と万里子母との会話というより、悦子が自分自身と対話しているような感じ?万里子母への若干攻撃的かつ批判的な対応も、過去の自分を責めている?」と思わせられた。
物語の作り方が、直接的ではなく間接的すぎない、絶妙な作り込みで、そこがすごいなと感じた。
なぜか引き込まれる
授業の課題のため購入しました。
淡々と進んでいく話の中で世界に引き込まれていきます。考察がありすぎて深いです。
登場人物の類似点や時代背景に注目して読んでみてください。初めてカズオさんの小説を読みましたが、他の作品も読んでみたいと思いました。
Posted by ブクログ
英国で暮らす日本人女性の回想話。
登場人物は皆、表面上は友好的なのに今一つ会話が噛み合っておらず、どこを読んでも「ん?」と頭を捻らされる。強い階級意識と罪悪感のようなものが心の交流を困難にしているのだろうか…と思ったがどうやらそれだけではない。
なぜ主人公の女性の娘は自殺してしまったのだろう?と疑問が物語の最初からついてまわるが、中盤と終盤に、万里子という少女が主人公に対して「なぜ、そんなものを持っているの?」と執拗にきく場面を読んで、ハッとするものがあった。
あの場面で、万里子は殺されると思ったのではないか?赤ん坊が殺され、猫たちも殺された。
主人公の罪悪感とは何か?
なぜ今、彼女は英国にいるのか?
つまり、娘は、行き場のないその境遇と環境、そして母親によって(間接的に)殺されたのだ。
記憶は主人公の都合の良いように操作されている。
佐知子が行ったのは米国ではなく、英国。景子=万里子、悦子=佐知子。この回想は、過去の自分を振り返ったもの。そう考えると全ての謎がとける。
この小説は読者が謎を解読する推理小説なのではないだろうか。
Posted by ブクログ
こういう過去を振り返っていく小説好き。その中でもカズオ・イシグロの作品は、身の上だとか何に苦悩しているかだとかが徐々に明かされていくとことか、語り手自身の解釈/脚色が入った記憶を語るところとかが面白いなと思う
Posted by ブクログ
この本は、戦後、将来の見えない薄暗闇の中を、手探りで生きている女性の人生を描いたものでした。
とても息苦しいような読後感になりました。
ぜひぜひ読んでみて下さい。
Posted by ブクログ
英文学というのを忘れて読んでしまうほど、自然。
ただ、夫を名前で呼ぶのには少し違和感があった。
原爆という背景をもちつつも詳細に語る事なく、悦子の家族、佐和子と万里子の物語が展開される。
悦子しかり、義理父しかり、過去の自分の行動に対して本当に良かったのだろうかという念が感じられる。
結果的に悦子は否定的に思っていた佐和子のように、じぶんを優先させイギリスへ行き、娘の景子を失う。
子猫を沈める佐和子は、娘がみた、赤ん坊を水に沈めた女のようだった。
うまく対比になっていた。
過去の行動について後悔はあるけれど、その時はその行動がいいかわるいかなんてわからない。ということが登場人物の行動からみてとれた。
昔だからしょうがないけど、二郎さんの態度は気に入らなかった。
Posted by ブクログ
遠い山なみの光
著者:カズオ・イシグロ
訳者:小野寺健
発行:2001年9月15日
『女たちの遠い夏』(筑摩書房):1984年
『女たちの遠い夏』(ちくま文庫):1994年
カズオ・イシグロの処女長編作。日本では『女たちの遠い夏』として1984年に発行されたが、その後、邦題改訂、訳の手直しもしてこのタイトル作品に。
カズオ・イシグロが生まれた地、長崎が主な舞台で、登場人物も日本人がほとんど。戦後間もないころ。原爆が落とされた長崎だが、原爆の話はほとんど出てこない。復興しつつあり、少しずつ庶民の生活ぶりが向上し、占領軍が出て行く直前あたり。主人公は、エレクトロニクス会社に勤める夫を持つ悦子。最初の子がお腹にいる。夫は会社で活躍し、多忙で、仕事にも燃えている。復興のためにつくられた鉄筋のアパートに住んでいたが、そこに夫の父親が遊びに来る。義父は福岡で1人住まいだが、悦子はもともと義父と知り合いで、その中で夫とも出会った仲。関係はとてもうまく行っている。しかし、義父と夫はそんなにあわない。義父は校長先生をしてきた人だが、最近、夫の幼なじみが書いた論文の中に自分のことが批判的に書かれていたため、その幼なじみに抗議をしたくて仕方ない。夫は、そんな父親の言うことを適当にあしらう。
悦子は、近所の一軒家に住む母娘と仲良くなる。東京から引っ越してきた母娘で、娘はまだ幼い。その母親は、どちらかというと自分優先で娘のことは放置しがち。学校に行かなくても気にしない。アメリカ人と付き合っていて、アメリカで住むことを目指している。もともと金持ちの家に育ったが、今はお金がなく、悦子から紹介されたうどん店で嫌々アルバイトをしたりしてしのいでいる。
戦前と戦後、日本では大きく価値観が変わったし、正義、不正義も真逆に変えられた。世代ギャップというか、年齢ギャップは大変著しい。そういう対立やすれ違いを描いていく小説。決して大きなストーリー性があるわけでなく、何気ない日常の会話を中心に話を進める。まるで小津安二郎の映画のような小説。
悦子は、結局、夫と離婚し、イギリス人と再婚し、新たに娘をもうける。最初の子も娘だったが、彼女は引きこもりで、マンチェスターで一人暮らし中に縊死してしまう。その傷を抱えながら、自らもイギリスの田舎に住みつつ人生を振り返る。
後書きは、訳者にくわえ、池澤夏樹が書いている。池澤はいつもながら素晴らしい後書きを書いている。それさえ読めば、この本の神髄が分かってしまう。
その池澤が書いているのが、この作品は日本文学ではない、という点。あくまでイギリス人が書いた作品なのだ。だからなのだろうが、長崎の平和祈念像について主人公悦子の意見として、「恰好がぶざま」「原爆が落ちた日のことやそのあとの恐怖の数日とはどうしても結びつかない」「遠くから見るとまるで交通整理をしている警官のようで滑稽にさえ思えた」と率直に書いている。僕も、高校の修学旅行で初めて見た時から、この像に違和感があった。ここになんでこんな〝アート〟な作品を置く必要があるのだろう。今もそう思う。
素晴らしい快作だった。長編での処女作だとは思えない作品。
Posted by ブクログ
処女長編小説ということだが、回想が小説の大半を占めるのは最初からだったようだ。悦子はイギリスでの現在の生活と長崎での過去の経験とを重ね合わせて回想している。私は過去の自分とこんなにはっきり会話できるだろうか。
過去はおぼろげなものだとしても、私のそれは虫食いだらけで、ぜんぜん掘り返せない。
会話のズレは、多かれ少なかれある。自分が10の言葉を発しても、相手が10で受け取ることはほぼできないといっていい。お互いに了解している会話でも、9割以上の理解ではないかと思っている。9割以上というのはあてずっぽうだとしても、自分の意図したことは100%伝わらない。それを嘆いているわけではなく、そういうものだと思っている。言葉や文章で伝えることには限界がある。伝言ゲームという遊びはこどもにそれを伝えることなのではないかと思う。
会話には全くすれ違っていることもしばしばある。お互いがお互いの言葉のボールを好きな方向に投げているような、自分の頭の中と会話しているような、お互いが言葉を発しているけれども、第三者から見ると全くかみ合っていない会話がある。この小説の中にもそれが出てくる。まったくかみ合っていない会話、自分のことが頭の中にたくさんあって相手の話が全然入ってきてない会話、自分のことしか言っていない会話。この小説には大なり小なりそういった会話のズレが出てくるが、それが普通なのかもしれない。
でもあえてこういう会話のズレを見せられるとそれを意識する。伝える努力をしなければ相手にはうまく伝わらないということが思い知らされる。一方で、会話のズレで楽しむこともできる。思い違いが後で笑い話になったり、意図的にズラすユーモアだったり。
小説の随所に、ホラーというよりも怪談といった方がしっくりくるようなシーンが出てくる。人間の狂気が薄暗いシーンで語られている。この怪談話のような回想シーンを読むと、過去にあった嫌なことや不快だったことなどのイメージは、薄暗い倉庫の屋根裏にでも収まっているように頭の中に記憶されているのだろうと想像できる。だとすると、こういう記憶には風を通して日を当ててやった方が良いように思う。頭の大掃除はどうやってやる?
解説を読んで、この小説がもともと英語で書かれたものだということを思い出した。日本の場面は日本の小説のようで、イギリスの場面は海外の小説のようだと感じていたけど、訳者が巧みだったことも知った。英語の原書を読むとどのような印象なのだろう。日本語を読むように英語を読めれば面白いのに。翻訳をする人たちはどのような感覚なのだろう。英語はただの記号の羅列としか思えないので、そういう感覚をいつか経験してみたい。
長崎の街を舞台にした小説を過去にいくつか読んだが、また読みたい。長崎は重い歴史をもった重要な場所だ。
Posted by ブクログ
カズオ・イシグロって村上春樹とよく似ているな~
イシグロの小説は何冊か読んできたけど、
この小説を読むと本当にそれを感じる。
この二人の共通点は、
どちらも「運命に対する態度」みたいなものを問題にしてるってことかな?
物語がかもし出す不気味さ、不安感も似ているね
相も変わらず回想調の美しい文章。。
白黒の日本映画のような哀感が素晴らしい
Posted by ブクログ
こういうはっきりしない、行間を読みながら、想像しながら読む物語は苦手だったけど読み切れた。結局、景子が自殺した理由とか細かいところは分からず、終始、佐和子が過去を振り返り何か自分の心を整理するような感かじがした。日の名残と打って変わり、薄辛い印象のある物語だが、純文学とはこういうものかと新しいジャンル触れることができた。
Posted by ブクログ
薄暗い、ぼんやりとしたお話しだった。みんな心に傷を負って、挫けないようただ淡々に生きている証のように思えた。
成り立つようで成り立たない会話の書き方があまりにリアルで唸る。それと同時に戦前・戦後の考え方が変わっていく瞬間を捉えていて奇妙だった。図らずともこの時期に読んだので、虚しさが増した。
それぞれが希望と絶望のギリギリのラインを必死に生きていたんだろうな。
「戦争でこんなに世の中が変わるなんて、考えてもみなかったわ」
Posted by ブクログ
作品を通して登場人物同士の会話が、終始噛み合ってないcommunication breakdown状態。
そしてスッキリしない空気感が、なんとも重いとまではいかない、独特な薄気味悪いグレーな雰囲気に満ちている。
個人的にはこのcommunication breakdown状態に、読むのに苦労した。。。
Posted by ブクログ
カズオ・イシグロの長編デビュー作。過去の傷を癒しながら未来に向けて再起を図る、2つの家族を描いた作品。戦後の長崎が舞台で、登場人物は日本人が中心となっている。やはりカズオ・イシグロの作品は、色のないモノクロの映像しか思い浮べることができない。土地やキャラクターなどの設定濃度が低いからだろう。またこの物語では、登場人物は比較的多いが、どの会話も淡々と流れていく。最終的に大きな見せ場があるわけではないので、刺激も少ない方だろう。そのため、じっくり噛みしめながら味わう作品なのかもしれない。
Posted by ブクログ
暗い影に纏われた作品。
時には原爆、時にはネグレクト、そして幽霊。
会話か噛み合わない登場人物。本質ではうまくいかないとわかっているが自らを偽る言葉を吐く人々。
そして佐知子の人生が悦子の人生にダブってみえてくる。時代に翻弄された女達の心に根ざしたものは同質だったのか。
匿名
作者がノーベル賞をとったので、どんな作品を書くか興味を持ったので読んでみました。
叙情的な文体は日本の純文学の影響を強く思わせます。
しかし、翻訳された文章は逆輸入した日本文学みたいで、少ししっくりとこないものがあります。ぎこちなさを感じました。
作者は作品ごとに新しい試みをためしているようなので、他の作品も読んでみたいと思いました。