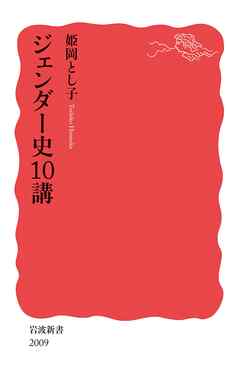感情タグBEST3
Posted by ブクログ
新書ということもあって平易で簡潔に書かれていて読みやすい。内容は女性史やジェンダー史の勃興から歴史叙述との関係、家族史や身体史や労働史、他には近代家族論、社会構築論、ポスコロなんかが扱われている。ほとんどの章で日本やアジアのことについての記述が含まれていて、読んでいて沸いた「日本やその他の地域ではどうなんだろう」といったような疑問にはある程度は応答してくれていて快適だった。
ジェンダー史は全く知らんので記述の確度は分からないけど、姫岡さんは全くの門外漢のぼくでも知ってるような方なので信頼できるとは思う
Posted by ブクログ
「ジェンダー史」の成立までと、それが明らかにしてきたものを10章に分けて説いている。
実は本書を読む前、ちょっと誤解していて、ジェンダー研究の歴史のかと思っていた。
が、そうではなく、歴史学の中で、ジェンダーがどのように主題化していくのかということだった。
ならば、どうして「ジェンダー史学」とか「ジェンダー歴史学」という言い方ではないんだろう?
「ジェンダー史」という言い方が、歴史学業界では普通なのかなあ?
前半4章は、歴史学の研究の流れが紹介され、この整理はとても分かりやすかった。
ジェンダー史は、第一波フェミニズム、第二波を経て、生まれた。
第一波では、これまで歴史学が顧みてこなかった女性を歴史学の対象とする「女性史」が成立し、第二波フェミニズムの時には、既存の歴史学が男性に偏向したものだと批判する「新しい女性史」が成立する。
しかし、いずれも女性という周縁的な内容を扱ったもので、既存の歴史学の幅を広げたもの、として済まされることになる。
そこでジェンダー史が現れる。
知と権力の関係の中で、どのように性差が意味付けられ、どんなメカニズムで社会の中に組み込まれ、はたらいていくのかを分析するもの(主にJ.スコットとその影響にある人たちの立場)だ。
つまり、社会構造を作り出す力として、ジェンダーを捉える。
ジェンダー史とは、その歴史的過程を跡付けていく学問ということのようだった。
著者はドイツ近現代の労働史を専門としてきた人というだけに、本書の中にある、「生産領域だけに注目する」だけでなく、家との連関を考えないと労働の全貌は把握できない、という指摘は説得力がある。
たしかに、労働や生産は、経済の問題となり、それは従来の歴史学でも主要テーマであったはずだ。
ある時期まで女性の姿がその領域に見えないのは、近代家族が成り立っていくのとセットで、女性が補助的な労働を担うものという役割が成り立っていったからであり、女性が労働に関わっていなかったわけではない。
これがごっそり「見えない」存在になっていたとすれば…と思うと、そら恐ろしい気持ちになる。
後半はジェンダー歴史学が明らかにしたものが取り上げられていく。
筆頭は家と家族。次に身体と性、福祉、労働、植民地、レイシズム、戦争と続く。
この辺りは、それぞれ1冊以上の本になっても不思議でない、問題が山積する領域。
(最後の章は、なんか突然終わってしまった感もある。)
権力機構の中で、女性が、社会的地位などにより、被害者にも加害者にもなるという錯綜が見られる。
単純なものが好まれる雰囲気も感じられる昨今だが、こういう社会の複雑さに向き合えるか。
読み終わってから、考えてしまった。
Posted by ブクログ
読んでいる途中だけど、第4章の記述の中で、歴史を考える上で、「正史」という見解はもはや成り立たず、ジェンダー史もある見方としての歴史の一つなのだ、という指摘は心に留めておく必要があると思った。
ジェンダー史だけでなく、障害者の観点から捉えた歴史とか、民族や移民の観点からとらえた歴史とか、多様な歴史の見方があるということを改めて気付かされる。
これまでの歴史の叙述から埋もれてしまった歴史を掘り起こし人々の歴史認識をズラすことに貢献してくれるのが、上記の新たな歴史学なのだろう。
だけど、できれば依拠した出典の明記の仕方がもう少しわかりやすいほうがいいなと思った。例えば、「〜〜(〇〇 2024)。」とか「〇〇(2024)によると、〜〜。」みたいな感じで。