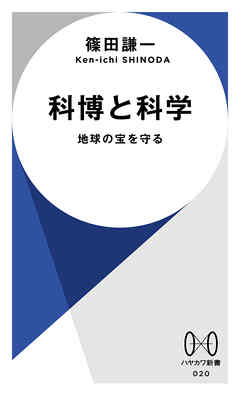感情タグBEST3
Posted by ブクログ
ハヤカワ書房が!新書シリーズを出している!と遅ればせながら気づき、まずはこの作品から読み始め。
「科学を文化に」のスローガンの意味は、読み通すと理解でき、科博及び科学に取り組む方々すべてを応援したい気持ちになる。
長いスパンで物事を捉えることの大切さを感じた。
Posted by ブクログ
科博内部の研究者から初めて館長職に就任した著者が語る、
博物館とは。科学系博物館とは。そして、国立科学博物館の
足跡と未来の展望について。
・はじめに
PART1 文化としての科学
PART2 博物館の役割
PART3 科博の実践――「リアル」の価値を問い直す
・あとがき
コラム、写真出典一覧有り。
科博の歩み、実情と未来への展望を伝える内容です。
技術開発と科学の進歩は、ホモサピエンスの進化と
ゲノム研究。古代ゲノムの解析での人類の進歩の研究へ。
それは、自然科学と人文科学の関係性。
自然科学も文化の一部として社会に定着させる重要性がある。
国立科学博物館の歴史は、理工系と自然史。
5つの研究部に専門家な約60人の研究者たち。
本館以外の施設と収蔵庫。約5,000万点の収蔵品数。
自然教育園の事。実験植物園には、ショクダイオオコンニャク、
ニュートンのリンゴとメンデルのブドウの木がある。
文化財と自然史財について。標本の価値。
博物館と法律。独立行政法人という位置。
そしてコロナ禍の苦心惨憺とクラウドファンディング。
以前、「標本バカ」川田伸一郎/著を読んでいたので、
光熱費の高騰は標本保存に影響を与えるだろうと心配して
いましたが、標本・資料が“地球の宝”としてのスローガンと
成り、クラファンを行ったことには、胸が熱くなりました。
また、その地域ならではの研究と標本がある、
全国の博物館との協働も、未来への布石になると思います。
この本がSFの大御所の早川書房から出たことも、嬉しい。
「科学を文化に」は未来への希望とも感じました。
Posted by ブクログ
書店で見かけて気になってはいたんだけど、直接のきっかけはどこかの書評から。科博、行きたいな~。一度だけ立ち寄った時も、短時間しか滞在できず、不全感しか残ってないからな~。本書を読んで、そういえばクラファンの話題で見かけたときにも、凄くいきたい気分が盛り上がったんだったと思い出した。それにしても、国立なのに国からの救済措置はろくに得られず、更には内部留保も許されんって、えらい厳しい条件だな。一般企業だと考えられんことだけど、こういうところにも、利潤企業最優先、公の部分については、自分たちが太ることしか考えん、っていう国の本質が垣間見えて嫌だな。本筋とは逸れるけど、そんなことが印象に残っちゃう。